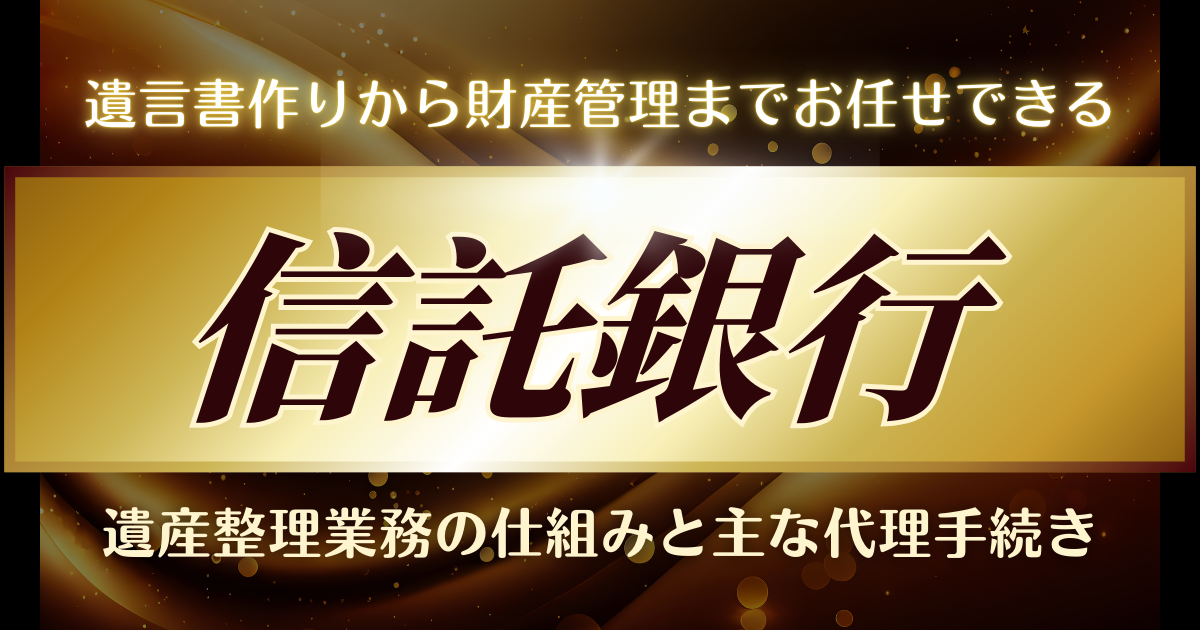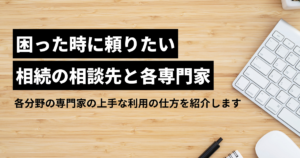悩める人
悩める人そもそも信託とはどんなこと?



遺言信託・遺産整理業務…?



こんな疑問・悩みを解決します!
- そもそも信託とは?
- 信託銀行の業務と機能
- 遺産整理業務の仕組み
- 遺言サービスの利用法
- 遺言を残しておきたいケース
そもそも信託とはどんなこと?
信託とは、ある人(委託者)が一定の目的(信託の目的)に基づいて自分の信頼できる別の人(受託者)に財産権を引き渡し、委託者本人又は第三者(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分してもらうという制度です。
信託は「信託法」という法律により、財産管理制度の一つとして認められています。



民法上の委任、請負、代理などの制度も財産管理制度の一つですが、信託の場合、財産権の他に財産の名義が受託者に変わる点がこれらの民法上の制度と大きく異なります。
従って、信託では、受託者自身の社会的な信用が大変重要となり、委託者との間に確かな信頼関係がないと成り立ちません。
それだけに受託者には、信託財産を自分の固有財産と分けて管理するなど厳しい義務が課せられ、信託財産の独立性が保たれています。



この信託業務を行なっているのは、信託銀行を始め、信託業務を兼営する都市銀行(2行)及び地方銀行の一部で、合計58社となっています(2024年10月時点)。
信託銀行の業務と機能
信託銀行は信託機能を持つことにより、多彩な金融サービスや財産管理に対するニーズに応えています。
業務としては信託業務を柱に、不動産、証券代行、遺言の執行などの併営業務と一般的な銀行業務を行なっています。
①銀行業務
- 預金
- 貸出
- 為替
②併営業務
- 不動産の売買・賃借の媒介
- 不動産の鑑定評価
- 証券代行業務
- 遺言の執行等
- その他
③信託業務
- 金銭信託
- 貸付信託
- 財産形成信託
- 年金信託
- 証券投資信託
- 特定金銭信託
- 有価証券の信託
- 金銭債権の信託
- 動産信託
- 不動産信託
- 土地信託
- 公益信託
- 特定贈与信託
- 遺言信託
- その他
信託業務は、信託された財産の種類によって、金銭信託、貸付信託などの「金銭の信託(カネの信託)」と、有価証券の信託、不動産信託などの「金銭以外の信託(モノの信託)」に分かれます。
それを機能の面から見ると、貸付信託や金銭信託などのように資金を企業の設備投資や個人の住宅資金などの貸出を中心に運用する「金融機能」と、動産、不動産、有価証券などの信託のように財産の管理・運用を行う「財産管理機能」に大別されます。



これらが一体となって、社会や私たちの幅広いニーズに応えているわけです。信託銀行は金融商品の豊富さや幅広い機能、高度な専門性を持つことから、金融のデパートと言われることがあります。
定期預金や外貨預金、住宅ローン、給与振込などを扱う銀行業務もあれば、不動産の売買や賃貸借の仲介、不動産会社との提携によるマンション・住宅の分譲、不動産の鑑定評価などの不動産業務もあります。
その他、証券業務として株式や債券の売買取次、証券投資についてのコンサルティングなども行なっています。
証券代行業務では、発行会社の委託を受けて株主名簿の保管と管理、名義書換など株式事務全般を代行しています。
さらに、国際業務も行い、外貨の両替、海外への送金なども取り扱っています。
遺産整理業務の仕組みと主な代理手続き
相続に関しては、遺産整理の代理業務と遺言書の保管・執行業務があります。
相続の開始から相続税の納付まで、決められた期間内に、相続財産の目録の作成から遺産の分割協議、相続税納付のプランニング、不動産や有価証券の名義書換、相続税・所得税の納付など、各種手続きを速やかに完了することが大切です。



それらを信託銀行がアドバイスを含めて徹底的に手伝ってくれるのです。手続きに不慣れな人や時間的な余裕のない人、弁護士・税理士などの専門家にツテがない人などには便利でしょう。
では、遺産整理の代理業務は具体的にどう進められるのでしょうか。
某信託銀行の遺産整理業務を例にご紹介しましょう。
某信託銀行では、財務コンサルタントを始め、必要に応じて税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家と共同で多面的に十分検討し、スケジュールを管理しながら遺産整理手続きを確実に実行します。
遺産整理業務の仕組みは次のようになっています。
- 遺産整理に関する事前の相談
- 遺産整理業務に関する委任契約の締結
- 法定相続人の確定
- 財産内容の調査・確定
- 財産目録の作成・交付
- 遺産分割のアドバイス
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割手続きの実施
- 相続税などの納付に関するアドバイス
- 相続財産運用計画の立案と運用
- 遺産整理業務完了の報告
1の「事前の相談」では、遺産整理の基本方針を固め、必要書類の取り寄せ方などをアドバイスしますが、ここまでは無料です。
相続人たちとの間で2の「委任契約」を結んで、初めて具体的な作業が発生します。
6の「遺産分割のアドバイス」では、不動産の価値を損なわないよう、また、ライフプランや納税などを踏まえた上手な分割方法について相談に乗ってくれます。
10の「相続財産運用計画の立案と運用」では、希望により、今後の生活設計や資産の運用、財産管理について運用計画を作成してくれます。



不動産の有効活用、売却、買い替えなどは、某信託銀行の不動産部が別途サポートします。
遺言信託の仕組みと手続き
遺言を残そうと思っても、相談相手を見つけるのは難しいもの。
書式は難解だし、作成後の保管方法も不安の種です。
まして、自分の思い通りに執行されるかとなると、誰でも心細くなるでしょう。



そんな人のために、「遺言信託」という便利な制度があるのをご存じでしょうか。信託銀行では遺言書作成の相談から、遺言書の保管・執行業務までを行なっています。
先ずは、遺言信託の流れを見てみましょう。
これから遺言を作成したいという人なら、事前の相談から執行の完了まで、全てを入念に手伝ってもらえます。
事前の相談では、必要に応じて、専門の弁護士や税理士の協力をもらいながら、きめ細かなアドバイスが受けられます。



十分な話し合いの後、遺言書の作成に移ります。これは、安全確実な公正証書遺言に限られますが、遺言者が望めば「二名以上必要な証人」も信託を受ける側から出してくれます。
遺言書が完成すると、公正証書遺言の正本と謄本(各一通)を預かってもらえるので、万一紛失したり盗み見られるといった心配がありません。
その後、定期的に遺言の内容、財産、相続人の異動や変更の有無を照会してきます。
異動や変更の連絡を入れると、必要な変更手続きの相談にも乗ってもらえます。
遺言の執行においても、責任を持って「遺言執行者」になってくれるので安心です。
生前、自分が決めた通りの内容で、相続人や受遺者に遺産の分配が行われます。
執行が完了した時点で「遺言執行顛末報告書」が作成され、相続人や受遺者に報告がなされて一連の信託業務が終了します。



某信託銀行では、遺言書の保管と遺言の執行も含めて「遺言信託」と呼んでいます。遺言信託の手続きを順を追って見てみましょう。
- 遺言に関する事前の相談
- 遺言書の作成
- 遺言書の保管契約・財産の保護預かり
- 異動・変更の定期的照会
- 遺言執行者への就職
- 財産調査への協力
- 財産目録の作成・交付
- 遺言の執行・実現等
- 遺言執行終了の報告



但し、相続財産を相続人同士で納得して上手に分割できるような遺言内容や状況であれば、遺言書の保管だけで、遺言執行を依頼する必要がない場合もあります。
このように、安全確実な方法で遺言に関する一切を取り仕切ってもらえる遺言信託ですが、いったいどのような場合に遺言を残した方が良いのでしょうか。
一つには、相続上のトラブルが予想される場合です。
子供がいない場合(法定相続では1/4が兄弟姉妹に行くので、配偶者に全てを残すことができない)、特定の人を後継者にしたい場合、再婚していた場合などがこれに当たります。
次に、法定相続とは異なる配分を考えている場合です。
企業オーナーや農業を営む人は、事業の継続を意図した遺言を用意しなければなりません。
主な財産が自宅である場合、配偶者にこれまで通り住み続けてもらうにも遺言が必要になります。
また、障害を持つ子供に多くの財産を残してやりたい人もこのケースに当てはまります。
次に、分割方法を具体的に指示したい場合です。
遺言の中に細かく分け方を書いておけば、貴重な財産を効果的に分配できます。
また、法定相続人以外に財産分与を考えている場合は、遺言に書き残さなければ意思が伝わりません。
亡くなった子の配偶者や介護してくれた人に報いたいと願う人は、決して少なくないでしょう。



遺言が気になっている人は、是非一度、近くの信託銀行で尋ねてみては如何でしょう。
まとめ
信託銀行では、本来の銀行業務の他にも、財産信託や証券代行など幅広い業務を行なっています。
中でも近年利用者が急増しているのが「遺言信託」です。



サービス内容はどの銀行もほぼ同じで、遺言書の作成と保管、遺言の執行、遺産分割・納税の代行など、相続に関する煩雑な手続きをサポートしてくれます。
利用に当たっては、遺言書の作成・保管のみの依頼も可能。
その際は、被相続人の財産を確認した上で遺言内容のアドバイスを行い、公証人によって公正証書遺言が作成されます。
また、相続が開始された後で相続手続きを代行する「遺言執行サービス」では、相続人への遺言内容の説明、財産目録の作成、財産整理、遺産分割のサポートなどを行います。
特に財産が多い場合や、親族関係が複雑なケースでは、相続トラブルを避けたり納税対策としても有効。
広範囲に亘る手続きをスピーディーに済ませなければならない時には、便利なサービスと言えるでしょう。



手数料は各銀行によって異なりますが、遺言書作成なら初回で30~40万円(目安)+公証人手数料。遺言執行は、基本報酬の他に、財産総額に応じた手数料が必要です。
また、相続財産を預けると手数料を割り引くなど、特典を設けているところもあるのでチェックしておきましょう。
いずれにしても、大切な資産内容を伝えるわけですから、銀行選びは慎重に検討したいものです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。