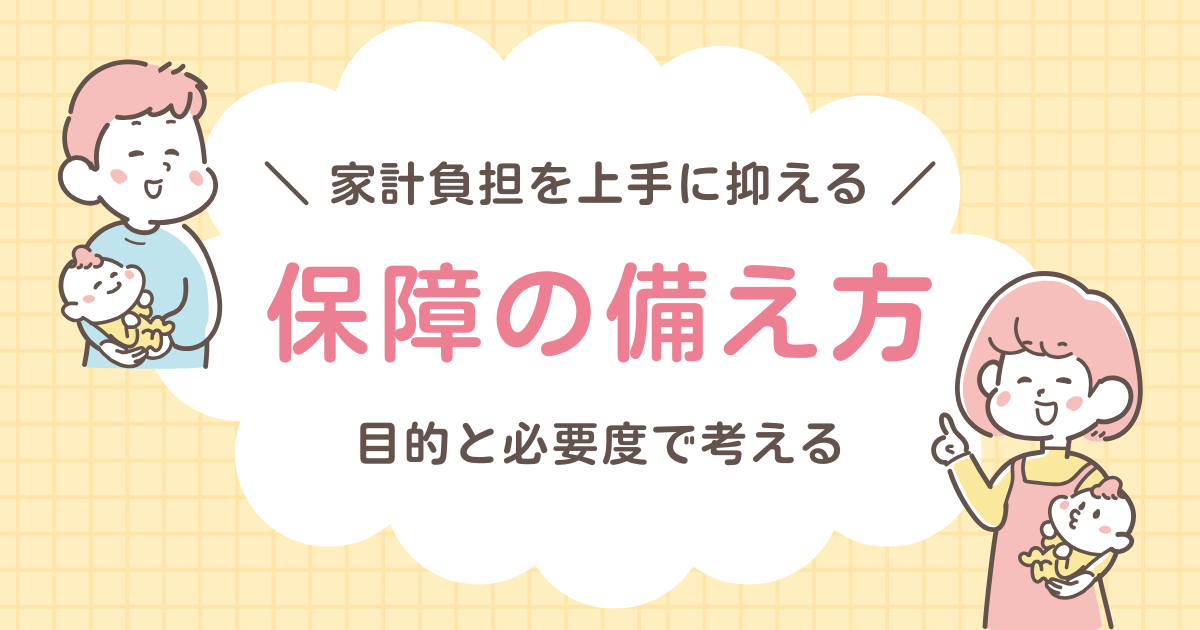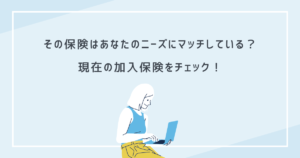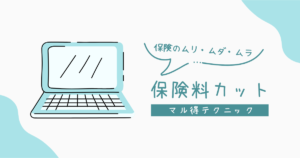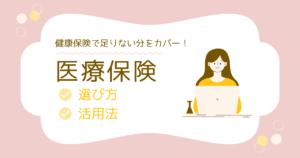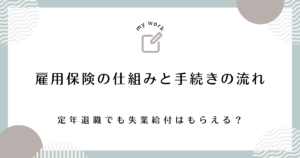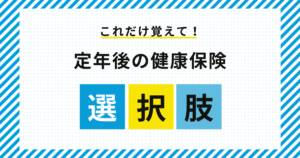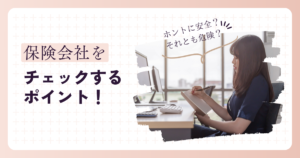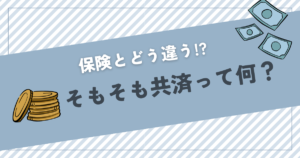悩める人
悩める人何に備えて加入するのか?



見直しのコツは?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 加入の目的
- 見直しの必要性
- 見直しのコツ
- 死亡保障の目的
- 医療保障の目的
はじめに
広く世の中に浸透しているにも関わらず、内容が殆ど理解されていない商品、その代表格が「生命保険」です。
日本では、全世帯の約89.2%もの世帯が何らかの形で生命保険に加入しています。
ところが、「どんな種類の保険に入っていますか?」「死亡保険金はいくらですか?」といった質問をすると、「え~と、死んだ時に保険金がおりるタイプです」「保険金は3,000万円だったかな?2,000万円かな?」「勧められるがままに加入したのでよく分からない」などと答える人が非常に多いのです。
例えば、洋服を買う時は色やデザインをチェックし、試着をして着心地や自分に似合うかどうかを確かめるものです。
また、値段も大きなポイントになります。
たかだか洋服1枚でも、このように色々な角度から検討します。
それなのに、どうして生命保険だけは、情報も集めず、勧められるがままに加入してしまうのでしょう。



保険も商品だということを忘れていませんか。あなたはお金を払って「保障」を買っているのです。
もちろん、保険のお世話になる事態が起こらない方が幸せです。
だからといって、適当に加入しておけば良いというものではありません。
自分の保険がどんな保障内容になっているか、きちんと答えられない人がいます。
用途も分からないものを買うなんて、普通はあり得ない話です。



こういう人は、一度じっくりと見直しをした方が良いと思います。いや、見直しはどんな人にも必要だと言えます。なぜなら、保険は家に次いで高い買い物だからです。
本格的な物価上昇が続く中、保険料を減らしたい人が増えています。
自分にとって必要な保障を見極めて、暮らしの安心を守りながら毎月の家計負担を上手に抑えましょう。
見直しのコツ
保障を見直す際、コツの一つ目は、「目的」を考えてみることです。
多くの人は、「何となく」入っていますが、先ず、これを止めることから始めましょう。
保険や共済に入る目的は保障を得ることで、「死亡保障」と「医療保障」の二つに大別できます。
自分や家族にとって必要なのは、死亡保障か医療保障か。
或いはどちらも必要なのかを考えます。
二つ目のコツは、保障の「必要度」を確認することです。
必要度に応じて、保障額を決めると良いでしょう。
では、それぞれの「目的」と「必要度」を見ていきます。
死亡保障の目的と必要度
死亡保障の目的は、遺族への生活保障です。
👇は、死亡保障が「必要」「あまり必要でない」の要素をまとめたものです。
- 社会人になっていない子供がいる
- 貯蓄が少ない時期
- 勤続年数が短い時期
- 子供がいる共働き夫婦の妻の分
- 独身(子供はいない)
- 共働き(子供はいない)
- 子供はすでに社会人
- 貯蓄がたくさんある



死亡保障の必要度は、社会人になっていない子供がいるか、いないかにより変わってきます。子供が社会人になるための年数が長いなら、必要度が増すので死亡保障額を多めに用意します。
貯蓄は万が一の際の生活を支える備えにもなるため、教育費や老後資金の準備ができていれば、保障額を減らすことができます。
また、公務員や勤務先に制度のある会社員は、在職中に亡くなると、勤務先から遺族へ死亡退職金などが支払われます。
これも保障の一部と考えることができ、金額は、勤続年数が短いと少なく、長くなるほど多くなります。



これを考慮すると死亡保障額は、若い世代ほど多めに、勤続年数が長くなるほど少なくすることができます。
必要な人に「子供がいる共働き夫婦の妻の分」とあるのはどういう意味でしょうか。
共働きの場合、夫は死亡保障を備えていても、なぜか妻は備えていないケースをよく見かけます。
子供がいて、二人の収入で家計を運営しているなら、夫だけではなく、妻も死亡保障が必要なのです。
医療保障の目的と必要度
次に、医療保障を見てみましょう。
医療保障の目的は、医療費の自己負担をカバーすることです。



注意したいのは、民間の医療保険等は、原則として「入院費用や手術費用」をカバーするものであり、医療費全般の負担を軽くするものではないことです。
加入する前に、先ず健康保険の「高額療養費制度」を知っておきましょう。
病院の窓口負担は69歳までは3割ですが、高額療養費制度より所得区分に応じた限度額があり、超過分は後日払い戻されます。
医療費の自己負担は青天井で掛かるわけではなく、一定の限度額が設けられているのです。
一般的な所得の人であれば、1か月の自己負担の目安は9万円前後です。
加入の健康保険によっては、更に上乗せの給付(付加給付)があります。
そのため、1か月の自己負担額が2~3万円といった健保組合は少なくありません。



ご自身が加入する健保組合のHPで確認してみると良いでしょう。公務員が加入する共済組合も付加給付があります。
医療保障の必要度が高いのは「入院リスク度」の高い人です。
要素を👇にまとめました。
- フリーランス(独身)
- 派遣社員(独身)
- 一人暮らし
- 正社員や公務員
- 健保組合・共済組合の付加給付がある
- 共働き(収入が分散されている)
フリーランスや派遣社員の人は、入院すると収入が減少する可能性があります。
特に独身だと働き手が一人なので、収入減は家計にダメージを与えます。



こうした要素の人は、ある程度の貯蓄が貯まるまで、医療保障で「入院リスク」をカバーします。
一方、正社員の人や健保組合加入の人は、入院リスク度が低いと言えます。
有給休暇がありますから、入院しても収入が途絶えることはありません。
高額療養費の付加給付があるなら、自己負担額は低く抑えられています。
また、共働きもリスク度が低くなる要因です。
このように「リスク度」を客観視して、医療保障の必要度を確認すると良いでしょう。
がん保障選びのポイント
がん治療は、長期間にわたることが多いです。
がんの三大治療とは、手術、抗がん剤治療、放射線治療で、近年、抗がん剤と放射線の治療は殆どが外来で行われます。
医療保障は、主に入院と手術の費用をカバーするものなので、外来での治療費は月々の収入や貯蓄から捻出することになります。



外来での治療が長引くがん治療の費用が心配な人は、がん保障で備えるのも一法です。がん保障タイプの商品選びのポイントは次の2つです。
- がん診断給付金が50万~100万円ある
がん診断給付金とは、がんに罹患した場合に一時金で支払われるものです。
まとまった額の一時金は、外来での抗がん剤・放射線の治療を受けた時に頼りになります。
- 保険料・掛け金は高くないものを選ぶ
保障はたくさん付けるほど、保険料や掛け金が高くなります。
がん保障も同様に、抗がん剤・放射線治療を受けた時に給付金が受け取れるなど、手厚くするほど家計への負担も重くなります。
がん保障は、がん診断給付金をメインとした「保険料や掛け金が低廉なタイプ」を選ぶと良いでしょう。



保障を得る「目的」と「必要度」を整理することで、見直しは自分でできます。暮らしの安心を守りながら、家計の負担を上手に抑えていきましょう。
まとめ
生命保険に加入しようという場合、必ず「目的」がある筈です。
例えば、死亡しても残された家族が生活できるよう加入する、病気やケガで入院しても医療費や住宅ローンが払えるよう加入する、といった具合です。
生命保険にはガンや介護といった個別の心配事に対して、ガン保険、介護保険といったピンポイントにニーズを満たすものもありますが、死亡すれば、その死亡原因が何であれ保険金が出る死亡保険や、老後になったら年金が支払われる生存保険、入院すれば入院給付金が出る医療保険などが基本的な保険となります。



大きく分けると、生命保険でカバーできる保障機能は、「死亡保障」「老後保障」「医療保障」の三つしかありません。先ずは、あれこれある心配事を、この三つの保障に分類してシンプルに考えることが大切です。
次に、保障の対象となる人それぞれに、これら三つの保障機能の優先順位を付けましょう。
全ての心配事に対して厚い保障が得られれば、これほど安心なことはありません。
ところが、安心しようとしてあれこれと保険に加入してしまうと保険料が高くなり、暮らしを圧迫することになってしまいます。



家族の一人ひとりにとって「本当に必要な保障の種類は何か」を考えてみましょう。そうすると、面白いことが分かってきます。家族の中の役割によって、必要としている保障の種類が大きく違うということです。
例えば、生計を維持している一家の大黒柱であれば、何といっても死亡保障が重要ですし、住宅ローンなどを抱えていれば医療保障も必要です。
働いていない妻であれば、死亡した時の経済的ダメージは小さいため、生命保険の重要度はそれほど高くありません。
怖いとすれば、貯蓄が少ない時期に、病気やケガで長期入院したら医療費を負担しきれないこと。
そこで、医療保障が重要になってきます。
また、女性の方が平均寿命が長い傾向にあり、夫よりも老後保障に対するニーズは高いようです。
子供については、病気やケガで長期療養した時のための医療保障で十分でしょう。
このように、一人ひとり優先順位が違うので、先ずは、あなた自身の優先順位を付けることが大切です。



ガンになったら、交通事故に遭ったら、介護状態になったら…。暮らしの中の危険(リスク)を心配し始めたらキリがありません。見直しの第1のポイントは、あなたが抱えるリスクに優先順位を付けることです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。