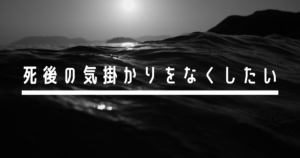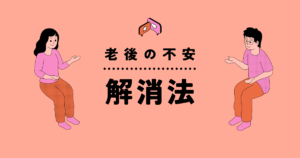悩める人
悩める人終活は、何歳ぐらいから始めるのが良いのか?
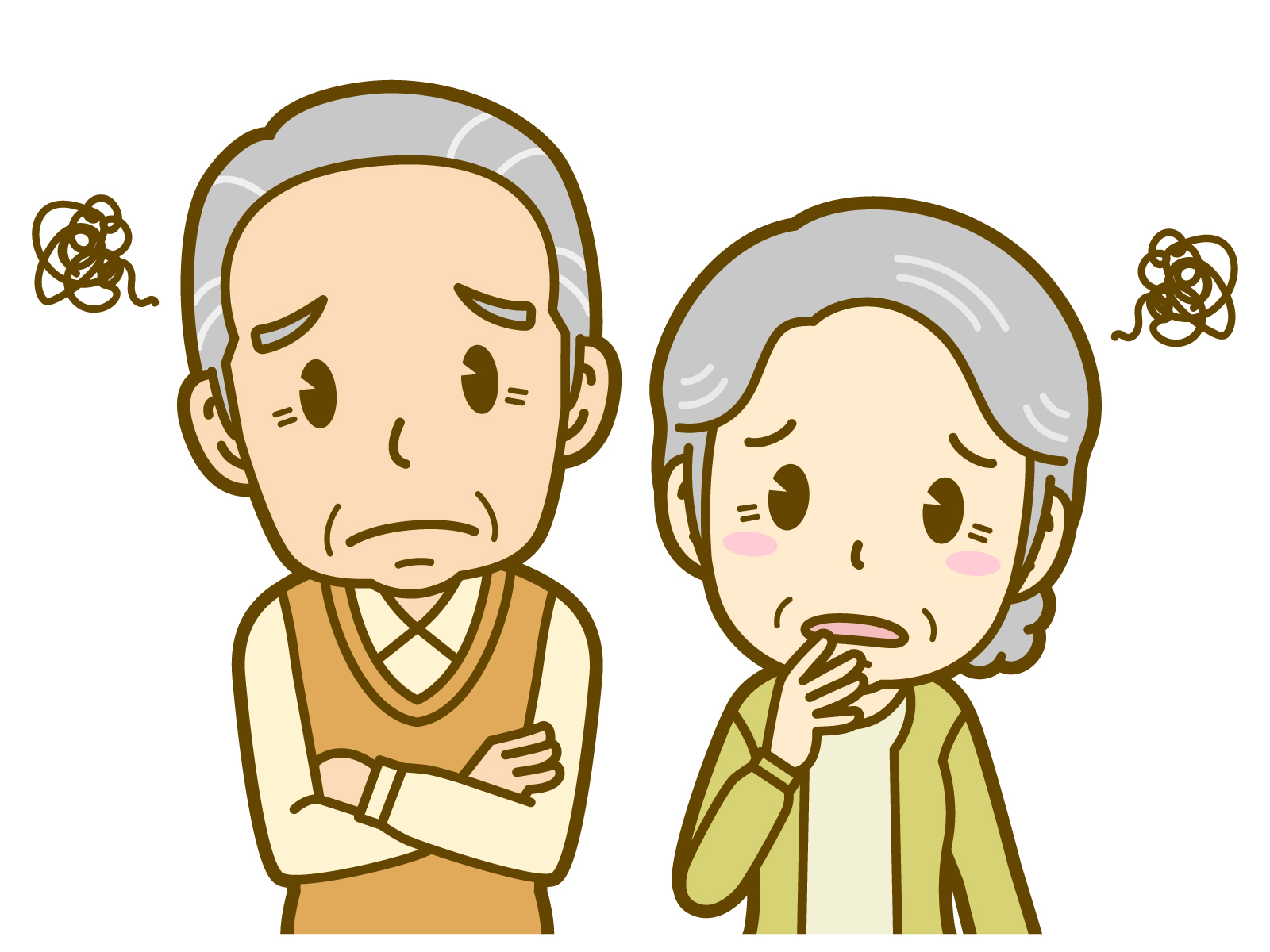
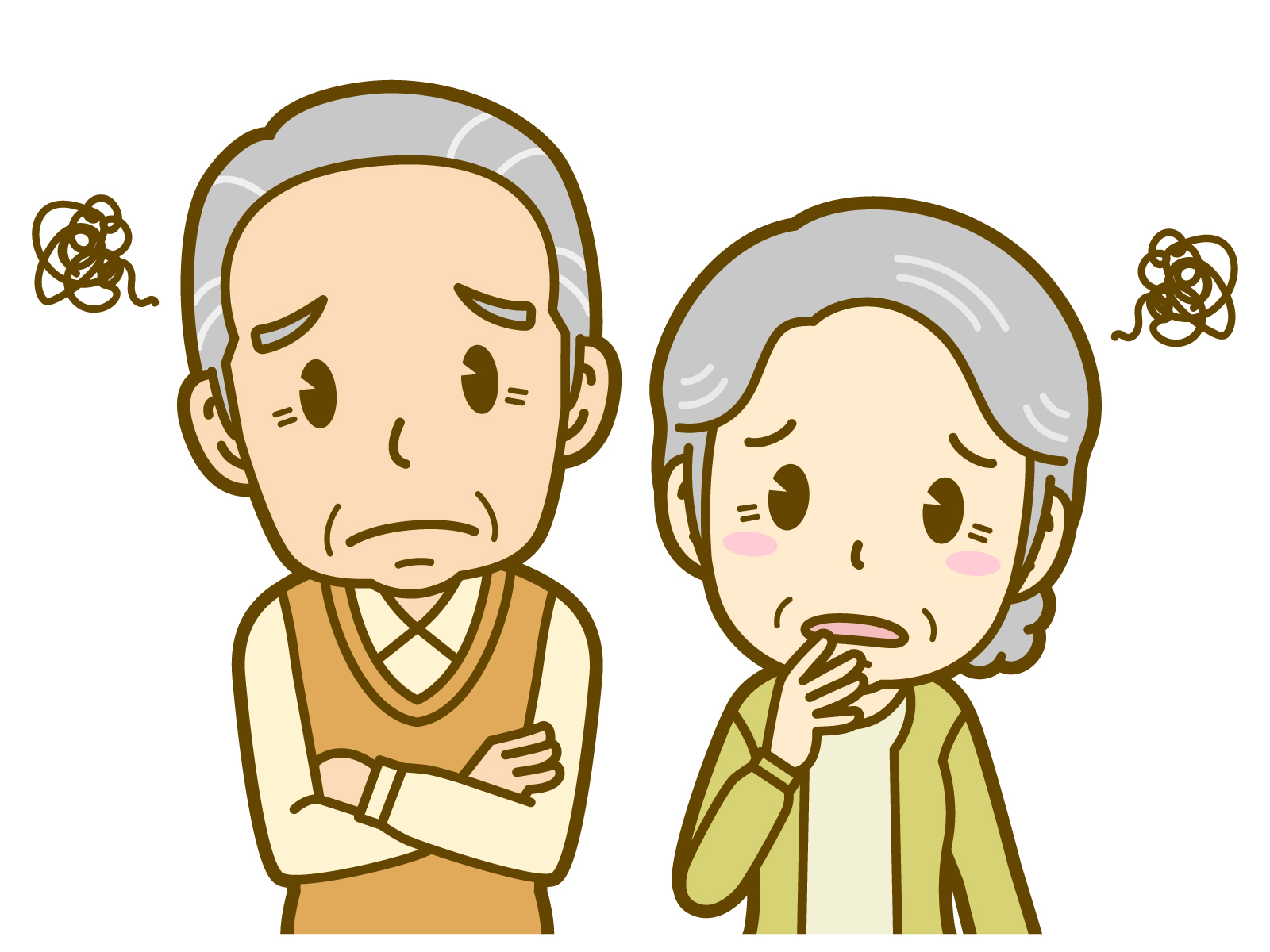
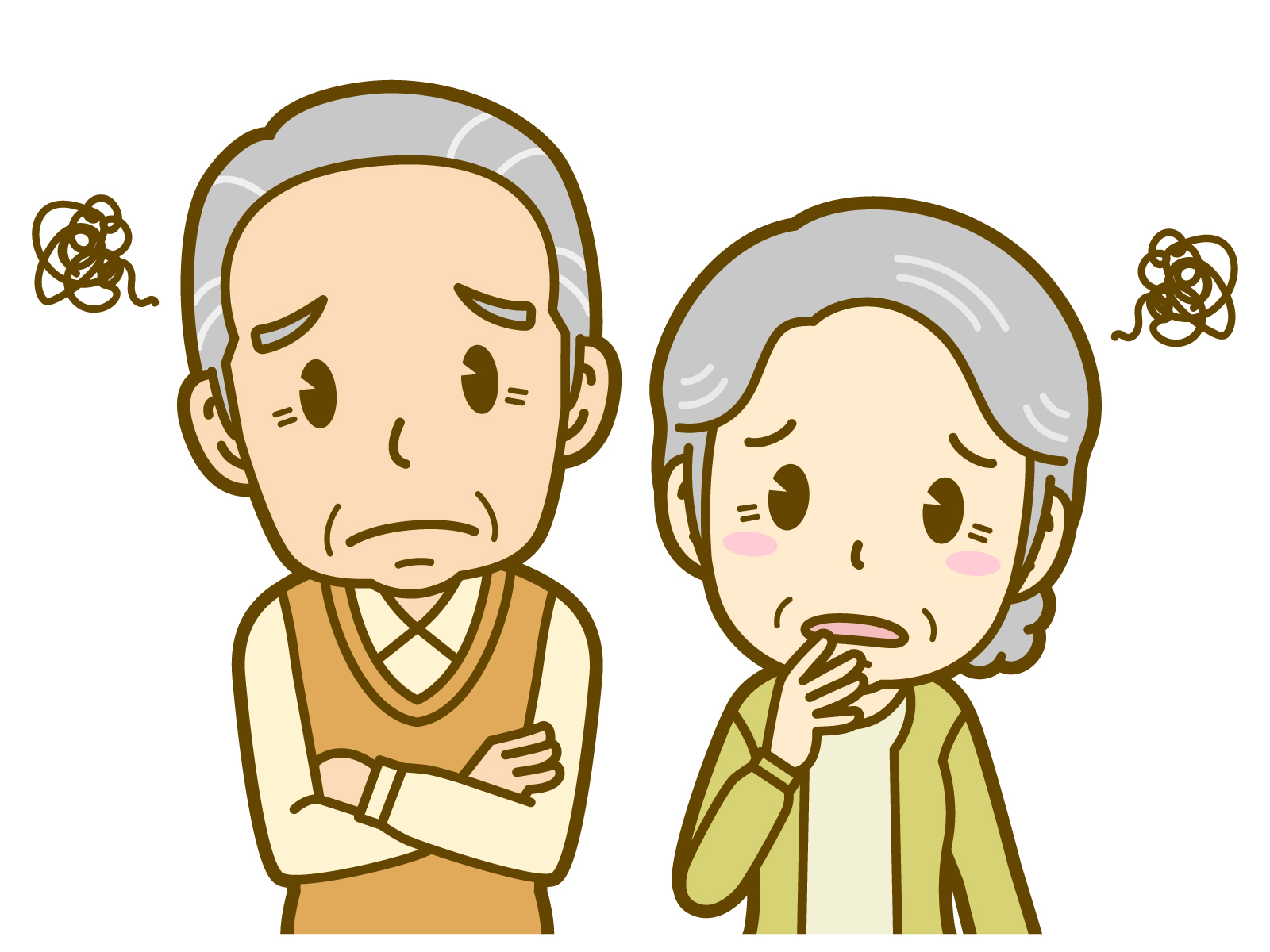
終活とは、具体的に何をすれば良いのか?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 終活とは
- 老いじたくの心得
- お墓について
- 葬儀について
- 相続について
- 生前整理について
- 終活のはじめどき
終活とは
近年、終活という言葉が、あちこちで聞かれるようになりました。
「人生の終わりのための活動」の略であるとか、「人生の終い方」のことであるとか、色々と定義されますが、その内容に鑑みれば、「後顧に憂いを残すことなく、人生を謳歌するための人生設計」のことであると考えた方がしっくりきます。



つまりは、「これからの人生を、より良く生きるための準備活動」だという定義の方が相応しいと言えます。
終活という言葉自体は、一説によれば、2009年にある週刊誌の編集者が最初に使ったとされていますが、翌年2010年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、以降、着実に社会的な認知を得るようになってきました。
今日では、終活という言葉を知らない人の方が少ないくらい、一般化しています。
本ブログ読者の中にも、既に終活に取り組んでいるという方が少なくないのではないでしょうか。
どんな活動のことを言うのか?
さて、これほど社会的に認知されている終活ですが、具体的にどんな活動をするのでしょうか。



終活としてどんなことをするのか、については色々な考え方もあり、必ずしも一様ではありませんが、一般的には次のような課題について考えたり、準備をしたりすることを指すようです。
- お墓をどうするか
- お葬式をどうするか
- 遺産相続をどうするか
- 身の回りの整理(生前整理)
これら四つの項目に、「介護が必要になった時にどうするか」ということを加える考え方もあります。
いずれにしろ、ここで取り上げたような課題について、自らの意思で、予め決めておくことで、いざという時に、本人はもとより、家族が慌てることのないように準備することが終活だと言えます。
かつては、2世代・3世代が同居するような大家族が多く、世代を超えたコミュニケーションが緊密でした。
また、地域社会との関係性も密接であったことから、万が一の場合の備えや、地域社会との協力体制等が機能しており、何か分からないことがあっても、誰かが教えてくれたり、手助けしてくれたりしました。
しかし現代では、世帯が核家族化し、また生活拠点の流動化も進んだために、地域コミュニティの関係性が希薄になってきています。
そのため、例えば親が亡くなった時に、誰に連絡をして、どのように葬儀式を進めれば良いのか分からない、ということも増えてきています。
そうした社会構造の変化を受けて、子世代に面倒なことを任せるのではなく、自分の死後のあれこれを予め決めておくことで、子世代に迷惑を掛けないようにしたいという意識が高まっているのです。
子世代に迷惑を掛けたくない、ということが、終活の大きな目的になっていることは事実ですが、同時に、終活をすることによって、後顧の憂いがなくなり、自分の人生を思う存分謳歌できるという側面もあります。



最近では、子世代に迷惑を掛けないために、予め決めるべきことを自分で決めておくことが、結果的に自分の人生を楽しむことに繋がるという意識も広がっているようです。
具体的に何をすれば良いのか?
では、終活として、具体的に何をすれば良いのか、ということについて見ていきましょう。
某マーケティングリサーチ・コンサルティング会社の調査によれば、具体的な終活として考えていることは、第1に「生前整理」、第2に「葬儀費用等の準備」となっています。
そして、終末期の希望をまとめておいたり、相続の準備をしたりするということが続きます。
遺言書を書いたり、エンディングノートを準備したりするといったことは上位にはありませんが、これらはそれ自体が終活の具体的内容というよりも、「どのような形で終活の結果を残すのか」という手段の話であり、決して終活における重要度が低いということではないことを理解しておく必要があるでしょう。



つまり、自身の葬儀をどうするかを決め、決めたことを遺言書やエンディングノートに書き示す、ということです。
最近では、自分の葬儀をどのようにするのかを事前に葬儀社に依頼しておく「葬儀式の生前予約」を受け付けてくれる業者も多く、自身の死後、遺族に見てもらうエンディングノートにその旨を書き付けておくことで、遺族に負担を掛けないようにするということも増えているようです。
エンディングノートは、色々な種類が市販されていますので、そうしたものを活用しても良いでしょうし、また、形式にとらわれず、一般的なノートに書き記すということでも問題はありません。
本人しか分からない情報がエンディングノートにまとめてあれば、亡くなった後の手続きをスムーズに進めることができ、残された家族は随分助かるでしょう。
亡くなった人の希望や気持ちも伝わります。



重要なのは、「きちんと記録を残す」ということなのです。エンディングノートに、決まった形式はありません。何回書き直しても構いませんし、書きたいところだけ書いても良いのです。
老いじたくの心得
- 元気なうちから時間を掛けてスタートする
財産整理や相続といったお金に纏わることから、医療、お墓、葬儀に関することまで、決めることは多岐にわたります。
想像以上に時間が掛かるため、できるだけ早くから始めると安心です。
- 自分の「好き」を振り返り、自分の「思い」を優先する
「本当は自宅で最期を迎えたいけれど、家族に負担を掛けたくない」など、終活に関する事柄は家族に遠慮をしてしまいがち。
しかし、先ずは自分の気持ちに素直になり、どうしたいか考えてみましょう。
- 終活はコミュニケーション(家族との対話を忘れない)
家族のために良かれと思ってしたことが、実は家族にとっては迷惑だったということもあります。
先ずは、自分の希望を伝え、家族の意見を聞いて決断を下すのが、自分も家族も笑顔になる終活の秘訣です。
- 楽しくポジティブな気持ちで取り組む
終活は決してネガティブなものではなく、自分の過去の思い出や自分の趣味嗜好などを見つめ直し、人生の晩年を充実させてくれるもの。
幸せな晩年を過ごすためにも、ポジティブな気持ちで取り組みましょう。
- エンディングノートは定期的に見直しを
終活で最初に取り組んでほしいエンディングノートは、早くから書き始めた方が良いですが、自分の考えは年齢や環境の変化などで変わるので、一年に一度のペースを目安に見直すことをお勧めします。
お墓について
先祖代々のお墓があり、そこがご自身の墓所になるのであれば、終活としてのお墓の問題はないということになります。
しかし、自分の入るべきお墓が決まっていないのであれば、予め準備をしておくことは必要です。



「生きているうちから、お墓のことなんて…」と思われる人もいるかもしれませんが、生前に自身のお墓を用意しておくことは、昔から行われていました。近年、終活の一環として、ご自身のお墓を用意される人は、少なくないようです。
お墓が必要かどうかを考える
先ずは「お墓が必要かどうか」を考えることが第一歩です。
お墓を建てるというのは、そのお墓を子々孫々にわたって継承していくことが前提となります。
そのため、子世代や孫世代にお墓を継承してもらうことが難しい場合には、必ずしもお墓が必要ということにはなりません。
その場合には、永代供養墓等を検討することになります。



永代供養墓もお墓の一種ではありますが、墓石を建てるのではなく、寺院や霊園側が、半永久的に、或いは一定期間、お骨を管理し、供養してくれるというもので、無縁墓・無縁仏になってしまう心配がありません。
また、最近では室内墓苑(屋内型永代供養墓)と言われる形態も人気が高まっています。
都市部等では新たに霊園を造ることが難しいため、増加傾向にあります。
霊園は郊外にあることが多いのですが、室内墓苑は、都市部で交通の便の良いところが多く、お参りしやすいというメリットもあります。
どんなお墓にするかを考える
墓所(墓地)を手当てし、墓石も建てる、ということであれば、先ずは「墓所選び」です。
墓地は経営母体によって大きく3種類に分類されます。
1つ目が「公営墓地」。
地方公共団体が管理・運営するものです。
公営墓地に対する「民営墓地」には、公益法人や宗教法人による「公園墓地」と、寺院に付属する「寺院墓地」の2種類があります。
公営墓地は費用が安く済むというメリットがある反面、人気が高く、抽選になることが殆どで、なかなか希望通りに購入することが難しいという側面もあります。
民営墓地は、公営に比べれば費用は高くなりますが、公園のように整備されていたり、区画等のバリエーションが豊富であったりと、好みに合わせて選べるというメリットがあります。



尚、寺院墓地の場合、そのお寺の檀家になることが必要条件であることも少なくないので、注意が必要です。
葬儀について
お葬式を行う意義には、宗教的な意味合いも多分にありますが、同時に故人の関係の方々にきちんとお知らせするという社会的な意味合いもありますし、また、遺族の心の整理のための通過儀礼という側面もあります。
近年では、お葬式を営まず、お別れ会のようなものを催すというケースも増えているようですが、これは宗教的な意味合いを除いていても、関係の方々に知らしめるという社会的な意味合いに重きを置いているということであり、決して「葬儀不要」という意識ではなく、お葬式の一つの形態であると考えるのが妥当でしょう。



近年、近親者だけで行う「家族葬」が増えています。これは、お葬式の意義の中でも、とりわけ「遺族の心の整理」に重きを置いたお葬式の形と言えます。
家族葬とは、家族を中心に近親者やごく親しい関係にある人だけで行う葬儀のことです。
会葬者がごく親しい人たちに限られることで余計な気遣いをせずに済み、遺族や会葬者が故人とゆっくりお別れができるのが特徴です。
家族葬のメリット・デメリット
家族葬の大きなメリットは、弔問客が限定的で少ないことから、接客応対に煩わされることなく、親しい人たちだけで、じっくりと故人とのお別れができるという点にあります。
よく「家族葬は費用が安く済む」ということをメリットだと喧伝されることもあるようです。
家族葬は、通夜振る舞いなどの飲食接待費や返礼品などの費用は掛かりませんが、棺、遺体を運ぶ車両費、火葬場の利用料金などは掛かります。
また、友人・知人に参列していただく場合は、もてなしの費用も必要です。
一方で、弔問客が少ないために香典による収入があまり見込めないことも覚えておきましょう。



確かに、弔問客に対する振る舞いや、返礼品の用意がないことで、結果的に費用が安くなることはありますが、決して「家族葬=費用が安い」というわけではないことに注意が必要です。
また、デメリットとしては、家族葬にすることで、訃報をお伝えする範囲も限定的になるために、後日、自宅の方へ弔問に来られる人が増え、そうした個別の対応が必要になることも少なくないということが挙げられます。
家族葬が良いのか、一般葬が良いのかについては、こうした点を考慮して選択することが肝要です。
生前予約
万が一、親が亡くなったというような状況に直面した時に、遺族の人が最も困るのは、誰にお知らせすれば良いかということです。
親戚関係はともかく、友人関係や仕事の関係先等については、予めリスト化しておくことが肝要です。
また葬儀については、葬儀業者が細かくサポートしてくれるので、実施に当たって困ることは少ないかもしれません。
しかし、祭壇をどうするのか、弔問客への返礼品をどうするか等々、その場で判断しなければならず、思った以上にお金が掛かってしまったということにもなりかねません。
そうならないためには、予めご自身でそうした細々したことを決めておくことが得策です。



最近では、生前予約と言って、式次第一式を予め決めておくというサービスを提供してくれる葬儀業者もあります。予算についても、予約の時点で決まっているので、実施後に高い金額を請求されるということも防げます。
相続について



相続について、きちんと考え、どのような相続を実行するかについて、予め明確にしておくことは、終活において、とても重要なポイントの一つと言えます。
相続についての考え方
相続について事前に考える際には、次の二つの視点を重視する必要があります。
- 遺族の間に争いが起きないように公正な相続を考える(A)
- 相続税の負担が遺族に圧し掛からないように節税対策を考える(B)
Aについては、言うまでもなく、「残された財産を、相続人間でどのように分割するか」ということです。



相続人の間で不公平感が残ってしまうような財産分割をしてしまうと、相続が、「争族」或いは「争続」になってしまうのです。
遺産相続に当たっては、法律で相続人の範囲が決められています。
もちろん、被相続人の意思で、法定相続人以外の人に財産を分与することもできます(遺贈)。
しかし、法定相続人には、遺留分といって、一定の法定相続人に最低限残しておかなければならない一定の財産割合が決められています。
この遺留分を下回る財産しか分与されない相続人が納得しなければ、法律に基づいて、他の相続人に請求をすることができます。



相続が「争族」になってしまう原因の一つには、こうした不公平感が生まれるような相続財産の分割をした場合が少なくないので、注意が必要です。
相続税に関する基礎知識
次に考えなければならないのが、相続税対策です。



相続税には、一定の基礎控除という制度があり、相続人の人数と、相続財産の総額によっては、相続税が掛からないケースがあります。
- 相続税の総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)=課税される遺産総額
また、基礎控除額を上回る財産額(課税遺産総額)に対して相続税が課税されますが、税率は相続額によって異なりますので、終活に当たっては、相続財産がどのくらいになるのかをきちんと整理した上で、相続税がいくらになるのかを予め計算し、納税資金をどうするかについてもしっかり計画しておくことが肝要です。
生前整理について
一般的に「生前整理」とは、ご自身の生活空間を整理整頓して、身の回りのものを片付けておいたり、資産の状況等について財産目録等にまとめたり、また最近ではインターネット上のSNS等を後々消去できるように、IDやパスワード等を記録しておくことを指します。
自身が亡くなった後に、残された家族等が困らないようにすることが大きな目的ではありますが、同時に、ご自身がより豊かに人生を謳歌するための準備でもあります。



特に、自身の生活空間を整理整頓しておくことは重要です。高齢者は、加齢と共に身体機能が衰えていくもので、家の中が乱雑だと、思わぬ事故を起こしてしまう危険性が高まります。
よく家庭内事故としては、お風呂場での事故(ヒートショック等)が取り沙汰されることが多いのですが、内閣府の「平成30年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の高齢者の家庭内事故の約半分は居室(居間や寝室等)で発生しており、風呂場等での事故発生割合は意外に低くなっています。
部屋の中が乱雑だと、電気コードに足を引っ掛けてしまったり、カーペット等のちょっとした段差につまずいてしまったりと、転倒事故になりやすいのです。



高齢者の場合には、骨折等が切っ掛けで寝たきりになってしまうこともあるので、健康寿命を延ばすためにも、身の回りを整理整頓しておくことは大切なことなのです。
生前整理を進める上では、先ず「不要なモノを捨てる」ことが大事です。
ひと頃、「断捨離」という考え方が流行しましたが、終活においても、この考え方は有効です。
不要なモノを処分した上で、生活空間を整理整頓し、家庭内事故が発生しないようにすることが生前整理の第一歩だと考えましょう。
また、同居している家族が多い場合には、何事につけ家族と話をすることで、万が一の際に家族が困ることは少なくなるでしょうが、もし高齢のご夫婦のみ、或いは単身世帯であれば、大切なことは必ず記録を残すように心掛けることも大切です。



最近では、「エンディングノート」と言って、終活のための記録ノートが市販されています。そうしたノートを有効活用することも、終活を円滑に進める一助になるかもしれません。
終活を始める時期



終活は、何歳ぐらいから始めるのが良いのですか?



不安を感じた時が、終活をスタートさせるタイミングです。終活最大のメリットは「不安の解消」です。
終活をどのように捉えるかによって、適切なタイミングは違ったものになります。
必ずしも「何歳になったら取り組むべき」というようなものではありません。
早い人ですと、50代で終活を始める人もいるようです。
ただ、平均的には、70歳くらいで始める人が多いようです。



私は、終活を「自分が死んだ後のこと」を考えたり準備したりする活動だとは捉えていません。もちろん、そうしたことも終活の一部ではありますが、それらに加えて、「これから先の人生を、どうやって自分らしく過ごすか」ということも、終活の重要な視点だと考えています。
ですから、介護が必要になったらどうしたら良いのか、認知症を患ってしまったらどうしたら良いのか、ということを、元気なうちに考えることも「終活」と考えています。
歳を重ねていくと、色々な不安が心を過るようになります。
しかし、自分一人で悩んでいても、なかなか解決できないことも多いのです。



しかし、解決策はたくさん用意されています。自分が不安に思うことについて、何らかの解決策を事前に用意することができれば、その不安を抱えたままで過ごすこともなく、自分らしい人生を送る大きな助けとなると思います。
終活とは、そのように、自分が不安に思うことに解決策を予め見つけておいて、心配事に煩わされることなく、人生を楽しむための活動とも言えると思います。
ですから、「自分の将来に何かしらの不安を感じた時」が、終活の始めどきだと思うのです。
- これからの自分の生活をどうすれば良いのか…
- 認知症になってお金の管理ができなくなってしまったら…
- もし自分が寝たきりになったら…
- 介護が必要になったらどうしよう…
- お墓や葬儀の準備も自分でするべき?
- 遺品整理をどうすれば良いか…
- 死んだ後、私の財産ってどうなるの?
こうした不安や、心配事については、きちんとした終活をすれば、解消できることが多いものです。
要は「分からない」から不安になるのであり、「どうすれば良いか」が明確になれば、それだけで多くの不安や心配事が、かなり解消される人もいると思います。
一番辛いのは、「どうして良いか分からない」という不安な状態をずっと続けることなのです。
エンディングノート



終活をやろうと決めたら、最初に何をすべきですか?



エンディングノートを活用することが最も効果的です。そして、不安を覚えたら、自分で抱えずに、誰かに相談することが大事です。
いざ終活をしようと決めても、いったい何から始めたら良いのか戸惑う人が多いと思います。
そんな人には、エンディングノートを活用することをお勧めしています。
これはあなたの身の回りや財産についての情報や、家族に対する気持ちなどを1冊にまとめて書くものです。
エンディングノートは市販のものがたくさん販売されているので気に入ったものを使っても良いですし、自分でノートに書き出しても構いません。
「市販のエンディングノートだと、埋めなくてはいけないページがたくさんあって大変そう…」という人は、好きなページから書き始め、書きたくないページは飛ばして書いてOKです。
エンディングノートは、自分の頭の中や身辺の整理にも使えますし、あなたが亡くなった後に家族が読んだとき、あなたが何を考え、どんなことを希望しているのかが分かる1冊になります。
こうしたツールを上手に活用することで、きっと終活は上手くいくと思います。



誰でも、加齢と共に色々な心配事が出てくるものです。でも、その心配事を漠然と不安に思い続けるのか、誰かに相談して、解決策を見つけておくのかが、その先の人生を、明るく豊かなものとするかに、大きく関わってくると思います。
まとめ
終活という言葉は、ここ15年で急激に普及し、今や殆どの人がその言葉を一度は耳にしたことがある時代となりました。
しかし、実際に終活をしている人は、まだそこまで多くないのが実情です。
日本では、「何となく死を連想することを遠ざけたい」という風潮があり、「縁起が悪い」と感じる人も少なくないようです。



しかし、終活は決してネガティブなものではなく、今までの人生を振り返りこれからの人生をどう生きていくかを考えることで、最後まで自分らしい人生を楽しく送るための手引きとなる存在です。
死の間際「こんな筈ではなかったのに…」と、後悔や不安を抱くことがないように、明るくポジティブな気持ちで終活に取り組んでみましょう。
終活というと多くの人がイメージするのは、「相続」に関することではないでしょうか。
もちろん相続や財産に関わることは非常に重要な要素の一つですが、それ以外にも、介護や医療、お墓、葬儀といった人生の晩年や死後に纏わる様々な事柄が挙げられます。
こうした事柄に対し、それぞれに自分の考えや希望をまとめたり、手続きをするのには想像以上に多くの時間が掛かります。
「まだ終活なんて自分には早い」と思っていると、あっという間に時間が経ち、終活が中途半端のまま終わってしまうということも…。
また、人間は誰しも歳を重ねれば体力や気力が衰え、何か新しいことを始めたり決断したりするのが億劫になるものです。
体が不自由になれば、手続き一つするのも一苦労となるでしょう。



そうなる前に、できることは元気なうちから少しずつ始めるのが満足のいく終活をするためには非常に重要となります。
そして何より大切なことは、自分の過去を振り返り、後悔のない幸せな人生を締めくくるには、今後どうすれば良いか自分の心を見つめ直すこと。
気持ちの棚卸しをすることが、終活の最初の一歩と言えるでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。