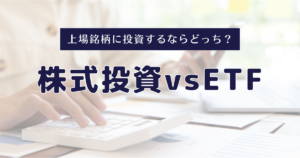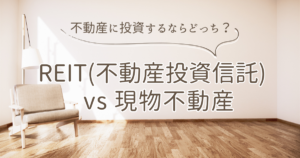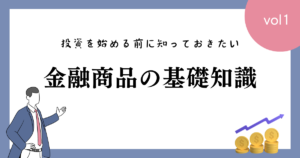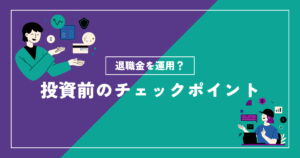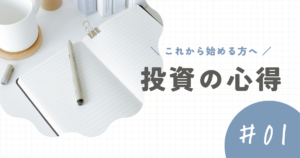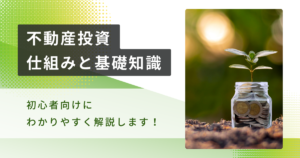悩める人
悩める人投資信託をよく勧められるが、検討する際のポイントは?



投資信託の主なメリットとリスクは?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 投資信託の仕組み
- 投資信託の分配金
- 投資信託のコスト
- 投資信託のメリットとリスク
- 投資信託の運用方式
- 投資信託の種類と特徴
- 投資信託の取引方法
- 運用する際のポイント
投資信託の仕組み
初めて資産運用をする場合、幾つかのハードルがあります。
それは、
- 運用や投資に関する知識を深めること
- 運用資金を貯めること
- 定期的に資産状況を確認する時間を設けること
などです。



このハードルを乗り越える手段が投資信託です。先ずは、投資信託の仕組みを押さえておきましょう。
投資信託は、大勢の投資家から資金を集め、複数の株や債券、不動産などで運用することから、一般的に「ファンド(基金)」と呼ばれています。
投信委託会社と呼ばれる「運用会社」が投資信託を設定、運用指図をし、「管理(受託)会社」と呼ばれる信託銀行が市場を通じて売買を行い、顧客資産を保管・管理しています。
また、「販売会社」である銀行や証券会社は、投資信託を多くの投資家に説明・販売をするという形になっています。



投資する銘柄や運用の手法などは、プロである「ファンドマネージャー」が行なってくれますので、資産運用の初心者でもすぐに取り組みやすいという特徴があります。
要は金融市場のあらゆる商品を対象に、運用の専門家が運用方針や収益予測に基づいた商品を開発します。
それを販売会社がより多くの投資家に投資してもらい、収益を目指していく金融商品です。
他の運用法のように、投資家自身が運用方針や手法を考える必要はありません。
専門家の運用を基に株式や債券などに投資できるので、他の商品と比べて「手間や費やす時間が掛からない運用法」でもあります。



また、大勢の投資家から資金を集めて、株や債券、不動産など運用方針に沿って複数の投資を行う仕組みですので、少額から投資ができます。
投資信託は、通常1万円から購入できますが、近年ではネット系の証券会社を筆頭に100円や500円からでも購入できるようになっており、手軽に始められる投資としても注目を集めています。
投資信託のリターンは、投資信託自体の運用成績によります。
例えば、ある投資信託が投資家から集めた資金(純資産総額)100億円で運用を開始したとしましょう。
この投資信託の運用が上手くいけば、この純資産総額は運用益により増加します。
仮に105億円に増加した場合、単純に利益率は5%ですので、投資家も5%のリターンを得ているということになります。
分かりやすく言えば、1万円で買った投資信託が、1万500円に値上がりしたということになります。
このように投資信託では、運用により価格が変動します。
この価格を「基準価額」と言い、株価と同様に毎日変動していますので、運用結果が悪い時には当然下落することになります。
基準価額の変動と同時に、預かり資産(純資産総額)も増減しています。
運用が上手くいっている投資信託は、基準価額も上がり、純資産総額も増加しています。



単純に言えば、基準価額が1万円の時に買った投資信託を、1万1千円で売れば、その差額に口数分を掛けた金額が利益となり、反対に下がっていれば損となります。
投資信託では先ず、「運用する期間」を考えることが必要です。
投資信託は、専門家が運用方針を定め、運用率を高められるように、株や債券などに分散投資するもの。
よって、短期的に値上がり益を狙うものではないことを理解しましょう。
当然、投資の手段によって損得はありますが、中期から長期の運用を通して、リスクの平準化(平均化)を図りながら、収益を目指すという考え方になります。
投資信託の分配金
投資信託には、分配金というインカムゲインがあります。
分かりやすく言えば、株式の「配当金」と似た性質のお金です。
例えば、毎月分配型と書かれている投資信託は分配金が月々受け取れるタイプです。
投資家としては、ちょっとした収入になり、投資している実感が得やすくなります。



但し、投資信託の中には分配金がないものもあります。どちらを選ぶか迷った時のために、違いを押さえておきましょう。
普通・特別分配金
分配金とは、投資家から預かった資金を運用し、生み出された利益の一部を決算ごとに投資家に還元するお金です。
運用益から払われる分配金のことを「普通分配金」と言います。



但し、運用結果によっては分配金の額が減ったり、分配金が払われないこともあります。この点が、銀行の利息と異なるところです。
運用益が出ていない時に分配金を出す場合は、投資信託が集めた資産の中から払わなければなりません。
このお金のことを「特別分配金」と言います。
投資元本を取り崩して支払われます。
分配金は、元本を取り崩して支払われるため、実際には得しないことも。



投資信託は株などで運用するため、必ず運用益が得られるわけではありません。そのため、分配金として支払うお金が足りない場合は「純資産を削って」払わなければなりません。
いずれも投資信託の資産総額から支払われますが、普通分配金は投資の利益ですので、受け取る際に税金(配当所得)が掛かります。
しかし、特別分配金については投資家が投資した資金が分配金として戻ってきているのと同じです。
そのため、利益とはならず、非課税扱いになります。
再投資(無分配)型
分配金なしの投資信託は、「再投資型」と呼ばれます。
このタイプには分配金がありませんので、インカムゲインが得られません。



そう書くと「損なのでは?」と感じるかもしれませんが、そうではなく、むしろ運用効果としては得になります。
再投資型は、運用益を再び投資信託の資産に組み入れ、投資(再投資)する仕組みです。
例えば、投資信託の純資産総額が100億円で、今年の運用益が2億円(2%)だったとしたら、純資産総額は102億円になります。
一方、分配金ありの投資信託は運用益を投資家に還元します。
分配金の支払い総額が2億円だったとしたら、支払いを終えた段階で純資産総額が102億円から100億円に戻ります。
この「2億円の差」がポイントです。
仮に翌年の運用益がどちらも2%だった場合、再投資型は2億400万円の利益を得ます。
一方、分配金ありの投資信託は純資産総額が100億円に戻っていますので、利益は2億円です。



つまり、分配金となる資金を再投資することにより、より大きなリターンが得られる複利効果となります。
このような特徴があるため、投資効率を高めたい場合は「再投資型」を選ぶ方が有利になります。
投資信託に掛かる主なコスト
投資信託は自分に代わってプロに運用をしてもらうわけですから、その分のコストも掛かります。
投資信託には、主に3つの手数料があります。
- 購入時(販売)手数料
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
「購入時(販売)手数料」が掛かるのは購入する時だけですが、「運用管理費用(信託報酬)」は利益を出せたかどうかに関わらず、保有している期間中ずっと信託財産から差し引かれます。
- 購入時手数料 … 購入時に販売会社(銀行や証券会社など)に支払う手数料のこと。投資信託の購入額に一定の率を掛けた額で、その率は投資信託によって異なる。購入時手数料が掛からないものは「ノーロード型ファンド」と呼ばれる
- 運用管理費用 … 保有している間、運用・管理などの対価として、間接的に負担する費用のこと。年率で表示されており、投資信託によって異なる。利益を出せたかどうかに関わらず、日割り計算で信託財産から自動的に日々差し引かれる。支払った運用管理費用は、運用会社・販売会社・信託銀行で配分される
- 信託財産留保額 … 途中で売って現金化する時(解約時)に徴収される。売った際の代金から差し引かれる。率などは投資信託によって異なる。但し、徴収されない投資信託もある。償還時には掛からないが、稀に購入時に掛かる投資信託もある



投資信託は証券会社の他、銀行などでも購入できます。同じ商品でも販売会社によって手数料などの条件が異なる場合もあります。商品を検討する際はチェックしましょう。
購入時(販売)手数料
先ずは、投資信託を購入する際に、販売会社である銀行や証券会社に払う「購入時(販売)手数料」です。
金額としては投資信託の価格の5%以下のものが多く、手数料が掛からない「ノーロード型」と呼ばれる投資信託もあります。



販売手数料について重要なのは、投資信託を購入する度に発生するという点です。そのため、購入頻度が多い人ほど注意が必要です。
運用管理費用(信託報酬)
2つ目は「運用管理費用(信託報酬)」と呼ばれるもので、投資信託を保有している間に発生します。
運用管理費用(信託報酬)は、分かりやすく言えば、投資先の入れ替えや組み入れ銘柄の売買などを行うための管理費です。
そのため、運用の手間が掛かる投資信託は高く、掛からない投資信託は安くなります。
例えば、積極的にリターンを狙うアクティブ型は、銘柄を厳選し、細かく入れ替えます。
つまり手間が掛かるため、運用管理費用(信託報酬)も高くなります。



この手数料は「運用会社」「販売会社」「信託銀行」それぞれに分けて支払われます。投資信託の残高に応じて「年率数パーセント分」と決まっており、毎日資産から差し引かれます。
ただ、仮に運用管理費用(信託報酬)が安かったとしても、保有期間が長くなるほど手数料負担は積み上がっていきます。
そのため、中長期で保有しようと考えている人ほど運用管理費用(信託報酬)が安い投資信託を選ぶことが重要になります。



少なくとも「信託報酬の率よりも運用実績の高いファンド」を選ばないと、利益になりません。
信託財産留保額
3つ目は、投資信託を売却し、換金する時に掛かる「信託財産留保額」です。
このお金も、売買の頻度が多くなるほど負担になります。
ただ、購入時(販売)手数料や運用管理費用(信託報酬)などと比べると金額は低く、0円に設定している投資信託もあります。
そのため、それほど大きな負担にはなりにくく、購入時(販売)手数料と運用管理費用(信託報酬)を優先して確認した方が良いと言えます。



厳密に言えば、手数料とは異なりますが、「解約する際に差し引かれる」という点で注意が必要です。
投資信託の主なメリットとリスク
投資信託のメリットには主に、
- 少額から購入ができる
- 株式や債券などに分散投資できる
- 専門家であるファンドマネージャーが運用してくれる
- 個人では難しい対象にも投資できる
などがあります。
直接投資ができない海外の株式や債券、不動産など、個人では難しい対象にも手軽に投資することが可能なのが投資信託の魅力の一つです。
また、販売会社や運用会社が破綻しても、信託財産は信託銀行に保管されているので、預けている資産は保全されます。
リスクの種類や大きさは、投資対象などによって異なります。
主なリスクには、
- 価格変動リスク
- 為替変動リスク
- 信用(デフォルト)リスク
- 金利変動リスク
などがあります。
投資信託の投資先は様々ですが、投資先の分野や業種などは予め決められています。
例えば、投資先に株を含む(含むことができる)ものは「株式投資信託」と言い、株を含まず、債券などに投資するものは「公社債投資信託」と言います。
株の方が債券よりも値動きが大きくなるため、リスク・リターンも株式投資信託の方が大きくなります。



投資信託選びでは、どんなものに投資し、どのくらいのリスク・リターンがあるのかを把握することが重要で、これを把握する書類が販売会社が交付する「目論見書」です。
目論見書には、
- 投資信託の特徴
- 運用方針
- 運用に係るコスト
- 投資対象
- 運用リスク
など、その投資信託自体のことがまとめられており、投資家が購入する際には、販売会社は必ず「交付・説明」することが義務付けられています。



購入を決める前に必ず内容を確認するようにしましょう。
投資信託の運用方式
投資信託の運用には、次の2通りの方法があります、
一つは「ファミリーファンド方式」です。
これは、複数の投資信託(ベビーファンド)の資金をマザーファンドに集めて運用する方法です。



投資家はベビーファンドを購入します。このベビーファンドを運用する主体(マザーファンド)は同じですが、各々のベビーファンドは、マザーファンドに対する投資の割合が異なります。
大きな資産で投資効率も上がり、手数料も安くなりますが、一つのファンドに偏るので、それが下がった時のリスクも大きくなります。
もう一つは「ファンド・オブ・ファンズ方式」です。
これは複数の投資信託に投資して運用する方法です。
色々な会社の投資信託で運用できますが、株式や債券には運用できません。



色々なファンドに投資するので、分散投資効果が高く、リスクを低減でき、複数の投資信託の選択を行う手間が省けますが、信託報酬が二重に掛かるなどコストが上がります。
さらに投資信託は、「インデックス型」と「アクティブ型」に分けられます。
インデックス型は、株価平均や指数平均など、各運用商品の平均値に即して運用していく投資方針です。
一方、アクティブ型は、収益が上がっている対象に、積極的に投資を集中させていく方法です。
投資対象の入れ替え等を機動的(アクティブ)に行う運用方法となります。



言い換えると「平均」と「集中」でしょうか。尚、初心者には、「ファンド・オブ・ファンズ方式」の「インデックス型」がお勧めです。
- アクティブ型 … ファンドマネージャーの独自判断 ➡ プロの運用手腕にお任せ
- インデックス型 … 日経平均や株価指数などに連動 ➡ 平均株価や指数に依存
投資信託の種類と特徴
株式型投資信託
投資信託の中で、投資先に「株」を含められるタイプのものを「株式型」と言います。
投資信託の種類としては、このタイプが主流で、国内の株に限らず、海外の株に投資するものもあります。



国内株式型投資信託は、日本の証券取引所に上場している株式を対象にしています。一方、海外株式型投資信託は、日本国内の株式ではなく、欧米など外国の証券取引所に上場している株式を運用先とする投資信託です。
では、個別株を買う株式投資と株式型の投資信託はどう違うのでしょうか。
株は、銘柄によって「最低投資金額」が異なり、数万円で買えるものもあれば、100万円を超えるものもあります。
そのため、買いたい銘柄が予算オーバーで買えないこともありますし、複数の銘柄を買いたい場合も、予算に合わせて厳選する必要があります。
その点、投資信託は1万円程度から投資できますので、予算による制限を受けにくくなります。



買う銘柄を絞ったり、そのために個別銘柄の業績などを分析する手間が掛からない点も、投資初心者にはメリットと言えるでしょう。
さらにメリットが大きいのは、外国株への投資を考えている人です。
株は先進国共通の運用手段ですので、国外にも市場があり、銘柄数も国内株の数倍になります。
世界に目を向ければ利益獲得のチャンスも広がりますし、米国、欧州、アジアなどの市場で、成長力のある魅力的な銘柄を見つけられる可能性もあるでしょう。



ただ、そのためには更なる分析が必要になります。分析する銘柄数が増えますし、外国株について調べるに当たり、言語の壁にぶつかることもあります。
外国の経済状況や市場の状態などについての情報も入手しづらいでしょう。
外国株を買うための口座を開く必要もあります。
個人では買えない銘柄もあります。
そのような課題も、投資信託であれば解決できます。



株式型の投資信託は、主に国内外の株を中心に投資するもの。投資信託ごとに投資先の選択・運用・分配に関する方針があり、投資家はその方針を見て売買します。投資方針などを目論見書で確認しましょう。
債券型投資信託
投資信託の中で、投資先に株を含めて良いものを株式型と呼ぶのに対し、株を含めてはいけないものを「公社債投信」と言います。



株式型は、必ずしも株で運用しなければいけないわけではありません。仮に債権のみで運用していても、株を組み入れても良いのであれば、その投資信託は「株式型」に含まれます。
一方、公社債投信は、株を含めることができません。
投資対象となるのは、国内外の国債、地方債、社債などです。
つまり、公社債投信は債券で運用する投資信託と言えますが、債券のみで運用している投資信託が公社債投信とは限らないということです。



国内債券型投資信託は、国内の債券を投資先として運用するものです。主に公債(国債・地方債)を運用先とするものや、企業が発行する社債などを運用先とするものがあります。
公社債投信や債券を中心で運用する債券型の投資信託は、基本的に元本割れしない債券などで運用するため、株式型と比べてリスクが小さくなります。
元本割れリスクを抑えつつ、効率良くリターンを狙いたい場合は、例えば、積み立て貯金のような感覚で、債券型投信を買っていくのが良いかもしれません。



債券型の投資信託は、主に国内外の債券で運用するもの。投資信託ごとに投資方針がある点は株式型と同じですが、公社債投資信託は株には投資しません。投資家はその方針を見て売買します。投資方針などを目論見書で確認しましょう。
もう少しリスクが取れるのであれば、海外の発行体の債券を組み入れるタイプを検討してみることもできます。
海外の債券は、国内のものよりも利回りが高いことがあり、より大きなリターンが狙えます。
また、格付けが低めの発行体の債券を組み入れたものは、更に大きなリターンが狙えます。
もちろん、リターンが大きいほどリスクも大きくなりますので、目論見書でどんな国の、どんな発行体の債券を組み入れるのか確認することが大事。
目論見書には、発行体の格付けなども書かれています。
格付けが高いほどリターンが小さくなり、格付けが低いほどリターンが大きくなります。
海外債券型投資信託とは、海外の国債や公社債、社債などで運用される投資信託です。
国内債券型との大きな違いは、海外市場の債券で運用するので、海外株式と同様、為替変動による影響を受けやすいということです。
外国債券は現地の通貨で購入しますので、円に換算する時の為替レートによって基準価額や分配金の額が変わります。
購入時よりも円高になった場合は「元本割れ」するリスクがあります。
また、新興国(エマージング)の債券などで運用されている場合、その国の政情や財政状況などの影響を受ける恐れ(地政学的リスク)があります。
投資対象の国や地域の事情を考えて投資しなければなりません。



海外の債券は日本国内の債券に比べて、利回りの良いものがたくさんありますが、為替や地域情勢などのリスクも高いと認識しましょう。
不動産投資信託(REIT)
リート(REIT)とは、「Real Estate Investment Trust」の略称で、不動産投資信託のことです。
投資信託の一種ですが、通常の投資信託と違い、証券取引所に上場されています。
REITは、投資家から集めた資金を不動産投資法人がまとめ、オフィスビル、居住用マンション、商業施設、物流施設、ホテルなどの不動産に投資し、賃料収入や不動産売却益を投資家に分配する仕組みの商品です。
株式や債券と同じように、REITにも国内REIT、海外REITがあります。
証券取引所に上場している日本のREITは、JAPANの「J」を付けて、「J-REIT(ジェイ・リート)」と呼ばれます。



一般的に、土地や建物など現物の不動産に投資するには多額の資金が必要ですが、J-REITは数万円~と少額から手軽に間接的な不動産投資ができるのが大きな魅力です。
J-REITは株式と同じように、証券取引所の取引時間中にリアルタイムで売買ができます。
株式市場では通常、株式と株価という言葉を使いますが、J-REITについては「投資口」「投資口価格」と呼びます。
J-REITは全国の証券会社で購入・売却できます。
J-REITの大きな魅力は、収益の殆どを配当金として投資家に分配する仕組みになっている点です。



現物不動産と違い、売りたいと思えばいつでも売却できるなど、換金性が高いのもREITの利点です。
税制面でも現物不動産より優遇されています。
REITは金融・証券税制が適用され、「源泉徴収ありの特定口座」(原則、確定申告が不要)を選べます。
これに対し、現物不動産は、運用で収益を上げても控除はなく、所得としてそのまま計上されます。
REITはインフレヘッジに有用な金融商品とされます。
但し、元本割れリスクがあります。
例えば、不動産市況の変動や不動産の損壊、空室率の上昇などによる価格変動リスク、分配金減少リスクなどがあるので注意が必要です。
REITは現物不動産よりも手軽に投資できますが、不動産投資法人ですので、株式会社のように倒産リスクもあります。



因みに、REITは用途別に見ると、一般的にオフィスビル、商業施設などは景気に敏感、住居系は景気に左右されにくい傾向があると言われます。
複数のリートを組み入れた「リートファンド」もあり、1万円程度から購入できます。
因みに、海外のREITで運用する投資信託は「グローバルREITファンド」と言います。
例を挙げれば、「フィデリティ・USリート・ファンド」「ラサール・グローバルREITファンド」などがあります。
一般的に「グローバルREITファンド」は購入時の手数料が比較的高く設定されていますが、積み立てやキャンペーンによって安くなる場合もあります。
上場投資信託(ETF)
ETF(上場投資信託)とは、株式と同様に証券取引所に上場している投資信託のことです。
正式名称の「Exchange Traded Funds」の頭文字を取って、ETF(イーティーエフ)と呼ばれています。
通常の投資信託と違い、ETFは市場が開いている間にリアルタイムで変動する価格で売買できます。



ETF(上場投資信託)は、投資信託とはいえ、どちらかと言えば「株式」に近いものと考えて下さい。
全国の証券会社を通じて購入・売却ができ、指し値注文が可能です。



投資信託の場合、銀行などの金融機関でも購入できますが、ETFは、証券会社のみで取り扱われ、証券市場での直接売買となります。
ETFは株価指数、債券指数、商品指数などの指標に連動するように、投信会社によって運用されています。
代表的なものには「日経225連動型」「東証株価指数(TOPIX)連動型」などがあります。
日本株の他、外国株、REIT(不動産投資信託)の指数に連動するETFなども揃っています。



簡単に言えば、インデックス運用の投資信託が株式市場に上場していると考えて良いでしょう。
ETFには値下がりリスクはありますが、株式のような倒産リスクはありません。
一般的に株式よりもリスクが抑えられており、初心者にも比較的分かりやすい商品と言えます。
ETFも投資信託の一種なので、運用で得られた収益の一部は、分配金として投資家に支払われます(金ETF、商品指数ETFには分配金がありません)。



分配金をもらうには、そのETFの権利確定日に保有していなければいけないので、注意しましょう。
ETFには、銀行、食品、電気機器、医薬品、自動車、機械、不動産など業種別株価指数を連動対象とする「業種別ETF」もあります。
業種を絞って、株式の代替として活用する投資ができるのもETFの魅力の一つです。
通常の投資信託と比べると、保有中の運用管理費用(信託報酬)などのコストはETFの方が安い傾向があります。
しかし、似たようなタイプのETFから選ぶ際は、運用管理費用が安いかどうかよりも、売買が活発な銘柄を選ぶのが大切なポイントです。
ETFの購入を検討する際は、売買代金が多い銘柄をチェックすると良いでしょう。



ETFの購入を検討する場合、取引量が少ない銘柄には注意が必要です。流動性が低いと、売りたい時に売れないなど売買が成立しない場合があるからです。
ETFの1日の売買高は、株式の売買高のように新聞・ネットなどでも確認できますので、流動性を判断する際の参考にしましょう。
バランス型投資信託
バランス型投資信託とは、運用先をバランス良く選択して投資するものです。
株式型・債券型・REITなど、また各々の国内型・外国型といった各投資信託を、バランス良く投資していく運用方針となります。



これは各種類の投資信託を均衡して保有することで、分散投資を自ら考えずに行えるという特徴があります。その一方で、運用先の投資比率や運用方針などをしっかり把握して投資しなければならないという注意点もあります。
例えば、株や不動産の価格は好景気の時に上がりやすいため、株式型やREITも景気の回復期や上昇期に強いと言えるでしょう。
好景気の時は円安も進みやすいので、外貨建ての投資信託についても同じことが言えます。
一方、債券は不況の時に値上がりします。
値動きとしては株や不動産と逆になるため、景気の停滞期、下落基調の時などに持つのが基本的な考え方と言えます。
但し、景気がこの先どうなるかは、誰にも言い当てられません。
どちらか一方に賭けるのはリスクですし、景気動向に合わせて細かく売買するのは手間が掛かります。



そのような時は、「バランス型」と呼ばれる投資信託を検討してみると良いでしょう。但し、バランス型投資信託は、他の投資信託に比べて、手数料などのコストが高い傾向にあります。
株と債券は反対の値動きをしますので、好景気になれば株が上がり、不景気になれば債券が上がります。
結果、投資信託そのものの価値は変動しにくくなります。
また、国内の商品は円で運用しますので、円安になると価値が下がります。
インフレで物価が上がり、生活費が増える可能性もあります。
その際、外貨建ての投資信託を持っていれば、円安によるマイナスを補うことができます。
円安になるということは「外貨が高くなる」ということですので、外貨建ての商品を組み込んだバランス型投資信託の価値も変動しにくくなるのです。



経済環境の変化で保有する投資信託は値動きします。バランス型に組み入れられた商品も値動きしますが、どれかが下がれば、どれかが値上がりするため「資産全体の額」は変わりにくくなります。
自分で複数の投資信託を組み合わせることもできますが、そのためには手間が掛かります。
複数の投資信託を買うための資金も必要です。
その点、バランス型であれば「少額で複数の商品」を買うことができるため、時間、手間、資金を抑えることができるのです。



バランス型が便利なのは、組み入れた商品の値上がり・値下がりによって投資配分が変わった時に、投資比率を修正してくれる点です。この作業を「リバランス」と言います。
例えば、投資資金を4種の投資信託に分け、25%分で株式型を買っていたとしましょう。
バランスを保つには、この割合を維持する必要があります。
しかし、株式型の価格が上がると、資産全体における株式型の割合も増えます。
25%から30%、40%と増えることで、資産全体として株価の変動に影響されやすくなります。
それを防ぐために、株式型の一部を売り(又は債券型を増やして)、再び25%の状態に戻すのが「リバランス」です。



リバランスを手作業で行うためには資産配分を細かく確認し、増えた分を売却する必要があります。その手間を自動化できるのがバランス型のメリットなのです。
ラップ口座(ファンドラップ)
投資信託は、複数の投資先を組み入れた「パッケージ型」の商品です。
投資信託ごとに投資方針や組み入れる商品が決まっていますし、投資先や投資の比率も投資信託が考えます。
これは投資信託の長所であり、短所とも言えるでしょう。
投資先の選択などを任せたい人にとっては、その際に掛かる手間などが掛からないというメリットがあります。
ただ、自分が望む銘柄を取捨選択できなかったり、投資配分などを調整できない点はデメリットです。
例えば、バランス型の投資信託の配分について、単純に4分割するのではなく、国内株を少し多めにしたいと考える人がいるかもしれません。
国内の主力株を中心としつつ、為替差益が狙える外国株も少し混ぜてほしいと考える人もいるかもしれません。
そのような人に向いているのが「ファンドラップ」です。
これは、証券会社や銀行などが投資方針をヒヤリングし、運用方法を提案したり、投資の実務を受託するものです。



投資信託がパッケージ型、個人で株や債券を選ぶ投資がオーダーメイド型だとすれば、ファンドラップはその中間の「セミオーダーメイド型」と言えるでしょう。
自分の投資方針などを伝えるため、投資信託では実現できなかった細かなポートフォリオの調整ができます。
つまり、投資信託の短所が解消できます。
投資家の資産配分の組み合わせのこと。ポートフォリオを組む主な目的は、リスクを軽減しながら、効率的な分散投資を行うことです。投資する資産の配分を変えることで、リスクやリターンを調整することができます
投資方針とは、例えば、どれくらいリスクを取るか、どれくらいのリターンを狙うかといった基本的なことから、海外に投資したい、中長期で投資したいといった希望も含みます。
このような方針を受けて、証券会社などが投資先や投資資金の配分などを提案します。



提案の理由や、知らない投資用語などがある場合も、この時に説明を受けることができますので、専門知識や投資経験がなくても特に問題はありません。
もう一つ特徴的なのは、運用する資産の売買と管理を証券会社などが行う点です。
ファンドラップは、証券会社などと投資家が投資判断を任せる契約(投資一任契約)を結びますので、この契約に基づき、利益が出た時の利益確定も、損失が出た時のロスカットも証券会社などが行います。
保有・運用している商品で損失が出た場合に、売却して損失額を確定させること。確定していない状態は「含み損」と言います。反対に利益が出ている状態は「含み益」、確定させることを「利益確定」と言います
また、運用中の投資信託は常に値上がり・値下がりするため、投資資金の配分が変わります。
例えば、ある投資信託が値上がりすれば、資産全体の中でその投資信託が占める割合が大きくなります。
結果、リスクが大きくなったり、自分の投資方針と合わなくなることもあるのです。
そのような歪みを修正するために、投資先を入れ替えたりする作業もファンドラップが行います。



投資では、利益確定やロスカットの判断が難しく、複数の商品に投資している場合は全体のバランスも定期的に確認する必要があります。その作業を代行してもらうことで、運用中の手間を軽減することができるのです。
ファンドラップは、証券会社が一任で運用してくれることから、非常にメリットが高いという反面、運用自体が全て上手くいくとは限らないという点も理解しておきましょう。
当然、運用当初に「年率%を目指す」とか「何%のリスクは許容する」など、運用方針を決めて運用を行うのですが、投資である以上、その通りにいかないこともあります。
その際には、全て投資家の自己責任であるということを理解しておくことが大切です。
また、運用を一任された証券会社も、運用をするのですから、それ相応の手数料を徴収しますので、通常に自分で投資信託を購入し運用するよりもコストが掛かるということを理解しておきましょう。
投資信託の取引方法
投資信託の取引方法には2通りあります。
一つは「償還」です。
投資信託の中には運用期間が初めから決められているものがあります。
よってこれは、運用期間中に「分配金」などを受け取りながら最後まで保有し、期間を終えた後に返金してもらうやり方です。
もう一つは「中途換金(売却)」です。
これは、運用期間中に解約して換金することです。



但し、中途換金時の基準価額が購入時よりも下回っている場合、損失が発生することになります。
当然、投資信託も投資なので損得はありますが、多くの場合、運用期間中に分配金が支払われます。
よって一概に、買った時と売った時の基準価額の差だけが重要とは言えません。



売却するまでに受け取った分配金の合計額と、購入時と売却時の基準価額の差を足したものが実際の損益です。投資家は、このトータルの金額を把握しなければなりません。
運用する際のポイント
投資を始める前に最低でも次の2点はご自身で決めておきましょう。
- 運用期間を設定する
- 年間の想定収益率(利回り)を決める
投資期間
投資信託は分散投資効果が高く、その分だけ株などと比べて、リスク・リターンが小さくなります。
そのため、利益を得るためには「時間」を味方につけることが重要です。
中長期(3年~10年)で保有することで、ローリスクの状態を維持しながら、利益を積み増していくことができます。



先ず押さえておきたいのが、投資の成果(利益)は、「投資資金×利回り×投資期間」の3つの要素で決まるということです。
投資資金は、基本的に多いほど有利です。
投資資金が多いほど、資産は増えやすくなります。
例えば、1年当たりの利回りが3%だった場合、投資資金10万円の人の利益は3千円ですが、100万円なら3万円になります。
利回りも高いほど有利です。
利回りが高いほど、資産増加のスピードが早くなります。
投資信託の中では、債券で運用するものよりも株で運用するものの方が利回りが高くなりやすく、国内と海外の商品では、為替レートの変動が影響するため、国内の商品で運用する投資信託よりも、海外の商品で運用する投資信託の方が利回りが高くなりやすいと言えます。



但し、投資信託の利回りは確定していませんので、元本割れするリスクがあります。大きな利回りが期待できるものほど、損失が出る可能性も大きくなる点に注意が必要です。
投資資金と利回りが同じであれば、投資期間が長い方が有利です。
利回りがプラスであれば利益は時間と共に増えていきますし、時間を掛けることができるのなら、ローリスク・ローリターンの商品でも大きな利益を生み出すことができます。
投資信託は、この特徴を生かすことができる商品と言えるでしょう。
積立方式
上記では、投資信託は時間(投資期間)を長く設定することで大きな利益が得られることを説明しました。
その点と関連して、もう一つ重要なポイントがあります。



それは、投資信託をコツコツ「積み立てる」ことで、利益に影響する3要素の1つである投資資金を増やすことができるということです。積立も、時間を活用した投資手法の一つです。
- 投資の利益=投資資金×利回り×投資期間
投資信託は少額で購入できるため、月々投資できる金額は小さくても、長く続けることで着実に資産(元本)が大きくなります。
また、積立によって投資資金が増えていくと、資産が増えるスピードも上がります。
例えば、投資資金が10万円の時の利益は、利回りが5%だったとして5,000円です。
しかし、100万円になれば利益は5万円です。



投資の利益は「投資資金×利回り×投資期間」ですから、投資金額が増えるほど利益が大きくなり、資産が増えるスピードも上がっていくのです。
月々1万円ずつ積み立てていく場合、100万円になるまで8年ほど掛かります。
しかし、月2万円なら4年、月3万円なら3年以内で到達します。
そのため、投資信託の積立では、長く続けることと、月々の積立額をなるべく増やすことが効果アップのポイントと言えます。



積立でもう一つ重要なのは、「分散効果が働く」ことです。コツコツ積み立てるということは、購入のタイミングを分散するということです。そのため、投資先を分散するのと同じように、値動きの影響を受けにくくなります。
例えば、月々1万円ずつ投資信託を買うとしましょう。
すると、1口1万円の時は1口買えますし、5,000円に下がった時は2口、2万円に上がった時は0.5口買うことになります。
このような買い方をしていくことで、安くなった時に多く買い、高い時には少しだけ買うことができます。



投資の基本である「安く買って高く売る」の「安く買う」(安い時にたくさん買う・高い時には少ししか買わない)という作業が、積立によって自動的にできるわけです。
積み立てている投資信託が値下がりした場合、保有している投資信託の価値は下がります。
しかし、安く買い増すことができます。
逆に、値上がりした時は買い増す量が減りますが、保有している投資信託の価値が上がり、資産が増えている筈です。
結果、積立をしている人にとっては、上がっても下がっても良い状態になります。
また、値動きに一喜一憂したり、値動きの動向を予測する必要もなくなるのもメリットです。
まとめ
投資信託は、投資家から集めた資金を運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などで運用してくれる金融商品です。
「投信」「ファンド」とも呼ばれ、証券会社、銀行などで購入できます。
海外の株式や債券、不動産など個人が直接投資するのが難しい対象にも、投資信託を購入することで手軽に投資できます。
多くの投資信託は1万円程度から買うことができ、少額でも幅広い分散投資が可能です。
ネット証券などでは1千円程度から買える商品も扱っています。



預貯金と違い、投資信託には元本保証がありません。利点やリスクは投資対象などによって異なります。購入を検討する際は、どのようなリスクを持つ商品なのかを必ずチェックしましょう。
また、販売会社や運用会社が破綻しても、信託財産は別の信託銀行に保管されているので、預けている資産は保全されます。
投資信託の価格は「基準価額」と言います。
投資信託では運用で得られた収益の一部は、決算ごとに「分配金」として投資家に還元されます。
分配をせずに収益を全て再投資に回す「無分配型」もあります。
毎月、分配金が支払われるタイプの投資信託を「毎月分配型投資信託」と言います。
分配金を年1~2回出す一般的な投資信託と比べると、毎月分配型は一見、魅力的に思えるかもしれません。
しかし、運用資産から毎月多額の分配金を出す仕組みになっているため、収益を再投資するタイプに比べて必然的に運用効率が落ちます。
定期的に収益を得たいというリタイア層に毎月分配型は人気がありますが、分配をせずに収益を再投資に回す「無分配型」や年1、2回決算型(分配)の投資信託を選んだ方が良いでしょう。



可能なら、国内と海外、債券と株式など、投資対象地域や資産の種類を分散して購入していくのも有効な方法です。
分配金のうち、元本の運用によって生じた収益から支払われる本来の分配金は「普通分配金」、決算日の基準価額が個別元本を下回る時に個別元本から取り崩して支払われる分配金は「元本払戻金(特別分配金)」と呼ばれます。
投資信託は運用方法によって、株価指数などに連動する「インデックスファンド」、株価指数などを上回る運用成果を目指す「アクティブファンド」に分類されます。
インデックスファンドは株価指数などと同じような値動きをするので、初心者にも比較的分かりやすい商品でしょう。
アクティブファンドは運用が上手くいけば大きな利益を得られますが、株価指数を下回る場合もあります。
投資信託に掛かるコストには、買う時に販売会社に支払う「購入時手数料」、利益を出したかどうかに関わらず、保有している間ずっと信託財産から差し引かれる「運用管理費用(信託報酬)」などがあります。
購入時手数料の掛からない「ノーロードファンド」の取り扱いは銀行でも徐々に増えていますが、取り扱い数はネット証券が圧倒的に多いと言えます。
同じような商品であれば、コストが安いものの方が有利でしょう。
とは言え、コストが安いという観点だけで銘柄を選ぶのは、選択の幅を狭めてしまいます。
例えば、運用管理費用は一般的にインデックスファンドよりもアクティブファンドの方が高い傾向にありますが、それなりの理由があります。
アクティブファンドは株価指数などを上回る運用成果を目指すため、ファンド内での頻繁な株式売買のコストを始め、専門のチームが調査・分析を基に投資対象や組み入れ比率、売買のタイミングを判断するなどの手間が掛かるのです。



尚、プロが運用するからといって、リスクが軽減するわけではありませんので過信は禁物です。
投資の世界では、国内の株式と債券、海外の株式と債券という伝統的な四つの資産を持つのが分散投資の基本とされます。
投資信託を複数購入する際も、分散投資を心掛けると良いでしょう。
値動きの傾向が異なる複数の資産をバランス良く組み合わせた「バランス型ファンド」もあります。
このタイプは、一つのファンドで分散投資の効果が得られます。
近年、初心者には理解できないような複雑な仕組みの投資信託が増えており、商品の運用リスクや仕組みが分からないのに勧められるまま買って、後でトラブルに発展するケースが増加しています。



投資信託に限らず、自分が十分に理解できない金融商品には安易に手を出さず、どのような商品なのかを調べて勉強することから始めましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。