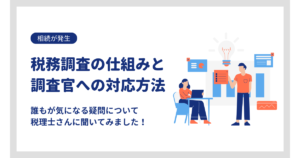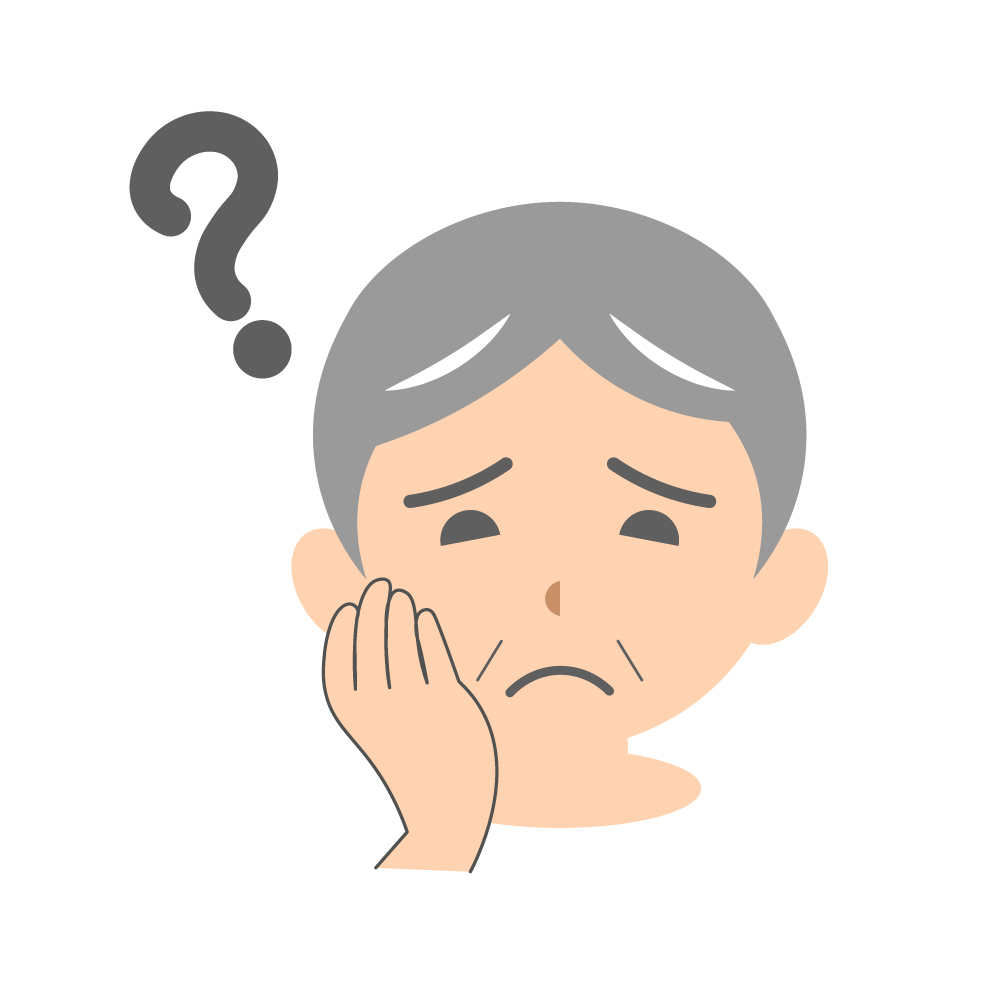 悩める人
悩める人相続税の計算は、どうなっているのか?
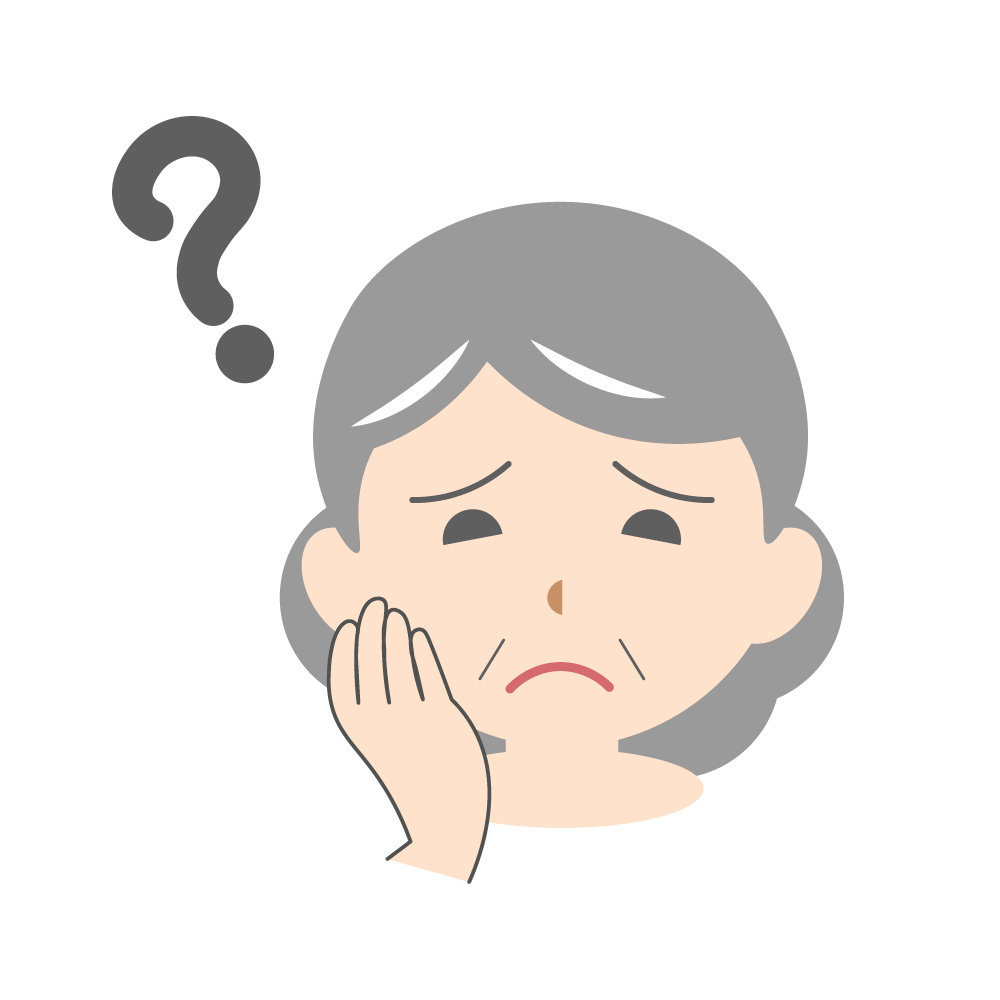
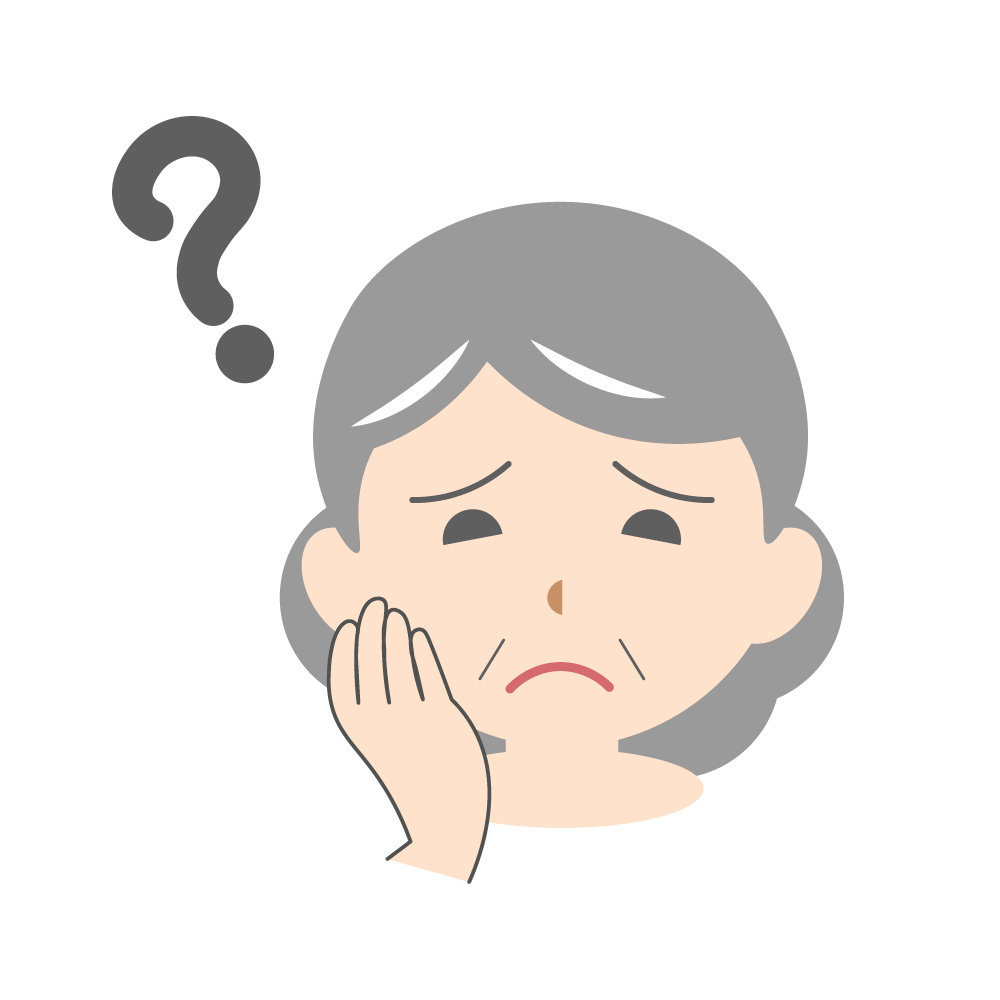
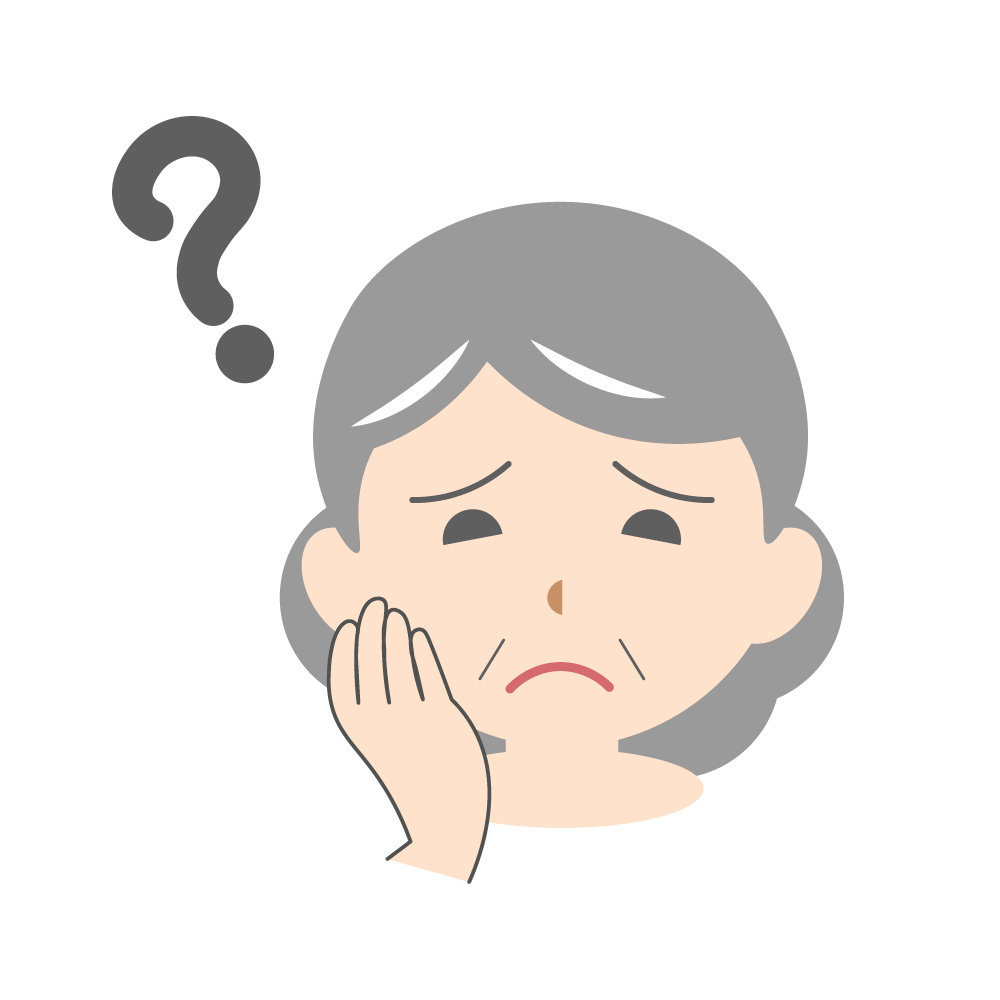
相続税の2割加算?税額控除?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 課税財産・非課税財産
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除
- 相続税の二割加算
- 相続税の税額控除
- 贈与税の計算方法
- 相続税・贈与税の納め方
相続税計算の流れ
相続税の計算は「相続金額に税率を掛けて控除額を引けば良い」と言うほど簡単ではありませんが、きちんと順序を追えばそれほど難しいものではありません。
次に税額計算の主な流れをまとめました。
- 相続税の求め方 -
- 課税価格の計算
- 相続発生
- 財産の分割
- 各人別に相続した財産の金銭的価値(課税価格)を求める
- 相続税の総額の計算
- 求めた課税価格をいったん合計する
- 合計した課税価格から基礎控除をマイナスする
- その課税価格を法定相続人に法定相続分で分割したと仮定
- 分割した課税価格から仮の相続税額を求める
- 仮の相続税額を合計
- 各人別の納付税額
- 合計した相続税額を実際の相続分で相続人にあん分する
- 各相続人ごとに税額を確定する
この流れの中でポイントとなるのは、
①課税価格の計算
②相続税の総額の計算
③各人ごとの税額の計算
④各種控除の利用
の4点です。



これらの順番は入れ替えることはできません。手順を無視して、いきなり「相続税速算表」を使ったりすると、全然違う税額が出てしまうのでご注意下さい。
計算に当たって調べておく必要があるのは、
①相続財産の課税価格(相続税評価額)
②法定相続人の人数
③財産の分割割合
です。
③については、相続税の申告時に決まっていなくても、法定相続分で分割したことにして税額を計算・申告することも可能です。



但し、その場合は、控除などが受けられなくなる可能性があるのでご注意下さい。
相続税の課税財産・非課税財産
相続税が掛かる財産
相続税の対象となる財産(課税財産)には、次のものがあります。
- 相続財産
相続や遺贈、死因贈与のどれかによって取得した財産です。
土地や建物などの不動産、預貯金、有価証券、家財道具など、経済価値のあるものは全て含まれます。
- みなし相続財産
被相続人が死亡したことで、契約上指定された人が受け取る財産です。
被相続人が直接残した財産ではありませんが、公平性を保つために、相続税法上は相続税の課税対象としています。
みなし相続財産には、次のようなものがあります。
- 保険金 … 生命保険だけでなく、損害保険のうち、偶然の事故による死亡に伴って支払われるものも対象になります。共済金なども同じです。基礎控除とは別に、法定相続人1人につき500万円の控除があります
- 死亡退職金・功労金 … 被相続人が死亡したことで、本人に支払われる筈だったものが相続人に支払われます。これも相続人1人につき500万円の控除があります
- 年金やその他の定期給付金 … 被相続人の死亡後に支払われるものです。特別な控除はありません
- 3(7)年以内の贈与財産
相続開始前3(7)年以内に、被相続人から贈与を受けている場合です。



2023年12月31日までは、3年内加算のルールだったのですが、2024年1月1日からは「7年内加算」のルールに変更されました。
3(7)年を超える以前の贈与財産は対象になりません。
この場合は、その贈与を相続財産に入れるので、相続税もそれだけ掛かります。
しかし、贈与税を支払っている場合、その贈与税の分を、相続税額から差し引くことができます。
尚、遺言で借金を免除してもらった場合は、その分の金をもらったことになるので、相続税の対象となります。



相続や遺贈等で取得したものだけでなく、3(7)年以内の贈与財産も相続税の対象です。
債務控除
債務控除とは、相続財産から予め差し引かれるもので、相続税の対象外です。
- 被相続人の債務
マイナスの遺産のこと。
具体的には、被相続人の借り入れ金や未払金、預り金(預かっている敷金や保証金)などがあります。
- 葬式費用
埋葬や告別式などに掛かった費用、お寺に払うお布施、戒名料は債務控除されます。
但し、墓地購入費用や香典返し、法要の費用は控除されません。



被相続人の債務や葬式費用は、債務控除分として相続財産から差し引かれます。
相続税が掛からない財産
非課税財産とは、相続税の掛からない財産のことで、具体的には以下の通りです。
- 祭祀財産
墓地や墓碑、位牌、仏壇、祭具、花輪代など。
- 公益事業用財産
宗教や慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が、その事業に供するもの。
- 国等に贈与した財産
相続や遺贈により財産を取得した者が、その財産を国等に贈与した場合の財産。
- 心身障害者共済給付金の受給権
地方公共団体から支給される、心身障害者の給付金を受ける権利。
- 退職金・保険金の非課税分
死亡退職金・生命保険金のうち、500万円×法定相続人の人数の額まで。



祭祀財産や国等への寄付などは相続税が掛かりません。
相続税の計算方法
相続税の基礎控除
相続で先ず心配なことは、
- 相続税が掛かるか?
- 掛かるとしたらいくらになるか?
ということです。
相続税を計算するには、先ず「相続対象になる財産がいくらになるか」を計算します。
財産の総額から借入金などマイナスの財産を引くと、課税の対象となる財産総額が出ます。
この財産総額から「基礎控除額」を引いた額が「課税遺産総額」です。
この金額がマイナスになれば、相続税は掛かりません。



相続税が掛からないのに、あれこれ悩むのは徒労です。最初に、課税価格と基礎控除額を確認しておきましょう。
基礎控除額を知るために、先ず法定相続人の人数を特定しておくことが必要です。
基礎控除額は、相続人数で自動的に計算されるからです。
具体的な計算式は、次の通りです。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円
例えば、父母と子供2人の家庭で、父が亡くなった場合、相続人は母と子供2人の合計3人になります。
この場合、基礎控除額は「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」となります。
相続財産の総額が4,800万円以下なら相続税は掛かりません。
相続を放棄した人がいる場合も、基礎控除の計算上では、放棄がなかったものとします。
尚、養子は、実子がある場合は1人、ない場合は2人まで人数に入れます。
課税価格の合計
課税価格は、財産を取得した各相続人が個別に取得した財産の評価額です。
相続税の対象となる財産の評価額なので「相続税計算の基」になります。
各相続人の算出した課税価格を合計したものが「課税価格の合計」です。



つまり、課税価格の合計が基礎控除額を上回った分に対して相続税が掛かることになります。逆に、課税価格の合計が基礎控除額を下回っていれば相続税は掛かりません。
課税価格は次の手順で計算します。
- 相続した財産の評価額を計算する
- みなし相続財産の金額から非課税金額を控除したものを加える
- 相続時精算課税適用財産の評価額を加える
- 債務(借金)や葬式費用を引く
- 相続開始前3(7)年以内に贈与された財産の評価額を加える



先ずは各相続人ごとに相続財産の課税価格を合計していきます。
相続税の総額
相続税の総額は、課税価格の合計から基礎控除額を引いた額(課税遺産総額)を法定相続分通りに分割したと仮定して計算します。
相続税の総額は次の手順で計算します。
- 課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額
- 課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=各法定相続人の仮取得金額
- 各法定相続人の仮取得金額×税率=各法定相続人の仮相続税額
- 各法定相続人の仮相続税額の合計金額=相続税の総額
相続財産のうち、誰が何をどう取得しようと、又は相続人の誰かが放棄しようと、相続税の総額は変わりません。
相続税の総額は、課税価格と相続人の人数で自動的に算出されるものなのです。



先ずは、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分通りに分けたとして、相続税の総額を算出してみましょう。実際に各相続人が納税する相続税については、この後に計算します。
- 遺産全体の課税価格総額を算出する (ここで、債務控除分を差し引いておく) … A
- 基礎控除額を計算する … B
- A-B=課税遺産総額 … C
- Cを各相続人が法定相続分で分けた場合の相続額を計算する … D
- D×税率=各相続人の相続税額 … E
- 各相続人のEを合計する … F
Fが、相続税の総額になります。
その後、この相続税の総額を基に、各相続人が納付すべき相続税額を計算します。



課税遺産総額に対する相続税額を求めることで、どのように遺産分割しても相続税総額は同額になるのです。
各相続人の相続税額
各相続人の税額は、相続税の総額に各相続人が取得した財産割合を掛けて算出します。
取得した財産が全相続財産の50%であれば、税額も相続税総額の50%になるのです。
各相続人の相続税額は次のように計算します。
- 各相続人の相続税額=相続税の総額×あん分割合



あん分割合とは、課税価格の合計額に対する各相続人の取得額の割合です。
法定相続人が法定相続分で分割した時の税額は、あくまでも相続税の総額を計算する上での仮の数字です。
ここまでは自動的に計算できますが、各相続人が実際に納付すべき相続税を計算するには、各相続人が取得する相続財産の価格が必要になります。
各相続人の相続税額は、相続税の総額を各相続人が受け取った相続財産の取得分に応じて分けることで算出されます。
つまり、相続税の総額を財産の取り分に応じて分配するということです。
各相続人の相続税額の具体的な計算方法は、次の通りです。
- 各相続人ごとに、相続税の総額に占める「各相続人の相続税の課税価格」を計算する … A
- 相続税の総額に「あん分割合」を掛けて、各相続人の算出税額を計算する … B
- 各相続人の立場に応じて「税額の加算や控除」を行い、各相続人の納付する税額を計算する … C



相続税の総額を「あん分割合に応じて配分」した金額が、相続人ごとの納税額となります。
例えば、相続税の総額が6,000万円で、相続財産の3分の2を相続人A、3分の1を相続人Bが取得した場合、各相続人の相続税額は次のようになります。
- 相続人Aの相続税額=6,000万円(相続税の総額)×3分の2=4,000万円
- 相続人Bの相続税額=6,000万円(相続税の総額)×3分の1=2,000万円



これで各人の相続税額が算出されました。しかし、まだ終わりではありません。次に説明する「2割加算」と「税額控除」を行なって、最終的な納付税額を確定させます。
相続税の2割加算
相続や遺贈によって財産を取得した人が、次の①又は②以外の人である時は、前段階で算出した相続税額の20%相当額を加算することになっています。
①1親等の血族(父母又は子)
②配偶者
つまり、相続税が2割増になるのは、祖父母、兄弟姉妹、代襲相続人となっていない孫、赤の他人になります。
被相続人と血縁関係が近い人と遠い人(もしくは血縁関係のない人)の相続税が同額なのは不自然だからです。
また、2割加算の対象には、被相続人の養子となった被相続人の孫、ひ孫(直系卑属・代襲相続人である者は除く)も含まれます。
つまり、養子であっても、その養子が孫であれば2割加算になるのです。
尚、法定相続人であれば、加算されても、基礎控除がなくなるわけではありません。



配偶者と子、父母以外の相続人の税額は2割増になります。
相続税の税額控除
これまでの手順によって求めた各人の税額から、最後に各種の税額控除額を差し引きます。
これで、その人の納付する相続税額が確定します。
つまり、税額控除分だけ払う相続税が安くなるのです。
相続税の税額控除は、
①贈与税額控除
②配偶者の税額軽減
③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国税額控除
の6つです。
控除する順番は、①~⑥の順と決められています。



相続税の計算では「控除」という言葉がいくつか出てきます。それぞれ「何」から「何」を控除するのかが異なっているので、混同しないようご注意下さい。
例えば、この段階で用いられる「税額控除」は、求められた「税額」から直接金額をマイナスできる控除です。
逆に「基礎控除」や「生命保険金の課税控除」などは、それぞれ税額を求める前の「課税財産額」からマイナスするタイプの控除です。
また、「速算表」にも別な控除があります。



税額控除には、各相続人の立場に応じて適用される控除があります。最後に各相続人の税額から「税額控除」を引いて納付税額が決まります。
贈与税額控除
相続開始前3(7)年以内の贈与財産には「相続税」が課税されます。
しかし、贈与された時点で贈与税を納めている場合は二重に税金を払うことになってしまいます。
そこで、相続税では二重課税を防ぐために「贈与税額控除」を設けているのです。



贈与税を納めた相続人は、その時に納めていた贈与税額をこの段階でマイナスすることができます。
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続人になる場合、配偶者の相続する財産が「法定相続分」又は「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは相続税が非課税となります。
例えば、父、母、子の家庭で、父が10億円の相続財産を残して死亡した場合、法定相続分通りに相続すると、配偶者である母は5億円相続することになりますが、相続税は掛かりません。



つまり、配偶者が「法定相続分以内」の財産を相続する場合は無税で、たとえ法定相続分を超えて相続する場合も「1億6,000万円まで」は無税だということです。
配偶者の税額軽減は婚姻期間に関係ありませんが、原則として「申告期限後3年以内に分割が終了」し、かつ「申告期限までに申告書が提出」されている場合に限り適用されます。
但し、配偶者がいくら相続するかは、二次相続の際の子が納める相続税も踏まえると良いでしょう。
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、その者が本来納めるべき相続税額から一定額を控除できます。
これを「未成年者控除」と言います。



相続人のうち18歳未満の者については、その者が18歳に達するまでの養育費を考慮して控除を認めています。
未成年者控除の要件は4つ。
- 相続開始日に18歳未満であること
- 相続又は遺贈により財産を取得したこと
- 法定相続人であること
- 相続開始日に日本国内に住所があること
尚、未成年者は原則として法律行為を行えないので、特別代理人を選任する必要があります。
- 未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)



1年未満の端数については切り上げて1年とします。本来納める相続税の金額から10万円が差し引かれます。
未成年者控除の金額が、その未成年者が払うべき相続税額を超えた場合は、税額を超えた分をその未成年者の扶養義務者となる相続人が自分に掛かる税額から控除して良いことになっています。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、「障害者控除」が適用されます。
これは、障害を抱える相続人が遺産を相続した時の負担を軽減する目的で設けられている制度です。
満85歳になるまで、一般障害者は1年につき10万円が、特別障害者は1年につき20万円が控除されます。
障害者控除を受けるための要件は3つ。
- 相続時に日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
- 障害者である相続人が相続財産を取得すること
控除額が相続税額を超える場合には、その差額は扶養義務者となる他の相続人の税額から控除されます。
- 一般障害者 … 10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
- 特別障害者 … 20万円×(85歳-相続開始時の年齢)



いずれも1年未満の端数については切り上げて1年とします。
相次相続控除
被相続人が過去10年以内に別の相続で財産を取得した、いわゆる二次相続の場合、「相次相続控除」を受けられます。
前回の相続で相続税を支払っている場合は、その分の税額のうち一定額を今回の相続税から控除できます。
例えば、亡くなった父(今回の被相続人)が祖父から土地を相続し、その際に土地についての相続税を納めていた場合、今回の土地を相続する際の相続税額から一定額が控除されるのです。



10年以内に続けて相続があった時に、2回目の相続(二次相続)で1回目に払った相続税の一部を引くことができます。但し、適用できるのは「相続人」に限定されています。
外国税額控除
海外にある資産を日本国内に住んでいる人が相続によって取得する場合、その財産の所在地国で相続税が課せられるケースがあります。
こうした時は、海外の税と国内の税の二重払いになる恐れがあるため、海外で課せられる税金の分は国内の相続税額から控除しても良いことになっています。
これが「外国税額控除」です。
外国税額の控除できる金額は、これまでに説明した5つの相続税控除後の相続税額と、相続した外国財産のうち海外で相続税を課せられた時の税額の、いずれか少ない金額になります。



外国税額控除は、海外で相続税を払っていた場合、日本での相続税額から海外で納めた相続税額を控除できるというものです。
贈与税(暦年)の計算方法
贈与とは、言わば「生前の相続」と考えられるので、贈与税については「相続税法」で定められています。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、110万円を超える額の財産をもらった時に掛かる税金。



つまり、贈与税の基礎控除は110万円。法人から贈与された場合は、贈与税ではなく「所得税」が掛かります。
110万円というのは、1人が受けた贈与財産の総額です。
何人からもらったかは、問題ではありません。
贈与をしてくれた人ごとに計算するのではなく、もらった財産の全てを合計した額が贈与税の課税価格です。
その暦年課税による贈与税の計算ですが、1年間(1月1日から12月31日)にもらった財産の評価額の合計額(課税価格)から基礎控除額の110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、更に控除額を差し引いた額が納税額です。
すなわち、
- 暦年課税の贈与税額=(贈与財産の評価額の合計額-110万円)×税率-控除額
という算式で表すことができます。
例えば、成年である受贈者が1年間に父親から現金300万円、祖父から時価500万円の有価証券をもらった場合は、いずれも直系尊属のため、
- (300万円+500万円-110万円)×30%-90万円=117万円
となり、117万円の贈与税を支払うことになります。
相続税・贈与税の納め方
相続税や贈与税は申告納税制度です。
相続や遺贈によって財産を取得した人は、自分で税額を計算して申告・納税します。
相続税の申告期限は、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」となっています。
つまり、被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内です。
例えば、被相続人の死亡日が2月9日であれば、その年の12月9日が申告期限となります。



もし、期限内に申告をしなかったり、実際にもらった財産の額よりも少なく申告していた場合には、後で加算税などが課せられますので、注意が必要です。
申告は、相続によって財産を取得した人が行わなければなりませんが、相続人が2人以上いる場合などは、それぞれが別々に申告書を提出する必要はありません。
1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額を計算して記載すれば良いのです。
申告書の提出先は、被相続人が死亡した時に住んでいた住所地を管轄する税務署です。
財産を相続した人の住所地ではありません。
例えば、相続人がそれぞれ札幌と福岡に住んでいたとしても、被相続人の住所地が東京にあった場合には、全員が東京で申告することになります。
相続税の納付期限は、申告の期限と同じです。
つまり、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に納めなければなりません。
納付は相続人全員がまとめて行う必要はなく、それぞれが申告に基づいて、個別に行えば良いことになっています。
尚、納付先は税務署の他、最寄りの金融機関や郵便局の窓口でも納めることができます。
相続財産の金額が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告は必要ありません。
但し、配偶者の税額軽減など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例の結果、相続税が0円になった場合は申告が必要です。



これらの税額控除や特例は、申告することで初めて適用になるので注意しましょう。
一方、贈与税の申告・納付の期限は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日まで。
申告書の提出先は、申告する人(贈与を受けた人)の所在地を管轄する税務署となっています。
納税の期間も、申告期間と同じなので注意が必要となります。
贈与財産の評価額が110万円以下の場合は、申告をする必要がありません。
但し、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税などを適用する場合は、たとえ最終的に払う贈与税が0円になっても、贈与税の申告をする必要があります。



きちんと、申告しないと、これらの特例が受けられなくなるので注意しましょう。
延納
相続税は、申告期限内に全額を金銭で納付するのが原則です。
しかし、相続した財産が金銭ではなく、土地などの不動産が殆どといった場合には、それらを売却して現金化するのに時間が掛かるなど、どうしても現金で一括して納めるのが難しいというケースもあります。



現金での一括納付が困難な場合、納期限を過ぎてから「分割」で納める「延納」が利用できます。申請後「3か月以内」に税務署が許可又は却下の判断をします。
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産の割合が大きい場合は最高20年まで認められます。
相続税を払えないが相続した財産を売りたくない場合などに検討しましょう。
但し、延納は一定の条件を満たした場合にのみ認められるので、どんな場合でも延納できるというわけではありません。
延納が認められるための条件は次の通りです。
- 相続税の申告期限までに、延納申請書を提出すること
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で一度に納めることが困難な理由があること
- 延納税額に見合う担保を提供すること (但し、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
延納が認められると、延納した税額を延納期間で割った金額を、毎年一回支払います。
また、延納した税額には延納期間に応じた「利子税」が追加されます。
物納
現金の代わりに「物」で納めることが認められる場合があります。
物納は、延納でも相続税を払うことができない場合に、金銭ではなく不動産など特定の相続財産で納付する方法です。
物納が認められると、現金の代わりに物で納税することができます。
尚、物納できる財産には「順位」が予め定められています。
また、管理処分不適格財産は物納の対象にならないなどの条件があります。



相続財産を売却して現金で納税する方が税額を抑えられる場合もあるため、その点を踏まえた上で、物納を利用すべきかどうか良く検討してみる必要があります。
物納が認められるためには次のような条件を満たす必要があります。
- 相続税の納期限までに、物納申請書を提出すること
- 延納によっても、金銭での納付が困難であること
- 物納できる財産があること (管理処分不適格財産と見なされていない財産)
いったん物納を申請して許可された後でも、一時に金銭で納付できるようになったり、延納が可能になった場合には、物納を撤回することができます。



尚、単に物納を撤回しただけでは、納付までの期間に「延滞税」が掛かってしまいます。物納を撤回する時は、同時に「延納の申請」も忘れずに行いましょう。
まとめ
相続税額の計算は、次のように3つのステップを踏んで行われます。
- 課税価格の合計から基礎控除額を差し引く … A
- 法定相続分通りに相続したとして相続税総額を計算する … B
- 各相続人の相続税額を計算する … C
まず最初に、相続財産の評価額から課税価格の合計を算出し、ここから基礎控除額を差し引いた上で、これを法定相続分通りに相続したと仮定して全体に対する相続税額(相続税総額)を求め、その後に各相続人の相続した財産の割合に応じて各相続人の相続税額を決めるわけです。
Bの段階で相続税総額を計算することで、どのように相続財産を分割しても相続税の総額は同額になります。



相続税では、「一定の手順で求めた相続税の総額を各相続人などに割り振る」というやり方をします。一見ややこしそうですが、手順を踏めば計算自体は簡単です。
具体的な計算例
- 相続人 = 妻・長男・長女
- 妻 = 不動産8,000万円・現預金5,000万円・生命保険金6,500万円・葬式費用等マイナス600万円
- 長男 = 現預金6,000万円・株式2,700万円
- 長女 = 現預金6,000万円・株式2,700万円
①課税価格の合計を出す
- 妻 = 8,000万円(不動産)+5,000万円(現預金)+5,000万円(非課税限度額を引いた後の生命保険金)-600万円(葬式費用等)=1億7,400万円
- 長男 = 6,000万円(現預金)+2,700万円(株式)=8,700万円
- 長女 = 6,000万円(現預金)+2,700万円(株式)=8,700万円
- 合計 = 1億7,400万円+8,700万円+8,700万円=3億4,800万円
②課税価格の合計から基礎控除額を引く
- 基礎控除額 = 3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4,800万円
- 課税遺産総額 = 3億4,800万円-4,800万円(基礎控除額)=3億円
③法定相続分に応ずる取得額を計算する
- 妻 = 3億円×2分の1=1億5,000万円
- 長男 = 3億円×2分の1×2分の1=7,500万円
- 長女 = 3億円×2分の1×2分の1=7,500万円
④相続税の総額を計算する
- 妻 = 1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円
- 長男 = 7,500万円×30%-700万円=1,550万円
- 長女 = 7,500万円×30%-700万円=1,550万円
- 相続税の総額 = 7,400万円
⑤あん分割合を計算する
- 妻 = 1億7,400万円÷3億4,800万円×100=50%
- 長男 = 8,700万円÷3億4,800万円×100=25%
- 長女 = 8,700万円÷3億4,800万円×100=25%
⑥各相続人ごとの相続税額
- 妻 = 7,400万円×50%=3,700万円
- 長男 = 7,400万円×25%=1,850万円
- 長女 = 7,400万円×25%=1,850万円
⑦税額控除を適用する
- 配偶者の税額軽減額 = 7,400万円(相続税の総額)×1億7,400万円(妻の取得額)÷3億4,800万円(課税価格の合計)=3,700万円
⑧納付税額
- 妻の納付税額 = 3,700万円-3,700万円(配偶者の税額軽減)=0
- 長男の納付税額 = 1,850万円
- 長女の納付税額 = 1,850万円



こういうステップで計算していくわけです。難しく思えるかもしれませんが、速算表などを使えば簡単にできます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。