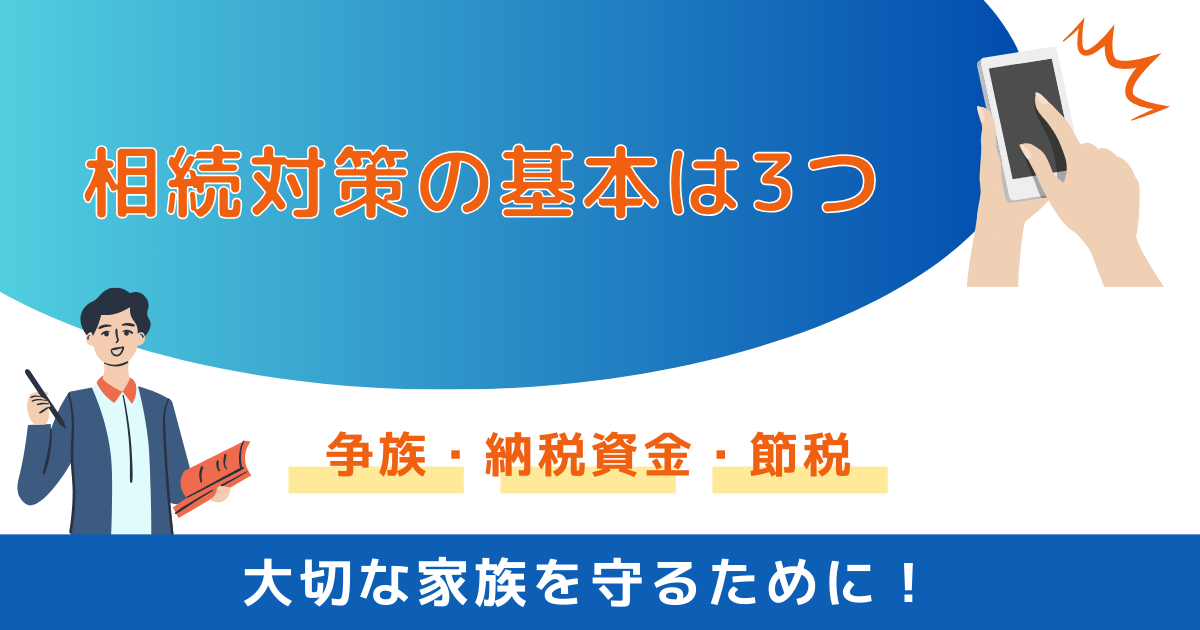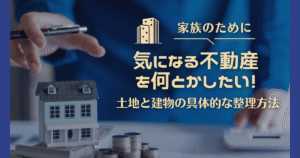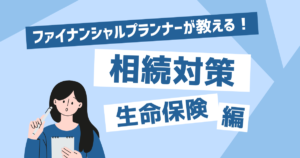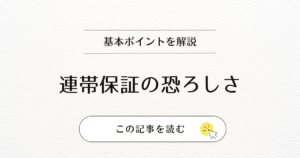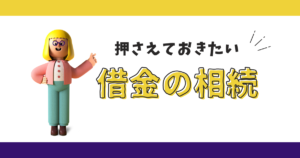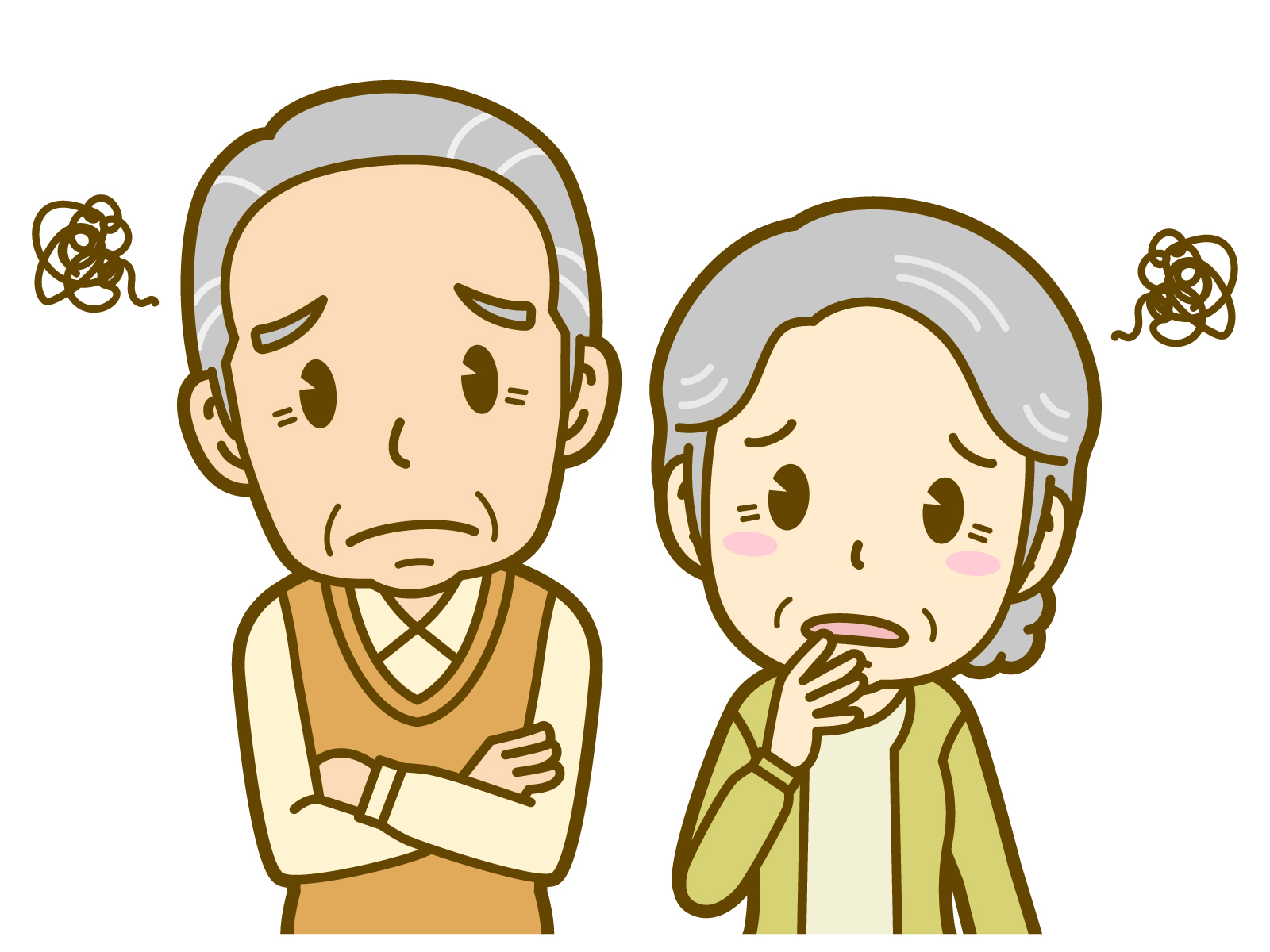 悩める人
悩める人大事な家族が「争族」とならないようにしたい…



相続税の負担を少しでも減らしたい…



こんな疑問・悩みを解決します!
- 対策の基本ポイント
- 対策の基本的な手法
- 節税対策
- 納税資金対策
- 遺産分割(争族)対策
- 対策のリスクと注意点
相続対策の基本ポイント
あなたが相続人、被相続人に関わらず、相続対策を講じる前に、先ず押さえておかなければならない、いくつかの基本ポイントがあります。



財産を残す人も相続する人も、先ずは対策の基本ポイントを押さえるところから始めましょう。
- できるだけ早く相続の準備を始める
- 相続に関する法律や税金についてよく知る
- 相続財産の内容をしっかり把握する
以上のようなポイントをクリアしたら、次にいよいよ相続対策に取り掛かります。
今から対策の準備をスタートするとして、どのような手を打てば良いのか、より具体的な対策法について見ていきましょう。



一口に相続対策と言っても、様々な観点がありますが、大きな柱となるものは次の3つです。
- 相続税の節税対策 … 財産を相続した人の相続税の負担を減らす対策
- 相続税の納税資金対策 … 相続発生後、10か月以内に相続税をきちんと支払えるようにする対策
- 遺産分割(争族回避)対策 … 残した財産を分割する方法で、家族が揉めないようにするための対策
財産リストを作成
相続対策として、先ず、財産の棚卸しをして「財産リスト(一覧表)」を作りましょう。
自分たちの財産がどれくらいあるか正確に分かっているという人は、案外少ないのではないでしょうか。
財産リストがなければ、誰に何を渡すか整理できませんし、相続税の概算も計算できません。
また、実際に相続が起こった際、生前に作った財産リストがあれば、遺族が財産を探す際にも便利です。



財産リストは、名義人ごとに、「プラスの財産」と「みなし相続財産」、そして、「マイナスの財産」に分けて作成します。
リストを作成したら、誰にどの財産を残すか、相続の方針を考えます。
法定相続分と違う分け方をしたいなら、遺言書を残すなどの対策が必要です。
生命保険は契約した当時と今の状況が違っている場合があるので、死亡保険金の受取人は今のままで良いか検討して、必要があれば変更手続きを。
財産の分け方を考える一方で、相続税が掛かるかどうかも確認しましょう。



財産が多い人や評価額が判断しにくい不動産や美術品などを持っている場合には、専門家への相談をお勧めします。リストは、できれば毎年更新を。
財産リストの作成は相続対策に欠かせませんが、今後の生活プランを見直す上でも役立ちます。
現在の資産と負債の状況が具体的に分かるので、今後の生活費への備えが十分かどうかを確認できますし、株式や不動産の時価を定期的に確認することで、運用の見直しや売却のタイミングなども検討できます。
プラスの財産
先ず、「プラスの財産」。
預貯金や土地など、種類ごとに残高や評価額を調べて、リストに書き込みます。
預貯金は、預金の種類や残高を記入します。
株・投資信託などは、評価額の合計だけを書いておいても構いませんが、証券会社から送られてくる明細書は別途保管しておきましょう。
どちらも金融機関や支店名も必ず記入します。
土地や建物は、できれば、登記事項証明書(登記簿謄本)を見ながら、所在地や面積を記入。
借地権もここに記入します。
不動産は名義も確認して下さい。
先祖代々の土地で名義変更をしていない例も見られるので、早めに解決しておきましょう。
評価額の出し方は、下記を参照して下さい。
ゴルフ会員権や高価な美術品などがあれば、その情報も記入します。
みなし相続財産
次に「みなし相続財産」です。
みなし相続財産は、「相続人」ではなく指定された「受取人」の財産となるので、分けて管理することが必要なのです。
死亡保険金のうち、みなし相続財産となるのは、契約者も被保険者も自分の契約のもの。
誰が受取人かも確認しておきましょう。
マイナスの財産
「マイナスの財産」には、ローンなどの債務を書きます。
種類(住宅ローンなど)や借入先、具体的な内容(完済予定日など)を記入しましょう。
借金の保証人になっている場合も、ここに記入を。
相続では保証債務も引き継ぐことになるので、必ず相続人に伝えておいて下さい。
相続税の節税対策



先ず一つ目は「節税対策」。つまり「納める相続税額をいかにして少なくするか」ということです。
節税対策は、相続財産の大きなところから手を付けるのが王道です。
財産のうち多くを占めるのが現金・預貯金等、次いで不動産です。
つまり不動産や現金の節税対策に取り掛かるのが、最も節税に効果的な対策と言えるのです。
節税対策のポイントの1つが「財産そのものを減らす」という方法。
その代表的なものが「生前贈与」で、生きている間に現金、土地などを贈与するという方法です。
節税対策のもう1つのポイントが「評価を減らす」という方法で、不動産に有効です。
- 相続財産を減らす … 相続人などへの少額贈与・配偶者への自宅の贈与など
- 相続財産の評価を下げる … アパートなどの賃貸経営・小規模宅地等の特例の活用など
- 税法の計算規定を利用する … 配偶者の税額軽減の適用・生命保険の非課税枠の活用など
色々な方法がありますが、先ずは現時点でどのような財産があり、いくらで評価されるのか、それに対する相続税額はいくらか、また納税資金は足りているのかをしっかり把握することが大切です。
その上で、それぞれの現状に合った適切な方法を選ぶことがポイントになります。



相続税の節税対策を考える時は、「相続税がどれくらい掛かるのか」ということが大切な軸になります。そもそも、遺産の額によっては、税金が掛からないこともあります。
- 節税対策 -
- 相続財産の内容と概算額、相続税の概算額を把握していますか
- 相続人などへの少額贈与は実行していますか
- 子供に贈与した預金口座を自分で管理していませんか
- 贈与税の配偶者控除を利用した自宅の贈与は実行しましたか
- 嫁や孫との養子縁組について検討しましたか
- 遊休地の有効活用はできていますか
- 墓地や仏壇の購入・改修は済んでいますか
- 自宅の建替え・増改築は必要ありませんか
生前贈与
財産に余裕がある時の相続対策として、生きているうちに家族に財産を贈与し、将来の相続財産を減らしておく方法があります。
子や孫への目的を絞った贈与には「非課税の特例」もあります。
生前贈与は、住宅取得や子育てでまとまったお金が必要になる現役世代の暮らしを豊かにすることにも役立ちます。



子や孫への贈与の特例には、教育資金と住宅資金に関するものもあります。但し、どちらも期限がある制度です。
贈与税の納め方には2種類の方法があり、自分にとって有利な課税方法を選べます。
1つは、110万円の基礎控除が適用できる「暦年贈与」です。
そして、もう1つの方法が、「相続時精算課税」です。
暦年贈与
一年単位で贈与税額を計算して課税する方法を「暦年課税」と言います。
この場合、年間(1月~12月)で、110万円までの贈与には贈与税は掛かりません。
暦年課税では、贈与された相手ごとではなく、その年に受け取った財産を全て合算した金額に対して課税されます。
例えば、同じ年に父から200万円、伯父から150万円を贈与された時は、年間で、合計350万円贈与されたと考えて、贈与税額を計算します。



暦年課税の基礎控除(非課税枠)は、贈与相手や資金の目的は問わないので、子の配偶者や孫など相続人以外にも幅広く生前贈与できるメリットがあります。
但し、子や孫名義の銀行口座を作って勝手に入金していても、通帳と印鑑などを贈与された本人が管理しているという実態がないと、贈与とは認められません。
通帳や印鑑を渡し、贈与の度に贈与契約書を作成しておくと万全です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、子世代に早めに財産を引き継がせて活用してもらおうという制度。
生前に財産を子などに贈与し、将来、相続が発生した時に、生前贈与分を含めて相続税を計算して税金を調整します。
累計で2,500万円までは贈与税は非課税で、それを超えた分には20%の贈与税が掛かります。



また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。
この制度は60歳以上の親から18歳以上の子(すなわち推定相続人)への贈与が対象で、「父と長男」など一対一の関係で利用します。
一度選択したら取り消すことはできないので、この制度を選択した父と長男の間では、暦年課税の贈与はできず、贈与は全てこの制度内で行うことに。
ただ、贈与者ごとに課税方法を選択することはできるので、よく考えて選びましょう。
居住用財産の配偶者控除
結婚20年以上の夫婦なら、贈与税の配偶者控除を活用しましょう。
この制度は、婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産、又は居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、最高2,000万円を課税価格から控除できるというもの。



通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度。基礎控除と一緒に利用できるので、合計で「2,110万円」まで非課税となります。
住んでいる自宅の一部又は全部を配偶者名義にしたり、新しく家を購入する資金を贈与する時に利用できます。
この特例を利用した贈与は、相続前3年以内に行なったものでも相続財産に取り込まれることはありませんので、夫の財産減らしに役立ちます。
対象となるのは、法律婚をしている期間が20年以上の夫婦です。
事実婚の期間はカウントされません。
また同じ夫婦間では一生に一回しか利用できません。
非課税の範囲内の贈与であっても、翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要で、贈与の翌年の3月15日までその家に住むなどの条件もあります。
名義変更に際しては「登記費用」が掛かります。
住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与は、最大1,000万円までの贈与が非課税になる仕組みで、自分の子供に対して「住宅の頭金だけでも出してやりたい」「住宅取得の資金を全額援助したい」などと考えている親のニーズに対応できるものです。
2026年12月までの期間限定の制度となっています(2025年7月現在)。
子世代の夫婦が自宅を共有するとして、この制度を上手く利用すれば、夫の親などから1,000万円、妻の親などから1,000万円、合計2,000万円を非課税にする、なんてことも可能です。



ただ、注意すべきは、この制度が、住宅取得のための「資金」にのみ適用され、自宅不動産「そのもの」の贈与には適用されないということです。
例えば、親が贈与した家を子が自宅にする場合などは、対象外になるため非課税にはなりません。
不動産の評価額に応じた贈与税が掛かります。
結婚・子育て資金の一括贈与
この制度を利用すれば、結婚式などの資金は最大300万円まで、また、子育ての資金を含めると合計1,000万円までの贈与が非課税となります。
結婚・子育て資金の一括贈与の対象者は、受贈者については「18歳以上50歳未満の個人」、贈与者は「その直系尊属(両親や祖父母など)」に限られます。
制度の対象になるのは、2027年3月31日までに、銀行や信託銀行などに受贈者名義の専用口座に入金(拠出)した財産です(2025年7月現在)。
受贈者は、この財産を結婚や子育てのために使ったことが分かる領収書などを金融機関に提出して払い出しを受けます。
教育資金の一括贈与
2つ目の制度は、教育資金の一括贈与です。
相続対策としても注目を集めています。
この制度は、受贈者1人につき1,500万円まで非課税で贈与することができ、受贈者は30歳未満で、贈与者はその直系尊属に限られています。
また、この制度も2026年3月31日までの期間限定です(2025年7月現在)。
結婚、子育て資金と同じように、専用口座に入金し、受贈者は、教育目的で使ったと分かる領収書などを金融機関に提出して払い出しを受けます。



但し、2019年4月1日以降に入金された資金に関しては、受贈者の前年の合計所得が1,000万円以上の場合、非課税にはなりません。
尚、定められた目的以外に使用されたお金や、受贈者が定められた年齢になった時の残額は贈与税の課税対象になり、贈与者が亡くなると、一定の場合を除き相続税が課税されます。
生命保険を活用する
生命保険は、①争族対策、②節税対策、③納税対策の全てに活用でき、資産家でも、財産がそれほど多くない人でも、一定の効果が見込めます。
生命保険が相続で活用できるのは、次のような特徴があるからです。
1つ目は、保険の保障対象となっている人(被保険者)が亡くなったとき、すぐに現金(死亡保険金)が準備できることです。
受け取った保険金は、葬儀代や当面の生活費、納税資金として使えます。
2つ目は、受取人を指定でき、死亡保険金が受取人の財産になることです。
遺産分割の対象とならないため、遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。
また、法定相続分とは別扱いなので、相続人以外にお金を残すことも可能。
生命保険は、受取人となる人が相続放棄をしたとしても、受け取れます。
被相続人に債務が多い場合、相続放棄せざるを得ませんが、そんな場合も保険金なら受け取れるというメリットがあります。
3つ目は、非課税枠があること。
相続人が受け取る保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税となるため、節税対策に有効です。



生命保険や共済などから支払われる死亡保険(共済)金は、契約者と被保険者、死亡保険金の受取人が誰かによって、税金の種類と掛かり方が異なります。
「契約者と被保険者が同じ」場合には「相続税」の対象となります。
死亡保険金の全額に課税されますが、相続人が死亡保険金を受け取る場合には、前述のように「500万円×法定相続人の数」まで、非課税になります。
「契約者と受取人が同じ」であれば、死亡保険金から、支払った保険料と特別控除額を差し引いた額が一時所得となり、一時所得の2分の1の額に対して「所得税と住民税」が掛かります。
「契約者と被保険者、受取人が全て別」ならば、死亡保険金は「贈与税」の対象。
他に贈与を受けた金額との合計額から110万円を差し引いた額に課税されます。



ところで、ここで「契約者」と言っているのは、保険料を実際に負担している人のことです。契約者以外の人が保険料を負担している場合には、「実質的な保険料負担者」と、被保険者や受取人との関係で、税金の掛かり方が決まります。
相続財産が多く、相続税の税率が高くなりそうなケースでは、親から子に毎年保険料を贈与し、「契約者と受取人=子・被保険者=親」という形で生命保険に加入する方法もあります。
この場合、死亡保険金は一時所得扱いとなります。



尚、生命保険の活用法は、その時々の法律や税制によって効果が変わる可能性も。数年ごとに確認が必要です。
- 生命保険でできる相続対策 -
- 節税
- 特定の相続人に多めに財産を残す
- 相続人以外の人に財産を残す
- 納税資金の確保
- 死亡保険金は、相続放棄をしても受け取れるので、債務がある場合に有効
小規模宅地等の特例
相続税は相続財産の総額に対して課税される税金のことで、現金は相続時の残高がそのまま評価額となりますが、土地や家といった不動産は、一定の方法で評価額が決定します。
不動産の評価額は評価される対象は同じでも、所有者や居住者によって評価額が変わるので、条件を利用して評価額を下げることで、相続税を低く抑えられます。



尚、評価額が下がったとしても、これはあくまで税額を計算するための価格なので、実際の価値は下がりません。
不動産の評価額が下がる時の最も多いケースは、自宅として住んでいる時です。
遺族の生活基盤を守るための配慮として、住んでいる自宅の土地は評価額が下がる仕組みになっています。
また、他人に貸している不動産がある場合も、不動産を貸すことで相続人が使用する権利を制限されてしまうため、評価額が下がるようになっています。



これは「小規模宅地等の特例」という制度が存在するからです。この特例により、評価額が最大で80%減額されます。この特例は不動産の面積が対象となるので、坪単価の高い土地ほど効果的です。
これを使うと、例えば5,000万円の居住用宅地が、1,000万円で評価されることになります。
これは大きな負担の軽減になります。
対象となる宅地は大きく分けて「居住用」・「事業用」・「貸付用」の3種類になります。
特例が適用されれば居住用と事業用は80%減額、貸付用は50%減額になるのです。
居住用宅地の場合、①被相続人が相続開始直前まで自宅として住んでいた土地であるか、②被相続人と生計を一つにしていた親族が住んでいた宅地である、のいずれかに当てはまる必要があります。



②の「生計を一つにしていた」というのは、例えば父親が所有している土地に、子供が自分たちで家を建てて住み、生活費を父親が出していたような場合です。
その上で、配偶者の場合、同居している親族の場合、別居している親族の場合で要件はそれぞれに異なってくるのでよく確認しましょう。
特に別居している親族の場合には細かい要件がいくつもあり、その全てに該当する必要があります。
土地の有効活用
相続における節税のポイントは、大きく分けて2つです。
「財産そのものを減らす」こと、そして「評価を減らす」ことです。
自分にとって価値があるものでも、評価額が下がれば相続税は安くなります。
アパート・駐車場経営
相続税の節税対策として従来から行われている方法に、使っていない土地に「アパートなどを建てて賃貸経営する」という方法があります。
相続税の財産評価では、アパートやマンションを建てて他人に貸している土地=貸家建付地の場合、評価額が下がります。
アパート建築のために現金を支出することで財産も減少。
銀行から借金をした場合でも、債務として相続財産から控除できるため、課税財産を減らすことができます。
一方で、アパートを建てると家屋という財産が増えます。
しかし、家屋はもともと評価額が低く、貸家であれば、更に「貸家権割合」が引かれるので、財産の評価額を圧縮できます。
加えて、アパートの敷地は「貸付事業用宅地」に該当するので、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を適用できます。



また、アパート経営は家賃収入というおまけも付いてきます。その結果、財産が増えますが、生命保険の保険料に充てたり、生前贈与を行うなど、相続税対策の幅が広がります。
アパート経営は上手くいけば非常に節税効果の高い方法です。
でも、それは机上の話。
実際には「経営=事業」の難しさがあり、リスクを常に意識しなくてはなりません。
先ず「空室のリスク」です。
空室が増えれば、建築費用を回収できず、赤字経営が続きます。
アパートが老朽化すれば、なおさら空室率が高くなり、賃料を下げざるを得なくなるでしょう。
行く行くは大規模修繕費用も必要になります。



仮に、経営が安定し、上手く節税できたとしても、アパートは「相続の際に分けにくい」というデメリットがあります。更地にして売却することも簡単にはできません。
アパート経営は、節税目的よりも、先ずは事業として有望かどうか、その事業を自分や家族ができるかどうか、遺産分割で問題が起きないかどうかを慎重に考えて判断しましょう。
- アパート経営のメリット -
- 土地の評価額が下がる
- 建築費用と建物評価額の差額の分が節税できる
- 小規模宅地等の特例を利用できる
- アパートなどの家賃収入が納税資金対策にもなる
- アパート経営のデメリット -
- 空室リスクがある
- 修繕費が掛かる
- 不動産価格下落のリスクがある
- 売却しにくくなる
- 財産の分割がしにくい
尚、土地の有効活用として「駐車場経営」という方法もあります。
アパート程の節税効果はありませんが、設備投資が少なく済み、比較的リスクの低い方法です。
それでもアパート経営同様、事業として有望かどうかなどをしっかり見極めて判断することが大事です。
土地の利用区分を変更する
土地は、宅地、田、畑、山林、雑種地などの「地目の別」に評価することになっています。
また、宅地は「1画地」を単位として評価します。
1画地とは、自分で利用している土地(自用地)、貸している土地、貸家の敷地といった「利用の単位となっている一つの区画」のことを言います。
ところで、路線価地域(市街地)にある宅地の場合、角地や二方に道路がある宅地は評価が高くなります。
また、その価額は、土地が接している道路のうちで最も高い路線価をベースにして決められます。



そこで、比較的広い土地が複数の道路に面している時は、土地の利用区分を変更・分割することによって、土地の評価額を下げることができます。
評価の区画が変わり、側方路線や二方路線の影響がなくなる場合があるからです。
特に、一方が幹線道路など路線価の高い道路に面している場合には効果的です。
等価交換方式を利用する
土地の有効活用を行いたいが、そのノウハウがなかったり、多額の資金を負担できず、自分では手が付けられないといったケースがあります。



こんな場合に検討されるのが、等価交換方式です。等価交換方式とは、地主とデベロッパー(土地開発業者)とが共同で、主に貸ビルや賃貸マンションなどを建設する事業方式の一つです。
地主は土地を、デベロッパーは建築費を出資して建物を建設します。
その後、土地の一部と建物の一部を「等価」になるように交換し合い、それぞれが土地・建物を所有するという方法です。
この方式を利用すれば、地主は土地の一部を手放すことにはなりますが、資金を全く負担せずに建物を手に入れることができます。
借入金が発生しませんので、返済のリスクもありません。
また、設計から施工、建築後の管理までを一括でデベロッパーに委託でき、デベロッパーの各種ノウハウを活かした資産価値の高い物件の取得が可能になります。



しかしその反面、設計や土地の評価額、交換比率などの面においては「デベロッパー主導」になりやすいという感は否めません。
- 等価交換方式のメリット -
- 借入金が発生しない
- 土地が貸家建付地として評価される
- 建物部分を賃貸にすれば賃貸収入が期待できる
- また、貸家の評価減も実現できる
- 設計や建築後の管理をプロに一任できる
- 等価交換方式のデメリット -
- 土地の一部を手放すことになる
- 設計、土地の評価額、交換比率などにおいてデベロッパー主導になりやすい
- デベロッパーが取得部分を譲渡した場合、権利者などが多人数になる
尚、このような土地の譲渡に対しては譲渡所得税が課税されますが、一定の要件を満たす場合には、特例により課税の繰り延べを受けることができます。
借地権と底地を交換する
地主さんが所有する土地の中には、先代或いは先々代から安い地代で他人に貸しているといったケースがよく見られます。
旧借地法による借地権は借地人の権利が非常に強く、いったん土地を貸したら、もう地主のところには戻ってこないというのが実情です。
土地を有効活用したり納税資金のために処分したいと思っても、地主の自由にはなりません。
もちろん借地人の側にも簡単には立ち退けない事情があるでしょう。



この解決策として有効なのが、借地人の借地権と地主の底地を交換する方法です。例えば、借地権割合70%の場合なら底地70%と借地権30%が等価になりますので、これを交換し、両者が借地権の付着しない土地を所有するのです。
もろちん「借地人の合意」が必要ですが、双方にメリットのあることなので、交渉してみる価値は十分あります。
また、税制上の優遇措置も受けられます。
このように同種類の固定資産を等価で交換し、一定の要件を満たす場合、譲渡はなかったものとして譲渡所得税が課税されません。
この特例を受けるためには「確定申告書の提出」が必要です。
- 地主のメリット -
- 完全所有権になり、土地の有効活用が可能
- 相続税の納税資金として売却もできる
- 譲渡所得税が課税されない
- 借地人のメリット -
- 借地権が所有権に変わり、資産価値が上がる
- 担保の設定や売却もできる
- 譲渡所得税が課税されない
空家の相続
相続と並んで困っている人が多いのが、空家になった実家の扱いです。
相続は、「欲しいものだけを選んで受け継ぐ」ということができません。
そのため、もう住む予定のない不動産であってもまとめて取得することになります。
空家相続で困るのが、1つは管理の問題です。
住人がいないと傷みが進むので、時々換気をしたり、庭の草むしりをしたりする必要があります。
遠方だとかなりの手間が掛かります。
2つ目の問題が、維持費です。
管理のために、水道・電気・ガスなどの料金を払い続けなければならない上、固定資産税も掛かります。
遠方の場合、交通費も馬鹿になりません。
さらに、3つ目の問題として、売った時の税金があります。
何とか売却できたとしても、支払う税金が多額になりがちで、相続人が負担に感じることもあります。
その結果、売れない・使われない空家が増えてしまい、社会的な問題になっています。



そんな、空家の増加を防ぐためにも、空家を相続した相続人が譲渡しやすいよう、「空家に掛かる譲渡所得の特別控除」が創設されました。
これにより、2016年4月以降に相続した空家を2027年12月31日までに譲渡した場合、一定の要件を満たすと、譲渡益から3,000万円が控除されます(2025年7月現在)。
- 譲渡価格-取得費-譲渡費用(仲介手数料等の諸経費)-特別控除=譲渡所得
- 譲渡所得×税率=所得税額



特別控除を利用すると所得税を大幅に節税できます。空家の譲渡益が3,000万円までなら所得税は0円、ということになるのです。
養子縁組で相続人を増やす
相続人が少ない時は、嫁や孫などを養子にし、相続人を増やすのも一法です。
相続人の数が増えると、次の節税効果があります。
- 基礎控除額が増える … 相続人が一人増えるごとに、基礎控除額が600万円増加する
- 累進税率が下がる … 各相続人の「法定相続分に応じた取得金額」が小さくなるので、適用される累進税率の区分が変わることがある
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠が大きくなる … 相続人が一人増えるごとに、非課税金額が500万円増加する



但し、相続税の計算上、法定相続人に含める養子の数には制限があります。実子がいる場合は一人、実子がいない場合には二人までです。
養子縁組は、節税だけでなく、相続権のない人に財産を相続させるための手段としても有効です。
世話になった嫁に財産を与える時などは、養子縁組の制度を積極的に活用すると良いでしょう。
遺贈の方法もありますが、嫁への遺贈は相続税が2割増しになります。
嫁を養子にすれば、2割加算の対象から外れるだけでなく、法定相続人が増えることにより基礎控除額が増えるなど、節税の面でも多くのメリットがあります。



尚、孫を養子にするケースも多く見られますが、孫は養子でも2割加算の対象になる点に注意しましょう。
嫁を養子にするリスクとしては「離婚」が挙げられます。
息子夫婦が離婚しても養子縁組は解消しませんし、嫁の財産はいずれ孫のものになる、という目論見も外れる場合があります。
その意味でも、節税だけを目的とした養子縁組は好ましくありません。
また「税務上」も、明らかに租税回避と認められる養子縁組は、相続税計算上の法定相続人の数に含めない扱いになっています。



養子縁組については、メリットとデメリットをよく考えて実行しましょう。実行の際は、少なくとも「他の相続人の同意を得る」などの配慮が必要です。
生前にできるその他の対策
墓地や仏壇を購入する
先祖代々のお墓に入る予定がなく、お墓を新たに用意する必要があるなら、死亡後ではなく生前に購入しておくのがお勧めです。
墓地、墓石、仏壇などの祭祀財産は、相続税法上「非課税財産」とされており、相続税の課税対象にならないからです。
相続開始後に遺族などが購入した場合は、購入した人の財産になります。
被相続人が残した財産ではないため、このメリットが生かせません。
また、相続後は葬儀の準備や諸手続きで慌ただしく、その意味でも生前に余裕を持って準備することをお勧めします。



尚、墓地などをローンで買って返済中に亡くなった場合、未払金は債務控除の対象になりません。節税効果のためなら、なるべく現金で購入しておきましょう。
孫に贈与する
財産は通常、親から子、子から孫へと承継されるものですが、子を飛び越して孫に贈与することで、相続税の課税を1回免れることができます。
相続時に孫に遺贈することでも同様の効果を得られますが、この場合は相続税が2割増しになるため、生前に贈与する方が得策です。
また、生前贈与であれば、相続財産の減少という効果もあります。
しかも孫などの「相続人でない者への贈与」なら、相続開始前3年(7年)以内の贈与であっても相続財産に取り込まれません(孫が遺贈を受ける場合を除く)。



尚、贈与は当事者の契約に基づいて行い、受贈者が贈与財産を管理する必要がありますが、幼児(未成年者)の場合には「親権者」が管理を行うことになります。
自宅の建替え・リフォーム
もし家の建替えやリフォームを考えているなら、生前に行う方が節税効果があります。
財産を現金で持っていると、相続税評価額は額面通りで評価されますが、建替え直後の家屋は建築費用の50~70%、リフォームはその家の固定資産税額にリフォーム費用の70%を加算した額が評価額になるからです。
固定資産税評価額が増加しない小規模なリフォームであれば、リフォーム費用の全額を相続財産から減らせる場合もあります。



とは言え、単に節税できるからという理由で建替えやリフォームに踏み切るのは本末転倒です。あくまでも「必要があれば」というのが大前提です。
相続税の納税資金対策



2つ目は「納税資金対策」。相続税の納税資金をどのようにして準備するか、という問題です。特に相続財産の大半が不動産といったケースでは、これを怠ると大変な事態になりかねません。
相続税は、相続発生から10か月以内に現金一括で納めるのが原則です。
期限までに納税できない場合は、延納や物納という方法もありますが、いずれも条件が厳しく簡単には利用できません。
また、延納に掛かる利子税はかなり高額なため、場合によっては銀行でお金を借りて相続税を払った方が有利なケースもあります。
納税資金を予め準備する方法としては、生命保険の活用や不動産の売却などがあります。
一般に同じ金額なら、現金で所有するより不動産で所有した方が評価額が低くなり、節税効果は高いです。
しかし、節税に努めるあまり、肝心の納税資金を確保できないのは本末転倒です。
バランスをよく考えながら、対策を立てなくてはなりません。



納税資金の対策では、生命保険の活用が効果的です。保険の種類は、死亡時に必ずもらえる「終身保険」がベストでしょう。
相続税法では、相続人が受け取った生命保険金のうち、1人当たり500万円までは非課税としています。
これを活用して、納税に保険金を充てることができれば助かります。
但し、非課税の対象となる保険契約は、「被保険者・契約者=被相続人」、「保険金受取人=相続人」の死亡保険金の場合に限られます。
保険に加入する際は、種類や契約内容を慎重に検討することが大切です。
- 生命保険を活用する … 生命保険金で納税資金の不足額を補う
- 金融資産を増やす … 財産が不動産ばかりという場合は、売却して金融商品で運用することも検討
- 現金収入を得る … 土地の有効活用などにより現金収入を増やし、支払い能力を高める
- 物納の準備 … 物納候補地の選定や、物納しやすい環境の整備など
- 節税対策をして、相続税額を減らす … 節税対策によって相続税が減れば納税資金の負担も減るので、無理のない範囲で節税対策を行う



どんな対策がベストか、無理なく納税できる方法を考えましょう。
- 納税資金対策 -
- 納税額の概算を把握していますか
- 納税資金の不足を補うための生命保険に加入しましたか
- 生命保険は終身保険ですか
- 生命保険の種類や契約内容を見直しましたか
- 財産が不動産ばかりの場合、不動産の売却について検討しましたか
- 延納の担保は準備されていますか
- 物納する予定の場合、物納財産や候補地の選定は済んでいますか
- 物納候補地の調査や要件の整備は行いましたか
遺産分割(争族・争続)対策



そして3つ目が、遺産分割を円満に行うための対策、いわゆる「争族・争続対策」です。たとえ節税や納税対策が万全でも、財産の分配を巡って相続人の間で争いが起こったのでは意味がありません。
- 遺産分割対策 -
- 遺言書を作成していますか
- 家族(親族)と遺産分割について話し合いましたか
- 残される配偶者の生活費などについて話し合いましたか
- 遺言がある場合、遺留分を侵している相続人はいませんか
- 法定相続分と大きく異なる遺産分けをする場合、家族(親族)は納得していますか
遺言書
遺産の分割については、相続人で話し合って決めることができれば理想的ですが、全員が納得するようにまとめるのはなかなか難しいものです。
皆がそれぞれに好き勝手なことを言い出して、収拾が付かなくなるといった事態に陥りがちです。



そこで、トラブルを未然に防ぐためにも、被相続人は自分の財産を誰に、どのように分配したいのかを、きちんと伝えるのがベスト。それを確実にするのが「遺言書の作成」です。
例えば、子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合には、全ての財産が妻のものになるのではなく、被相続人の親又は兄弟姉妹にも相続する権利が生じます。
しかし、このケースで「配偶者に全ての財産を相続させる」という遺言があれば、相続財産の全てが配偶者のものになるのです(親が相続人の場合は親に遺留分の権利あり)。
他にも遺言が必要なケースを下記👇に挙げました。
掲載していないケースでも、少しでもトラブルの心配があれば、遺言を作成しましょう。



また、遺言の内容は、相続人間に不公平を生むこともあります。その場合は、そのような財産の分け方にした理由を「付言事項」という形で遺言に書き添えると良いでしょう。
付言事項に法的効力はありませんが、遺言者がなぜこのような分け方にしようと考えたのかが分かると、財産を引き継ぐ側も冷静に受け止めやすくなります。
付言事項を書くことで全ての相続トラブルが防げるわけではありませんが、一定の効果はあるでしょう。
遺言書は通常、公証人に作成してもらうか自筆で書くことになります。
遺言書は何度でも書き換えることができるので、特に家族関係が複雑な場合は作成をお勧めします。
また、遺産の分割に関して最も大切なのは、残された配偶者の生活を考慮することです。
これについても親族間でよく話し合っておくことが必要でしょう。



亡くなった後のことは誰かに任せるしかありませんが、遺言書を用意すれば、自分亡き後の財産処分などについて、自分の希望を伝えることができます。
信託
信託は、信託銀行などに財産を預けて管理してもらう仕組みです。
「毎月〇〇円を指定口座に振り込む」などの条件を付けて契約することができるので、認知症の人や知的障害者、未成年など、判断能力が不十分な人が相続人になるとき、安全に財産を引き継ぐことができ、後見人が財産を勝手に使ってしまう事件も防げます。
申し込み時と管理時、手続きなどの実行時には、所定の手数料や報酬が掛かります。



信託とは、「委託者」が「受託者」に金銭などの財産を移転し、受託者は、委託者が設定した信託目的に従って、「受益者」のために、その財産を管理・処分する制度で、様々な種類があります。
遺言書を預け、遺言の執行まで依頼する「遺言信託」は、初期手数料と執行時の報酬で100万円以上と高額になりますが、最近では、安価な手数料で少額から利用できる商品も登場しています。
遺言書を作っておかなくても、死亡後の受取人を指定できるのが「遺言代用信託」。
預けた人(委託者)が生きている間は自分が受取人(受益者)になるように信託を設定し、自分が死亡した後は、妻や子などが受益者になるように決めておくことができます。
認知症の妻の施設の利用料を定期的に払ってもらいたいという時などに利用できます。
「生命保険信託」は、生命保険の死亡保険金を信託銀行に預けて、指定した人に定期的に支払うなどの管理をしてもらうもの。
最初の受取人が亡くなった後の、次の受取人も決めておくことができます。
「特定贈与信託」は、重度の心身障害者や中軽度の知的障害者・精神障害者が受益者となる時に、6,000万円或いは3,000万円までは贈与税が非課税となる制度。
親が子のために信託を設定するなどの利用が考えられます。



信託は、財産を預けて、安全に管理・処分してもらう仕組みです。財産の行方が心配なら、遺言や信託の利用も検討しましょう。
相続対策のポイントと注意点
二次相続を踏まえる
親からの相続で、両親どちらか1人目からの相続を一次相続、もう1人も亡くなった時の相続を二次相続と言います。
相続対策では「二次相続」まで考えることが大切。
二次相続では、兄弟間の争いが増え、また、税金負担が一次相続より重くなることがあるからです。
例えば、1回目の相続(一次相続)で父親が亡くなり、2回目の相続(二次相続)で母親が亡くなったとします。
一次相続では、母親が「配偶者の税額軽減」を使えるので、これを限度額まで使えば相続税の負担を大きく減らすことが可能です。
しかし、二次相続では、配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人が1人減るので、基礎控除額も減ってしまいます。
兄弟間の争いが増える原因の一つが、間に立つ親がいなくなること。
仲裁に入る親がいなくなり、親への気遣いもなくなるため、子供の時からの待遇や看護・介護負担の不平等の不満をぶつけ合うケースもよく見られます。
また、他の兄弟が相続した財産は、将来、自分には戻ってこない可能性が高いということも、二次相続を難しくしています。
例えば、親と同居していた長男が相続した実家は、長男に子がいなければ、将来は長男の妻の親族のものになる可能性も。
そのことに割り切れない思いを抱くこともあるかもしれません。
だからと言って、不動産を相続人全員で共有名義にしておくと、その次の相続の時に相続人が増えて大変なことに。



将来の相続へ揉めごとを残さないよう、先ず、関係者で話し合うことが大切。その上で、遺言書や資金準備、場合によっては養子縁組なども検討しましょう。
- 兄弟関係や遺留分に配慮した遺言書を準備しておく
- 分割の希望や方針を子供たちに伝えておく
- 遺言書の付言や、エンディングノートを活用して、気持ちを伝えておく
資産家や事業を営んでいる人は、二次相続を見込んだ対策が特に重要。
二次相続では、一次相続より税負担が重くなりがちなので、二次相続を見込んだ節税対策が必要に。
また、事業を継ぐ人に財産を集中させないと事業を続けられなくなることもあり、単なる財産分けとは違う視点での対策も検討すべきです。
- 小規模宅地等の特例が使えるようにしておく
- 一次相続で二次相続まで考えた配分にする
- 生前贈与をして、相続財産を減らしておく



前項までで、生命保険、遺言書や信託、不動産、生前贈与などを利用した具体的な相続対策について、説明してきました。一つひとつの具体的な対策を行うに当たっては、その前提として大まかな方針を決めておくこと、それを子供たちに説明して了解を取っておくことも大切です。
長生きする女性は、二次相続で被相続人になることが多く、その役割は重要。
同居する子に家を残すと不公平が生じるなら、その他の子に納得してもらうよう話しておくのも親の役目。
面倒を見てくれた子やその配偶者へどう報いるか、子供たちの関係に禍根を残さないよう、総合的な対策を検討しましょう。
子供がいない人であれば、親亡き後は兄弟や甥・姪が自分の相続人になります。



夫が亡くなった時の対策ばかり考えがちですが、自分の死後整理を誰に託すかということも含めて、相続対策をしておくことを忘れないで下さい。
短期間の間に相続が立て続けに起こってしまった場合、納税負担が非常に重くなることから、相続税では、「相次相続控除」と呼ばれる税額控除があります。
この控除は、一次相続から10年以内に相続が起こった場合に適用できます。
但し、二次相続の相続人が、一次相続の際に相続税の納付額がゼロの場合は、相次相続控除はありません。
生前対策に伴うリスク
相続対策は、現在の家族関係や財産、法律などを基に考えるもの。
しかし、私たちを取り巻く状況が、今後ずっと変わらないということはありません。



最も気を付けたいのは、家族の生死や結婚、離婚です。相続人となる人や法定相続分が変わってしまうからです。
例えば、独身で子供がいない人の相続人は、親、又は兄弟姉妹(或いは甥・姪)ですが、結婚して子供ができれば、相続人は配偶者と子に。
離婚や再婚でも、その度に相続人は変わります。
死亡保険金の受取人に指定していた人が先に亡くなった場合には、そのままにしておくと、自分が亡くなった時の死亡保険金が、既に亡くなっている受取人の相続人に支払われることになります。
分割の対象になる財産も、時間が経つごとに変わるものです。
誰かに相続させる筈だった預金を家のリフォームや介護で使ってしまった、生命保険を解約してしまった、不動産を売却したなど、財産に大きな変化があった時には、せっかくの遺言が意味をなさなくなることもあります。



自分自身の心境の変化もあるので、相続対策は一度行なったらそれで終わりではないと考えておきましょう。家族関係の変化や税制改正があった時はもちろんですが、何もなくても年に一度くらいは対策を見直しておくと安心です。
相続(税)対策は、生前のできるだけ早い時期に着手し、時間を掛けて行うのが基本です。
期間が短いとそれだけ無理が生じますし、相続開始直前の対策は効果を生じない場合もあります。



しかし、生前対策はいずれも机上の計算に過ぎません。将来の、いつ起こるか分からない「相続」を相手にするのですから、多かれ少なかれリスクが伴うことを忘れないで下さい。
また、税法や関連法規の知識も不可欠ですので、必ず税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナー、不動産コンサルタントなどの専門家と相談しながら行うようにしましょう。
- 相続(生前)対策に伴うリスク -
- 税制改正や経済情勢の変化
- 被相続人の財政の変化
- 税法の誤解・知識の不足
- 家族関係の物理的・感情的変化
- アパート経営などに伴うリスク



そして、もう一つ。相続税対策と言うと「節税」に偏重する傾向がありますが、本来は「納税資金対策」を先行して考えるべきです。
先ず、現状でどれだけの相続税が掛かるのかを割り出し、納税額に足りる金融資産があるかどうかを確認、不足するならどのように確保するのか検討します。
その上で、もっと税負担を軽くすることはできないか、というように考えると目的がはっきりします。
まとめ
「遺産争いなんて資産家だけのもの」と思っている人も多いかもしれません。
しかし、相続財産の多少に関わらずトラブルは起きますし、仲の良い家族でも残念ながら争いが起きる可能性があります。
相続での争いの種は、些細な感情の行き違いから、生活を脅かすような大きな問題まで様々です。
一番トラブルになりやすいのは、主な相続財産は被相続人の自宅だけであり、相続人が複数いるケースです。
自宅を売却し、売却代金を法定相続分通り分けられれば良いですが、実際には、配偶者や特定の相続人家族がその家に住んでいるケースもあり、そう簡単に売却できないことが多いでしょう。
さらに、相続人の1人だけが多額の贈与を受けている、又は、別の相続人が介護を一手に引き受けていたなどの場合、話は一層まとまりにくくなり、場合によっては裁判所で争うという事態も起こります。
財産が多ければ、相続税をできるだけ減らしたいと思うでしょうし、将来、納税するための資金準備も欠かせません。



財産が多くなくても、家族が相続トラブルに巻き込まれるのは避けたいはず。どんな立場の人にもそれぞれやっておくべき対策があるのです。
相続対策には、
①遺産分割対策
②納税資金対策
③節税対策
の3つの柱があります。



一番大切なのは、①の遺産分割対策です。被相続人の一番の願いは、残された家族が幸せに暮らすことでしょうし、残された家族も相続で仲違いすることを、望んではいないでしょう。
争族、つまり、親族間で争いが起きるのを避けるための対策は、財産を分けやすい形にしておいたり、生命保険を利用したり、遺言書を作っておくことなど。
具体的に対策を立てておく程ではなくても、自分の気持ちや希望を口頭で伝えたり、エンディングノートなどに書いておくことはとても大切。
争いを防ぐ効果が大きいでしょう。
遺言書に家族へのメッセージを加えても構いません。



財産を譲りたい人に生前に贈与するのも一つの方法です。非課税制度を活用すれば、節税対策にもなります。
その他の節税対策として、土地を多く持っているなら、土地活用で評価額を下げたり、小規模宅地等の特例を利用できるようにしておくと良いでしょう。
多額の相続税が掛かる人は、納税資金の準備も必要。
相続税は相続開始日(被相続人死亡時)から10か月以内に納めることになっていて、納付が遅れると延滞税が上乗せされます。
不動産を処分したり、売りやすい物件に買い替えておいたり、生命保険の死亡保険金を受け取れるようにしておくと良いでしょう。



相続対策と言うと、③の節税対策のことばかり考えがちですが、節税よりも大事なことは、残された家族が争わないように「遺産分割対策」を最優先に考えること、その上で、確実に納税できるように準備し、無理のない範囲で節税対策を行いましょう。
相続の手続きでは、相続人が誰かを証明する書類として、亡くなった人の誕生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、親が生まれた頃からのものも要ります。
戸籍は、親子関係と結婚の記録で、家族関係を知ることができます。
転籍と言って本籍を移した時には新しい戸籍が作られます。
また、過去に何度か戸籍法の改正があり、改正前の改製原戸籍謄本というものも存在します。
これらを全て揃えるのは大変な作業です。



相続対策など必要ないという人も、最低限、自分の相続人を証明する戸籍謄本を全て揃えておくと、残された家族は、手続きがグンと楽になります。
最新の謄本以外は内容の変更がないため、相続の手続きでは、発行日が古くても、用意した謄本を使うことができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。