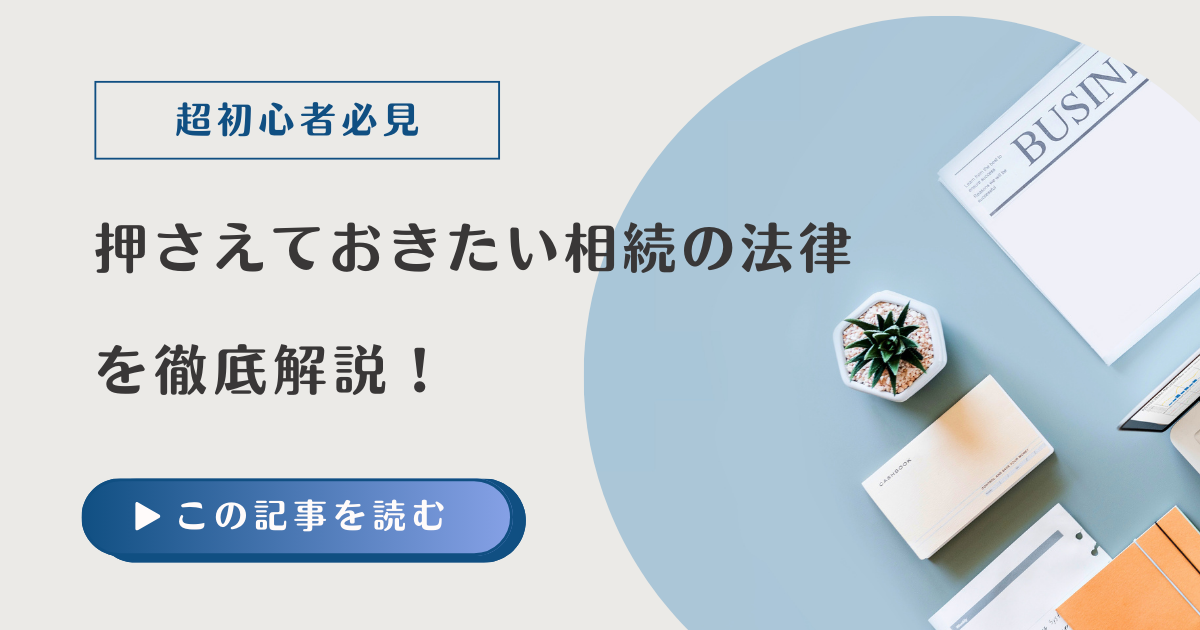悩める人
悩める人そもそも相続ってなんだろう?
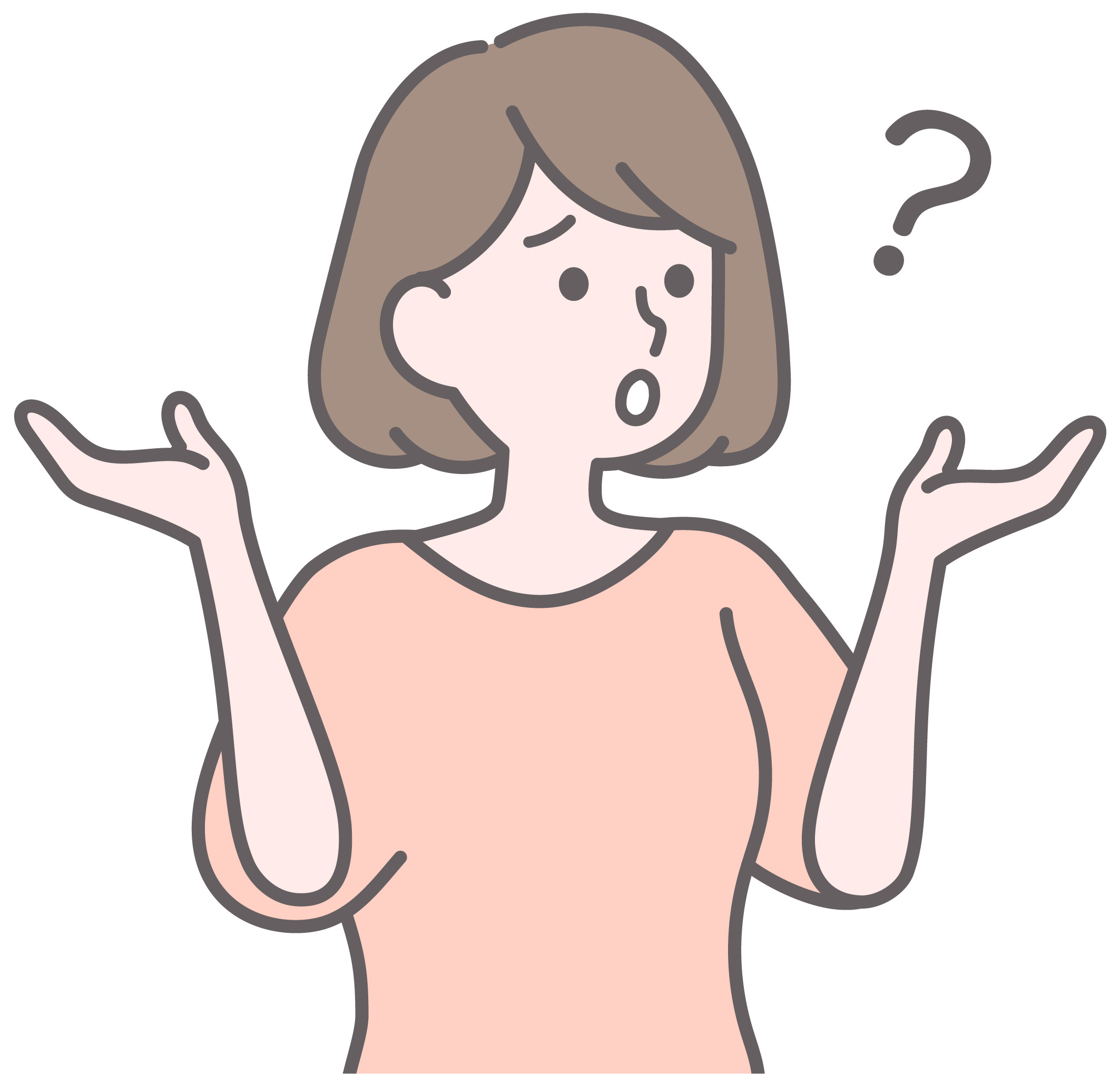
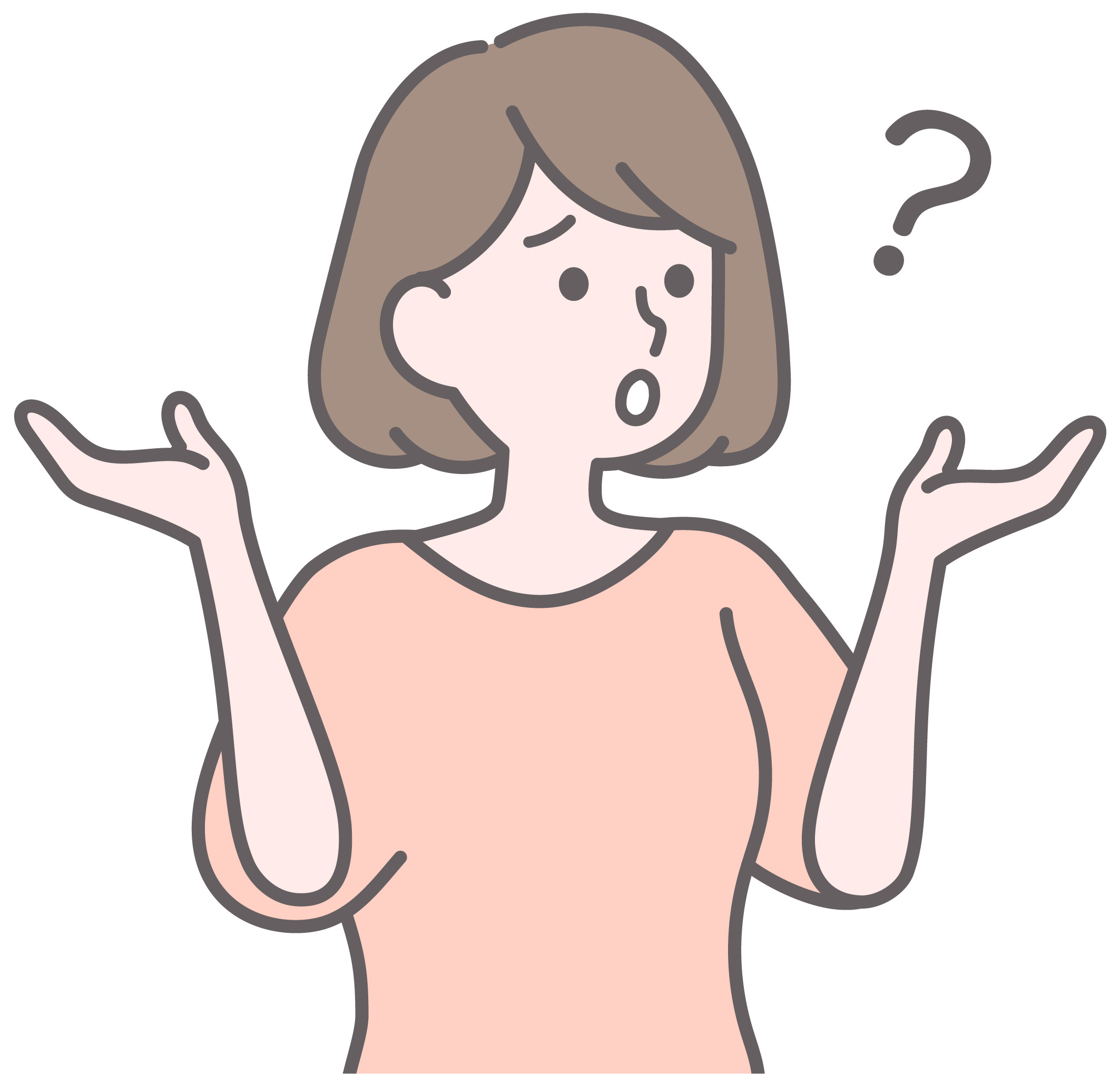
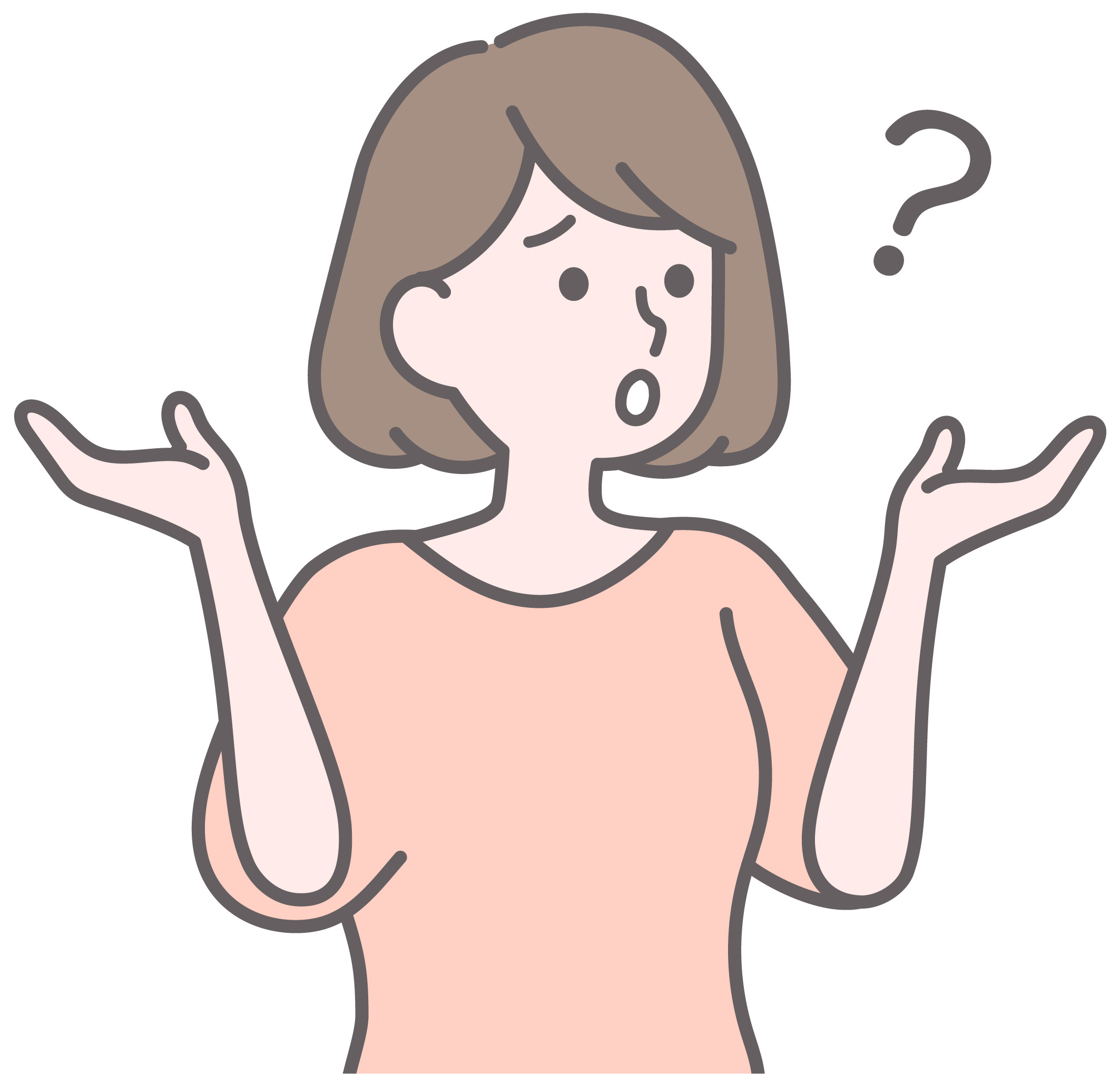
相続に関する法律の決まり?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 財産を受け取れる人の範囲 / 誰が受け取れる?
- 財産を受け取れる分量 / どれだけ受け取れる?
- 財産を受け取る方法 / どうやって受け取る?
相続とは
相続とは、ある人が死亡した場合、その人が持っている「正の財産」、或いは「負の財産」を、その人の子や配偶者などが受け継ぐことです。
この場合、財産を残す人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。



相続を考えるに当たって、「相続人」と「被相続人」は、一番最初に是非とも理解しておきたい言葉です。この2つの言葉はよく混同されるので、注意が必要です。
先に正の財産・負の財産という言葉が出てきましたが、正の財産とは、例えば現金、預貯金、不動産、株や商標権などのことを指し、負の財産とは、例えば住宅ローンやクレジットの未払金、手形金といったものを指します。
こうした「財産上の権利義務」が、人が亡くなった瞬間に、丸ごと相続人に移転するのです。
正の財産だけが相続の対象になると思われがちですが、負の財産も相続されることを十分理解しておく必要があります。



とは言え、これはあくまで法律上の話です。相続開始時において不動産や預金は故人の名義のままなので、実際に財産を自由に使えるようにするためには、相続人が名義変更などの手続きを行なってからになります。
原則として、被相続人の全ての財産上の権利・義務が、相続人に引き継がれるのが相続ですが、その人個人のみが持つ「一身専属権」は、相続の対象になりません。
一身専属権とは、運転免許や医師免許、生活保護受給権などです。
一身専属権は、本人の死亡により消滅します。



その人にしか行使できない資格や権利は引き継ぎません。
相続は、財産をあげる人やもらう人の意思とは関わりなく、人が亡くなると自動的に始まります。
被相続人がその時期を決めたり、相続人を選んだりすることはできません。
相続の法律
さて、相続は、「民法」という法律に定められています。
民法は、個人や法人の財産関係などを定めている法律です。
その中で相続は、個人が死亡した時の財産関係についての規定が、細かく決められています。
相続の規定には、具体的に次のような項目があります。
- 財産を受け取れる人の範囲
- 財産を受け取れる分量
- 財産を受け取る方法



次からは、この3つの項目に従って説明を進めていきます。
誰が遺産を受け取れる?
指定相続
現在、日本には「自分の財産の使い方は自分で決めて良い」という原則があります。
相続の場合も同じで、相続の際は、遺産を残す被相続人の意思が最優先されます。



被相続人は、自分の意思を「遺言」に残し、自分の意思通りに遺産を相続人に相続させることになります。これを「指定相続」と言います。
しかし、この原則を貫くと、困ったことになることもあります。
残された家族を差し置いて、他人に全財産を与えることを許すと、遺族の生活が立ち行かなくなってしまうかもしれません。
このため、遺族には、後述する「遺留分」という最低限の遺産の受け取り分があります。



つまり、被相続人が遺言で本当に自由にできる財産は、全財産から遺留分を除いた部分ということになります。
法定相続人
被相続人が遺言を残さずに死んだ場合や、遺言で誰が相続人になるかについて触れられていない場合、遺言書が形式不備などの理由で無効となってしまった場合は、法律(民法)で定められた親族が相続人となります。



この民法で決められた相続人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人には、大きく分けて「配偶者相続人」と「血族相続人」との2つがあります。
- 配偶者相続人 … 被相続人の妻又は夫
- 血族相続人 … 被相続人の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹
では、誰に法定相続人の資格があるのでしょうか?
先ず、被相続人の配偶者は、いれば必ず相続人となります。
被相続人の子も、いれば必ず相続人になります。
ここで言う「子」とは、養子縁組をした養子や、他家に養子に出した実子も含まれます。
被相続人に子がいない時は、被相続人の両親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属同士の優先順位は、被相続人に近い親等の人から相続人となります。
例えば、被相続人の父と祖母が存命している場合、父のみが相続人となります。
被相続人に子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の間には、優先順位はありません。



配偶者相続人、すなわち夫また妻は常に相続人になりますが、血族相続人には順位があり、最上位の者だけが相続人になります。血族相続人の順位は、次の通りです。
- 第1順位 … 子(又はその代襲相続人)
- 第2順位 … 父母などの直系尊属
- 第3順位 … 兄弟姉妹(又はその代襲相続人)
嫡出子・非嫡出子
前に挙げた「子」とは、被相続人の戸籍上の子でなければなりません。
被相続人と配偶者が、正式な婚姻中に生まれた子(嫡出子)はもちろんこれに当たります。
しかし、例えば愛人の子など正式な婚姻によらない子(非嫡出子)は、被相続人の「認知」を受けなければ相続人となることができません。



但し、非嫡出子は、生母に対しては、認知がなくても常に第1順位の相続人です。
認知は、被相続人が生前に認知の届け出を出す方法が一般的ですが、子が育ってからの認知や遺言による認知、DNA鑑定による死後認知も可能です。
相続欠格
法定相続人に該当すれば、誰でも相続する権利があるかというとそうではありません。
例えば、財産欲しさに親を殺した子に、財産を相続させるのは問題があるでしょう。
このように財産を得るために反社会的な行為をした相続人は、法律で相続人になれないようになっています。
これを「相続欠格」と言います。
以下のような場合、相続欠格に当たります。
- 被相続人や相続人を殺害した
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった
- 詐欺や脅迫によって遺言を妨げた
- 遺言書を偽造した



これらに該当する者は、何の手続きも必要なく、相続権を失います。また、遺贈を受けることもできません。
相続廃除
前に述べた相続欠格は、生命に対する侵害行為と、相続において一番重視される遺言への妨害行為に対する処置です。
ただ、ここまではいかなくても、「この人には財産を受け取らせたくない」と思う相続人がいるかもしれません。
この場合、いくら遺言で遺産を残さないことにしても、法定相続人には、後述する「遺留分」の権利があるので、一文も相続させないわけにはいきません。



こんな場合は、家庭裁判所に申し立てるか、遺言するかによって、「相続人廃除」の審判を受けることができます。これは、相続人の権利をはく奪するもので、認められると遺留分の権利も主張できなくなります。
相続廃除とは、その相続人から相続の権利を失わせることです。
審判による決定で、廃除された者は相続人になれなくなります。
具体的には以下のような場合に廃除することができます。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に重大な侮辱を与えた
- その他の著しい非行があった
但し、相続廃除は、被相続人の意思により、いつでも取り消すことができます。
尚、兄弟姉妹は廃除の対象になりません。
これは兄弟姉妹には「遺留分」がないためです。



兄弟姉妹に相続させたくない場合は、その旨の遺言を作成すれば良いのです。
また、廃除が認められると、該当する相続人は相続する権利を失いますが、相続放棄とは違い、代襲相続は認められます。
代襲相続
何らかの原因で、本来相続人になるべき人が相続人になれない場合があります。
前に述べた相続欠格や相続廃除の場合もありますが、主にその原因となるのは、被相続人よりも相続人になる予定の人が早く死んでしまうような場合です。
そのような場合は、本来相続人になる筈だった人の「子」が代わりに相続することになります。
子が相続する筈だったのに、子が親より早く死んでしまった場合は子の子、つまり被相続人の孫が、孫も既に死んでいた場合は孫の子、つまり被相続人の曾孫が相続人となります。



これを「代襲相続」と言い、代襲相続する人を「代襲相続人」と言います。
相続人になる筈だった人が被相続人の子だった場合、代襲相続に「何代まで」といった制限はありません。
しかし、相続人になる筈だった人が被相続人の兄弟姉妹だと、代襲相続は「一代限り」、つまり被相続人の甥・姪までと制限されています。
親が相続人となる筈だった場合は、逆に上の代に遡ります。
また、本来相続人となるべき人が相続人にならない場合にもう一つ、後で述べる「相続放棄」のケースがあります。
相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しないのです。
代襲相続が起きるのは、
- 相続開始以前の死亡
- 相続欠格
- 相続廃除
の3つの場合だけです。



相続放棄も、相続人となるべき人が相続人にならないという意味では似ていますが、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものと見なされます。従って、代襲相続は起こりません。
相続人不存在
相続人となるべき人の死亡や相続欠格・廃除、相続放棄などで、最終的に相続人がいなくなってしまうことがあります。



これを「相続人の不存在」と言います。
遺言によって、財産を受け取ることになっている第三者(受遺者)がいて、受遺者の受け取るべき財産が具体的に指定されていたとしても、以下の手続きが必要になります。
先ず、残された相続財産が、法人という形(相続財産法人)になり、債権者や受遺者の請求により、家庭裁判所が、その相続財産を管理する役目を持つ「相続財産管理人」の選任の公告をします。
この公告は、裁判所の前にある掲示板に掲示されるのと同時に、官報にも掲載されます。



これは「相続人探し」の公告も兼ねており、告示期間に相続人が名乗り出れば、通常の相続と同じ形になります。
それでも相続人が出てこない場合は、3回まで公告をし、最終的に見つからなければ、受遺者や債権者に財産を支払い、それでも残った場合、財産は国のものとなります。
特別縁故者
相続人が現れず、清算後の相続財産が残っている場合、「特別縁故者」は家庭裁判所に「財産分与の請求」をすることができます。



特別縁故者とは、相続人ではないが「被相続人と特別の縁故」があった人のことを言います。内縁の妻や夫は特別縁故者の代表的な例です。
他には届出をしていない事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた親戚・知人、又はこれらの人の家族などが挙げられます。
特別縁故者は、相続人不存在になった場合に限り、財産分与を受けることができます。



但し、最後の公告が終わって「3か月以内」に家庭裁判所に申し立てをし、審判で認められなければ財産分与は受けられません。
不在者財産管理人
相続は、相続人同士の話し合いで最終的な決着をつけますが、相続人の中に行方不明者がいた場合、相続の決着がいつまで経ってもつかなくなってしまいます。
そのため、その行方不明者に代わって相続財産を管理してくれる人を選び出します。



その人のことを「不在者財産管理人」と言います。
不在者財産管理人は、相続人や遺言執行者により、家庭裁判所に申し立てて選任されます。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人となるため、遺産分割協議などに参加できます。



他にも、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てて、行方不明者を死んだものとする、という方法もあります。
失踪宣告には、2つのパターンがあります。
先ず一つは、墜落した飛行機に乗っていたが、生存も死亡も確認されなかったため、行方不明として扱われているような場合です。
このような場合の失踪宣告を「危難失踪(特別失踪)」と言います。
もう一つは、蒸発してしまった場合など、特に危難に遭ったわけでなく行方不明の状態が続いているような場合です。
これを「普通失踪」と言います。



危難失踪では行方不明の状態が1年間続いた場合に、普通失踪では7年間続いた場合に、それぞれ家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをすることができます。
失踪を宣告された人は、危難失踪はその危難が去ったとき、普通失踪では行方が分からなくなってから7年間が経過した時点で、死んだことになり、それぞれ相続がスタートします。
失踪宣告の制度は、被相続人だけでなく、相続人のうちに行方不明者がいる場合にも利用できます。
どれだけ遺産を受け取れる?
遺贈
遺言で指定すれば、他人である第三者に財産を譲り渡すことも可能です。



このように、遺言で取り分を指定して遺産を受け取らせることを「遺贈」と言います。
遺贈には、「全財産の何分の何」という形で指定する「包括遺贈」と、「どこそこの土地」などと受け取るべき財産を具体的に指定する「特定遺贈」があります。
- 包括遺贈 … 全財産の1/4など、与える「財産の割合」を指定する
- 特定遺贈 … 〇〇の土地・△△の株式など、与える「財産を特定」する
包括遺贈の場合、遺贈を受ける人(受遺者)は相続人ではなくても、相続人と殆ど同じ扱いとなります。
つまり、被相続人に負債があれば、その負債を指定された割合で受け継いだり、また相続人同士の話し合い(遺産分割協議)にも参加することになります。
もちろん「遺産の放棄」もできます。
これに対し、特定遺贈を受ける場合であれば、被相続人の負債を受け継ぐことにはならず、遺産分割協議にも参加できません。
他の相続人から見ると特定遺贈は、結果的に相続財産の中から支払わなければならないという意味で、被相続人の負債のようなものと言えます。



但し、遺贈でも、他の相続人の遺留分を侵害することはできないので、注意が必要です。
遺留分
自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由です。
しかし、「全財産を愛人に与える」などという遺言が出てきたら、残された家族はたまったものではありません。



そのため、相続財産のうち一定の割合だけは、法定相続人の取り分とすることが認められています。この法定相続人の取り分のことを「遺留分」と言います。
遺留分は、誰が法定相続人となるかによって、その相続財産に占める割合が異なります。
具体的には次のようになります。
- 配偶者が法定相続人に含まれる場合 … 全財産の2分の1
- 子のみが法定相続人の場合 … 全財産の2分の1
- 親(或いは直系尊属)のみが法定相続人になる場合 … 全財産の3分の1
これらの分を、後で述べる「法定相続分」に従って分配します。



尚、どのような組み合わせでも、被相続人の兄弟姉妹に、遺留分はありません。
遺留分の対象となる財産は、被相続人が死んだ時点での全財産だけでなく、以下のようなものが含まれなければなりません。
- 相続開始前1年以内の贈与財産 … ⒜
- 遺留分を侵すことを双方が承知の上で贈与した財産 … ⒝
- 相続人に対する一定の贈与財産 … ⒞
先ず、被相続人の死亡日から逆算して1年以内の贈与は、誰に対する贈与であっても遺留分の対象財産に取り込まれます⒜。
また、1年より前の贈与でも、⒝に該当する場合は遺留分の対象財産になります。
⒞は相続人に対する贈与で、特別受益(後述)と呼ばれるものです。
死亡時の財産に、⒜~⒞に当たる額を加え、そこから債務など、負の財産を差し引いた額が、遺留分の対象になります。



もし実際に受け取った財産が遺留分より少なかった場合は、その差額を、遺贈や贈与を受けた人に請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った日から「1年以内」に行わなければなりません。
何もしないまま1年を過ぎると、時効により権利が消滅します。
遺留分を侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始の時から「10年経過」すれば、遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。
遺留分侵害額請求権の行使の仕方については、侵害されている側が一方的に「意思表示」すれば良いことになっています。



法的には口頭でも構いませんが、後にきちんと証明できるようにするため、配達証明付き内容証明郵便で通知するのが賢明です。相手が応じない場合は、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。
法定相続分
法定相続分とは、法律で決められた「それぞれの相続人の取り分の割合」です。
被相続人が遺言を残さなかったか、残しても一人ひとりの取り分に言及していない場合に適用されます。
また、遺留分をそれぞれの遺留分の権利を持つ人に分ける場合にもこの割合が基準になります。
この割合は、誰が法定相続人になるかによって異なります。
具体的な取り分は、以下の通りです。
- 配偶者のみ・子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみが相続人になる場合
それぞれ全額が相続人のものとなりますが、相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分割されます。
但し、兄弟姉妹の場合の例外として、異父母の兄弟姉妹(半血兄弟)は同父母の兄弟姉妹(全血兄弟)の2分の1の割合になります。
- 配偶者と子が相続人になる場合
配偶者が全体の2分の1、子が全員で2分の1となり、子が複数いれば、子の取り分である2分の1を人数分で均等分割することになります。
- 配偶者と直系尊属が相続人となる場合
配偶者が全体の3分の2、直系尊属が全員で3分の1となり、直系尊属が複数いれば、その取り分である3分の1を均等分割することになります。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は、その取り分である4分の1を均等分割することになります。



但し、前述の半血兄弟と全血兄弟の例外はここでも適用されるので、注意が必要です。
また、法律上の夫婦ではない、いわゆる内縁関係の相手は、配偶者として扱われません。
遺言がなければ、特別縁故者として、財産分与の請求以外に財産を受け取る手続きも取れません。
寄与分
被相続人の生前に、被相続人の事業に大きく貢献したり、被相続人の病気やケガの看護・介護に努めた場合など、被相続人の相続財産の増加・維持に大きく貢献した相続人は、その貢献によって増えた分の財産を、法定相続分とは別にもらうことができます。



この取り分を「寄与分」と言います。
法定相続分に沿って相続を行うと、自営業の親の仕事をずっと無償で手伝ってきた長男と、そうではない次男も同じ割合で財産を相続することになります。
親の財産形成への貢献度に関係なく、2人がもらえる金額が同じではバランスが悪いと言えます。
寄与分も特別受益(後述)と同様に「相続人の不公平を是正するための制度」なのです。
- 寄与分が認められる人 -
- 被相続人の事業に関する労務の提供をした人
- 被相続人の事業に関する財産上の給付をした人
- 被相続人の療養看護をした人



いずれの場合も、対価などを受け取っていないことが条件です。親族として当然であるような療養介護は含まれません。
相続財産のうち、どれだけ寄与分に相当する額があるかは、相続人同士の協議によって決められます。
従って、後で述べる遺産分割協議の時に自らの寄与分を主張しなければ、寄与分はもらえないことになってしまいます。
しかし、明確な基準がない上に、1人の寄与分が認められれば、当然、他の人の相続分が減るわけですから、皆が納得できるように話し合いで決めるのは非常に難しいと言えます。
話し合いが上手くいかない時は、寄与者(寄与分を主張する人)が家庭裁判所へ申し立てを行い、調停などで第三者を交えて解決を図ることになります。



しかし、寄与分として認められるケースは多くありません。例えば、事業に貢献したのであれば、殆ど無報酬で働いたというくらいでないと、寄与分は認められないのです。
特別受益
被相続人の生前中に、婚姻や養子縁組のため、或いは生計資金として、贈与を受けていた相続人を「特別受益者」と呼びます。
特別受益者が、被相続人の生前にもらった分を無視して遺産を分けると、他の相続人と比べて不公平が生じます。
この場合、生前にもらった分を遺産に加えて、それを基準に遺産分割を行い、その中から生前にもらった分を、相続財産を先に受け取った分として差し引きます。



これを「特別受益の持ち戻し」と言います。但し、生前贈与の全てが加算の対象になるのでなく、相続人の特別受益となる一定のものに限られます。
特別受益とは、次に該当するものを言います。
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
- 遺贈で取得した財産
例えば、妻と子2人が相続人となった場合で、相続財産が2,000万円あったとします。
このうち、子Aは被相続人の生前に、被相続人から土地の贈与を受けていたとします。
この土地が500万円だとすると、普通に分ければ配偶者1,000万円、子がそれぞれ500万円となりますが、子Aは生前に500万円分もらっているので、1,000万円もらったことになり、不公平が生じます。
そこで、相続財産をその土地も含めた2,500万円だと見なし、配偶者1,250万円、子はそれぞれ625万円ずつとします。
但し、子Aは生前にこのうち500万円分もらっているので、実際に子Aが受け取ることができるのは125万円(625万円-500万円)となります。
このようにして、実質的な公平が図られるのです。



計算の結果、マイナスになることもあります。つまり「もらい過ぎ」ですが、このような場合は相続分が「なし」になるだけで、もらい過ぎの分を返す必要はありません(遺留分の侵害がある場合を除く)。
どうやって財産を受け取る?
遺産分割協議
被相続人が遺言によって相続の割合を指定した場合にせよ、法定相続分に従って相続する場合にせよ、「何分の何」という形のままでは実際の財産を上手く分けられるとは限りません。
残された財産が現金だけなら割合に従って単純に分ければ良いのですが、例えば土地や家が残されている場合には、遺言により指定された割合や、法定相続分の割合通りに上手く分けられない場合もあり得ます。
具体的に誰がどの財産を相続するのか、或いは相続人同士で共有にするのかなど、問題も出てきます。
寄与分のある人がいる場合でも、どれ程の寄与分があり、その人にどれだけ相続財産を増やしたのかも、問題になってきます。



そこで、相続人全員が集まって、具体的に誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合う必要がでてきます。この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
この遺産分割協議は、当然、相続人全員で行う必要があります。
例えば、1人足りない状態で遺産分割協議を行うと、出席していない人に不利な分割がなされ、公平な協議にならない恐れがあるからです。
そこで、出席できない場合は、代理人を立てるなどの方法をとります。
この場合、注意しなければならないのが、他の相続人は代理人になれないということです。
相続人の代理人を認めてしまうと、極端な事例ですが、1人の相続人が他の相続人全員の代理人となり、1人で全ての遺産の分割を決めても良いことになってしまいます。
これでは、被相続人の意思が無視されてしまう恐れがあり、不公平です。
また、同じ理由から、複数の相続人が、同じ人を代理人にすることもできません。
結局、全ての相続人の数と同じだけの頭数が揃わなければ、遺産分割協議は始められないことになります。
協議の結果、全員が納得した段階で「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書に基づいて、不動産の登記や預金の名義変更など、実際に相続する財産・負債の名義を相続人に移転する手続きを行うことになります。
また、協議書は、相続税の申告の際にも提出することになっています。



この遺産分割協議書は、遺言と違って、形式・書き方に決まりはありません。縦書きでも横書きでも良く、ワープロでも構いません。要は、相続する財産が特定できるように書いてありさえすれば良いのです。
但し、不動産の登記などでは、印鑑登録された実印を要求される場合があるので、協議書には、必ず相続人全員が実印を使いましょう。
尚、この分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判の場に持ち込まれることになります。
相続放棄
相続人は、財産を必ず相続しなければならないのかというと、そうではありません。
例えば、親が借金だけを残して死んだ場合、子がその借金を必ず受け継がなくてはならないとすると、これは子にとってかなり酷なことです。



このような場合には、相続を拒絶することができます。これを「相続放棄」と言います。相続放棄をすることで、被相続人が残した借金の返済義務はなくなります。
相続放棄をする場合には、被相続人の死を相続人が知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行わなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと、自動的にそのまま財産、負債を受け入れる(単純承認)ことになってしまうので気を付けなければなりません。
相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったと見なされます。
このため、相続放棄をした相続人の子供が代襲相続をしたり、借金を肩代わりすることはありません。
相続放棄は、相続人全員ですることもできますし、1人だけですることも可能です。



相続放棄は一度手続きをしたら、取り消すことができません。但し、生命保険金などは、民法上の相続財産に含まれないため、相続を放棄した人でも受け取れます。
限定承認
相続財産の中に負債がある場合、相続財産を相続する前に清算してしまい、その結果、正の財産が残れば、相続することができます。
これを「限定承認」と言います。
限定承認では、清算の結果、負債が残った場合は、その負債を受け継ぐ必要はありません。
つまり、限定承認を行い、負債が残ってしまっても、返済の必要がなくなるというわけです。



ずいぶん都合の良い話ですが、実際のところ、限定承認の手続きは非常に煩雑です。残余財産にたどり着くまでには、一連の清算手続きを済ませなくてはなりません。
手続き上の不備で債権者に損害を与えた時は、賠償責任も生じます。
債権者が多く権利関係が複雑な場合は、弁護士などの専門家の助けが必要でしょう。
さて、限定承認をする場合は、相続開始を知った時から3か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に申述しなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと自動的に単純承認、つまり正・負両方の財産を抱えたまま相続することになるのです。



相続する負債が多い場合や、どのくらい負債があるのかはっきりしない場合に効果的な方法です。
しかし、限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。
相続人のうち一人でも単純承認で良いという人や、相続放棄をするという人がいれば、限定承認は認められません。
まとめ
相続とは、死亡した人の財産が、その人と一定の身分関係にある人に移転することです。
死亡した人を「被相続人」、一定の身分関係にある人を「相続人」と言います。
財産というと、不動産や現金、銀行預金、株式といったものが思い浮かびますが、このような「プラスの財産」ばかりが財産ではありません。
借金やローン、未払金など、もらってあまり嬉しくないものも財産の一部です。



相続するというのは、このような「マイナスの財産」も含め、一切の財産の権利義務を引き継ぐということです。プラスの財産は相続するが借金は要らない、というわけにはいきません。
相続人の範囲は民法で定められていて、これ以外の人が財産を相続することはありません。
具体的に誰が相続人となるのかは、被相続人の親族構成によって変わります。
また、相続人の構成によって、それぞれの相続人の相続分も違ってきます。
これらのことが、全て民法に細かく規定されています。
では、相続人以外の人が故人の財産を承継することはないのかというと、そうではありません。
財産を相続できるのは相続人だけですが、遺言をすれば、相続人以外の人に財産を残すことも可能です。



これは相続でなく「遺贈」と言います。また、遺言で法律の定める相続分を変えることもできます。この相続分のことを「指定相続分」と言います。
指定相続分が法定相続分と異なっていても問題はありません。
指定相続分が、法定相続分に優先します。
民法は相続の細かい規定を設ける一方で、被相続人が自分の財産を原則として自由に処分することを認めているのです。



但し、相続財産には各相続人の最低限の取り分として留保された「遺留分」があり、この部分だけは被相続人でも自由に処分することができません。
家族などへ財産を渡す方法は、相続や遺贈だけではありません。
生前に、「贈与」という形で子供に援助をすることもよくあります。
例えば、長女のマイホーム購入資金を援助する、長男の開業資金を援助するといったケースです。
このような相続人への生前の贈与は、遺産の前渡しと見なし、その贈与分も相続財産にプラスして遺産分割を行います。



これを「特別受益の持ち戻し」と言い、特別な贈与を受けた相続人を「特別受益者」と言います。
特別受益が生前贈与などを相続分から差し引く制度なのに対し、寄与分とは、相続分を増やすことができる制度です。
生前、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人には、遺産分割による相続分に加えて、その貢献の度合いに応じた相続分をプラスできます。
この増加分が「寄与分」です。
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続すると、残された家族は借金の返済に追われることにもなりかねません。



しかし、相続するかしないかは相続人の自由。相続人には、①無条件で相続する(単純承認)、②条件付きで相続する(限定承認)、③相続人とならない=相続しない(相続放棄)の3つの選択肢があります。
暴力を振るう、暴言を吐くなど、素行不良の子供に財産を一切渡したくないと考える人もいます。
遺言で財産を渡さないことにしても、子供には遺留分がありますので、相続分を完全になくすことはできません。
このような時は、家庭裁判所に「相続人の廃除」の申し立てをし、相続人の相続権を奪うことができます。
また、遺言で廃除の意思表示をすることも可能です。
相続人の廃除は、被相続人の意思による相続権のはく奪です。
しかし、自分に有利になるように他の相続人を殺したり、被相続人に無理やり遺言を書かせたような者は、廃除をするまでもなく自動的に相続権を失います。
これを「相続欠格」と言います。
相続人となるべき親族が既に死亡していたり、相続放棄などで相続人がいなくなってしまうことがあります。
このような状態を「相続人不存在」と言います。



行き場のなくなった財産は最終的には国のものになりますが、その前に「特別縁故者」に分与されることがあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人など、相続人ではないけれど「特別の関係」にあった人を言います。
内縁の妻や夫、親子同然に暮らしていた事実上の養子などがその代表例です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。