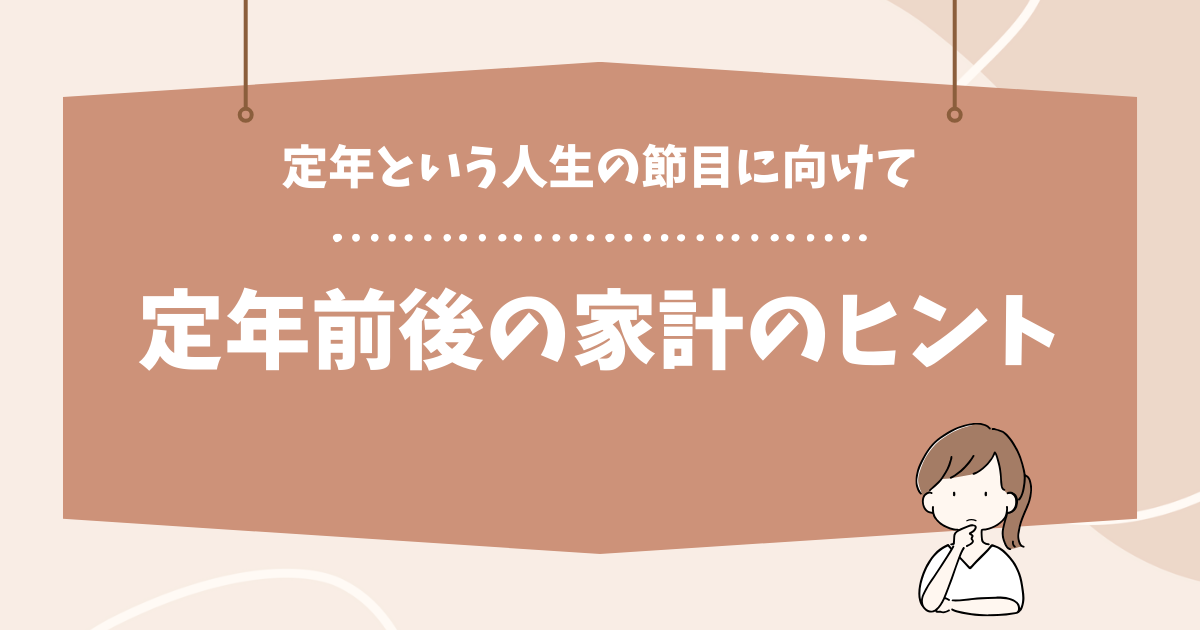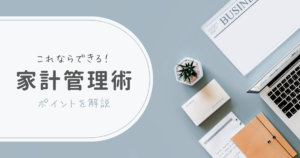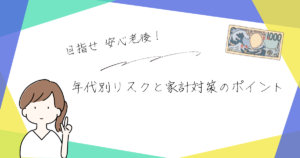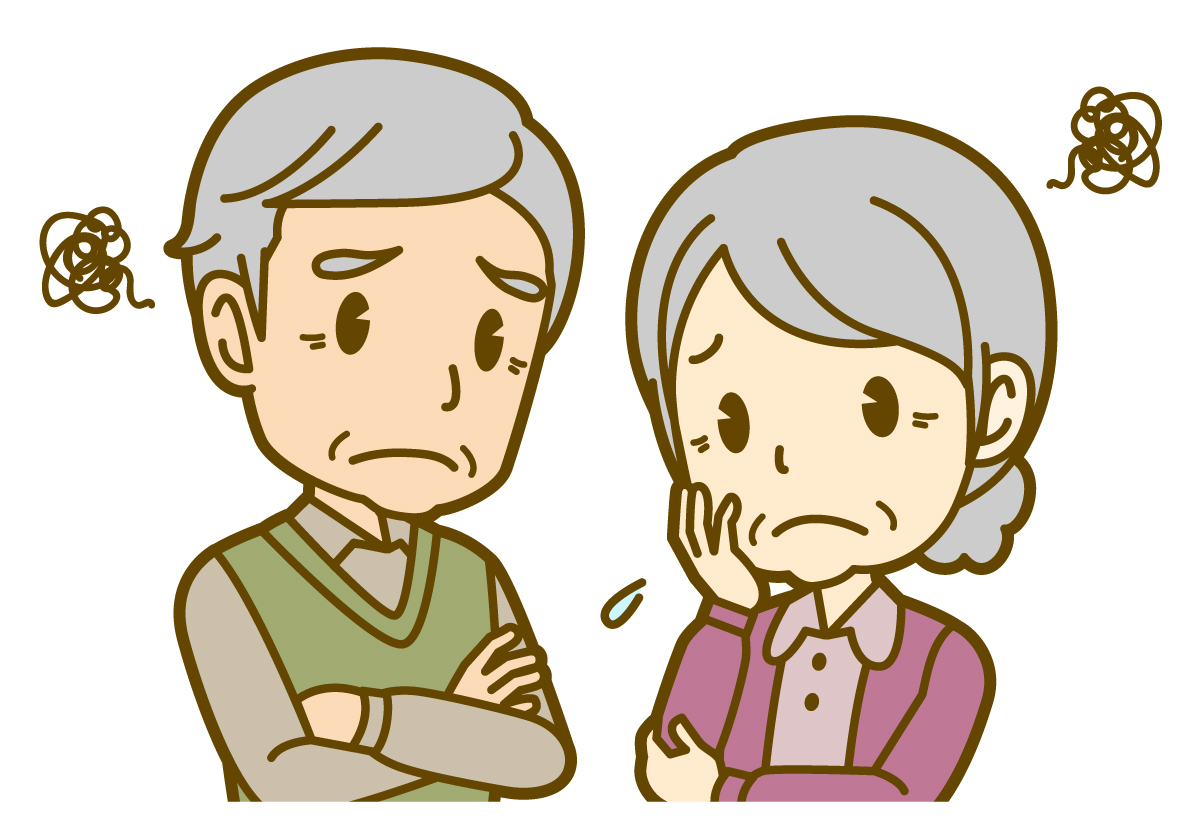 悩める人
悩める人老後を乗り切れるだけのお金が貯まっているのか不安…



今後、保険や住まいのお金をどう考えていけば良いのか分からない…



こんな疑問・悩みを解決します!
- 老後に必要なお金
- 生活資金の管理方法
- 支出の見直し
- 保険の見直し
- 住まいの費用
- 子供への援助
- 介護への備え
- 退職金の預け先
- 金融機関の見直し
金融資産と負債を把握する
定年前後は家計が大きく変わる時。
月々の給料で切り盛りする家計から、年金をベースに不足分を貯蓄などで賄う家計に変わるのです。
老後の生活の準備として、大切なのは、資産状況を把握することです。
預貯金、投資商品などの残高を書き出し、お金は予定通り貯まっているか、忘れていた埋蔵金はないか、マイホームの財産価値は今どれくらいかなどを確認しましょう。



また、借金がいくら残っているかも書き出し、家計の実力をチェック。家庭の資産状況を知ることが、定年に向けた様々な準備を進める上での基本情報となるからです。
例えば、年金の受け取り開始を遅らせることで年金額を増やすことができるという制度がありますが、年金受給を繰り下げるためには、受給開始までの生活費など、資産に余裕が必要となります。
自分の資産状況を把握していないと、繰り下げることができるのか、繰り下げる場合、何年なのか、などの判断ができないことになります。
バランス・シートの作成



このとき役立つのが「バランス・シート」と呼ばれるものです。表の左側にプラスの財産を、右側にマイナスの財産を書き出せば、我が家の財産が一目瞭然です。
- バランス・シート -
| 預貯金 | 万円 | 住宅ローン | 万円 |
| 国債・社債など | 万円 | 自動車ローン | 万円 |
| 投資商品 | 万円 | その他のローン | 万円 |
| 貯蓄型の保険 | 万円 | 合計(b | 万円 |
| その他 | 万円 | ||
| 土地・建物 | 万円 | ||
| 車など | 万円 | ||
| 合計(a) | 万円 |
- 純資産=(a-b) / 万円



老後の生活設計のために資産額の目安や増減を知ることが目的ですので、あまり細かい項目までは必要ありません。バランス・シートで管理すると資産全体の増減が一目で分かります。減った時はその理由をきちんと把握することが大切です。
3つのチェックポイント
バランス・シートを作ったら、3つの点を確認してみましょう。
1つ目は、金融資産の残高と内訳です。
残高が、「思ったより多い」「予定通り貯まっている」という人は良いのですが、「貯められていなかった」「教育資金に使ってしまった」という人は、退職までの貯蓄計画の練り直しが必要です。



同時に、金融資産の内訳もチェック。①預貯金、②国債や社債、③投資商品、④貯蓄型の保険(養老保険など)というように分類しておきましょう。②、③、④は元本割れリスクもあるので、運用先が集中していないかも確認して下さい。
2つ目は、プラス財産とマイナス財産のバランス。
プラスが大きければ、正味財産(純資産)は黒字となるので、取り敢えず「合格」となりますが、逆にマイナスが大きければ赤字。
持っている財産より借金の方が多いという不安定な状態です。



定年までに解消しておかないと、老後の頼みの綱となる退職金が、赤字解消で消えてしまいます。家計を見直して、ローンを減らしたり、貯蓄を増やしたりできないか、検討してみましょう。
3つ目は、マイナス資産の内容です。
ローンは定年前にできるだけ減らしておきたいもの。
借金の中身(残高・金利・返済期間)を調べ、今すぐ使う予定のないお金があるなら、返済を検討しましょう。
ローンは早めに返済すれば、その分の利息を払わずに済みます。
ローンが複数あるなら、金利が高いものから返していくのが基本です。
老後に必要なお金の計算例
現時点の財産を確認したら、老後に必要なお金をざっくりと見積もっておくと安心できます。
65歳以降の生活を考えながら、下図のように、①年金では不足する生活費、②持ち家に掛かるお金、③イベントのお金(車の買い替え・旅行・子供への援助など)、④病気や介護に備えるお金、⑤死後整理のお金(葬儀代など)の5つに分けて、金額を出してみましょう。
- 老後に必要なお金の計算例 -
- 年金で不足する生活費(①) … ひと月当たり3万円の赤字と仮定して、3万円×12か月×20年=720万円
- 持ち家に掛かるお金(②) … リフォーム・修繕代500万円、固定資産税や管理費30万円×20年=1,100万円
- イベントのお金(③) … 500万円
- 病気や介護に備えるお金(④) … 300万円×2人分=600万円
- 死後整理のお金(⑤) … 100万円×2人分=200万円
- 720万+1,100万+500万+600万+200万=3,120万円



実際に必要な金額は、家庭の事情によって違いますが、上記は、典型的な元会社員夫婦の20年分(65~85歳 / 64歳までは何らかの形で収入を得る前提)と考えて、試算しました。
住まいが賃貸なら家賃が掛かるので①が多くなりますが、持ち家でも、②が掛かりますし、65歳以降もローンが残っている場合には②の金額が増えてしまいます。
③は75歳までの比較的アクティブな時期に使いたいお金。
④は75歳以上に備えるお金となります。
⑤は終身保険に加入していれば、それを充てても構いません。



老後資金準備の取り敢えずの目標は、「①~⑤の合計額」より多くの金融資産を、65歳時点で準備しておくこと。不足するようであれば、定年後もしっかり働いて収入を得る、妻も働く、支出を見直すなどの対策を考えましょう。
基本生活費の管理方法
定年後はお金の流れが大きく変わります。
収入は会社からもらう給料だけだったのが、公的年金や企業年金、個人年金など、色々なところからバラバラに受け取ることになります。
金額も、現役時代の給料より減るでしょう。
月給でやり繰りし、ボーナスで赤字と臨時支出を賄っていた現役時代の家計から、年金をベースに、不足分を預貯金で賄う家計に変わるのです。



基本生活費は、年金などの「定期収入の範囲」で賄うのが鉄則です。
定期収入のひと月当たりの額を確認しておく
年金生活で予想外に大変なのが、毎月の定期的な振り込みがなくなってしまうこと。
公的年金の支給日は「偶数月の15日」で、2、3月分が4月というように、前々月と前月の2か月分が振り込まれます。
一方、支出は毎月発生するものが多いので、現役時代と同じように生活していると、2か月分の年金を1か月で使い切ってしまうかも。
月々の赤字をカバーしてくれたボーナスもなくなります。
収入増は見込めません。
支出をコントロールしないと、老後資金がすぐになくなってしまいます。



そこで、年金などの定期収入が、「どこから」「いつ(何月に)」「いくら」入金になるのか調べて、ひと月当たりに換算した受取額を確認しておくことが大切です。
尚、「ねんきん定期便」などで示された年金見込み額は、税金や社会保険料を支払う前の金額。
年金等の収入の中から、税金や社会保険料として10~15%は支払うものと考えておくと安心です。
月々の支出は別口座や袋分けで管理する
家計には、毎月は発生しないけれど、一年のうちどこかで必ず払うお金があります。
そこで、本来、家計管理や予算立ては、年間単位で考えた方が良いのですが、長年、毎月の給料ベースでやり繰りしてきた人なら、入出金管理は月単位の方が分かりやすいかもしれません。



それならば、1か月当たりに使える金額の範囲内で、上手くやり繰りする「仕組み」を作っておきましょう。
例えば、年金等の振込口座とは別に、支出のための銀行口座を作って、そこに毎月決まった額を入金して管理するという方法もあります。
或いは、自動引き落としになる光熱費や保険料は年金振込口座から支払い、現金でやり繰りする部分は引き出して、袋分けで管理するという方法もあります。



この場合、カードを使ったら、使った金額をカード引き落とし口座に入金すると良いでしょう。いくつかの方法を試してみて、自分がやりやすい方法を見つけておきましょう。
いずれにしても、例えば、食費や公共料金、保険料などの基本的な生活費は定期収入内に収め、旅行代などの臨時支出は、預貯金を取り崩す、といった我が家なりのルールを作っておくことが大切です。
社会保険料や固定資産税など、年払いや数か月に一度の支払いとなるものは、別の予算立てをしておいても良いでしょう。
大事なことは、定年後の「新しいお金の流れ」をしっかり把握すること。
最初はちょっと大変かもしれませんが、年金生活に慣れるまでは、新米主婦に戻ったつもりできっちり家計簿を付け、我が家のお金の流れを掴みましょう。



「基本生活費は年金から、臨時支出は預貯金から」など、支出のルールを決めておきましょう。
支出の見直し
よほどの蓄えや備えがない限り、年金生活に入ると現役時代と同じような暮らしは維持できません。
収入に合わせ、支出の見直しが必要です。
節約はストレスが溜まるものですが、途中で挫折しないように、また定年後の生活をつまらないものにしないために、メリハリをつけて取り組みましょう。



目標は、基本生活費を、年金などの定期収入の範囲で賄えるレベルまで、小さくしておくこと。定年を迎えてから慌てないように、今から少しずつできることを始めましょう。
固定費の見直し
さて、支出の見直しで、先ず手を付けたいのは「固定費」です。
家計支出の中で、毎月或いは毎年支払う金額が決まっている支出のこと。
家賃や各種保険料、クレジットカードやスポーツクラブなどの会費、衛星放送やケーブルテレビの契約料、インターネットや電話の基本契約料など。
固定費に対して、変動費は、食費、光熱費、レジャー費などで、消費行動によって金額が変わる。
食費や光熱費を1割減らすのは大変ですが、生命保険料や通信費などは、保障額や契約形態を見直すだけで1~2割は減らせることもあります。
ケーブルテレビや衛星放送の契約、年会費が掛かるクレジットカード、定期的なお取り寄せなども、この機会に、その必要性を考えてみましょう。
固定費の大物は「住宅ローン」です。
ローンが残る場合には、預貯金や退職金で一部繰り上げ返済して、毎月の返済額を減らしておきます(返済額軽減型)。
返済期間を短くする「期間短縮型」の方が利息を減らす効果は大きいのですが、定年後の家計の場合、「返済額軽減型」を選び、毎月の負担を減らす選択をするのも良いでしょう。
また、ボーナス払いの分だけ完済したり、金利の低いローンに借り換える手もあります。
各種保険料など、年払いや前払いが可能なものは、まとめ払いで節約を。
保険により割引率はまちまちです。
例えば、国民年金保険料なら、口座振替で一年分前納すると4,400円の割引になります(2025年度の場合)。



社会人になっても同居している子供がいるなら、基本生活費を劇的に減らす方法があります。食費や光熱費などとして、毎月、一定額を徴収するのです。
一人で部屋を借りて生活すれば、最低でも7万~8万円は掛かりますから、3万~5万円はもらっても良いのでは。
各自の携帯電話代は、もちろん子供自身に負担させましょう。
収入減に備え、夫婦それぞれの小遣いも基本的には減らす方向で。
また、冠婚葬祭費以外の交際費、洋服代、レジャー費、贅沢品費は、いざとなれば支出せずに済むお金です。
年金が少ないようなら、基本生活費とは分け、年間予算を立てて別途管理するようにします。



冠婚葬祭費やお中元・お歳暮代の節約は簡単ではありませんが、今後のお付き合いも含めて、整理してみては如何でしょうか。
惰性で続けていたお付き合いを見直し、金品のやり取りがなくても続けるべき関係なのかどうか、見極めるチャンスかもしれません。
- 食費・光熱費等 … 契約アンペア数の見直し・同居の子供からも一定額を徴収
- 各種保険料 … 契約内容の見直し・保険料のまとめ払い
- 国民年金保険料 … 保険料のまとめ払い
- クレジットカード … 不要なものを解約
- 住宅ローン … 繰り上げ返済・借り換え
- 携帯電話代 … 契約プランの変更・社会人の子供の分まで払わない
- 小遣い … 年間予算を決めて各自が別途やり繰り
- 交際費 … この機会にお付き合いを見直す
- インターネット関連の通信費 … 契約プランの変更・業者の変更
- ケーブルテレビなど … あまり見ていないなら解約
- スポーツクラブなどの会員 … プラン変更・解約



定年後の家計はメリハリをつけて、シンプル&コンパクトに。固定費を減らせば、支出カットの効果が続くので楽です。定年を機にお付き合いを整理すれば、余分な交際費もカットできます。
保険の見直し



定年前後は、保険見直しの最後のチャンス。必要な保障や補償を確保する一方、不要な保障や補償をカットして、支出を減らすことで、今後の生活に備えましょう。
生命保険や医療保険の分野では「保障」、損害保険の分野では「補償」という用語を使う。
言葉の意味は、保障は「一定の地位や状態を保つ」ことで、補償は「損失を補って償う」こと。
生命保険や医療保険は「今の生活を守るため」に加入し、損害保険は「損失を補うため」に加入するという違いがある。
生命保険(死亡保障)や医療保険は、年齢が高くなると支払う保険料も上がります。
また、健康状態に問題があると入れない可能性もあります。
見直しを思い立ったら、なるべく早く行いましょう。
死亡保障
死亡保障の主な役割は、
①遺族の生活保障
②死後整理費用の準備
③相続対策
の3つです。
定年間際で、子供が既に独立しているなら、①の目的での死亡保障はほぼ不要。
夫が会社員なら、遺族年金や死亡退職金は、若い頃よりもらえる額が多くなりますし、夫婦二人で使う筈だった貯蓄(老後資金)を一人で使うことになるので、資金に余裕ができるからです。
死亡保険は、世帯主が死亡しても残された家族が困らないよう加入するものです。
例えば、子供が独立するまでの学費や生活費を保障するためと考えると、子供が社会人になれば高額の生命保険は必要ないということになります。



支払っていた保険料は、年齢と共に高くなっていた筈ですから、見直しによって、大きな節約効果が見込めます。
②の死後整理費用は、預貯金で備えても構いませんが、保険で備えるなら、死亡時に保険金が必要となるので、満期のない「終身保険」を。
もう一つ、葬儀費用の備えとしてお勧めなのが「葬儀保険」です。
目安は最低で1人100万円~と考えておきましょう。
③の相続対策は、争続(争いが続く)や争族(親族で争う)対策。
資産家でなくても相続トラブルが増えていますが、保険は受取人を指定できるので、残したい人に財産を残せる利点があります。
相続税が発生した場合の納税対策としても利用できます。
- 遺族の生活保障 … 子供が独立していて、ある程度の預貯金があり、遺族年金がもらえそうなら不要
- 死後整理費用 … 葬儀代・お墓代など。目安は1人100万~200万円
- 相続対策 … 受取人を指定できるので、相続時のトラブルを減らすのに有効。相続税が発生した場合の納税対策にも使える
医療保険
続いて、医療保険の話です。
高齢になると病気への不安が増加し、入院した時の費用のために保障の大きい保険に加入している人も多いようです。
厚生労働省の患者調査によると、入院受療率(入院患者数)は、60歳前後から右肩上がりに高くなります。
また、高齢者の公的健康保険の自己負担も増える方向で見直しが進んでいます。
ですから、高齢者こそ、民間の医療保険に加入しておくと安心です。



但し、保険料の方も年齢と共に高くなるのが一般的。負担する保険料とのバランスを考えて加入しましょう。
老後資金に余裕があり、病気や介護に備えるお金として、預貯金を確保しておくことができるなら、医療保険には加入しないという選択もあります。
必要に応じてシンプルな保障に絞ることを検討しましょう。
損害保険
モノの損害を補償する損害保険は、定年までに築いた財産を守るのに必要な保険です。
火災保険は、建物と家財に別々に掛けます。
火災の他、自然災害も補償されますが、地震や津波が原因の損害や火災は原則として対象外。
火災保険に「地震保険」を付帯しておきましょう。
たとえ家が古くて価値がなくても、災害で住む場所がなくなっては困ります。
生活再建のために必要と考えましょう。
自動車保険
自動車保険は、車の事故で相手や自分が死亡したりケガをしたりした時、また、物を壊した時の補償。
事故状況によっては、数億円の賠償責任を負うこともありますが、強制加入の自賠責では補償は最高4,000万円で、物への補償はありません。
不足分は自分の財産から払うことに。
自分のためにも相手のためにも、加入しておくべき保険です。
また、個人賠償責任保険は、急増している自転車事故等で相手をケガさせてしまった時にも補償されます。
一つの契約で家族全員が対象になるので、自動車保険や火災保険に付帯しておくと安心です。
住まいの費用
持ち家であっても賃貸であっても、また、住み替えを考える場合でも、住まいの費用は、家計の中で大きな比率を占めます。
用意できた老後資金の中から、住まいにいくら掛けるかによって、他の費用に回せる金額も変わってきます。
住まいの費用は、これからの暮らし方とのバランスも考えて、確保しておきましょう。
住宅ローン
現在、賃貸であれば、家賃と更新料などがずっと掛かることになります。
定年を機に、家賃の安い場所に引っ越したり、退職金で家を購入する選択肢もあります。
持ち家の人は、「持ち家なら定年後は安心」と考えていませんか。
持ち家のメリットを生かすには、定年までに、できるだけローン残高を減らしておくことが必要です。
住宅ローンが残っていれば、家賃を支払うのと変わりません。



定年後にも住宅ローンが残る場合は、早めに準備が必要です。現役のうちに支払いを軽減、短縮する方法を考えましょう。
理想的には繰り上げ返済ですが、その余裕がない場合は退職金で一括返済を検討してみましょう。
年金生活になっても住宅ローンが残っていると、生活を圧迫することになります。
何よりもローンの完済を第一に考えましょう。
持ち家に掛かる費用
持ち家には、税金(固定資産税や都市計画税)、維持管理費などの所有コストが掛かることも忘れてはなりません。
税金は、標準的な広さのマイホームで年10万~20万円程。
その他、マンションの場合は、管理費と修繕積立金がずっと掛かり、一戸建てでは、外壁や庭のメンテナンス費用が掛かります。
内装や水回りのリフォームは、マンションも一戸建ても必要です。



定期的に大きい金額が必要となりますので、老後資金を考える時には必ず予算化しておく必要があります。今の家にずっと住み続けるつもりなら、今後必要となるリフォーム費用を見積もっておきましょう。
部屋を使いやすくするリフォームは、多少の不便を我慢すればしなくても済みますが、台所や浴室、トイレなどの水回りのリフォームは、定年後に一度は必要と思っておいた方が良いでしょう。
あまり手を掛けない場合でも、200万~300万円くらいの予算は見込んでおきましょう。
老後資金から捻出するのが難しい場合は、住宅ローンの支払いが済んでもリフォームの予算として毎月1~2万円程度を積み立てておけば、10年で100~200万円程度が貯まります。
助成金もありますので、早めに専門業者へ相談しておきましょう。
住み替え
定年後に住み替えをする場合、購入するか賃貸にするか、迷うこともあるでしょう。
持ち家には、地域との繋がりが深まりやすいという良さがあります。
ローンが終われば、家を追い出される心配もありません。
一方、賃貸では、暮らし方や経済状態に合わせて、柔軟に住まいを替えられます。
高齢になると貸してくれなくなるのでは、という不安もありましたが、現在、様々な高齢者向け住宅が建てられるようになってきたため、その不安は解消されつつあります。



購入か賃貸かは、用意できる資金や、その場所にどれくらいの期間暮らす予定かなどを考えて決めましょう。
持ち家の人が住み替えを考える場合には、元の自宅を売却したり貸したりと活用することで、資金を捻出することができます。
自宅がいくらで売れるか、いくらで貸せるかなどを調べておきましょう。
賃貸にする場合には、移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借上げ制度」もご検討を。
尚、住み替えで新たに家を購入する場合も、将来、自宅を活用することも考えて、売りやすい家、貸しやすい家を選ぶことが肝心です。
介護への備え
病気やケガで身体が不自由になった時や、認知症になった時に、生活の手助けをしてもらうのが「介護」です。
介護とはそれ自体が独立しているのではなく、ベースとなる生活があって、それを支援するものです。
施設介護に掛かるコスト
例えば、介護付き有料老人ホームなどの、介護が受けられる民間施設では、一般的に月額20万円前後の費用が掛かりますが、その多くは居住費(家賃相当額や光熱費)と食事のコストです。
ある施設の例では、月額24万円の内訳は、①住コスト12万円(家賃・水道光熱費・事務費)、②食費6万円、③雑費1万円、④介護費用5万円。



この場合、純粋な介護費用は5万円。通常の生活でも月15万~20万円は掛かることを考えると、先ずは老後の生活資金を準備しておくことが、介護への備えに繋がることが分かるでしょう。
自宅で介護を受ける場合には、外部に払う金額は少ないものの、1対1で面倒を見るため、介護する人の負担は非常に大きくなります。
たとえ配偶者や子供など、無償で介護を担う家族が複数いる場合でも、長時間の介護は介護する人の健康を損ねることも。
お金の面でも、軽度のうちはまだ良いのですが、重度になれば介護保険の利用限度額の範囲内のサービスでは不足するケースも。
その他、自宅で介護を続けるための住まいの改修費、光熱費、食費まで考えると、施設介護よりコスト高になる可能性もあります。



いざとなったら、自宅か施設か、また誰にメインの介護者になってもらいたいのかなどを、家族で話し合っておくことをお勧めします。
介護期間
さて、実際の介護期間はどれくらいなのでしょうか。
生命保険文化センターの2021年の調査では、平均的な介護期間は5年1か月。
月5万円の介護費用を5年分(60か月)用意すると、300万円。
この金額を目安に準備しては如何でしょうか。
夫婦2人分では600万円。



そんなに準備できないなら、取り敢えず1人分準備しておいて、介護資金が不足するようなら、葬儀は質素にし、そのためのお金を使うと考えれば、気が楽になるのではないでしょうか。
また、持ち家があるなら、家を担保にお金を借りたり、賃貸に出したり、売却したりして介護費用を賄う方法もあります。
いずれにしても、過度に心配するより、要介護状態にならないよう、適度に運動をしたり、引きこもらないよう、仕事をしたり趣味を持ったりしたいものですね。
退職金の預け先
退職金を受け取ったばかりの時には、少し気持ちが高ぶって、普段とは違う決断をしてしまうかもしれません。
せっかくもらったお金を増やそうと、この時期に舞い込んでくるうまい話に乗ってしまったり、衝動買いで大きな買い物をしてしまったり。



しかし、退職金の使い道や運用方法は、長期的な視点で考えておきたいもの。方針が決まっていないなら、受け取ったお金は、取り敢えず、短期の定期預金などに入れ、落ち着いてから、目的に合った預け先を探しましょう。
退職金専用の定期預金
さて、取り敢えずの預け先ですが、金融機関の中には、退職金専用に、金利を優遇した定期預金を用意しているところもあります。



金融機関にとって、定年退職はお客様獲得のチャンス。退職金を預けてもらって、その後の取引に繋げようとしているのです。
対象は、退職金受け取り後、3か月、半年など一定期間内の人。
金額は、受け取った退職金の範囲内で、最低預入額を例えば、300万円などと定めているところが多いようです。
金利は金融機関により様々ですが、中には、店頭金利にプラス1~2%と、現在の金利水準を考えると高いところも。
投資信託の購入とセットになっているものもあります。



但し、高金利での預入期間は、たいてい3か月、6か月と短め。例えば、500万円を2%で運用した場合、1年間預ければ年間利息は8万円(税引き後)ですが、3か月間だけならその4分の1の、2万円(税引き後)です。
また、預金保険制度で保護されるのは、元本1,000万円とその利息まで(1金融機関当たり)なので、それを超える額を預ける時には、格付けなどで、その金融機関の安全性を確認するか、複数の金融機関に分散しておきましょう。
社債、国債などを評価する指標の一つ。
アルファベットと数字で表されるが、AAAやAaaは格付けが高く、AA、A…B、Cとなるほど低くなる。
債券以外に、投資信託、保険支払い能力、デリバティブなどが格付けの対象になっている。
格付け会社は「Moody’s(ムーディーズ)」や「S&P(スタンダード&プアーズ)」などが有名。
預け先の選び方
続いて、今後の計画や目的に応じて、どう預け分けていくかを、保険まで範囲を広げて考えてみましょう。
まとまった金額の退職金ですが、何に使うかは決まっていますか?
恐らく、一つの目的だけということは少なく、例えば、300万円は家のリフォームに、100万円は旅行代に、残りは生活資金の不足を補う分やゆとり資金になどと、いくつかの目的が考えられるでしょう。
家のリフォーム費用のように、使う時期が決まっているお金なら、元本割れしにくい金融商品が向きます。
使う時期に合わせて満期になる定期預金や個人向け国債、また、養老保険や格付けの高い社債などを活用しても良いでしょう。
生活資金として、毎年一定額を使っていく予定なら、預貯金以外に、一時払いで個人年金保険に加入する方法もあります。
数年間の据え置き期間の後、毎年年金を受け取りますが、65歳から10年間、75歳から10年間と、期間をずらして2つの確定年金に加入しておいても良いでしょう。



もちろん、事前に保険会社の格付けを確認することが大切です。運用次第で受取額が変わる変額個人年金保険は、ゆとり資金で購入を。必ず使う予定のあるお金の運用先としてはお勧めできません。
死後整理のお金や子供に残す予定のお金は、一時払いの終身保険に加入しておくのも一つの方法です。
死亡した時の受取人を指定しておけるので、相続対策にも利用できます。



退職金は、衝動で預け先を決めないこと。退職金専用の有利な定期預金もあります。今後の計画や目的を考慮して、じっくり預け先を考えましょう。
金融機関の整理と見直し
定年は金融機関を見直すチャンス
金融機関は給与の受け取りや公共料金・クレジットカードの支払いなど日々の生活に欠かせないものですが、老後のお金を考える上で、利用している金融機関を見直すことはとても大切です。
給与振り込み先の銀行や住宅ローンで利用している銀行、金利が高いと聞いて開設したネット銀行や手数料の安いネット証券など、自分でも把握できないほど多数の金融機関に口座がある、という人もいるようですが、定年後は収入が限られるため、多くの金融機関に資金を分散していると自分の資産を把握しにくくなり、大切な資金を有効に利用できなくなる恐れがあります。



生活パターンやお金の流れが変わり、新しい生活を迎える定年は、利用する金融機関を見直すのに最適なタイミングと言えます。定年を機に整理してみましょう。
定年後は取引する金融機関をできるだけ少なくする必要があります。
自身の資産管理だけでなく、将来、自分が認知症になったり、亡くなったりした時に、家族が資産を把握しやすくするためです。
尚、ここで重要なことは、どの金融機関を利用しているのかを、配偶者や家族へ伝えておくことです。
金融機関名・名義・口座番号・凡その残高・ID・パスワードなどを書面にして家族に渡すか、保管場所を教えておきましょう。



今後付き合っていく金融機関を絞り込むことで、お金の管理だけでなく、将来の相続手続きも楽になります。いざという時に備えて、名義別に一覧表にしておきましょう。
定年後の金融機関の見直しポイント
ここで、老後資金の目的を、今一度書き出してみましょう。
①生活資金(基本生活費)
②使う内容や時期が決まっているお金(旅行などのイベントのお金や住まいのお金)
③病気や介護に備えるお金
④死亡時に必要なお金(葬儀費用やお墓代)
⑤ゆとり資金
の5つです。
このうち①のための口座は、年金生活でメインバンクとなる、年金が振り込まれる口座にする人が多いでしょう。
普段使いの口座なので、歩いて行ける場所に支店があるといった、利便性の良い金融機関を選びます。
①の口座が決まったら、②や③の預け先を考えましょう。
①と同じ金融機関でも構いませんが、最低限行なっておきたいのが、ペイオフ対策。
預金残高合計額が1,000万円を超える場合には、複数の金融機関に預け分け、分散しておきましょう。
④の死亡時に必要なお金は、葬儀費用など死亡後すぐに必要となるお金。
預貯金で残す場合には、万一の時、比較的下ろしやすい、期間が短めの定期預金が良いでしょう。



夫のためのお金は妻名義、妻のためのお金は夫名義の口座で準備しておいても良いですね。
⑤のゆとり資金は、その一部なら、リスクの大きい商品で運用しても良いお金。
但し、老後資金は減らさないことが重要。
商品の仕組みやリスクを知って、納得した上で選んで下さい。
株や投資信託、債券などに投資するのは、どんなに多くても⑤の金額が上限。
株や外貨に興味を持っているなら、専用口座を作って、⑤の資金の一部を入金し、その範囲内で運用に挑戦しましょう。
- 目的に合った金融機関を選ぶ
- 取引する金融機関はできるだけ少なくする
- 家族へ金融機関の情報を知らせておく
- 有利そうな情報を見つけても飛びつかない



管理の手間を考えると、付き合う金融機関は3~5行(社)くらいが妥当です。生活資金を入れておく口座は、足を運びやすい近所の金融機関にしましょう。
まとめ
希望する住まいや夢を実現するには、お金も重要な要素です。
老後に向けて、どれくらいの資金を準備できるのか、今こそ、じっくり考えるべき時でしょう。



「年金生活になるのが不安…」という人も、「退職金をもらえば老後は何とかなる!」と考えている人も、先ずは現状を把握してみましょう。
現在の貯蓄、退職までに貯められるお金、加入している個人年金や養老保険の満期金、退職金などの「プラスのお金」から、定年時に残る住宅ローンなどのローン残高、これから掛かる教育費、貯蓄から払う予定の大きな出費などの「マイナスのお金」を差し引いた金額が、定年時に準備できる老後資金です。
順調に貯蓄を増やしてきたので、一先ず老後は安心という人は良いのですが、準備できる資金が思ったより少ないのであれば、繰り上げ返済で住宅ローンを減らしておく、貯蓄のペースを上げる、60歳以降も働くなど具体的な対策を考え、実行していきましょう。
それでも予算が足りなくて、思い描いていた夢が実現できそうもないということであれば、内容を変更したり、工夫して予算の範囲内でできることをすれば良いのです。



お金がないことを悔やむより、あるものを工夫して楽しく暮らしていくことを考えましょう。
定年後の生活は、公的年金からの収入が中心になります。
さて、どれくらいもらえるでしょうか。
公的年金の支給開始年齢や、凡その年金額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認することができます。
その他、企業年金や、個人年金、その他の収入(配当・家賃収入など)がある人もいます。
それらの収入が何歳から何歳までいくら見込めるのか、調べて書き出しておきましょう。
年金収入が少ないとがっかりしてしまう人もいるかもしれませんが、それほど悲観することはありません。



お金のためだけでなく、生きがいも感じられる仕事を、現役時代とは違うペースで、楽しみながらするというのも良いものではないでしょうか。
退職後には、現役時代より遥かに少なくなった収入で暮らすことになります。
徐々に増えてしまった家計支出をいきなり減らすのは難しいもの。
何もかも減らしたり止めたりしなければならないとしたら、定年後の生活は本当につまらないものになってしまいます。



自分たちは何に対するお金を優先させるのか、生活のどこに重点を置くのかを、今から考えておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。