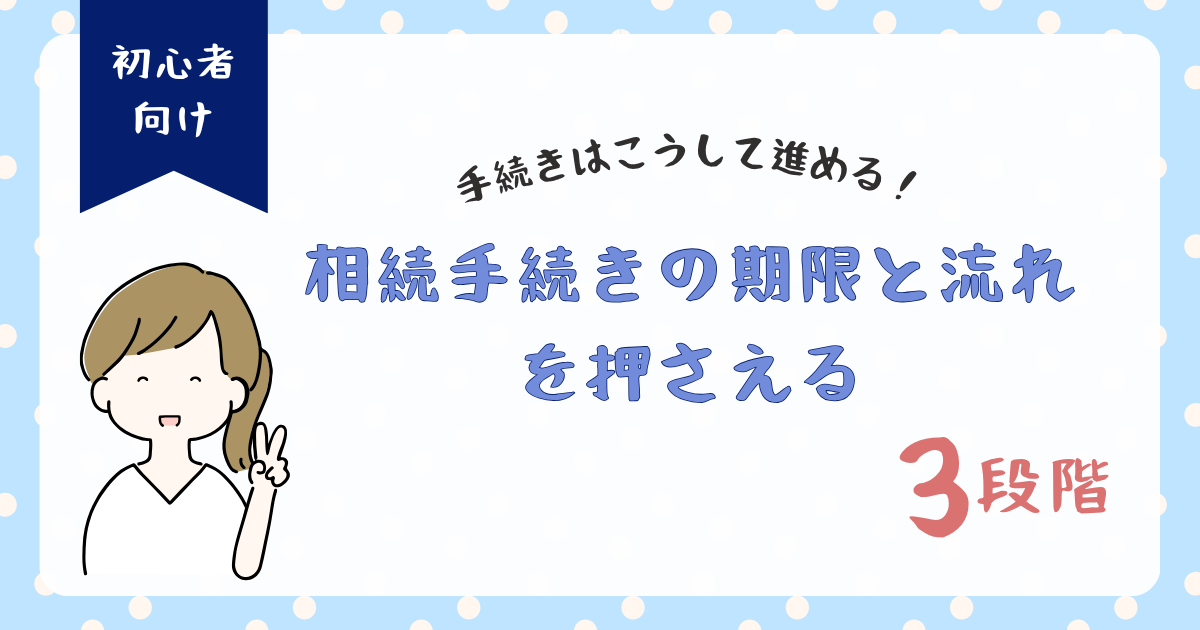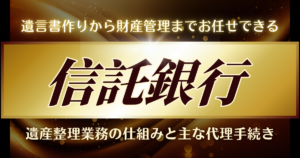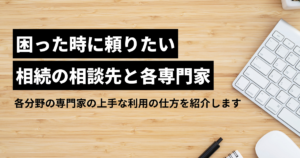悩める人
悩める人相続手続きって、何するの?



相続完了までにはどのくらいの時間が掛かる?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 相続手続きの進め方とポイント
- 主な相続手続きの期限と流れ
- 主要な手続きの詳細と関連事項
はじめに
相続の手続きといっても、何をどうしたら良いのか戸惑ってしまう人が大半でしょう。
相続は、自分に家族がいる限り、少なくとも一生に一度は迎える一大事。
肉親の死を目の当たりにするため、どうしても動揺してしまいがちです。



しかし、残念ながら、相続の各種手続きには期限があります。悲しみに暮れる遺族たちを待ってはくれないのです。次の「相続タイムスケジュール」を見ても分かるように、この進行は、大変ハードと言えます。
- 主な相続手続きの期限と流れ -
- 被相続人の死亡=相続開始
- 死亡届の提出=7日以内
- 遺言書の有無の確認と検認
- 戸籍の確認と相続人の確定
- 遺産・負債の調査
- 相続放棄・限定承認の申述=3か月以内
- 所得税の準確定申告=4か月以内
- 相続財産の確定・評価
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の移転登記=3年以内
- 相続財産の名義変更
- 相続税の申告・納付=10か月以内



このハードスケジュールを乗り切るには、無理せず余裕のある計画を立てて、速やかにそれを実行していく必要があるでしょう。
被相続人が死亡したからといって、すぐに相続財産の分割に、というわけにはいきません。
葬儀後には、初七日、四十九日と法要が続きます。
遺族がようやく相続問題に取り掛かれるのは法要の後、2か月くらい経ってから。
本格的な手続きはここからということになります。
となれば、最終目標となる相続税の申告・納税までの期間は、残り約8か月間。
その間に相続財産の調査・評価、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、財産の名義変更…と、複雑な手続きをこなさなければなりません。



これらをたった数か月間で済まさなければならないのは、なかなか至難の業。とてもゆっくり時間を掛けてできるシロモノではありません。
とりわけ不動産や預貯金、株などの金融資産があちこちに散らばっている場合は、必要書類や資料を集めるだけでも相当な時間と手間が掛かります。
ちょっとややこしい書類に手間取ってしまえば、2、3か月はあっという間に過ぎてしまいます。
タイムリミットの10か月を過ぎても、相続の手続きが終わらず、ペナルティーを受けなければならないという事態を引き起こさないためにも、綿密にスケジュールを組んで、手順通りに手続きを進められる態勢を作る必要があります。
相続開始直後の手続き



相続発生(被相続人死亡)日~四十九日法要。死亡届から始まって次々と手続きが目白押しです。
死亡届の提出
家族が亡くなったら、市区町村に「死亡届」を提出しなければなりません。
提出期限は、死亡後「7日以内」です。



但し、死亡届を出さないと、火葬や納骨に必要な「埋火葬許可証」が発行されないので、早めに提出しましょう。葬儀のスケジュールを考えると、死亡日か翌日には提出すべきです。
死亡届の用紙は、市区町村役場や病院にあります。
届出先は故人の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、医師の作成する死亡診断書(又は死体検案書)を添付して提出します。



同居の親族などが届出人となりますが、実際に役所へ出向くのは誰でも良く、葬儀社が代行してくれることが多いようです。
また、死亡診断書は生命保険金を請求する際にも必要になりますので、複数枚もらっておくと良いでしょう。
葬儀に纏わるお金
預金口座の凍結
葬儀には大きなお金が掛かります。
さらに、遺族が当面を暮らしていくための生活費も必要になります。
これら大きな負担に耐えるには、まとまったお金が入用になってきます。
これらの費用が、残された遺族全員で捻出できれば、それに越したことはありません。
しかし、亡くなった被相続人が一家の大黒柱で、預貯金の殆どが、被相続人名義になっていると、少し事態はややこしくなります。



預貯金口座の名義人が亡くなると、銀行などの金融機関は、一部の相続人が勝手に現金を引き出せないように、名義人の死亡を知った時点でその人の口座を凍結します。貸金庫やその他の取引も同様です。
凍結された口座は、遺産分割協議が成立して、更に相続人全員が署名押印した遺産分割協議書などの書類が揃うまで、原則として引き出しができなくなります。
但し、金融機関も全ての死亡情報を把握しているわけではないので、死亡後も口座が凍結されないケースもあります。
だからと言って、勝手に現金を引き出すと、相続人同士でトラブルになりかねないので、極力しない方が良いです。
やむを得ず引き出す場合は、何のためにいくら引き出したのか「使い道を記録」し、「領収書などの証拠」を残しておくようにしましょう。
尚、「葬儀費用のため」であれば、相続人全員の同意の下、被相続人の口座から現金を払い出してくれる金融機関もあります。



残された家族の生活費については、銀行口座の凍結を見越して、事前に考えておく必要があります。生命保険に加入していれば、死亡保険金は遺産分割協議が終わっていなくても受け取ることが可能です。
相続税控除の対象
葬儀に掛かった費用は相続税の計算上、相続財産から控除することができます。
申告の際には「明細書に内訳を記入して添付」しなければなりませんので、きちんと記録しておくことが大切です。
葬儀業者の支払いだけでなく、僧侶への読経料やお布施、お車代、飲食代、手伝ってくれた人へのお礼など、葬儀に掛かった費用は全て、ノートなどに忘れず書き留めておきましょう。
控除を受ける際の重要な資料となります。
中でも、葬儀の際には、領収書の残らないお金がたくさん発生してしまうので、その点も漏らさず記入しておきましょう。
葬儀に関わるお金の中で、一番注意しておきたいのは、やはり「香典」です。
参列者が多ければ、香典の額もかなりのものになります。



紛失などがあっては一大事。きちんと管理しておく必要があります。信用のおける人に受付とお金の集計を頼み、香典リストを作ってもらうようにしましょう。
受け取った時点で開封し、「誰から」「いくら貰ったか」をはっきり書き記しておくのです。
お金はその日のうちにまとめておいて、一括管理するのが良いでしょう。
ちなみに、香典の場合は、極端な高額でない限り、贈与税の対象にはなりません。
葬儀で全てが終わったわけではありません。
遺族が入信している仏教の宗派によって違ってきますが、初七日、四十九日、百カ日と法要が続いていきます。
しかし、これら葬儀以降の法要に掛かる費用については、相続税の控除の対象になりません。



ただ最近では、初七日の法要を、葬儀の日や、埋葬を済ませた直後に行うケースが増えてきています。このような法要に掛かる費用は、葬儀費用に含めても構わないとされているので、控除の対象となり得ます。
また、香典返しに掛かる費用や墓地購入の費用なども、控除の対象外になります。
公共料金の名義変更
葬儀が済んだら、故人の口座がある各金融機関に死亡届を提出します。
ここで、銀行から「死亡日現在の預貯金・借入金の残高証明書」を受け取ります。
相続財産を計算する時に必要になるからです。
それ以降、相続人全員の承認があるか、相続が確定するまで、預貯金は封鎖されます。
そのため、口座の引き出し・解約だけでなく、電気・ガス・水道など公共料金の引き落としもできなくなります。
従って、銀行へ死亡届を出すついでに、公共料金の名義変更も行なっておきましょう。
故人がクレジットカードを使用していた場合は、そのクレジット会社にも死亡届を出す必要があります。
遺言書の確認
遺言書の存在は、相続において大きなウエイトを占めています。
遺言書がある場合は、原則として「遺言書の指定通り」に、財産を分割することになります。
先ずは、遺言書があるかどうかを確認します。
遺産分割が終わった後に遺言書が出てくると、手続きをやり直さなければなりません。
仏壇の中や銀行の貸金庫など、故人が保管しそうなところを十分に調べましょう。



公正証書遺言を残している場合は公証役場に原本があるので、遺品の中に遺言書の謄本がなくても最寄りの公証役場に問い合わせれば遺言書の有無が分かります。
遺言書が発見され、封がしてあった時は、勝手に開けてはいけません。
封印のある遺言は、相続人又はその代理人の立ち合いの下、家庭裁判所で開封することが法律で定められています。
また、公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認は偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きです。



2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に自筆証書遺言を保管している場合は、検認が不要です。
相続開始後4か月以内の手続き



四十九日法要~相続発生4か月。相続財産の把握、準確定申告でそろそろ相続準備に取り組む時期です。
相続放棄・限定承認
葬儀、初七日、四十九日の法要が済んでひと段落ついたら、そろそろ相続財産の手続きに掛からなければなりません。
中には、被相続人の残した借金のため、正の財産より負の財産の方が多い場合もあります。
この場合は、相続発生後から3か月以内に「相続放棄」の手続きをとると、被相続人の残した負の財産を受け継がなくて良いことになります。
但し、相続財産全てを放棄してしまうことになるため、正の財産も受け取ることができません。
また、相続財産を全て清算してしまい、その後、正の財産が残れば相続できるという「限定承認」の手続きも、相続発生後3か月以内なら選択が可能です。
どのくらい財産があるのか、ローンなど負の財産もあるのか、もしあるのならどのくらいなのか…などを確かめて、大ざっぱで良いのでとにかく相続発生後3か月以内は、遺産の把握に力を入れましょう。
この時期なら、相続放棄、限定承認という大きな切り札を使うことができるからです。



しかし、3か月が経過してから借金に気付いたのでは、もう手遅れです。注意しましょう。
財産確認でやっておきたいことは、先ず、相続の対象となる財産を全てリストアップしておくことです。
現金・預貯金以外の財産は、👇の記事に掲載している評価方法を用いて、相続税計算用の評価額を算出します。



算出された正の財産から負債額を差し引いたものが、最終的な相続財産の合計となるわけです。
準確定申告
「相続税をちゃんと払わなければ…」と相続税ばかりに気を取られてしまい、もう一つの隠れた税金をどうしても忘れがちになります。
隠れた税金とは、「所得税」のことです。
たとえ死亡した人であっても、被相続人が亡くなった年に被相続人にかかる所得税の申告は、怠ってはいけません。
通常の確定申告は、翌年の2月16日~3月15日までの間に行うことになっています。
しかし、年の途中に亡くなると、死亡した時点で所得が確定するので、死亡日から「4か月以内」に確定申告をしなければなりません。
これを通常の確定申告とは区別して、「準確定申告」と言います。
準確定申告の手続きは、亡くなった被相続人本人に代わって、準確定申告の納税も含め、相続人が納税代理人となって行います。
その税額は被相続人の債務と見なされるので、相続人が、被相続人の本来払うべき税金を立て替えた場合、その相続人は相続財産から税金分を受け取ることになります。
これとは全く逆に、準確定申告により還付金を受け取った場合は、その還付金を相続財産に含めなければなりません。



被相続人が会社員だった場合は勤務先が年末調整を行なってくれるので基本的に申告は不要です。但し、医療費控除などを受けられる場合には、還付のための申告を行うことができます。
相続開始後10か月以内の手続き



相続発生4か月~10か月。遺産分割協議、相続税の申告・納税。相続の完了まであと一息です。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰が引き継ぐか決める会議です。
遺言書で分割を禁止されていない限り、相続人は誰でも分割協議を開くことができます。
但し、遺言書による「指定相続」が上手く進行している場合は、この協議を開く必要はありません。
相続税は、相続発生後10か月以内に納めなければなりません。
10か月を過ぎると、税金を延滞したということで「加算税」を支払わなければならないのです。
そうならないよう、なるべく早めに遺産分割協議を始める必要があります。



かと言って、慌てて決めてしまうのも困りもの。例えば、いったん遺産分割が成立した後、再度協議をやり直して再分割すると、相続人間で贈与が行われたものと見なされてしまうのです。
金額によっては「贈与税」が課されてしまいます。
このような出費はムダ以外の何物でもありません。
「取り敢えず」「何となく」という気持ちで協議するのは避けましょう。
法定相続人の調査・確定
遺産分割協議にかかる前に、相続人の戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を確定することから始めます。
原則として、法定相続人全員の出席が、協議を開く条件となるからです。



戸籍調査なんて大げさに思えますが、密かに認知した子供がいたり、家族には内緒で甥や姪と養子縁組をしていたり…、という可能性もゼロとは言えません。
それらの事実を知らないまま遺産分割協議を終えても、その協議内容は無効となります。
結論から言うと、相続人を確定するためには、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せることが、多くのケースで必要です。
戸籍調査は、被相続人の本籍地で戸籍謄本を請求することから始めます。
そして、そこに記載された情報を基に、一つ前の戸籍謄本を入手します。
本籍地の市区町村が変わっていれば、請求先も変わります。
これを地道に繰り返し、出生した時の戸籍まで遡り、最終的には、被相続人の親の代の戸籍まで辿ることになります。
尚、各地方自治体で戸籍のコンピューター化が進められています。



コンピューター化された戸籍謄本は、従来の縦書きから横書きになり、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、除籍謄本は除籍全部事項証明書と名称も変わっています。
多少の表現の違いはありますが、記載内容は、従来の戸籍(除籍)謄本と同じです。
改製原戸籍謄本はそのままです。
戸籍・除籍謄本は、本籍地(又は旧本籍地)の市区町村の戸籍担当窓口で請求する他、郵送による請求もできます。
請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人が請求する場合は本人の委任状が必要です。



戸籍調査は、慣れていないと難しい面もあるため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に頼む方法もあります。とにかく、相続人全員の出席が、協議を開く大原則であることを覚えておきましょう。
遺産の評価・確定
また、遺産分割協議を始める前に、遺産の総額・範囲や、財産評価の確定もしておかなければなりません。
どんな財産があるのか、その総額はどのくらいなのかが分からなければ、遺産分割の仕様がないのです。
さらに遺産の額を間違えていたり、後に隠れ財産が見つかったりした場合、その協議は無効になります。



法定相続人、遺産額をしっかり整えてようやく協議に入ることができるのです。
未成年者や行方不明者がいる場合
遺産分割協議は、「相続人全員の参加」が大原則です。
また、遺言による包括受遺者がいる時は、その者も協議に参加します。
相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。
さらに相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任しておく必要があります。
通常、未成年者については親権者が法定代理人として財産管理を行いますが、遺産分割に関しては例外です。
例えば、故人の妻と未成年の子供が相続人の場合、妻と子供は利益が相反する関係にあるため、妻が子供の代理人となることはできません。



特別代理人の選任は、親族の中から適切な人を候補者に立て、子供の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。未成年の子供が二人いるなら、二人の特別代理人の選任が必要です。
判断能力に欠ける認知症の相続人がいる状態で遺産分割協議を行なった場合、その遺産分割協議は無効になる可能性があります。
有効な遺産分割協議を行うためには、相続人は「意思(判断)能力」と「行為能力」を有していなければならないとされているからです。
相続人が認知症などで判断能力を欠く場合は、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、その相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。



このように、精神上の障害により判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう、代理人が生活と財産を保護する制度を「成年後見制度」と言います。
遺産分割協議は「相続人全員の合意」がないと成立しません。
そのため、行方不明者がいると、遺産分割協議が滞ってしまいます。
戸籍や住民票などで調査を尽くしても行方が分からない時は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
その人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産分割協議を進める方法があります。



通常、不在者財産管理人には、申立人が推薦する利害関係のない被相続人の親族などがなります。適当な人がいなければ、家庭裁判所が弁護士などの専門家を選任します。
遺産分割協議書の作成
相続人同士で協議が成立、遺産の分割が確定したら、次は遺産分割協議書の作成に入ります。
協議書の作成は法律によって義務付けられているわけではないので、作成しなかったとしても、合意した内容は無効になりません。



しかし、協議内容を巡って対立が起きた場合、協議書があれば証拠となるので、無用な争いを未然に防ぐことができます。
また、遺産分割協議書は、相続税の申告だけでなく、銀行預金の名義変更や相続登記の際にも必要になります。
つまり、いずれにせよ作成が必要です。
遺産分割協議書は、遺言書のように、民法で定められている堅苦しいルールはありません。
内容がはっきり分かるものであれば、どのような形式でも構いません。
縦書き、横書き、手書き、ワープロ、何でもOKです。



大事なことは、誰がどの財産を取得するのかを、もれなく明確に記載することです。そして、作成した書面に全ての相続人が目を通し、納得したら、相続人全員が署名・押印します。
印鑑は必ず市区町村役場に届け出た「実印」を使用して下さい。
遺産分割協議書は、常に「印鑑証明書」とセットで使用することになります。
書類は相続人の人数分作成して、それぞれが保管します。



その他、トラブル防止という意味では、相続人の間で取り決めた債務の分割方法や、代償分割がある場合の代償金額や支払条件なども記載しておくと良いでしょう。
調停・審判
遺産分割協議は、必ずしも1回で済むとは限りません。
相続人同士主張が嚙み合わず、延々と平行線を辿ったまま、というケースもあるのです。
その場合は、複数回にわたって協議を開くことになります。



しかし、それでも合意できないなら、家庭裁判所に「調停」の申立て、更には「審判」を仰ぐことになります。調停は、お互いの意見を正確、公正に出し合える場として役立ちます。
遺産の名義変更
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書も出来上がれば、次は遺産の名義変更の手続きをします。
とりわけ土地・建物のように、登記制度がある財産は、被相続人の名義から、相続人の名義に変更する手続きが必要なので、大変手間が掛かります。
通常、不動産の場合、「実際の所有者」と「登記簿上の所有者」は、殆どが同一人物です。
しかし、中には、不動産の名義が先代の名前のままになっているケースもあります。
確かに、土地・建物を所有して、そこに住んでいる限りは、名義は誰の名前でも構わないでしょう。
「相続が発生したからといって、手間とお金を掛けて、わざわざ相続登記などしたくない」というのも一つの考えです。
しかし、そのままにしておくと「これは私の不動産だ」と主張できないのも事実。
例えば、不動産の売却をしたり、担保に入りたりということは、登記手続きをとっていないと無理です。
相続登記をせずに死亡し、次の代への相続が発生すると、更に面倒なことになります。



2024年4月1日から、相続した不動産について名義変更(相続登記)を行うことが法律で義務化されました。不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割協議が成立したら、早めに相続登記を行いましょう。
不動産以外の財産の名義変更も必要です。
名義のあるものは全て、名義変更又は解約の手続きをしなければなりません。
名義変更が必要な財産には、不動産、銀行口座の他、株式、ゴルフ・リゾート会員権、自動車などがあります。
いずれも、いつまでにという期限はありませんが、そのままにしておくと、銀行口座は凍結されたままになり、株式の配当金の受け取りや株主優待を受ける権利などが行使できません。
遺産分割がまとまったら、なるべく早く手続きをとりましょう。
相続税の申告・納付
遺産分割協議も成立、相続財産の名義変更も無事終われば、そろそろ相続税の申告・納税の手続きに入ります。
相続税の申告と納税は、相続発生後10か月以内に済ませなければなりません。
もし、この期限を超えてしまうと、延滞税などの加算税によるペナルティーが待っているので、期限は必ず守るよう注意しましょう。
延納・物納
相続税があまりに多額なため、現金で一度に払いきれないという場合は、相続税を分割払いにする「延納」や、不動産・国債・美術品などのモノで払う「物納」の方法を選択できます。
延納・物納の手続きも、相続税の申告・納税の期限と同じく、相続発生後10か月以内。
延納・物納をするための申請書を、所轄の税務署に提出します。
手続きの際、遺産の分割を終わらせていることが条件になります。



但し、延納や物納はあくまでも例外的な制度です。納付方法の優先順位は、①現金一括納付➡②延納➡③物納です。
尚、延納期間は利息に相当する利子税が掛かります。
物納の場合も物納財産の収納の日までの間、利子税の負担が生じます。
修正申告・更生の請求
相続税の計算は複雑なため、計算を間違えて申告してしまうケースも少なくありません。
或いは、使える特例を使わずに計算して、相続税を多く払ってしまっているケースもあります。
申告後に間違いに気付いた時は、速やかに間違いを是正しなければなりません。
申告した税額が少なかった時は「修正申告」をして不足分を納めます。
逆に申告した税額が多かった場合は、「更正の請求」をして納め過ぎた税金を取り戻すことができます。
修正申告ができるのは、計算ミスの他、新たな財産が見つかった場合や、財産を過小に評価していた場合などです。
修正申告の期限は特にありませんが、税務調査などで指摘を受ける可能性があります。
指摘を受けてから修正する場合、過少申告加算税が掛かります。
税務署の指摘を受ける前に自主的に修正申告すれば、加算税は掛かりません。



但し、自主的に申告した場合でも、遅れた日数によっては「延滞税」が掛かります。修正申告は、相続税を申告した税務署に、修正申告書を提出して行ないます。
一方、計算ミスや財産を過大評価して税額を多く申告してしまった場合は、申告した税務署に、相続税の更正の請求書を提出します。
更正の請求期限は、相続税の申告期限から「5年以内」です。
但し、未分割だった遺産について遺産分割が行われた場合や、遺留分減殺請求があり、返還又は弁償すべき額が確定した場合など、一定の事情により税金を払い過ぎている状態になった時は、その事情が生じたことを知った日の翌日から「4か月以内」に請求をします。
まとめ
家族が亡くなると、通夜、葬儀、告別式と慌ただしく時間が過ぎていきます。
併せて市区町村への届け出もしなければならず、悲しんでいる間もないほど、様々な手続きをこなしていかなければなりません。
葬儀や死亡後の事務手続きが終われば、今度は相続の手続きを始めます。
相続の手続きは様々あり、一つひとつ順を追って進めていくことになります。



大事なことは、常に「時間」を意識しながら準備していくということ。と言うのも相続の手続きの多くには、「期限」が設けられているからです。
中でもポイントになるのは、相続開始から3か月後と10か月後です。
「3か月」というのは、「相続放棄」又は「限定承認」の手続きの期限です。
つまり、相続するかしないかは「3か月以内」に決めなくてはならないのです。
この重大な決断をするためには、相続財産の内容をきちんと調べる必要がありますが、財産調査は意外と時間が掛かるものです。
ただ3か月後に相続するか否かを決めれば良いわけではなく、それまでの準備が大変なのです。
一方、「10か月」は、「相続税の申告と納付」の期限です。
正しく申告・納付するためには、前提として「遺産分割の話し合い」を終わらせなくてはなりません。
話がまとまらず申告や納付が遅れると、無申告加算税や延滞税が課されることもあります。
また、被相続人が個人事業者などで、生きていれば所得税の確定申告が必要だった場合には、「4か月以内」に「準確定申告」を行う必要があります。
各財産の「名義変更」も必要です。
名義変更に期限はありませんが、トラブルを防ぐためにも、遺産分割が確定したら速やかに行いましょう。



10か月という期間は、長いようでいて、あっという間です。手続きの多くは相続人の共同作業になりますので、一つひとつに思った以上の時間が掛かります。何事も早めに着手し、心に余裕を持って行いましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。