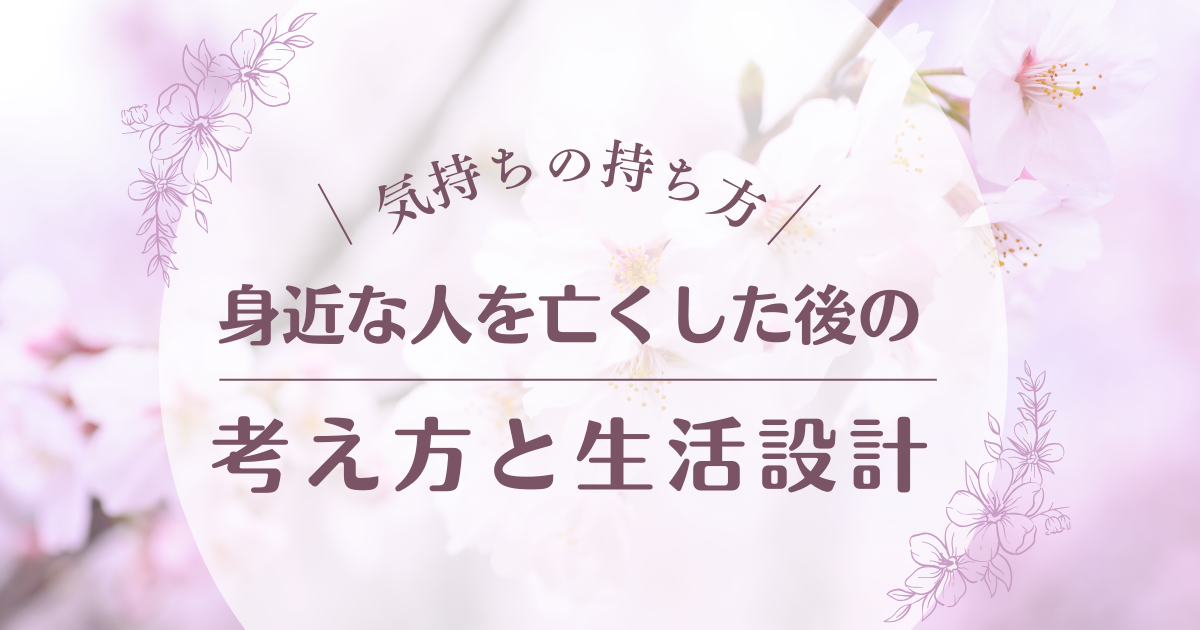悩める人
悩める人身近な人が亡くなった後の生活で考えること…?



困った時はどこに相談したら良い?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 身近な人を亡くした後の生活設計の立て方
- 大切な家族を亡くした後の気持ちの持ち方
- 人生の終い方のヒントと終活ですべきこと
- 今後の出来事と必要なお金の整理について
- 困った時のセーフティーネットと相談窓口
生活設計(お金)
身近な人が亡くなると、生活の形が変わり、改めて生活設計を見直す必要があります。
この先、どのような出来事が起こるのかを予測し、どれくらいお金が必要になるのかを整理しておきましょう。
遺族が受け取れるお金
遺族が受け取れるお金としては、故人に財産がある場合は遺産に加え、厚生年金や国民年金の遺族年金、会社員なら死亡退職金や弔慰金、保険に加入していたら死亡保険金などが受け取れます。
これらは、遺族の今後の生活費の基盤となる大切な資産です。
死亡退職金は、故人が勤めていた会社に規定があれば、死亡による退職金として、企業より支払われるお金です。
これにプラスして弔慰金が支給されることもあります。



金額や受け取るための手続きは、勤務先に確認しましょう。
故人が生命保険や共済に入っていれば、死亡保険金が支払われます。
必ず保険証券が発行されている筈なので、故人の身の回り品を確認してみましょう。
保険には生命保険、損害保険、共済、勤務先の団体保険などがあります。



医療保険に加入していたか、他の保険に医療特約が付いていた場合は「病気やケガなどで入院していた分の給付金」も受け取ることができます。
損害保険は、保険種類が傷害保険の場合、ケガや事故などを理由とする入院、死亡に際し保険金が支払われます。
尚、保険金や給付金は請求しなければ支払われないので、忘れないようにしましょう。
公的年金には「遺族年金」と言って、被保険者によって生計を維持されていた家族に支払われる年金があります。
但し、全ての人が受け取れるわけではありません。
保険料の納付状況、故人の職業や子供の有無、婚姻期間などによって受給できるかどうかが決まり、金額もそれぞれ異なります。
また、故人の加入していた年金の種類によっても違います。
国民健康保険、健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度などに加入していた方が亡くなった場合、掛かった葬祭費・埋葬料の一部が支給されます。
一般に、国民健康保険や後期高齢者医療制度からは「葬祭費」が、健康保険からは「埋葬料」が支給され、名称や金額は制度などによって違いがあります。



葬祭費は葬儀の翌日から2年以内、埋葬料は死亡の翌日から2年以内と期限があるので、忘れず申請しましょう。
今後の出来事とお金の整理
人生では節目節目で大きな出費がある他、生活スタイルの変化に応じて生活費も変わってきます。
ライフプラン表(ライフイベント表)とは、自分や家族の年齢と、何年後にどのようなライフイベントがあるか、どんなことをしたいかを記入した表で、いつ頃、どのくらいのお金が必要になるのかという目安になります。
ライフイベントとは、人生の節目になるような、大きな出来事のことです。
例えば、子の進学、就職、結婚、出産、自分の定年、住宅購入、リフォーム、住み替え、車の買い換え、有料老人ホームへの入所などがあります。



家族で海外旅行をしたい、などの希望があれば、それも書き加えます。別居か同居に関わらず、親や子の年齢も書き入れておきましょう。
今後のことを計画するならば、親の介護や子供の結婚なども念頭に置く必要があるからです。
バランスシートとは、預貯金を始め金融資産や不動産、借金など、自身の持っている資産と負債を一覧にしたもので、今の段階での正味財産の把握に役立ちます。
これらの表を作成することにより、一生に掛かるお金のある程度の金額が把握でき、今後の生活設計に役立てることができます。
収支から考える生活設計
ライフプラン表やバランスシートができたら、次に「キャッシュフロー表」を作成します。
キャッシュフロー表とは、現在の収支状況と今後のライフプランを基に将来の収支状況を予想し、貯蓄残高の推移を時系列にした表です。
キャッシュフロー表には以下の4項目が必要です。
- 年間収入
- 年間支出
- 年間収支
- 貯蓄残高
尚、一般的に年間収入には、可処分所得を記入します。
可処分所得とは、給与・賞与等の年収(総収入)から、税金や社会保険料を差し引いた「手取り金額」のことで、自分で自由に使うことができるお金のことです。
これを作成することで、人生の終わりまでのお金の動きをシミュレーションすることができます。
また、家計の問題点にも気付くことができるため、それに対する対策が立てやすくなります。



70~80歳辺りで貯蓄残高がマイナスになる人は、今の収入や支出では、老後まで安心して暮らせないということになります。働けるうちに収入を増やす、又は支出を減らす手段を考えなければなりません。
元気に働けるうちなら、例えば資格を取るなど、収入を増やすために何をしたら良いのか、計画的に考え行動に移すことができます。
キャッシュフロー表は、このように人生を計画的に進め、将来的にお金に困らないようにするために作ります。



それだけでなく、例えば「毎年旅行をしたい」「いずれ有料老人ホームに入りたい」など、自分の思い描く夢や願望を加えることで、実現に必要な資金計画も具体的に考えることができます。
資産運用の考え方
低金利の今の時代は、お金を普通預金に預けておくだけでは殆ど増やすことはできません。
リスクが取れる人は少しずつでも運用するのも良いでしょう。



但し、やみくもに投資するのは危険です。運用の原則を守りながら、手堅く運用しましょう。
先ずはライフプラン表やキャッシュフロー表を作成し、「いつ頃」「どんな用途」で、「どれくらいのお金」が掛かるのか、大まかに知っておきます。
当面の生活費、老後資金、住宅修繕費、子供の結婚資金など、目的別に把握しておき、運用もその目的に応じて行います。



目減りすると困る当面の生活費は、安全性が第一です。いつでも引き出せるよう、定期預金や普通預金に預けておきましょう。
老後資金を貯めることを考えるなら、個人年金保険に加入するのも一つの手です。
但し、払い込む保険料が年金で戻るかどうかを確認し、納得できるものを選びます。
その他、投資の勉強をするのなら、投資信託の積み立てで、リスクを抑えた運用を行うのも良いでしょう。



但し、投資に回して良いのは「一定期間使わない資金の一部」のみです。金額は、今ある資産のうち「今後5年超使わない資金の1~3割程度」を上限とします。
金融商品を利用する場合には、その仕組みや内容が理解できるものだけにしましょう。
生活設計(暮らし)
生きがいを持つ
身近な人を失った悲しみは、なかなか癒えるものではないでしょう。
しかし、自分や家族の生活を守り、健康に暮らしていくためにも、一人の世界に閉じこもっていてはいけません。
お金のことも大切ですが、人生は長いのですから、これからの老後を如何に楽しむか、生きがいを持つことを考えましょう。



生きがいを感じるためにも、仕事は辞めないことです。状況が許せばフルタイムで働かなくとも、パートタイムや、収入がお小遣い程度のものでも良いでしょう。
仕事は収入になるだけでなく、人や世の中の役に立てているという実感を持つことにも繋がります。
趣味や、それを通じた仲間を持つのもお勧めです。
人は周りの人と繋がりを持ちながら生きていくようにできています。
人との触れ合いが喜びをもたらしてくれます。



昔からの知り合いは時間の経過と共に自然と少なくなるものです。趣味などのサークルに所属し、若い世代の友人も作っておきましょう。
- 仕事を持つ
- ボランティアをする
- 趣味を持つ
- 気の合う人と交流する
- 友人を持つ



仕事や人との触れ合いが「心の糧」になります。人との繋がりを積極的に持ちましょう。
人生の終い方を考える
60歳を超えたら考えておきたいのが、自分の介護問題を含めた終活です。
人生100年時代とするなら、80歳になった時に、あと20年の人生があるわけです。
お金や住居など何もかも全てを整理してしまうと、生き生きとした人生を送れなくなってしまいます。
「終活」+「長生きに備えた準備」の二本立てで今後の人生を考えておくのがお勧めです。
エンディングノート、遺言書も準備しておきましょう。
自分の亡き後に家族が揉めないよう、遺産分割は公平に考えておきます。
また、子供たちには人生の終い方について、生前からよく説明し、納得させておきましょう。
子供がいない場合は、誰に託すのかも考えましょう。
財産のうち、特に大きな部分を占めるのが、やはり持ち家です。
住宅をどうするかは、自分自身の介護問題と併せて考えておく必要があります。
将来的に、住宅を売却して高齢者施設への入居費用に充てるつもりなら、予め子供たちに伝えておきましょう。
子供に残すことを考えるのであれば、二世帯住宅にするのも一つの手段です。



高齢者施設への入居を考えている場合は、必ずいくつかの施設を見学・体験してみましょう。納得のいく施設を選ぶためにも、できれば50代のうちから検討を始めたいものです。
また、困った時は、土地や建物、マンションなどの不動産を担保にしてお金を借りることができる不動産担保ローン、リバースモーゲージなどを利用することも考えてみましょう。
- 終活 -
- エンディングノートを書き始める
- 遺言書の検討をする
- 人生の終い方を家族と話し合う
- 突然倒れた時のための連絡先を持ち歩く
- 自分の持ち物の整理
- 長生きの準備 -
- 介護が必要になった時のことも考え、資金を貯めておく
- 若い世代など、人との交流を幅広く持つ
- 思い出の品、大切なものは取っておく
- 住まいを確保する
- 介護施設や高齢者住宅も検討する



長生きした場合も考慮して計画を立てること。介護が必要になった時のことも考えておきましょう。
住まいの選択肢
生涯に必要なお金の中でも、大きな部分を占めるのが「住宅費」です。
持ち家で住宅ローンを組んでいる場合、一般的には「団体信用生命保険」に加入しています。
そのため、故人名義の住宅ローンについては保険で完済され、遺族が相続すれば、そのまま住み続けることができます。
住む場所があるだけでも安心できるものです。
賃貸住宅に住んでいる場合や、持ち家でも団信に入っていなかったなどで、住宅ローンが残る場合、家計への負担は非常に大きなものになります。
保険金や遺産が多く残されていれば、家賃や住宅ローンの支払いもその中でやり繰りできるかもしれません。
しかし、そうでなければ、家が狭くなったり、不便になったとしても、家を売る、家賃の安いところに引っ越すなどして、住居費をなるべく減らすことを考えることになります。
そして、住宅は多くの場合、年数が経てば経つほど売りにくくなります。
処分するなら、値段の付く早いうちの方が良いでしょう。
賃貸住宅を借りるにしても、収入が安定していない場合は借りにくいという現実があります。
持ち家を売却したにも関わらず、賃貸住宅がなかなか見つからないということにならないよう、並行して進めることが大事です。



但し、早急に結論を出すのは避けて、じっくり考えるようにします。低収入世帯への減免を設けている公営住宅や母子生活支援施設などもあるので検討してみるのも良いでしょう。
- そのまま持ち家で暮らす
- 安い賃貸に住み替える
- 家族と同居
- 住居を購入
- 高齢者向け施設へ



住まいの問題は、今後自分や家族がどのように暮らしていくかに深く関わります。人生設計と照らし合わせて検討しましょう。
各種制度
生活保護
故人の収入によって生活費の殆どを賄っており、更に遺族年金などで生活していけない場合、当然、自分自身が働くなどして、不足分を補わなければならなくなります。
しかし、病気がちだったり、小さな子供がいたりすると、何らかの事情で働けず、どうしても生活していけないという場合もあるでしょう。



そうした困窮者を助ける仕組みが「生活保護」です。生活保護には、様々な種類があり、必要に応じて費用が扶助されます。
- 生活保護の種類 -
- 生活扶助 … 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
- 住宅扶助 … アパート等の家賃
- 教育扶助 … 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助 … 医療サービスの費用
- 介護扶助 … 介護サービスの費用
- 出産扶助 … 出産費用
- 生業扶助 … 就労に必要な技能の習得等に掛かる費用
- 葬祭扶助 … 葬祭費用



生活保護が受けられるのは、次の項目を満たしても尚、生活困難である人のみです。
- 所有している資産があれば売却などし、生活費に充てること
- 病気などなく、働くことができる人は能力に応じて働くこと
- 年金や雇用保険、児童手当などの法律や制度で給付を受けることができる場合は、先ずそれを利用すること
- 親族などからの援助が可能な場合は援助を受けること



生活保護を受けたい場合、先ず最寄りの福祉事務所に相談してみましょう。他の支援制度などを活用できないか、一緒に検討してもらえます。
さらに家庭訪問や資産のチェックなど、保護の対象となるかどうかの調査を行なった上で、支給という流れになります。
申請の際に調査のために、預金通帳や給与明細など、収入状況が分かる資料を提出しなければならないこともあります。
また、受給が始まってからも、収支状況を毎月報告する義務がある他、ケースワーカーによる年数回の訪問調査を受ける必要があります。



生活扶助や住宅扶助は家族数やその構成、住んでいる地域などによって異なりますが、最低限の生活の保障に必要な金額が支給されています。
相談窓口
日本では困難を抱えた人に対して、様々なセーフティネットが設けられています。
制度は多岐にわたり、仕組みが複雑なものもあります。



困ったこと、分からないことがあったら、最寄りの相談窓口に相談してみると良いでしょう。
- 困った時の相談窓口 -
- 生活のお金に困っている … 各市区町村役場・福祉事務所
- 病院の治療費に困っている … 掛かり付けの病院の社会福祉士等
- 年金に関する相談 … 日本年金機構・ねんきんダイヤル・年金事務所
- 住宅ローン返済に困っている … 利用している金融機関の窓口
- 高齢者の総合的な相談 … 地域包括支援センター・社会福祉協議会
- 心の悩みや問題に関する相談 … こころの健康相談統一ダイヤル
- 子育てや介護についての相談 … 各市区町村役場・福祉事務所・地域包括支援センター
- 奨学金に関する相談 … 独立行政法人 日本学生支援機構
- 就職に関する相談 … 最寄りのハローワーク
生活保護や低利での融資、ひとり親家庭や高齢の単身世帯が受けられる支援制度もあります。
働くのに必要な資格・技能習得が無料でできる制度もあります。
困った時は一人で抱え込まず、先ずは家族や友人に相談してみることが大切。
話をすることで解決の切っ掛けに繋がることがあります。
家族や友人に相談しにくい時は、公的機関の相談窓口を利用しても良いでしょう。
抱えている問題によって、様々な相談窓口があります。
身近な人を亡くしたばかりの今は、ただ辛く、先行きも暗く感じられるかもしれません。
でも、あなたは一人ではありません。
周囲に助けてくれる人や、社会の仕組みが存在します。
一人で抱え込まずに、周囲に助けを求めて下さい。
まとめ
身近な人を失うということには、言葉に尽くせない辛さがありますが、悲しみに沈んでばかりはいられません。
これからは、自分や家族の生活を守っていく必要があります。
先ずは冷静に、今後の生活にどれだけお金が掛かるのかを予測しましょう。
次に、遺族年金や死亡退職金、自分の働きによる収入や年金などでどの程度賄えるのかを、大まかに計算してみます。
そうすると、自分の今後の生き方がある程度見えてくる筈です。



年金保険料を支払っていれば、老後、国民年金や厚生年金などの公的年金を受け取ることができます。自分の受け取れる年金の額は、定期的に送付される「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で予想することができます。
亡くなった人の収入で生活費の殆どを賄っていた場合、遺族年金などがあったとしても、収入がかなり減ることになります。
家族が一人減っても生活費などの出ていくお金はあまり変わらないため、これまでと同じように生活していくのが難しくなることも考えられます。
さらに、子供がいるのであれば、就職するまでには教育費などが掛かります。
そうすると殆どの人は、働いたり、お金を運用したりするなど、何らかの手段によって収入を増やす必要があるでしょう。
今の家に住み続けるのか、住み替えるのかといった、老後の住まいをどうするのかという問題もあります。
様々な手を尽くしてみてもどうにもならない、本当に困った時には、生活保護などの公的な扶助制度を利用したり、各種窓口に相談したりすることも検討してみましょう。
- 今後の生活で考えること -
- 生きがいを持つ
- 終活について考える
- 住まいの問題について考える
- 遺族が受け取れるお金を知る
- 今後の生活に掛かるお金を計算する
- 一生の収支を把握する
- お金の運用について考える
- 生活保護
- 困った時の相談窓口



今は人生100年と言われる時代。お金のことも考えなければなりませんが、生きがいを見つけ、長い老後をいかに楽しむかということも前向きに考えてみましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。