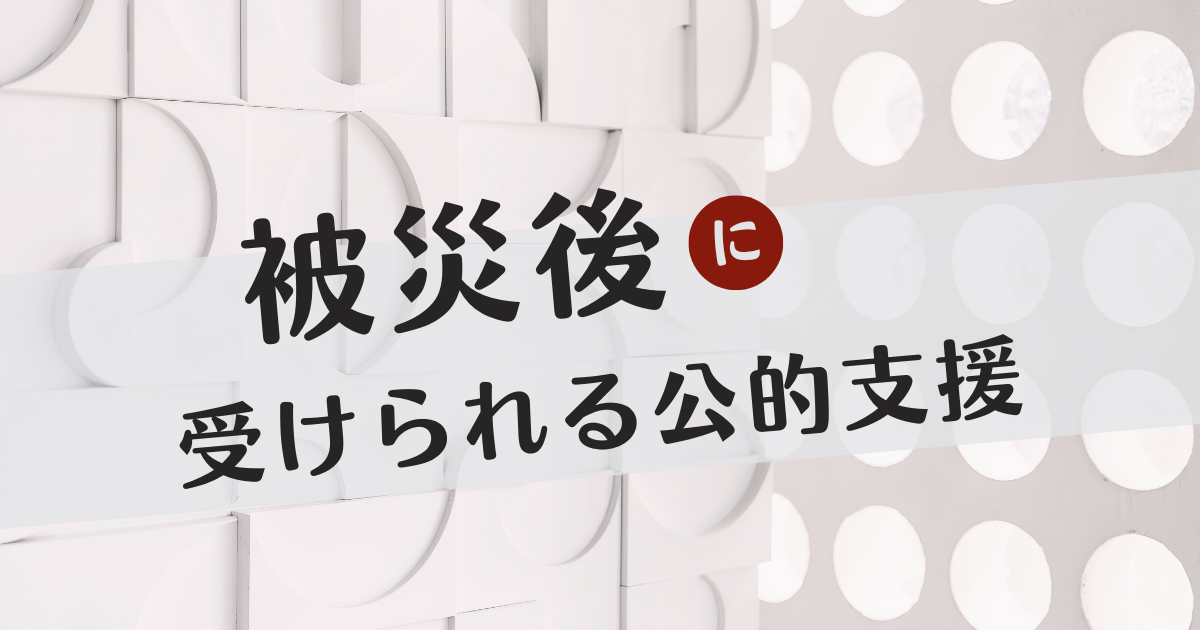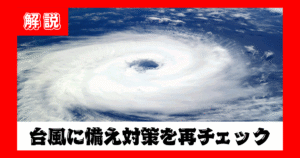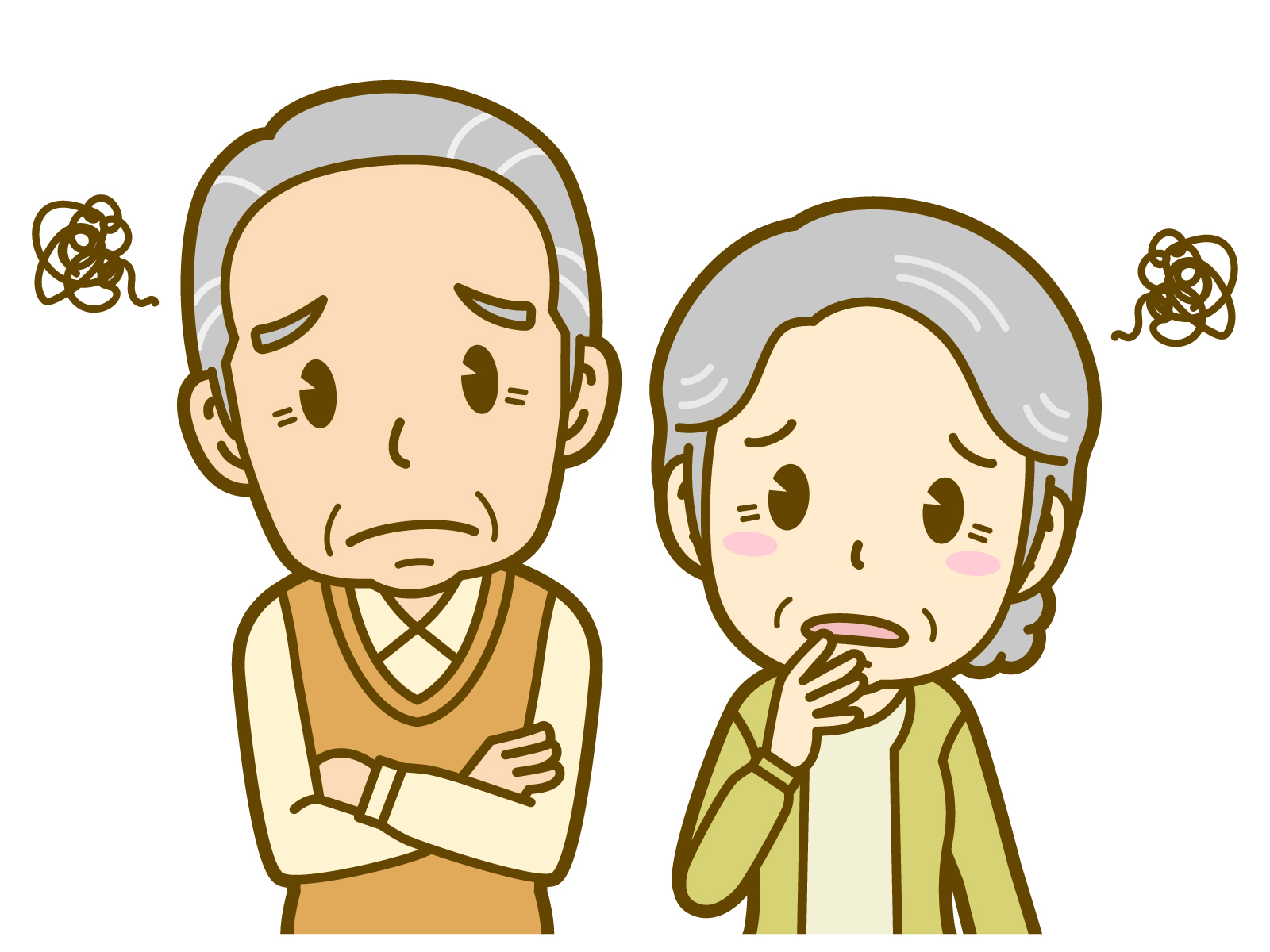 悩める人
悩める人被災後に受けられる公的支援を知りたい…



災害後にトラブルが起きたら…



こんな疑問・悩みを解決します!
- 被災後に利用できる公的支援・もらえるお金
- 火災保険・火災共済の具体的な内容と必要性
- 災害後にトラブルが起きた際の対処・解決法
受けられる公的支援
もしも、被災して一命を取り留めても、安堵する間もなく損壊した住まいを整え、日常生活を立て直すという作業が待ち構えています。
そこには大変な労力と時間を要し、加えて多くの費用を捻出しなければなりません。



自然災害で多くを失った時、個々の力だけで暮らしを立て直すことは困難であり、そんな時には私たちを支える公的支援も存在します。但し、これらの利用に当たっては、自ら申請するのが基本となります。
当記事では、被災後に受けられる主な支援について、申請窓口・手続き方法・必要書類まで確認していきます。
罹災証明書を取得する
被災後の生活再建に当たり、先ずすべきは「罹災証明書」の交付手続きです。
市区町村が住宅の壊れ具合を個々に判定、被害の程度を証明する書類で、持ち家・賃貸を問わず「公的支援を受ける際には先ず必要」になります。
本人又は同居の家族が、被災後「原則1か月以内」に居宅のある市区町村に申請します。
その後、市区町村の職員などが住家を訪ねて確認する「住家の被害認定」が行われます。
罹災証明書に記載される被害の程度は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」と6区分で、区分により受けられる公的支援の内容が変わります。
判定結果に疑問があれば、それを知った日から「3か月以内は最大2回まで」再調査を受けられます。
広域災害になると多くの世帯が被災するため、罹災証明書の申請・交付手続きが速やかに進まないことがあります。
また保険金や共済金の請求では、調査員が被害宅に出向いて損害調査が行われますが、訪問に時間を要することもあります。
被災後、損害状況の確認を受けずに片付けてしまうと、どのような損害を受けたのか、証明できなくなってしまいます。



いずれ調査員の訪問を受ける場合でも、先ずは「被害状況の写真」を撮っておくことをお勧めします。尚、写真を撮る際は安全を確かめた上で行いましょう。
屋根瓦や窓ガラスの破損など、一部損壊に該当する小さな被害だけの場合は、市区町村職員の現地調査を受けることなく、写真判定のみで罹災証明書の交付を受けられます。
- 罹災証明書を申請してから受け取るまでの流れ -
- 災害発生
- 被害の記録をして申請 (被災者)
- 被害家屋の調査・判定 (自治体)
- 罹災判定内容の説明 (自治体)
- 不服あり -
- 再調査の申請 (被災者)
- 再調査の実施及び結果の説明 (自治体)
- 必要があれば罹災台帳の修正 (自治体)
- 罹災証明書発行・受け取り (被災者)
- 不服なし -
- 罹災台帳への記入 (自治体)
- 罹災証明書発行・受け取り (被災者)
住家に大きな被害を受けたとき



台風や大地震で被災したら「支援金」がもらえます。災害で住宅が被災した時にもらえる支援金について知っておきましょう。
被災者生活再建支援制度は、阪神・淡路大震災を切っ掛けに設けられた制度で、市区町村で10世帯以上、又は都道府県で100世帯以上の住宅が全壊するなどの、大規模な自然災害の被災世帯に、国と全都道府県の基金から支援金を支給します。
支給要件は、
①住宅が全壊した
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が及び、やむを得ず住宅を解体した
③災害の危険な状態が継続し、住宅に住めない状態が長期間続いている
④住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ住むことができない
⑤中規模半壊し、補修をしなければ住むことが難しい
です。
支援金は、住宅の被害程度によって支給される「基礎支援金」と、被害を受けた住宅の再建方法(建築・購入・補修・賃借)に応じて支給される「加算支援金」の二段構えになっていて、例えば、被害程度が被災世帯のうち①②③に当たる場合は「基礎支援金」が100万円、その後、住宅を建設・購入で200万円、補修で100万円、賃借して50万円の「加算支援金」がもらえます。
支援金は住まいに深刻な被害を受けた世帯に向けた「生活再建のスタート資金」と位置付けられるもので、持ち家世帯だけでなく賃貸入居世帯も対象です。
使い道は自由で、災害弔慰金や火災保険金など、他の給付とも関係なく受け取れます。
申請期限は、基礎支援金が災害発生日から13か月、加算支援金が37か月以内。



被災時に「実際に居住していた世帯」が対象ですから、空き家や別荘、賃貸オーナーが所有する物件などは支給の対象外です。
被災後に住宅の修理が必要なとき
災害救助法は、被災者の命を守り、保護を図るために適用される法律です。
人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある市区町村に適用され、発災直後から衣食住に関わる物資の給付を始めとした救助が行われます。
法が適用された地域には、様々な被災者支援策が官民を挙げて講じられることになります。
- 避難所、応急仮設住宅の設置
- 食品、飲料水の給与
- 被服、寝具等の給与
- 医療、助産
- 被災者の救出
- 住宅の応急修理
- 学用品の給与
- 埋葬
- 死体の捜索及び処理
- 障害物の除去
救助メニューの一つ「住宅の応急修理」は、一定の被災世帯が住宅修繕を受けられるものです。
対象になる世帯は、住宅が半壊・中規模半壊又は大規模半壊となった世帯、或いは準半壊の世帯で、大規模半壊以外は資力等を勘案して給付が判断されます。
居室・キッチン・トイレなど、日常生活に必要な最小限度の被害部分が対象で、市区町村が業者に修繕を委託して実施されます(現物給付)。
被害区分が半壊以上で、応急修理に1か月超かかると見込まれる場合、最長6か月にわたり「仮設住宅」に入居することもできます。
尚、被災住宅の被害拡大防止のため、準半壊以上の世帯は1世帯当たり5万円以内の緊急修理等を受けられます。



被災後の生活で必要な救助を受けられます。問い合わせ先は「都道府県」又は「市区町村」です。
災害で家族が死亡・重い障害を負ったとき
同生計の人が災害で亡くなった時は、残された家族に「災害弔慰金」が支給されます。
災害との因果関係が認められる災害関連死や、災害で行方不明になり、3か月を超えて生死不明となった場合も対象になることがあります(家族の申し立てが必要)。
- 生計維持者 … 500万円
- それ以外 … 250万円
災害が原因で障害を負った場合は、「災害障害見舞金」が支給されます。
両目の失明や要常時介護など重度の障害を負った場合が対象です。
- 生計維持者 … 250万円
- それ以外 … 125万円



いずれの制度も、1市区町村のうち住居が「5世帯以上」滅失したなど被害の大きい自然災害が対象です。問い合わせ先は「市区町村」です。
自治体による独自の支援制度
被災者生活再建支援制度は、1市区町村に10世帯以上が全壊となった災害などが対象なので、それに満たない災害では、住宅が全壊しても支援金の給付を受けられません。



こうした時、都道府県や市区町村による「独自制度の給付」を受けられることがあります。
例えば、法適用とならず支援金が受けられない場合に、支援金と同等の給付を行うところや、支援金とは別に独自の支援金を支給し、両方の給付を受け取れるところもあります。
給付を受けられる基準はそれぞれが定めており、支援金の対象にならない半壊で給付されるものもあります。



都道府県が独自給付制度を設けていますが、その内容はそれぞれ異なります。問い合わせ先は「市区町村」です。
義援金を受け取るには
日本赤十字社や中央共同募金会、NHKが、災害ごとに受け付けている義援金は、決められた配分基準で各自治体に配られ、それが被害程度に応じて被災者に配られます。
第1次配分、第2次配分といったように、何度かに分けて配られることもあります。
大切なお金を公平に配分するため、災害の規模などにより、被災者に実際にお金が渡るまで時間が掛かることもありますが、配られた義援金の使い道は自由で、被災者にはとても助かるお金です。



受け取りは罹災証明書を携え市区町村窓口へ。郵送でも受け付ける場合があります。
被災後に住宅ローンが返せなくなったら
住宅ローンの返済に困った時は、当面の返済猶予や、返済方法の変更が可能です。
罹災証明書を携え、銀行に被災した旨の申し出を。
融資銀行の他、旧住宅金融公庫で融資を受けた人は住宅金融支援機構にも相談できます。



ただ、支払い猶予を受けても住宅ローンはなくなるわけではありません。返済不能が確実なら「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」によるローン減免の相談を受けることも検討しましょう。
これは住宅ローンや事業用ローンを利用している個人を対象に、自己破産をせず、災害弔慰金や被災者生活再建支援金、及び500万円程度の自己資金を手元に残し、ローン減免について相談できるものです。
個人信用情報(ブラックリスト)に登録されたり、保証人に請求されることもありません。
手続き支援は弁護士などの専門家が行いますが、弁護士費用は公費で賄われ無料です。



弁護士会の被災者向け法律相談で問い合わせてみても良いでしょう。手続きはメインバンクに直接出向いて申し出ます。
借家が倒壊して住めなくなったら
入居している賃貸住宅が全壊するなどして居住不能になったら、賃貸借契約は終了します。
住まいからは出ていかなくてはなりませんが、賃料の支払い義務はなくなり、敷金も全額が戻ります。
また、住まいが全壊又は大規模半壊、中規模半壊となった入居者は、被災者生活再建支援金の支給を受けられるので、漏れなく手続きをしましょう。
罹災証明書は入居者、オーナーいずれも申請可能です。
住宅が滅失していなければ、損壊部分があっても賃貸借契約は継続します。
その後も住み続けることができ、損壊部分の修繕義務があるのはオーナーです。
修繕してもらえない場合、入居者はオーナーに家賃の減額を求めることができます。



但し、修繕する上で一時退去が必要な場合、入居者はそれを拒めません。被災後に賃貸借契約でトラブルになったら、弁護士などに相談を。
被災して住む家が確保できないとき
住宅全壊など住家を失ったり、半壊以上で応急修理に1か月超かかると見込まれ、自ら住まいを確保するのが難しい時は、「応急仮設住宅」の提供を受けられます。
プレハブ住宅の他、トレーラーやコンテナハウスなどが提供されることもあります。
賃貸住宅などを自治体が借り上げて提供する「借り上げ仮設住宅」も最近は増えています。
いずれも無料で住むことができますが、あくまでも仮住まい。
住めるのは原則2年間、応急修理完了までの入居は6か月です(延長されることもあります)。



仮住まいの2年間のうちに住宅確保が難しい場合、それ以降は自治体が建てる家賃の安い「災害公営住宅」に住むこともできます。問い合わせ先は「市区町村」です。
再建や修繕にお金が足りないとき
罹災証明書を交付された人が利用できるのが、住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」です。
住宅を建設・購入・補修をする場合が対象で、準半壊、一部損壊は補修にのみ利用できます。
低利で全期間固定ですが、要件(物件、融資額、返済額、返済期間、年齢など)を満たす必要があります。
申込みは被災日から2年間。
自治体から利子補給などの支援が行われることもあります。
60歳以上の人を対象に住宅再建・修繕を後押しする「災害復興住宅融資・高齢者返済特例(災害リバースモーゲージ)」は、新たな家や今ある土地を担保に融資を受け、毎月利息のみを支払うものです。
夫婦世帯では両者が死亡するまで住むことができ、死亡後に相続人が土地と建物を売却して元本を一括返済します。
この時、債務は残りません。



申込前に住宅金融支援機構によるカウンセリング相談が必要です。先ずは「お客様コールセンター」にお問い合わせ下さい。
その他の支援策
一定の災害で事業所が休業となり、一時的な離職や休業を余儀なくされた会社員には、雇用保険から失業等給付を受けられる特例措置が実施されます。
災害により住まいや資産、仕事を失い、生活困窮に陥った時には「生活保護」の申請を。
住所地の市区町村が窓口ですが、東日本大震災では、広域避難者であっても利用できる措置が取られています。
困った時の公的貸付もあります。
「災害援護資金」は、災害で負傷したり住居が半壊以上になるなどの損害を受けた人が利用できる貸付で、世帯員数に応じた所得制限があります。
「生活福祉資金」は、金融機関から借り入れが難しい低所得世帯や高齢者世帯などが利用できる貸付です。
緊急小口資金は無利子で10万円以内、福祉費は150万円までが目安です。
火災保険(共済)の内容と必要性
台風や地震などの自然災害で住宅や家財に損害を受けた際、火災保険や火災共済でカバーできる場合があります。
補償の範囲や補償額は個々により異なりますので、ご加入の保険や共済の内容をチェックしておきましょう。
台風などによる風水害の場合
自然災害による住宅や家財の損害は、「火災保険(損保会社)」や「火災共済(生協など)」でカバーできる可能性があります。
「火災」という名称でも、火災だけではなく、台風や集中豪雨が原因で被った損害も対象になることがあります。
一口に台風と言っても、暴風など風による損害と、浸水など水による損害がありますが、火災共済ではこれらをまとめて「風水害」として保障。
一方で火災保険は、風が原因の損害を「風災」、水が原因の損害を「水災」として別々に補償します。
台風などの損害をカバーできるかは、火災保険や火災共済の契約で異なり、対象外とするものもあります。



対象になるとしても、どのような場合に、どの程度受け取れるかは、個々の商品や契約で異なるため、事前に確認しておくことも大切です。
地震による損害(地震・津波・噴火)の場合
地震による損害もカバーできる可能性があります。



ただ地震はいつ・どこで・どの規模で起きるかが分からないため、受け取れる金額はどの商品でも概ね小さめになります。
生協などが扱う火災共済の地震保障は、いずれもそれぞれの団体が設ける独自保障で、カバーされる内容や支払い条件はそれぞれ異なります。
損保会社の火災保険は地震を補償対象外としており、「地震保険」をセットすると補償を受けられます。
地震保険は通称「地震保険法」に基づく官民一体の制度で、損保会社と共に政府も保険金の支払い責任を負う特殊な保険です。
よって、どの損保会社で加入しても、条件が同じであれば、補償内容や保険料は一律です。



地震をカバーする商品は他に、地震保険金額が最大で火災保険と同額になる火災保険の特約や、単独で地震補償が得られる少額短期保険などがあります。
分譲マンションの場合
自然災害で分譲マンションやマイカーが損害を受けた場合、保険や共済でどのようにカバーできるのでしょうか?
一戸建てでは、所有者が住宅や家財に保険や共済を掛けます。
一方、分譲マンションでは「専有部分(室内)」は個々の所有者が、「共用部分(それ以外)」は管理組合がそれぞれ火災保険などを掛けています。



管理規約によりますが、国交省の標準管理規約では、専有部分とは「壁から内側」の部分を言います。よって損害を受けた部分に応じて、それぞれの契約先に請求することになります。
所有者が家財の保険や共済に加入していれば、家財の損害もカバーできます。
躯体やエレベーター、エントランスなどの共用部分に損害を受けた時は、マンション管理組合が加入する火災保険で補償を受けられます。
地震保険がセットされていれば、地震被害にも対応できます。
マンションの共用部分も、火災保険金額の50%を上限に地震保険に加入できます。
マイカーが損害を受けたら
自然災害でマイカーに損害を受けた時は、自動車保険に任意で付帯できる「車両保険」で補償を受けられます。
自動車事故の他、浸水による車両水没、風災による破損など、一定の自然災害による損害もカバーできます。
但し、補償内容は契約により異なるので確認が必要です。
車両保険は地震などが原因の損害は補償の対象外となりますが、「車両全損時一時金特約(名称は保険会社により異なる)」を付帯させて補償を受けることは可能です。
地震などが原因でマイカーが廃車となった時が対象で、車の時価を上限に、最大50万円を受け取れます。
契約照会制度
被災時に保険証券や共済証書がなくなり、どこで、どのような契約をしたのか不明となった場合でも、保険金などの請求はできます。
自然災害の影響で契約の手掛かりを失った時に利用できる窓口があるので、そちらに問い合わせて契約を突き止めましょう。
生命保険・損害保険、共済のそれぞれについて、業界ごとの窓口が設けられています。
災害救助法が適用された地域で被災された個人が対象で、原則として被災した本人及び家族が利用できます。
但し、契約先や契約内容が分かるまで、しばらく時間が掛かることもあります。
- 各種生命保険 … 一般社団法人 生命保険協会
- 各種損害保険 … 一般社団法人 日本損害保険協会
- 各種共済 … 一般社団法人 日本共済協会



保険や共済は、本当に困った時に利用する非常用グッズですから、保険の証券・共済の証書のコピーを非常用袋に入れておけば、請求もスムーズです。
受け取った保険金・共済金と税金について
自然災害が原因で受け取った保険金などに税金は掛かりません。
また、受けた損失の額によっては、以下2つの方法で所得税の全部又は一部の軽減を受けられます。
いずれか有利な方法を選び、確定申告で手続きをします。
- 雑損控除
所得から住宅や家財、マイカーなど生活必需品の損失額を差し引ける制度です。
その年で引き切れないほど大きな損失がある時は、翌年以降3年間にわたり損失額を繰り越せます。
受け取った保険金などは、損失額から差し引き計算します。
地方税軽減のための手続きは不要です。
- 災害減免法
住宅や家財に損害を受け、受け取った保険金などを差し引いてもなお、時価の2分の1以上の損害が生じる年収1,000万円以下の人は、所得税の免除又は軽減を受けられます。
単年度のみの減免で、損失額を翌年以降繰り越すことはできません。
地方税の軽減は別途、市区町村に問い合わせましょう。
災害後のトラブル対処法
被災後は、今までの暮らしが一変することもしばしばです。
これまで当たり前にあったものがなくなり、様々な問題が発生することもあります。
我が家が被害を受けるだけでなく、更に他人に損害を与えてしまう深刻な事態も。



それらの多くは法的トラブルですから、専門家の力を借りて解決に臨むことも必要になります。
近年急増しているのが「火災保険や共済を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など「保険金や共済金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談です。
事業者による勧誘・契約は災害後や台風シーズンに増加する傾向がありますので、注意が必要です。
安易な契約はせず、悩んだら相談窓口に連絡しましょう。
被災後のトラブル
被災後に起こりうるトラブルは様々で、どれも暮らしに関わる深刻なものばかり。
住まいを失い賃貸契約や不動産の問題が、家族の死亡で相続問題が、隣家に損害を与えて近隣トラブル…。



これらは全て法律が絡むトラブルです。個人で解決が難しいこれらの問題は、ためらわず弁護士など専門家へ相談を。
被災後は、被災地の弁護士会の他、日弁連の下に全国の弁護士が協力して無料相談に取り組んでいます。
近年は、裁判をせず話し合いで解決する「震災ADR(裁判外紛争解決手続)」が設置されることもあります。
また各地にある「法テラス」は、市民の法的トラブルを解決する総合案内窓口です。
被災者向け無料相談の他、WEBによる情報提供が行われており、誰でも利用できます。



税理士や不動産鑑定士などの専門家が無料相談会を催すこともあります。困った時は遠慮せずに専門家に相談をして、解決に臨みましょう。
クーリング・オフ
「保険を使って自己負担ゼロで住宅修理ができる」
「保険申請もサポートする」



被災後、こうした訪問勧誘が来たら警戒を。トラブル激増!安易な契約は禁物です。
- ずさんな修理工事をされた…
- 災害で被害を受けたと保険会社に言うよう嘘を強要された…
- 不審に思い解約を申し出ると、支払われる保険金の50%を違約金として請求された…
こんなトラブルが「消費生活センター」などに多く寄せられています。
被害は被災地に限らず、全国各地で発生しており、安易な契約は禁物です。
ケースによりますが、うっかり契約をしても「クーリング・オフ」を利用して、一方的に契約を解除できます。
契約時に交付される法定書類の受け取りから「8日以内」であれば、工事開始後であっても解除できます。



法定書類を交付されていない場合は、期限なく契約解除することができます。悩んだら、相談窓口に連絡しましょう。
施設賠償責任保険



災害で近隣住民に損害を与えてしまった…



過失が認められれば「損害賠償責任」が生じることも。
自宅が損壊するだけでなく、隣家に損害を与えることも考えられます。
自然災害が切っ掛けで起きたことは、通常は不可抗力として民法上の損害賠償責任は問われませんが、住宅等の維持・管理等に重大な落ち度があるなど、自分の側に過失が認められれば、民法上の損害賠償責任が問われます。
この時、「個人賠償責任保険」に加入していれば、被害者への損害賠償金をカバーすることが可能です。
但し、個人賠償責任保険には、地震免責事項が定められているため、地震・噴火・津波が原因の損害に対しての賠償には保険金が支払われません。
トラブルが生じないように、平時から住宅のメンテナンスを欠かさないことがとても大切です。
施設賠償責任保険
所有する家が空き家になると、防犯や景観面で周囲に悪影響を及ぼすことがあります。
空き家は自然災害で損害を受けても、被災者生活再建支援制度などの公的支援は受けられません。
さらに、空き家の火災保険は住宅用ではなく、事務所や店舗用になるなど、一定の条件があったり、契約自体ができなかったりする場合もあります。
また、地震保険は契約することができません。
やむを得ず空き家の所有を続ける場合には、何らかの対策を考えておく必要があります。
自然災害で空き家が損壊、近隣の住宅に損害を及ぼした時は、所有者が加入する個人賠償責任保険では対応できません。
空き家に「施設賠償責任保険」の契約をしていれば、隣家への損害賠償金をカバーできますが、取扱いは損保会社により異なります。
尚、地震・噴火・津波が原因の損害賠償は対象外となります。
まとめ
深刻な風水害が各地で相次いでいます。
政府の地震発生予測で確率が低いとされる地域でも、想定を超える大地震が起きています。
自然災害による被災と、誰もが無縁でいられない時代となりました。
近年では、災害救助法適用市区町村数が、東日本大震災時を上回る年も珍しくなくなっています。
自然災害で多くの人の命や財産が危険にさらされ、保護を必要とする状況に追いやられているのです。
災害は、ある日突然やってきます。
幸いにして命を守ることができても、生活の基盤である住まいを失ったり、仕事がなくなったり、健康を損なったりすることもあります。
私たちを支えるいくつもの柱を、自然災害は一瞬にして奪い去ってしまいます。
しかし、私たちの暮らしはその後も続きます。
失った住まいを再建し、修繕し、或いは引っ越し、家財を再び買い揃え…。



その時、必要になるのは言うまでもなく「お金」。災害を逃げ延び、生活再建のフェーズでやってくるのが、お金の問題なのです。
たとえ被災したとしても、誰もが「自分らしい暮らし」を望んでいる筈です。
困った時に不本意な選択を余儀なくされ、辛い暮らしを強いられることなどないよう、正しい知識を基に準備を進めておくことが大切です。
被災後の生活再建を被災者が自らの力だけで行うのは困難ですから、被災者を支える公的支援制度もあります。
公的支援制度には支援金や弔慰金、税の減免など様々なものがあり、窓口や手続き時期はそれぞれ異なります。
必要な支援を受けるには、そのそれぞれについて、被災者自ら申請をしなくてはならないため、その際は正しい情報が欠かせません。



但し、公的支援は、それだけで生活再建が成し遂げられるほど十分な内容ではないのです。我が国では、被災後の生活再建は「自助・共助」が基本とされ、公助(公的支援)は「側面的支援」に止まるとされます。
例えば、住宅が全壊した世帯が受け取れる支援金は、最大でも300万円です。
これだけで生活再建や住宅再建を図るのは多くの世帯には困難でしょう。



この時、火災保険や地震保険、火災共済などで備えていれば、被災後に保険金や共済金を受け取れ、生活再建は大いに支えられます。適切に加入し、速やかに請求手続きをしましょう。
公的支援が限られる中では、準備の有無が被災後の生活再建を左右することにもなるのです。
保険や共済によってカバーされる内容は、商品や契約により異なります。
持ち家で貯蓄が少ない、ローン残高が多い世帯は、被災後の家計リスクが大きくなります。
我が家の居住地のリスクに見合う、適切な契約内容に整えることにも取り組みましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。