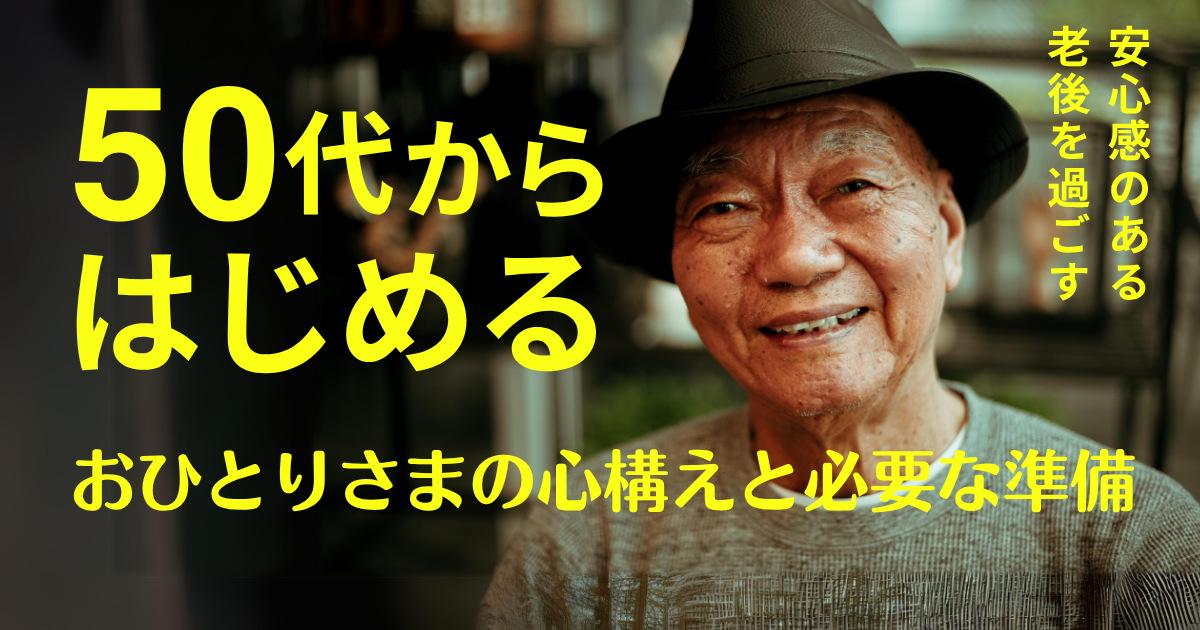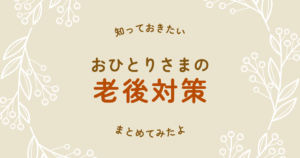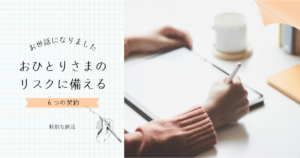悩める人
悩める人将来、認知症になったり寝たきりになってしまったら…
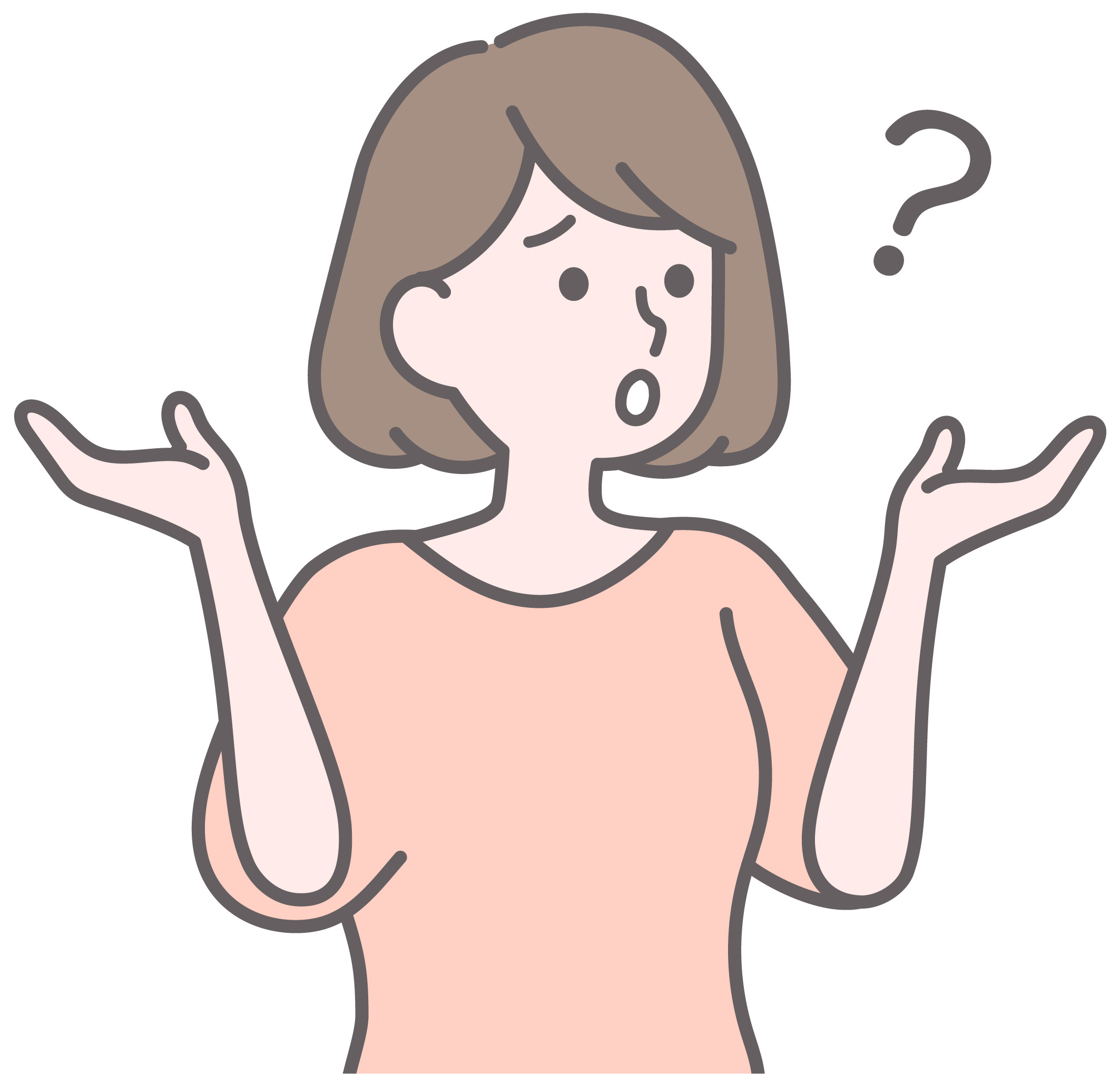
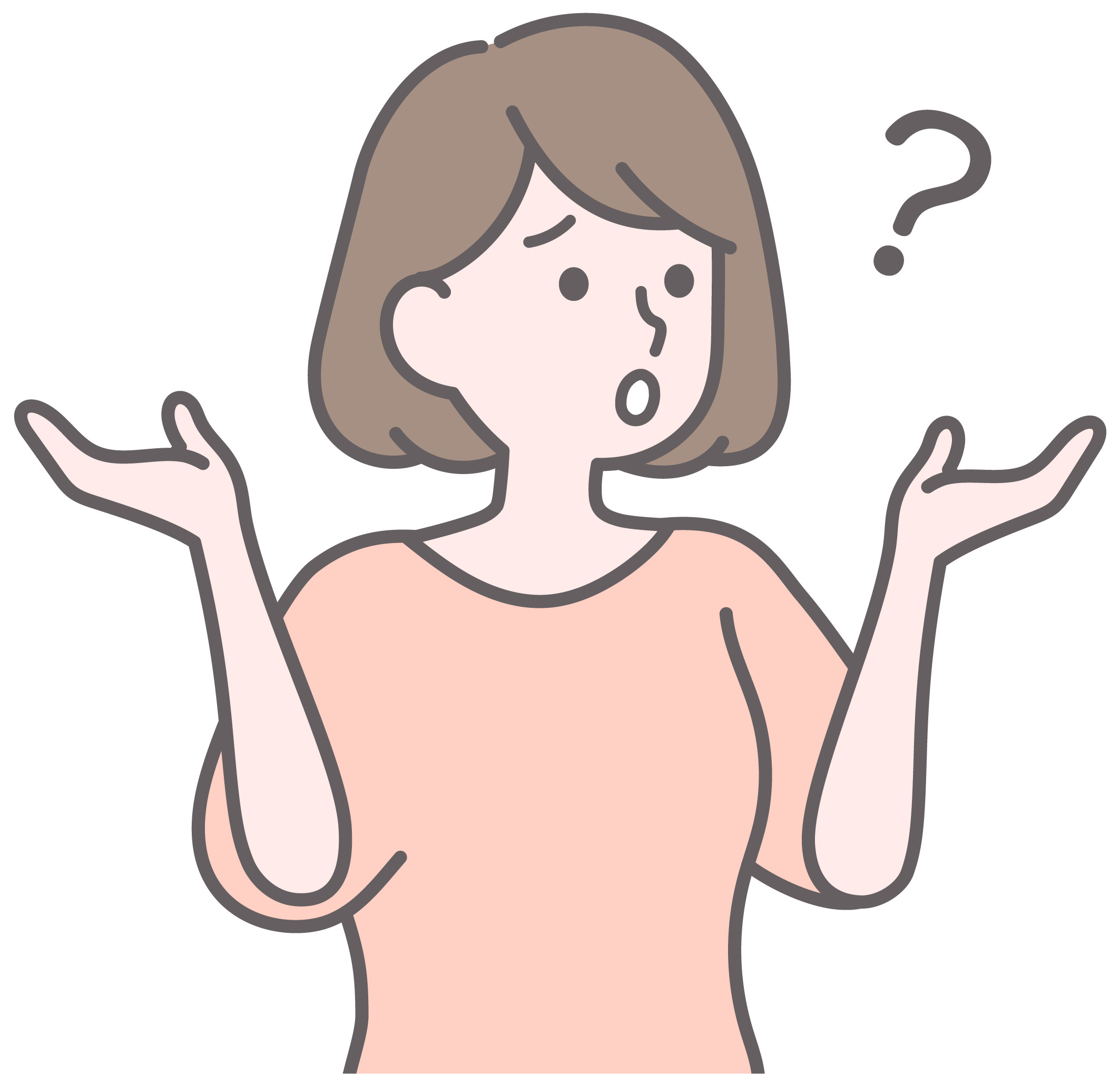
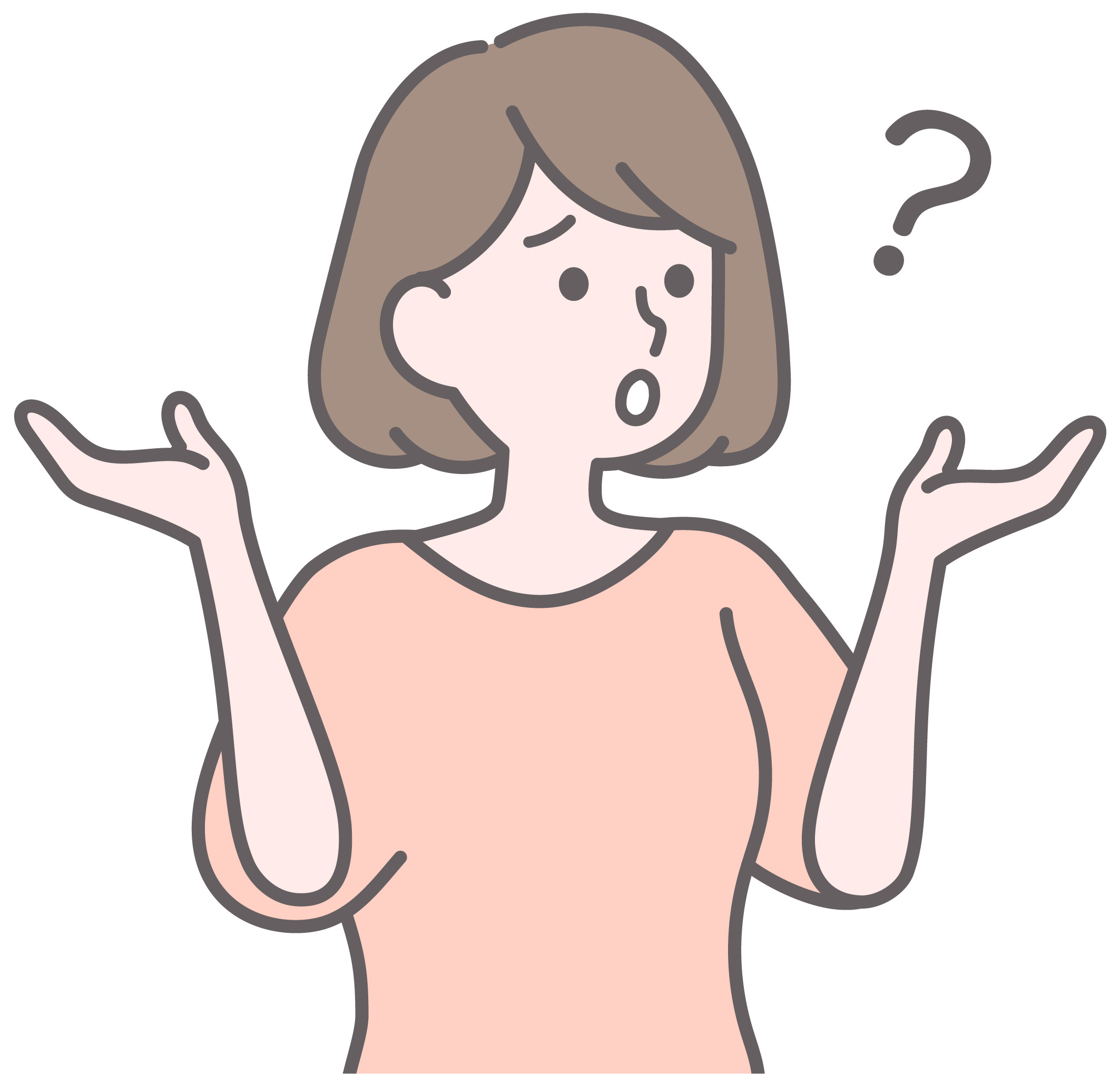
自分が死んだ後の整理はどうなる?



こんな疑問・悩みを解決します!
- おひとりさまが考えておくべきこと
- 将来のことが依頼できる契約について
- 生前と死後に関する契約の注意点
おひとりさまの心構えと必要な準備
頼れる身内がいない「おひとりさま」にとって、今後困った時に頼れる先を決めておいたり、自分の死後のことを誰かに行なってもらったりすることについて、早めに考えておくことが必要です。
例えば、あなたが亡くなった時、誰が訃報を連絡してくれるのでしょうか。
葬儀やお墓への埋蔵、老人ホームに入っていた場合の支払い、あなたの遺品の整理…、やるべきことはたくさんあります。
そして、最後に残る財産は、どうしたいでしょうか。
相続人が誰もおらず、あなたを支援してくれた人(縁故者)がいない場合には、最終的には「国庫行き」です。
死亡後のことだけではなく、もしかしたら、今後認知症になってしまうこともあり得ます。
その場合、あなたの財産は誰がどうやって管理するのでしょう。
通院・入院などの際、金融機関から預貯金を引き出して支払ったり、介護施設や介護サービスの契約手続きなどを行なうことが難しくなったりと、命に関わる不安が出てくるかもしれません。
認知症にならずに済んだとしても、体調が思わしくなく、食事や買い物といった日常生活に困ることがあるかもしれません。
将来のことが依頼できる契約



この先困るかもしれないことや、確実に行なってもらわなければならないものに対して、今から依頼する人と契約を結んでおくことができます。
認知症になってしまった時のために依頼しておく「任意後見契約」や、自分の死後、葬儀や納骨、遺品整理などを行なってもらうために依頼しておく「死後事務委任契約」、一人で過ごしている自分のことを見守ってもらう「見守り契約」や、財産管理を行なってもらう「財産管理契約」、見守りと財産管理をまとめて行なってもらう「任意代理契約」、自分の財産の行き先を決める「遺言書」など、様々な方法があります。
生前と死後の手続きを誰に頼んだら良い?
「おひとりさま」と言っても、全く身寄りがない人もいれば、遠い親戚だけど身寄りがある人もいます。
身寄りがある人も、疎遠だから頼れる存在ではないというケースと、単に頼りたくないと考えるケース、迷惑を掛けたくないと考えるケースに分かれます。
全く身寄りのないケースは、誰かに代理人になってもらったり支援してもらったりしなければなりませんが、親族がいる場合は、その人に頼ることができるかどうかによって、頼む相手が変わります。
何をどこまで依頼するのかによって異なりますが、最も大切なのは相手との相性。
専門家に依頼するなら、専門家としての実力や実績ももちろん大切ですが、何よりも重視したいのは人柄です。
生前から死後のことまで同じ人に依頼することが多く、長期にわたって支援してもらうことになるので、相性は重要です。
そして、年齢もできれば20歳くらい離れた人に頼むのが安心です。



先ずは、生前や死後の依頼を引き受けている専門家に相談してみたり、セミナーに行ってみたりして、どのような人なのか知ることから始めてみましょう。
判断力や理解力が低下してきたら?
認知症になったら…。
高齢化が進む現在、自分だけは大丈夫などとは思えない問題でしょう。
もし判断能力が低下して、自分の身の回りのことができなくなれば、日常生活を送ることが難しくなるでしょう。
預貯金を引き出したり施設への入所契約ができなくなったりしますし、日々の食事に困るかもしれません。
加えて、押し売りや詐欺に遭う可能性も高くなり、大切な財産を失ってしまうことになりかねません。
身寄りがあれば、その人がある程度は身の回りのことを行なってくれたり、あなたの代理人(後見人など)になってくれたりするでしょう。
でも、頼れる身寄りがない場合には、その時に備えて誰かに依頼しておかなければなりません。
そんな時に活用したいのが「任意後見契約」です。
任意後見契約
任意後見契約とは、予め信頼できる相手と契約をしておき、認知症になってしまった時にその相手に後見人になってもらい、法律行為の代理を行なってもらうものです。



主に「財産管理」と「身上監護」を行なってもらいます。成年後見制度という制度の一つである「任意後見制度」がこれに当たり、更にもう一つ、「法定後見制度」という制度があります。
これは、判断能力が不十分になった時に配偶者や四親等内の親族が家庭裁判所に申し立てをし、後見人などを選んでもらう制度です。
判断能力の程度に応じて、補助人、保佐人、後見人が選ばれ、それぞれ後見人などが行なえる範囲も異なります。
一方、任意後見制度は申し立てをしてくれる親族がいなくても、判断能力が低下した時に契約した相手に家庭裁判所に申し立てをしてもらえるようにしておくもので、予め決めておいたことを後見人に行なってもらいます。
どんな契約でも良いわけではないので、この任意後見契約は必ず「公正証書」で作成します。
体が不自由になったり寝たきりになったときは?
将来、認知症になるかどうかは分かりませんが、認知症になってしまった時に備えるなら、上記にあるような「任意後見契約」を結んでおくことができます。
しかし、任意後見契約は、「判断能力が低下」した時に利用できるものであって、判断能力がある場合には、寝たきりになったとしても、足が不自由で預貯金を引き出しに行けなかったとしても、代理人として行なってもらうことはできません。



そのような時のために契約しておけるのが、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」です。任意代理契約は、見守りと財産管理を行なってもらうものです。
認知症になってしまったら「任意後見契約」に移行することになりますが、認知症にならなかったら、死亡するまでこの契約は有効です。
今後の体力低下に備えて契約するのも目的の一つですが、任意後見契約を結んでいた場合、自分の判断能力が衰えていることを、依頼した相手に気付いてもらう必要があります。
認知症になってしまった時のためにと「任意後見契約」で依頼したのに、判断能力が低下しているまま過ごさなければならないのでは、契約した意味がありません。



そのような時のために、任意代理契約によって依頼相手に関わってもらうこともできます。もし、見守り契約だけで良いのなら、「見守り契約」として契約することもできます。
見守り契約は、週に1回程度の電話連絡や、月に1回程度の面談を通して、定期的に今の状態がどうなのか気にしてもらうものです。
これらの契約は、行なってもらう内容を自由に決めることができ、報酬も両者で取り決めることができます。
旅立ち後の後片づけは?
「おひとりさま」が最も気にするのが、自分の死亡した後のことについて。
葬儀や納骨、家財の処分など、頼れる身寄りがないからこそ心配するのです。
これらを依頼するには、「死後事務委任契約」を結んでおかなければなりません。
死後事務委任契約の場合、あなたの死後、すぐに支払いが発生するため、契約書で預託金の額を決め、依頼する相手に預けておきます。
また、報酬額についても両者で決めることができ、これらは契約書に記載されます。
この報酬額と契約を実行した時に掛かる実費(葬儀代・遺品整理代など)が、預託金だけで足りない場合、あなたが亡くなったあと財産から支払われます。
尚、死後事務委任契約と併せて「公正証書遺言」も作成します。



先に紹介した「任意代理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」などの契約は、法律行為を行なってもらう契約です。ですから、契約書の内容は、行なってもらう「法律行為」のことが書かれています。
例えば、死後事務委任契約の場合は、次のような内容です(一部抜粋)。
- 通夜・葬儀・告別式・火葬・納骨・埋蔵に関する事務
- 老人ホーム入居一時金の受領に関する事務
- 家財道具や生活用品の処分に関する事務
- 行政官庁等への諸届事務
- 以上の各事務に関する費用の支払い
他の契約も同じように、かなり大まかな内容になっています。
そして、この契約書の中に依頼者への報酬額や預託金も記載されます。
尚、契約内容の変更や、契約の解除もできます。
葬儀を行なってもらうにしても、誰に声を掛けてほしいのか、どのような葬儀にしてほしいのかなど、色々な要望があるのではないでしょうか。
自分が望んだことを行なってほしいのなら、それが分かるように要望を伝えておかなければなりません。
例えば、訃報の連絡先や葬儀の内容、菩提寺があれば連絡先、戒名について、納骨先や供養に関すること、遺品の処分や形見分けなどです。
「誰に」「どのように」など具体的に伝えましょう。
また、賃貸マンションに住んでいるのであれば、不動産業者や家主さんの連絡先も伝えておかなければなりません。
これらの法律行為を行なうに当たって、こうしてもらいたいなどの要望があるのなら、別途、書面などに残しておくことが必要です。



但し、どこまで行なうのかは契約依頼の相手次第ですので、何でもお願いできるわけではないことは理解しておきましょう。
生前と死後に関する契約の注意点
掛かる費用
見守りや財産管理を行なってもらう「任意代理契約」や、認知症になった時に身上監護や財産管理を行なってもらう「任意後見契約」、死亡した時に葬儀や遺品整理などを行なってもらう「死後事務委任契約」などは、公証役場で作成します。



任意後見契約以外は公証役場で作成しなくても構わないのですが、無用なトラブルを避けるため、殆どの場合は公証役場で作成されます。ですので、契約書作成には公証役場への手数料が必要になります。
また、契約書の原案作成に専門家が関わる場合は、その専門家への報酬も必要です。
そして、実際に契約が開始された時には、事前に取り決めた報酬を支払っていくことになります。
尚、遺言書以外の契約は、一つの契約書にまとめて作成できるため、自分が必要だと思う契約を一緒に作成すれば、作成費用も1回分で済みます。
依頼できない
任意代理契約にしても任意後見契約にしても、生きている時に支援してもらう契約を実行してもらうためには、報酬が掛かります。



この費用を負担するのが難しいため「契約できない」人もいます。生きている間、毎月報酬が発生するからです。
特に、判断能力が低下した時のための任意後見契約の場合、依頼する人への報酬の他に、任意後見監督人への報酬が必要になります。
任意後見契約をスタートさせるには、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選んでもらわなければならないからです。
契約している相手がたとえ弁護士であっても、必ず任意後見監督人は選ばれます。
任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所があなたの財産状況などから決めますが、任意後見契約をスタートしてからあなたが亡くなるまでの間、ずっと二人分の費用が発生するため、かなり負担が大きくなります。
そうなると、誰かに頼みたくても頼めないということも起こるのです。
不正行為
全ての契約と遺言書を作成し、その実行をAさんに依頼しているとしましょう。
初めに任意代理契約が開始しました。
数年経った頃、あなたに認知症の症状が表れ判断能力が低下してきました。
本来ならここでAさんは任意後見契約に移行すべきです。
しかし、Aさんにはそれができない事情がありました。
実は、あなたの判断能力が低下してきたのを良いことに、Aさんはあなたの財産を少しずつ着服していたからです。
任意後見契約に切り替えるには、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選んでもらわなければなりません。
任意後見監督人が付けば、Aさんの不正は明るみに出る恐れがあります。
そのため、任意後見契約に切り替えることなく、あなたが亡くなるまでの長期間、不正行為が行われてしまうこともあるのです。
契約の流れ
契約の流れは👇次の通りです。
任意代理契約で依頼したことを行なってもらっている時に判断能力が低下してきたら、任意後見契約へ移行します。
家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選ばれたら任意後見契約が開始になります。
あなたが亡くなると、任意代理契約や任意後見契約は終了となり、死後事務委任契約へと移行します。
身元保証人を確保する
「おひとりさま」で老後を迎える人は「身元保証人」が気になるものです。
病院や施設が患者や入所希望者に身元保証人を求めることがあり、中には保証人がいないと入所を認めない施設もあるからです。
保証人には、子など身内がなることを期待され、高齢の場合、身内でも2人の保証人を求められることもあります。
これは医療費や施設利用料金の滞納があった時や、手術や治療、介護方針に対する同意など、病院や施設側が勝手に判断や決定をできない場面になった時、それを行なえる家族、又は家族に準ずる人が求められるためです。
保証人を頼めるような親族がいない場合は、身元保証人を代行してくれる団体などを利用することを検討してみましょう。



身元保証人の代行は、契約の内容によって利用料金や支払い方法が異なります。料金やサービス内容を確認し、いくつかの団体を比較して自分に合ったものを選びましょう。
急に体調を崩すなどして、保証人がいないという不安から慌てて身元保証契約をするのは避けたいものです。
また、身元保証の契約をすれば当然支払いが発生します。
推定相続人の調査や、財産調査などが事前に行なわれるなど条件もあります。



尚、後見人になっている弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家は保証人になることはありません。入院費などの債務を保証できないのはもちろん、医療の同意もできません。
身元保証のみを団体などに依頼し、生前や死後の契約は専門家に依頼するか、全てのことを団体などに依頼するのか、検討しておきましょう。
遺言書を用意する
まだまだ生活を謳歌したい「おひとりさま」にとって、耳を塞ぎたいことかもしれませんが、自分が死んだ後のことも考えてみましょう。
自分が残した財産などは、放っておくと、勝手に法律の順番通り相続人に相続されてしまいます。
しかし、相続されるといっても、自分の財産を把握しておかないと、「何が誰にいくのか」さえ分かりません。
先ずは、自分の財産を洗い出してみましょう。
持ち家なら不動産が残りますね。
また、預貯金もあります。
株などの有価証券がある方もいらっしゃいます。



自分が亡くなった後、これらをどうするか?どうしたいのか?それを残すのが「遺言」です。財産、遺品から携帯内のデータまで、どう処分してほしいかを文書にしておきましょう。
あなたが独身で子供がいなくても、親が生きていれば、あなたの遺産は親が相続します。
親が既に亡くなっている場合は、兄弟がそれぞれ相続することになります。
兄弟が全員亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人になります。
誰も相続人がいない場合には、あなたの死後、財産は相続人以外であなたと生計を同じくしていた人などの縁故者もしくは国のものになります。
まして、兄弟や甥・姪と疎遠になっていて頼るつもりがないのなら、自分の財産をその身内に渡すのか、慈善団体などへ寄付するのかなども考えておかなければなりません。



甥や姪と親しかったり、世話を受けたりして、自分の財産を相続させたいと考えるのなら、甥や姪が財産を受け取れるように「遺言書」を作成しておきましょう。
ペットの依頼先を考える
ペットと一緒に暮らす「おひとりさま」も少なくありません。
ペットとの生活は安らぎやハリが持てるという人も多いでしょう。
ただ、心配なのは、飼い主が先に亡くなってしまった場合です。
大切なペットのために、自分が元気なうちに自分の死後にペットの面倒を見てくれる人を見つけておくことが必要です。
そして、世話をお願いするお金も用意しておく必要もあります。
お世話をお願いしたペットが亡くなった場合は、自分と同じお墓に入れてほしいとか、自分と同じ場所に埋葬してほしいという希望がある場合は、きちんと文書にして、お世話をお願いする人に分かるようにしておきましょう。
但し、お世話をお願いした人がペットより先に亡くなる可能性はゼロではありませんし、またお願いしようと思っていた人が病気や家の事情などでペットのお世話ができなくなることもあり得ます。
犬や猫、爬虫類や熱帯魚などを引き取ってくれるお店や団体も予め調べておきましょう。
老人ホームや高齢者施設への入居などで、ペットと一緒に暮らせなくなったり、お世話ができなくなった時のためにも必要です。
また、おひとりさまが病気や事故で入院した時にも、不在中のペットの世話をしてくれる人も探しておきましょう。
但し、お願いしていた人が都合で引き受けてもらえないこともあるので、やはり預かってくれる団体やお店を探しておくことも大事です。



自分の死後、ペットのお世話を頼む場合は、「負担付き相続の遺言」か「負担付き遺贈の遺言」を作成するという方法があります。
- 子供など自分の相続人に頼む時 … 負担付き相続の遺言
- 相続人以外の人に頼む時 … 負担付き遺贈の遺言
負担付き遺贈とは、財産をあげる見返りに一定の義務を負担してもらう遺贈のことです。
例えば、「私が要介護状態になった時に、介護をすることを条件にマンションを遺贈する」、「自分の死後にペットの世話をしてくれる条件で相続財産の3分の1を遺贈する」など。
約束が守られれば、遺言に基づいて遺贈が実行されることになっています。
また、ペットのお世話について、お願いしたいことを具体的に書いておきましょう。
ペットの癖や嗜好、食事の内容、散歩、掛かり付けの獣医、トリミング、予防接種などについて合意書のようなものを作っておくと、頼まれる方も安心です。
負担付き相続や負担付き遺贈の遺言を作成する場合は、必ず「遺言執行者の指定」をしておきましょう。
遺言執行者は、自分の作った遺言の内容を実際に実行してくれる人です。
遺言執行者は、例えばペットのお世話を引き受けた人が、合意書などに基づいて面倒を見てくれているかどうかのチェックをし、もし誠実にできていない時は、きちんと行なうように催告します。
それでも態度が改まらなかった場合は、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。



但し、遺言執行者がいつまでチェックすれば良いのか、決まりはありません。予め遺言執行者に、いつまで頼むかを決めておくと良いでしょう。
尚、受贈者(遺贈を受ける人)が義務を負担できない場合は、遺贈を放棄することで、義務からも逃れられます。
負担付き遺贈をする場合には、遺贈者と受贈者は十分に話し合っておくことが必要です。
まとめ
今や日本人の平均寿命は、男性は81.09歳、女性は87.13歳と世界でもトップクラスです。
もちろん長生きをして、その分、人生の終盤を思う存分楽しめるのは喜ばしいことですが、先が予想できないのが人生です。
長寿化で老後が長くなれば長くなるほど、そのリスクがあることも知っておかなければなりません。
もし、自分に身寄りがない場合、その終末期を考えると不安が過るのも当然でしょう。
体調が急変しても誰も助けてくれないのではないか、死んでも発見されないのではないか、葬儀はどうなるのか…。



これら不安を全て解消するのは難しいですが、事前に少しでも備えを講じておけば不安を和らげることはできます。いざという時に慌てないよう、あなたにとって「何かの時に駆けつけてくれる家族や友人・知人」は誰なのかを考えておきましょう。
人生で最も辛いことは孤独だとも言われます。
井戸端会議のような場で愚痴をこぼし合うところから、お互いを支え合う関係になることもあるでしょう。
切っ掛け作りのためにも、地域のサークルやボランティア活動に参加してはどうでしょうか。
他人から頼りにされるような存在になれば、自分が頼りにできる相手も見つかるでしょう。
その上で、次に紹介する方法を講じておけば、少しは不安が解消される筈です。
- 先述した委任契約や後見契約を結ぶ
信用できる人とお互いに契約書を交換できれば、気持ちの面でも落ち着けるでしょう。
しかし、心情的にいくら親しくなっても、なかなかそこまで信頼できる相手を見つけられないのが現実かもしれません。



そういう場合は、弁護士や司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家に相談すると良いでしょう。重要なことを任せるのだから慎重を期すため、事前に他の仕事を通じて信頼関係を築いておくことです。
- 葬儀やお墓について「生前契約」をしておく
業者や団体に自分の希望を伝え、生前契約をしておくと安心です。
生前契約は、葬祭業者を始め、互助会やNPOなどで扱っています。
内容は、業者ごと或いは団体ごとに、葬儀のみを行なったり、死後の手続きの処理から財産の整理、遺言の執行まで取り扱ったりと千差万別です。
生前、費用は一切支払わなくても良い業者もあれば、予約金や葬儀の概算費用の支払いを求める業者もいます。
民間企業である以上、破綻する可能性もあるので、契約時に高額の費用を要求する業者は避けた方が良いでしょう。



契約前に、サービス内容と費用をチェックしておきましょう。その際、この契約とは別に、自分の死を業者や団体に連絡してくれる友人や知人を決めておくことです。
さらに、これまでトラブルはなかったのか、解約時の契約金の取り扱いはどうなのか、契約は確実に実行されているかなども調べておきたいものです。
業者の中には、葬儀の内容や費用の支払い方法などを公正証書にしてくれるところもあります。
これならより安心でしょう。



葬儀の相談については、全日本葬祭業協同組合連合会が受け付けているので、相談があれば問い合わせてみるのも良いでしょう。
- 遺品や財産の処理の方法を決めておく
「自分らしい葬儀の予約もしたし、お墓の手配も済ませたし、これでもうひと安心、いつお迎えが来ても大丈夫…」と思いたいところですが、もう一つやっておかなければならないことがあります。
それは、自分が亡くなった後に残されるであろう、様々なものの整理や処分の手配です。
近しい親族を見送った経験のある人ならよくお分かりだと思いますが、人が一人亡くなると、葬儀やお墓の問題の他にも色々な手間が掛かってきます。
縁のある人々や所属していた会に対するお知らせから始まり、加入していた生命保険の手続きや、口座振替が行われている銀行口座の整理、金融資産の精算、ローンの整理、クレジットカードの解約に、それまで住んでいた住宅や家財の処理、諸契約の解除、可愛がっていたペットの行く末、等々。
このような様々な死後の雑事処理は、友人に頼むには余りにも煩雑で荷が重い仕事です。
また、家財の整理に当たっては、逆に知っている人には見られたくないものもあるでしょう。



そういった死後の処理作業について、今では生前にお願いしておける団体や業者もあるのです。先ず、家財等の整理に関しては「遺品整理業」という、ちょっと耳慣れない業者さんが引き受けてくれます。
ものが溢れるこの時代、遺品を形見分けできる家族や友人がいたとしても、よほど高価なものでない限りもらってはくれません。
かえって迷惑にさえなってしまうことが多いようです。
遺品整理とは、そういった引き取り手のない家財を部屋から運び出し、処分し、場合によってはその部屋の清掃も行なってくれるというサービスです。



友人などに頼む他に、遺品整理業者と生前に契約を結ぶという方法があります。費用は、自分の財産から葬儀費用などと共に支払ってもらうようにすると良いでしょう。
「将来に備える」ということはもちろん大切で、必要なことですが、そのために「今」を大きく犠牲にしなければならない、ということでは決してありません。
少々大げさですが、今も昔も人間というもの、本当は明日の命さえ分からない存在なのです。
不安というものは「生きている限り」なくなりません。
逆に考えれば「生きているという証」でもあります。
「不安だ、不安だ」と言ってばかりもいられないので、どこかで腹を括って不安の正体を見据え、できる手は打っておきましょう。
そして、ある程度の手を打ったならば、少し気を楽にして、自分の心を見直してみませんか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。