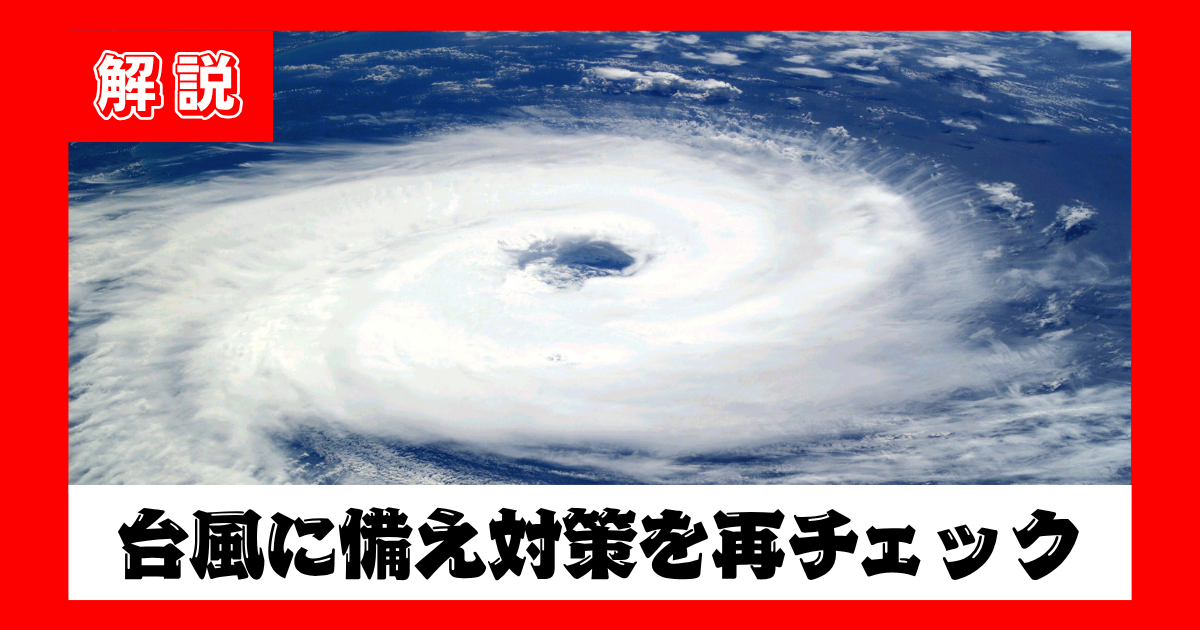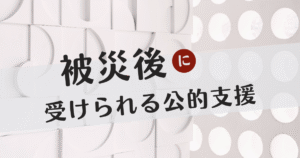悩める人
悩める人台風に備える対策は?



直前の準備で減災はできる?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 被災のリスク
- 避難への心構え
- 避難をするタイミング
- 自宅で安全に過ごすための備え
- 避難所で必要なプラスαの心構え
- 台風前の準備リスト
はじめに
台風やそれに伴う大雨が発生すると、水害や風害などの災害が引き起こされる可能性があります。
浸水、停電、断水、強風による家の破損…。



多種多様な被害を最小限に止めるために、対策しましょう。台風が迫っている時に自分の身や家を守るために準備しておくべきことをご紹介します。
被災のリスクを知る
先ずは、日頃から自宅のある場所に「どんな被災リスク」が「どの程度」あるのかを確認して下さい。
ハザードマップで自宅のある場所の災害リスクを見てみましょう。
防災ハザードマップは、市区町村の窓口でもらえる他、都道府県のホームページからも確認することができます。
防災ハザードマップには、洪水、津波、土砂災害など自然災害時の被災想定区域や、地域の避難場所、避難経路が表示されています。



自分の住んでいる地域にどのような被害が想定されているか、最寄りの避難場所はどこかなど、確認しておきましょう。浸水や土砂災害、高潮が発生する恐れの高い区域にお住まいの方は避難の準備が必要です。
但し、該当区域外だからといって安心してはいけません。
ハザードマップで危険とされる区域でなくても、被災する可能性があります。
近年は台風の巨大化によって、予想もされていなかった場所に甚大な被害が広がりました。
特に周囲と比べて低い土地や崖のそばなどに住んでいる場合は「市区町村が発信する防災情報」を参考にして、避難する心づもりをしておきましょう。
避難のタイミングと心構え
もう間もなく、台風が迫ってくるという時に、ポイントになるのが避難をするタイミングです。
大雨・台風時における避難情報(警戒レベル)では、レベル3が「高齢者など避難に時間が掛かる人の避難」、レベル4が「全員避難」の目安になっています。
もちろん風が吹く前、雨が降る前から警戒しておくに越したことはありません。
自宅が危険区域に該当している場合に確実に安全が確保できるのは、危険区域外に逃げる「広域避難」です。
近隣の避難所の利用や高所に避難する垂直避難は広域避難が難しい場合に検討をしましょう。



ただ、避難先がいくら安全でも道中に低地や橋があると事故に遭うリスクが高まります。避難前にハザードマップで安全な移動ルートを確かめておきましょう。
逆に、避難を「しない」時の目安を知っておくことも役に立ちます。
基本的に浸水が20センチを超えた場合、徒歩での避難はできないものと思って下さい。
水流もあり、足が取られて大変危険です。
車で避難をする場合も、30センチ浸水すれば機械系統が故障し、車ごと流されてしまう危険性もあります。



非常用持ち出し袋は平常時から用意しておき、台風の前には、中身をもう一度見直して下さい。その時の家族構成や健康状態、ライフスタイルによって必要なものも変わってきます。
- 飲料水
- 食料品
- ヘルメット
- 軍手
- 衛生用品(マスク・ウェットティッシュ・除菌スプレーなど)
- 日用品(タオル・洗面用具など)
- 生理用品
- 常備薬
- 懐中電灯
- 携帯ラジオ
- 予備電池
- 貴重品
地方や離島など、交通の便が悪い地域の場合、交通網が遮断されてしまうと必要物資が届きません。
その分を考えて用意しましょう。
自宅で安全に過ごすための備え
どの家でも共通して行なってほしいのは「強風対策」と「大雨対策」です。
先ずは強風で窓が割れないよう補強を。
そして、屋外にあるものは風で倒されたり飛ばされたりしないように、屋内へ避難させておきます。
水害リスクの低い地域でも、大雨対策として、事前に屋外にある排水溝や雨どいがきちんと機能するか確認を。
もし詰まっていると、雨水が溢れかえってしまうので、掃除を忘れずに。
特にベランダのある家では排水溝が詰まっていると、ベランダ浸水が起きます。
あっという間に水が溜まっていき、室内に水が浸水してきます。
もし自宅が水害リスクの高い区域にあり、予想される浸水の深さより低い場所に床や玄関がある場合は、土嚢で浸水を抑えます。
地域によっては「土嚢ステーション」があるので活用して下さい。



しかし、直前の準備では土嚢が調達できないこともあります。代替策として、段ボールとゴミ袋、ビニールシートを材料にした防水壁を作りましょう。
- 大きなゴミ袋を2重にして袋の半分を目安に水を入れる
- 袋の口を結んで締め、水嚢を作る
- ブルーシートの上に段ボール箱をのせて、箱の中に水嚢を入れる
- 箱を閉じて、ブルーシートで包む
自動車を保有する場合、水没しないよう事前に高台へ移動を。
近くに屋内式の立体駐車場があれば、そちらへ移動させておけば飛来物も避けられて安心です。
停電と断水、ガスの供給停止に備えて、入浴や洗濯などの電気や水、ガスを使う家事を済ませてしまうのも大切な準備です。
水は浴槽に満タンまで貯めておけば、生活用水として利用できます。
その際は、水漏れのトラブルにならないよう配管が故障していないか確認して下さい。
またマンションは電気で水をくみ上げている場合があり、水道が復旧しても電気が通らないと水が出ないので注意です。
保存食として、節水のために水を使わずに食べられるものを準備しましょう。
停電で電子レンジを使えないことも考慮して、冷めても美味しく食べられるメニューを。
災害時には精神的にも身体的にもストレスがかかりやすいので、消化の良いものだと尚良いでしょう。



災害時はもちろん、普段から防災情報にアンテナを張り、知識と最新情報を照らし合わせて、最善の判断を下していきましょう。
- 家の備え -
- 植木鉢、物干し竿、サンダル、屋外収納ボックス、自転車など屋外のものは室内へ移動するか、ロープなどで固定する
- 強風対策用として、窓の外側に防風ネットを張る
- 非常用持ち出し袋は玄関付近に用意する
- ラジオやテレビ、ネットなどで地域の災害情報を把握する
- 停電・断水などに備え食料や水の備蓄、懐中電灯を用意する
- スマホや携帯電話のバッテリーを充電しておく
- 水や電気、ガス不要で食べられる食事を用意する
- ハザードマップで自宅のリスクを見直す
避難所で必要な心構え
高齢者
決して「快適」とは言えない避難所で体調を維持するために、先ず用意したいのが「自分に合った食べ物」。
味の好みだけでなく、噛む力や飲み込む力に合わせた食べやすいものを備えておきましょう。
次に「常用薬とお薬手帳」。
入れ歯や眼鏡など、生活に欠かせないものをワンセットで用意すると良いでしょう。



また「生活不活発病」予防のため、避難所で過ごす際には意識して体を動かすことも大事。家族や周りの人も声を掛けてあげて下さい。
乳児・幼児連れ
赤ちゃんを連れて避難所に行く場合は、2~3泊の旅行と同じような準備を考えておくと良いですね。
液体ミルクも活用を。
定期的に賞味期限をチェックして、ストックを更新しておきましょう。
赤ちゃんが泣き止まずに周囲が気になる場合は、部屋を別にしてもらえるよう避難所の職員に相談を。



また、いつもと違う状況は子供にもストレスです。安心して過ごせるよう、好きなお菓子や、遊び慣れた玩具も用意できると良いでしょう。
ペット連れ
環境省発刊の「人とペットの災害対策ガイドライン」では、災害時には飼い主がペットと同行避難することを求めています。
しかし、避難所の中に同伴避難できるかどうかは自治体の指示に従って下さい。
予め近くの避難所のルールを調べておきましょう。



非常事態において「ペットは人間よりも厳しい環境に置かれる」可能性も。避難した人の中には色々な人がいます。互いを思いやって助け合うことが大切です。
まとめ
いつ起こるか分からない地震や台風などの自然災害。
近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨、いわゆるゲリラ豪雨も増加傾向にあります。



自然災害は避けられるものではありませんが、災害による被害を最小限に止めることは、日頃の備えによって可能になります。台風の場合は数日前から予報が出ますので、前もって準備できます。
家屋の浸水だけでなく、物が飛んできて窓ガラスが割れる危険性があります。
窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っておけば、被害を最小限にできるかもしれません。
また、来ると分かっていれば、事前に安全な場所に避難もできます。



あと、携帯トイレは最低1週間分を備蓄しましょう。断水や停電が起きると、トイレが使えなくなります。どんな人でも排泄は我慢できません。1人につき1日5回、1週間で35回分が目安です。
- 準備リスト -
- 防災ハザードマップを確認
- 避難のタイミング・避難場所・避難経路・避難の方法を確認
- 非常用持ち出し袋と備蓄品の用意
- 強風対策・大雨対策をする
- 電気・ガス・水道の停止に備える
- 室内の安全チェック
- 日持ちする食料を用意する
- 情報収集に必要なスマートフォンの充電、ポータブル電源(蓄電池)の備え
- 地域の避難訓練等に参加
災害時は、自分だけではどうにもできないことが当然出てきます。
大規模災害では公助はすぐには来てくれません。
その時は、隣近所での助け合いがとても大切になってきます。
いずれにしても、先を見越した早め早めの行動を心掛けましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。