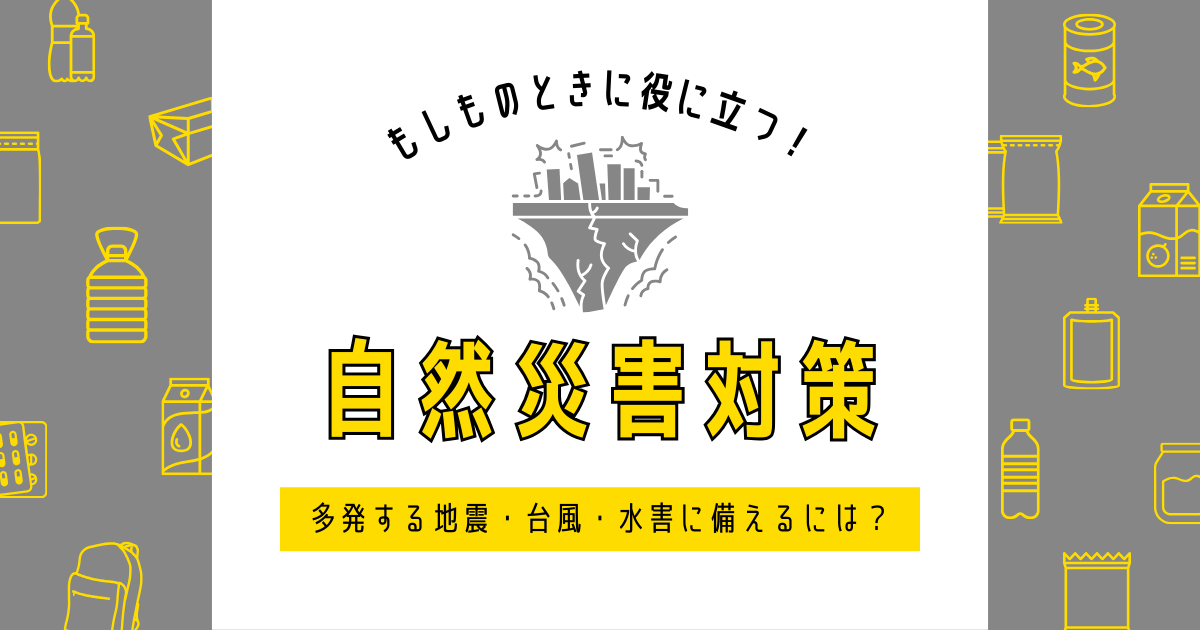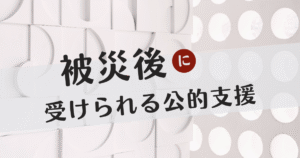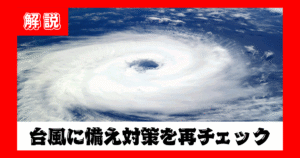悩める人
悩める人自分の家と地域の災害リスクを把握するには?
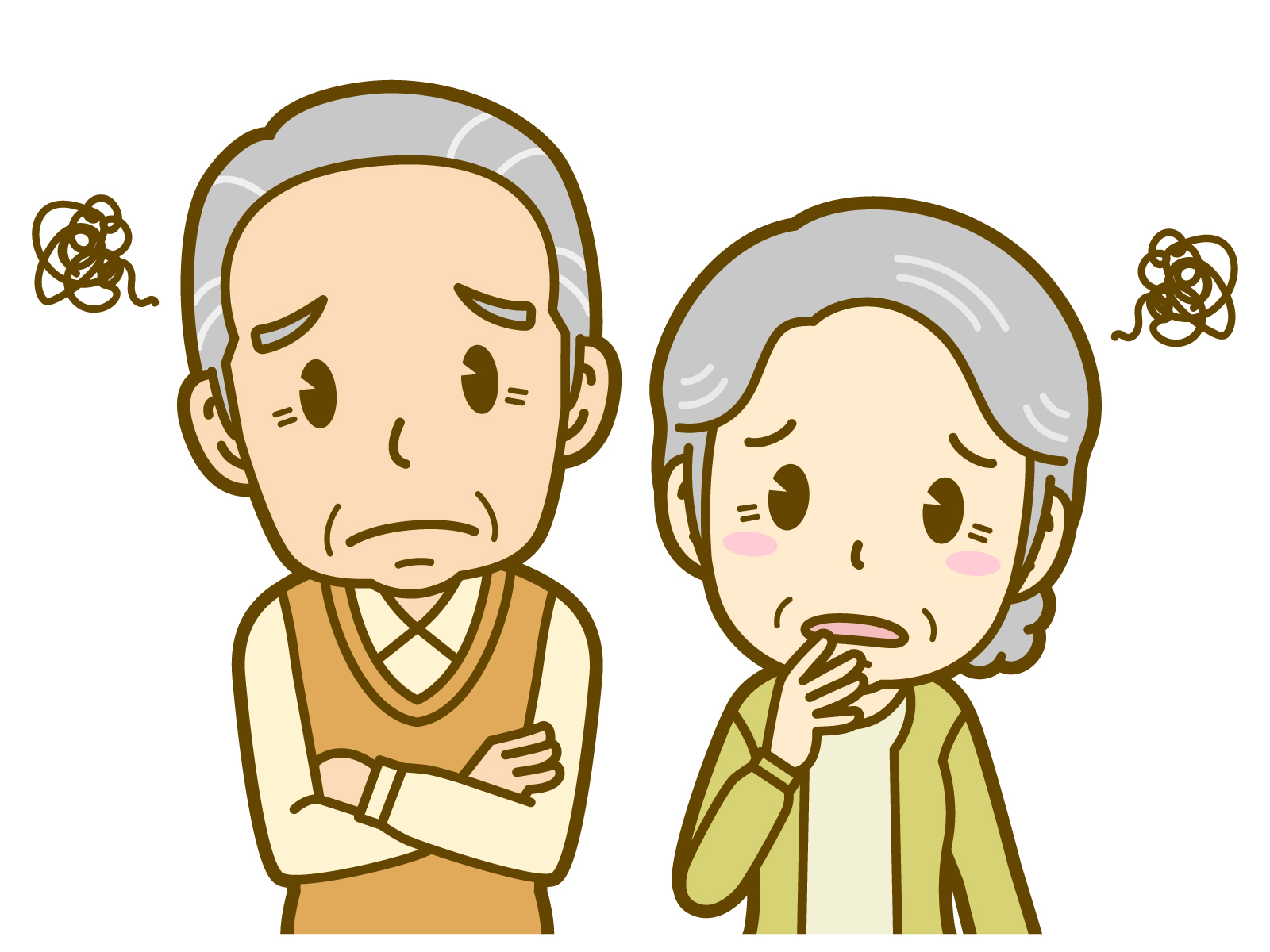
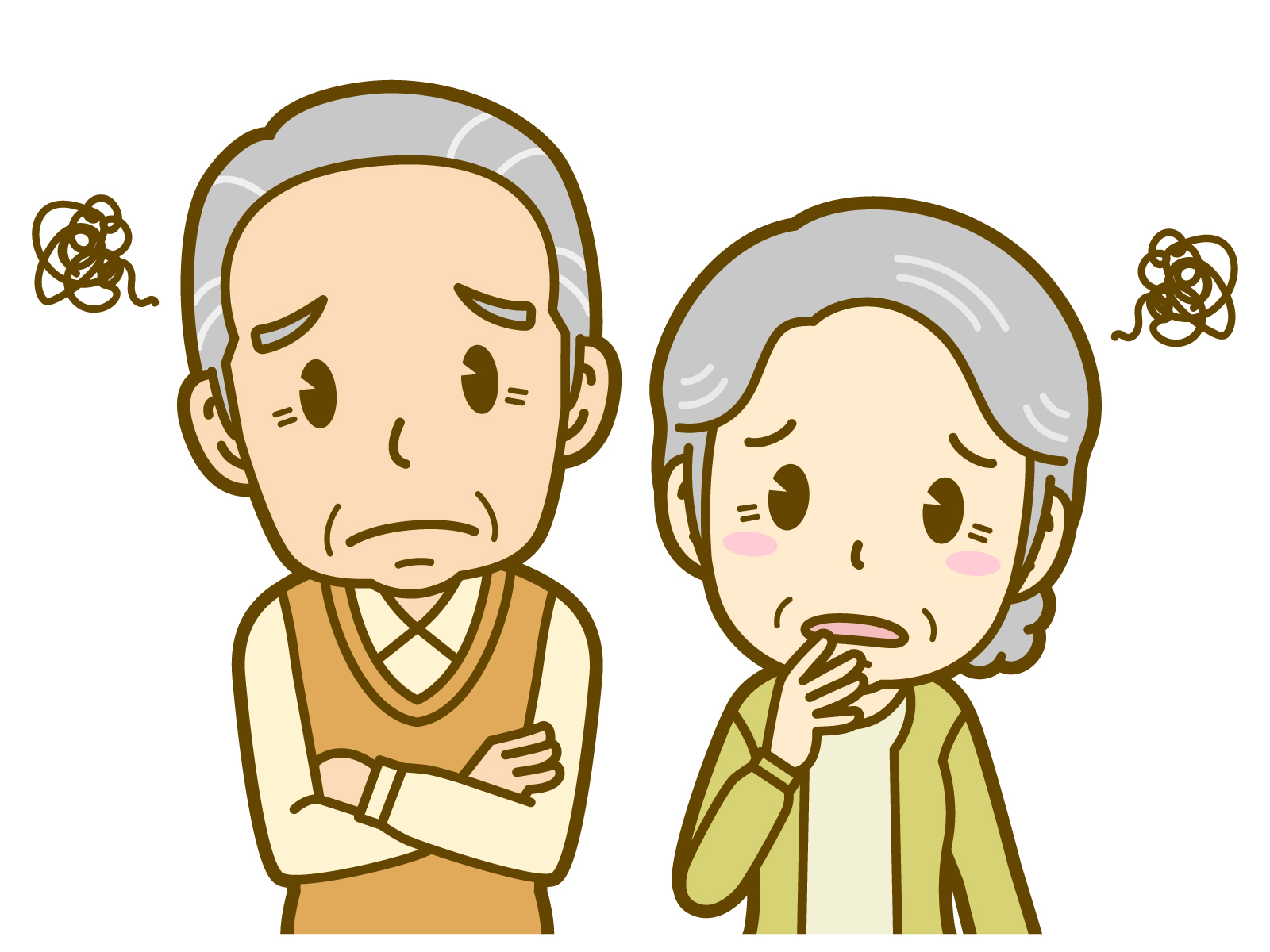
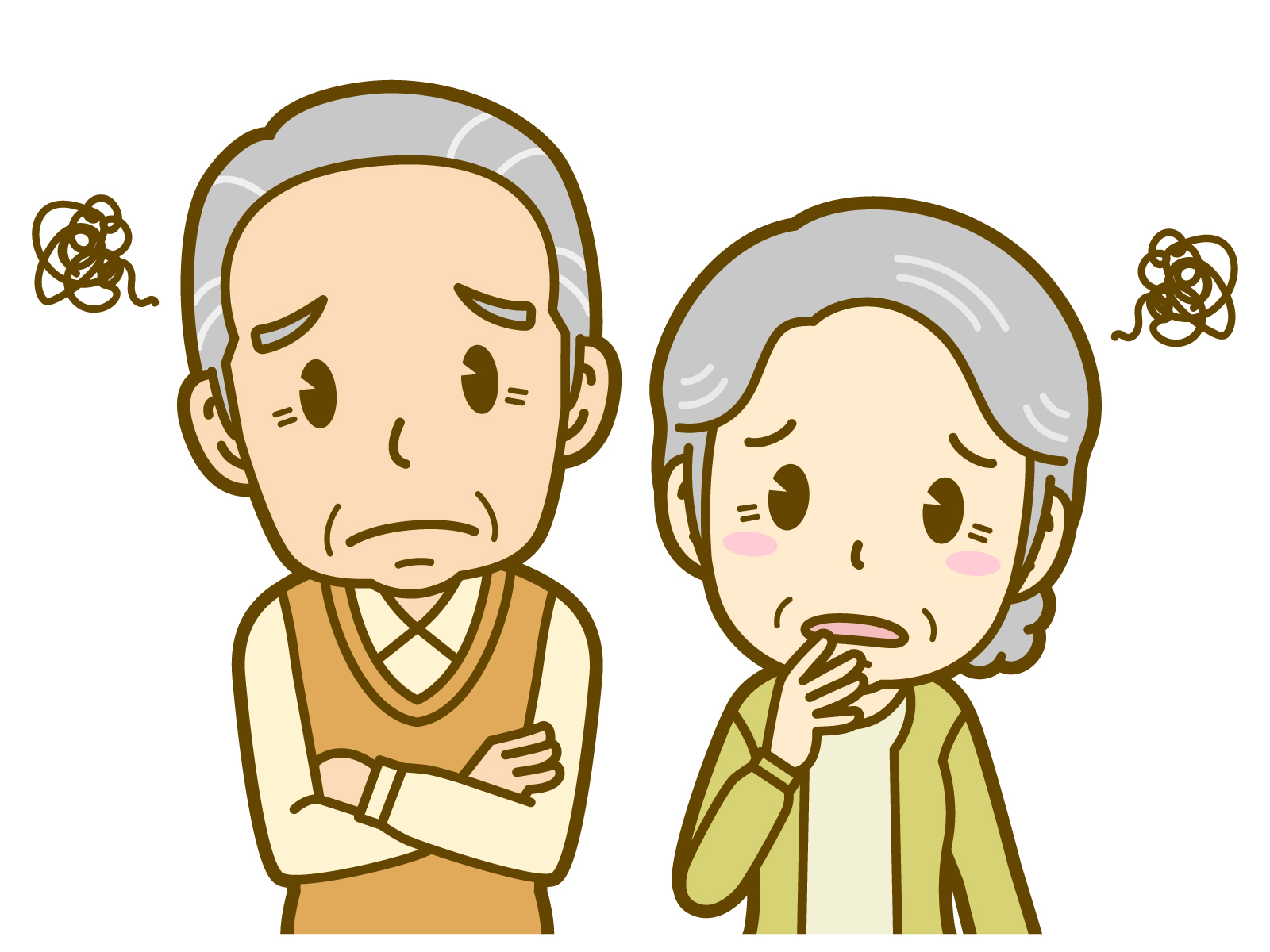
今すぐしておきたい災害対策とは?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 自然災害対策
- 用意しておくべき備蓄品
- 避難用品の選び方
- 出火時等の対処法
- 保険の加入の目安
自然災害対策
近年、日本周辺が地震の活動期に入ったと指摘する研究者は多く、ゲリラ豪雨も増加傾向にあります。
地震、津波、台風、土砂災害など、自然災害にいつ遭遇しても不思議ではありません。
地震は家屋倒壊、火災、液状化、津波の、台風は河川氾濫、土砂崩れの恐れがあります。
また、暮らしの中でもちょっとした不注意で火災になることもあります。
そんな被害に遭わないためにどうしたら良いのでしょうか。
ハザードマップの確認
先ず取り組んでほしいのが、地域の災害リスクを知るということです。
自治体が作成しているハザードマップで、地震や洪水の被害を受けやすいかどうか調べておきましょう。



防災対策は、先ず自分の家と周辺地域の自然災害リスクを自治体が公表している各種ハザードマップなどで正しく把握した上で行わないと意味がありません。
避難用品や備蓄品を何でもかんでも揃えている人がいますが、それは敵を見ずに刀を振り回しているようなものです。
ただ、ハザードマップは一つのシミュレーション結果に過ぎず、想定以上の被害も出ています。
大事なのは「災害の履歴を知る」こと。
図書館にある市史、町史などで、今住んでいる土地は過去にどんな災害があったのか、河川氾濫や土砂災害など、その土地の特徴や弱点を知る必要があります。
- 防災ハザードマップを確認
- 地域の災害履歴を調べる
自然災害リスク
では、そもそも自然災害リスクにはどのようなものがあるのでしょうか。
大きく分けると地震による「建物倒壊」「液状化」「津波」「延焼火災」、台風や集中豪雨による「洪水・浸水」「土砂災害」が挙げられます。
近年は短時間での強雨発生回数が増えています。



自分の家と周辺の状況を把握し、自然災害リスクが少ないという判断を下すことができれば、たくさんの避難用品を揃える必要も少なくなるでしょう。
- 自分の家と地域の災害リスクを把握する
耐震診断・補強工事
一方、例えば建物倒壊や液状化のリスクがあったら、対策工事が必須です。
耐震化や液状化対策工事はかつては高額でしたが、現在は技術向上や工法が多種になったため、比較的安く済ませる方法もあります。
耐震性は、建築年数である程度分かります。
1981年6月に耐震基準が強化され、「新耐震基準」と呼ばれています。
1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた建物は耐震性が低い可能性が高いです。
また、木造住宅では新耐震基準をより厳正化した、2000年基準があります。
2000年5月以前に建てられた木造住宅の中には耐震性が不足している可能性もあります。



自宅の耐震性に不安があれば、自治体の相談窓口などへ行き、「耐震診断」を受けましょう。
震度6強レベルの地震でも持ち堪えられるか、どの柱や壁が劣化しているのかなどが分かります。
費用は約10万円からですが、自治体によっては補助制度もあります。
必要があれば「補強工事」をしましょう。
- 耐震診断を受ける
- リスクに応じた適切な対策を講じる
室内の地震対策
日本の場合は地震ハザードマップの想定震度が5強や6弱であっても、震度6強以上の地震に見舞われる可能性は全国どこにでもあります。



全ての家で震度6強の地震が来るという前提で耐震化や液状化の対策工事を行うと共に室内の地震対策として「倒さない」「出さない」「落とさない」の3ないチェックが必要です。
具体的には、例えばタンスや食器棚、本棚など背の高い家具と天井の間に耐震ポールを壁寄りの位置に取り付けます。
空の段ボール箱で天井との隙間を埋めておくだけでも同様の効果があります。
二段重ねタイプの家具は上下を器具で固定し、食器棚や戸棚は扉の取っ手にフック類を掛けて開かないようにしておきます。
食器棚や窓のガラスには飛散防止用フィルムを貼っておきましょう。
薄型テレビは紐類で固定します。
壁に飾ってある絵画や賞状、先祖の写真などの額のガラスはアクリルに換え、フックを釘ではなくL型やC型のスクリュー式にします。



部屋の中で要注意なのが、食器や本などが詰まった棚と窓ガラスです。棒やベルトで棚を固定したり、フィルムを貼ってガラスの飛散を防いだりすることが必要です。
- 室内の安全チェック
- 室内の耐震補強をする
避難用品・備蓄品
地震だけでなく台風や豪雨などのリスクがある場合は、避難用品や備蓄品を揃えておかねばなりません。



その場合、最優先すべきは避難所に備蓄されている水や乾パン、毛布ではなく、他の人が持っていないものや、他の人と共有できないもの(入れ歯・コンタクトレンズ・歯ブラシなど)です。
- 避難所に用意されていないもの
- 他の人が持っていないもの
- 他の人と共有できないもの
大規模災害に備えるには、少なくとも1週間分の備蓄が必要。
東日本大震災発生時、東京でも食料や生活用品が店頭から消えたことを覚えているかと思います。
災害時に本当に物を必要としている被災地への供給を妨げないためにも、普段から一定の備蓄をしておくことは、災害の多い日本に住む者のマナーだと言えます。



下記の備蓄品リストを参考に、高齢者や乳幼児向けに追加して用意すべきものなどを家族で話し合ってみて下さい。
- 飲料水 … 最低3日分・1人1日3リットル
- 保存食 … ご飯・缶詰・レトルト食品・乾燥野菜・スープなど
配給のメインはパンとおにぎり。
毎日3食炭水化物だと栄養に偏りが生まれ、病気になる恐れがあります。
調理しなくても常温で食べられるレトルトのカレーや、野菜スープ、乳酸菌入りのビスケットなど、栄養のバランスを考えて食料を用意しましょう。
- 衛生用品 … マスク・消毒薬・除菌ウエットティッシュなど
- 軍手
- ヘルメット
- 笛
- ティッシュペーパー
- トイレットペーパー
- 卓上用カセットコンロ
- 予備ボンベ
- ライター
- 携帯ラジオ
- 懐中電灯
- 予備電池
- ランタン
- ゴミ袋
- ポリ袋
- 毛布
- 運動靴
- メガネ
- コンタクトレンズ
- 体温計
- 非常用トイレ
- 日用品 … タオル・洗面用具など
感染症対策として、マスクや除菌ウエットティッシュを。
そして停電、断水に備えトイレ用のアイテムを用意しましょう。



どんな災害でも「知らせる」ことは重要。そこで力を発揮するのが、近所に素早く危険を伝えることのできる「笛」です。遠くまで音が届く防災用の笛がお勧めです。
自宅だけでなく、第二の避難場所となる車のトランクにも毛布や非常用品を備蓄しておきます。
- 高齢者 … 常備薬・義歯・義歯ケース・高齢者用オムツ・使い捨てカイロ
- 乳幼児 … 哺乳瓶・粉ミルク・離乳食・スプーン・紙オムツ・おしり拭きシート・おもちゃ類
- 妊産婦 … 生理用品・断熱マット・アルミブランケット
- ペット … 食べ慣れているペットフード・ケージ



但し、人を救えるのは人だけです。定年後は家にいる時間が長くなるので、日頃から地域やマンション内などのコミュニケーションを図り、密にしておくことも大切です。
- 避難用品・備蓄品を揃える
- 地域の避難訓練等に参加
- 近隣とのコミュニケーションを密にする
家族内の話し合い
また、災害時の行動について事前に家族と話し合うことも重要です。
年に1、2回の頻度で、緊急連絡先や避難方法などを話し合いましょう。
①連絡方法
離れた親戚や友人の家に、家族一人ひとりが安否確認の連絡を行う「三角連絡法」を実践しましょう。
②集合場所
広場や学校など、家族が落ち合う場所を決めておきましょう。
③在宅避難と分散避難
大雨・土砂災害等による警戒レベル4「危険な場所から全員避難」というのは、危険区域で災害懸念のある人が対象です。
自宅の安全が確認できた人は、自宅で暮らす「在宅避難」が原則です。
電気、水道が止まっていても、感染症の心配もなく、よく眠れます。
避難する場合も、避難所だけでなく、2階への垂直避難、自治会館、親戚・知人宅、車中避難などの「分散避難」を検討します。
- 家族間の連絡方法の確認
- 家族との合流場所の確認
- 避難所や避難経路の確認
出火時等の対処法
さらに、地震や火災が起きた場合でも、迅速に行動できるようにしておきます。



先ずは、下記の「出火時等の対処法 : 4つの手順」を頭に入れておいて下さい。
①知らせる
火災が発生したら、「火事だ!」と声を上げたり、笛を吹いたりして近くの人に知らせます。
そして、119番通報します。
自分だけで何とかしようとすると煙や炎が広がり、逃げ遅れる危険性があります。
②消す
火災が発生したら、素早く消しましょう。
出火から3分以内なら、消火器や水を使って消せる場合があります。
但し、天井に燃え移ると、一度に火が広がるフラッシュオーバーの危険があるのですぐに避難します。
③助ける
自分の安全を確保しつつ余裕があれば、逃げ遅れた人がいないか呼び掛け確認しましょう。
もし助けが必要な人がいたら、周囲に応援を求め協力し、姿勢を低くして安全な場所まで誘導します。
④逃げる
天井に火がついたり、煙が充満してきたら、直ちに姿勢を低くして安全な場所に避難しましょう。
全員避難を確認した上で、他への延焼・拡大防止のため、部屋や玄関ドアを閉めて空気を遮断します。
シチュエーション別の対処法
加えて、シチュエーション別の命を守る行動です。



緊急地震速報や地震の揺れを感じたら、閉じ込められないように、先ず「避難経路の確保」が大切です。
①自宅
すぐに玄関のドアを開けましょう。
比較的狭く柱の数が多い玄関は安全ゾーンと見なされ、避難に適しています。
②オフィス
ドア付近にいる人はドアを開け、安全ゾーンに移動、間に合わなければ机の下などに潜って下さい。
③地下鉄
社内に煙が充満したり浸水してきたら、係員の指示がなくても非常用コックを開き、安全確認後避難しましょう。



係員の指示を待つのが原則ですが、常にその指示が正しいとは限りません。
④屋外
ガラスや看板が落ちてくる危険がありますので、先ず建物から離れましょう。
車を運転していたら、ハザードをつけて徐行、左側に寄せて停車します。
いずれの場合も、その場の安全ゾーンを確認し、自ら避難して命を守る必要があります。
火元やガス栓の確認は揺れが収まってからで構いません。
津波の危険がある場合、警報の有無に関わらず避難し、最悪を想定して遠くより高所に逃げ、避難した後は警報解除まで、元の場所に戻らないようにしましょう。
たとえ1人でも避難するよう心掛けて下さい。
保険加入の目安
過去の災害で、命は助かってもその後の生活ができないという被災者が大勢いました。



それらの手助けともなるのが「火災保険」や「地震保険」です。気を付けたいのは、火災保険は「地震が原因による火災は適用外」ということです。
地震による火災被害、津波被害、建物損壊の補償を受けるには「地震保険」が必要です。
地震保険は火災保険に付帯した保険で、火災保険に入らないと加入できません。
最近の火災保険は火災・風災・水災などを組み合わせるものが多いようです。
水災補償は台風による土砂崩れや浸水被害に備えている分高額なため、付けるべきか悩む人も多いと思います。



川や山に近い住宅はもちろん、都心部でも低地や谷地は注意が必要です。ゲリラ豪雨が起きた際、水が一気に集まり、処理が間に合わなかった水がマンホールから溢れ出る可能性があるからです。
- 過去に浸水被害があった地域
- ハザードマップで浸水リスクがある
- 土砂崩れのリスクがある
- 高潮の被害を受けやすい
- 一戸建て
- マンション低層階
- 都心部の低地や谷地に住んでいる
地震保険に入った方が良いのは、多くの住宅ローンが残っている人です。
家を買った直後に被災すれば、住み家を失った上にローンはまるまる残ってしまいます。



自宅兼用で仕事をしている人も、被災すれば家を失い収入も絶たれてしまうため、加入をお勧めします。
- 1981年以前に建てられた木造家屋
- 地盤が軟弱
- 液状化のリスクがある
- 沿岸から10キロ未満
- 住宅ローンの残高が多い
- 自宅が仕事場を兼ねている
- 火災保険・地震保険の補償内容の確認
- 保険加入はリスクを十分に把握してから
まとめ
いつ起こるか分からない地震や台風などの自然災害。
近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨、いわゆるゲリラ豪雨も増加傾向にあります。
自然災害は避けられるものではありませんが、災害による被害を最小限に止めることは、日頃の備えによって可能になります。



先ずは、自治体が作成している「防災ハザードマップ」で、住んでいる場所の災害リスクを確認しましょう。防災ハザードマップは、市区町村の窓口でもらえる他、都道府県のホームページからも確認することができます。
防災ハザードマップには、洪水、津波、土砂災害など自然災害時の被災想定区域や、地域の避難場所、避難経路が表示されています。
自分の住んでいる地域にどのような被害が想定されているか、最寄りの避難場所はどこかなど、確認しておきましょう。
もしも住まいが古い木造住宅であれば、「耐震診断」を受けた方が良いでしょう。
特に、1981年以前に建てられた建物は、「旧耐震基準」で建てられていますので、「新耐震基準」を充たしていない可能性があるのです。



耐震診断の費用は概ね10~30万円となっています。費用の一部を助成してくれる自治体もあります。申請に必要な条件は、自治体により異なりますので、住んでいる市区町村に問い合わせてみましょう。
もちろん、家の中の安全対策も大切です。
家具を壁や天井に固定する、照明や壁掛け時計などを落下しないように固定する、逃げ道に物を置かないなど、安全チェックをしておきましょう。
また、ライフラインが止まった場合を想定して、非常用持ち出し袋と備蓄品を備えておきましょう。
災害は突然起こります。
必ずしも家にいるとは限りませんし、家族が一緒にいる時に発生するとも限りません。



家族とは、安否確認の方法を話し合っておきましょう。
携帯電話が繋がりにくくなったり、充電ができなかったりといった事態も想定されます。
今のうちに災害が発生した場合の合流場所を決めておきましょう。
第2候補、第3候補まで決めておくと安心です。
また、「遠くの親類より近くの他人」と言われるように、日頃から近所の人や地域の自治会との繋がりを持っておくことも災害の備えとして大切です。
さらに、インターネットやスマートフォンでの情報収集も有効。
事前に公的機関の防災メールや防災アプリを入れておくと安心です。



但し、SNSはデマが流れることもあるので、複数媒体での確認が大切です。
- 住んでいる場所の危険を把握しておく
- 万が一の時のための準備を早めにしておく
- 日頃から地域の活動に参加して繋がりを持つ
いずれにしても、先を見越した早め早めの行動を心掛けましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。