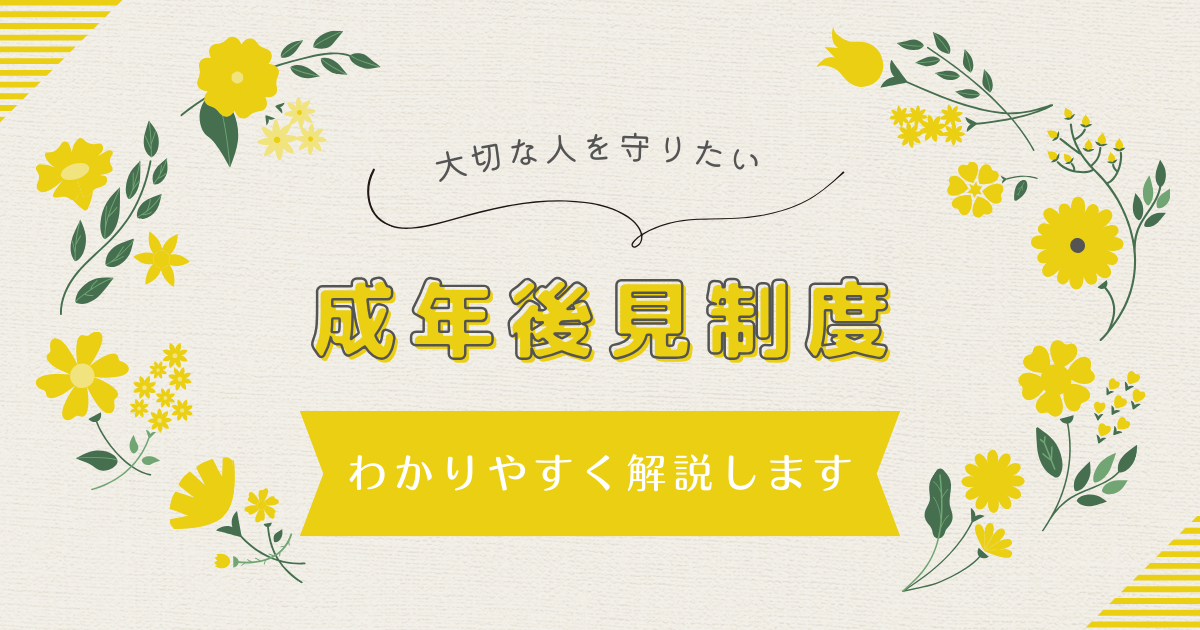悩める人
悩める人成年後見とはどんなもの?
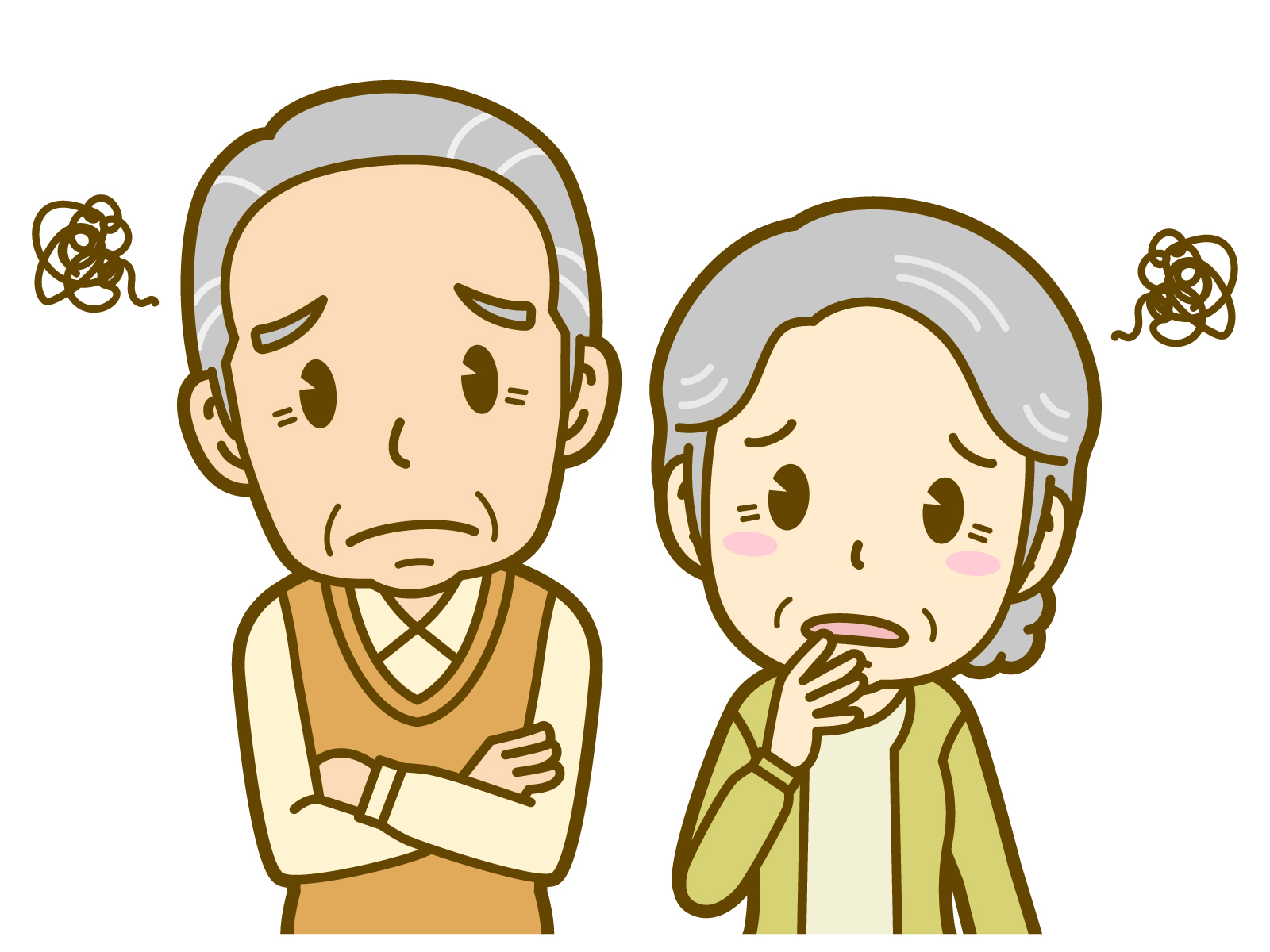
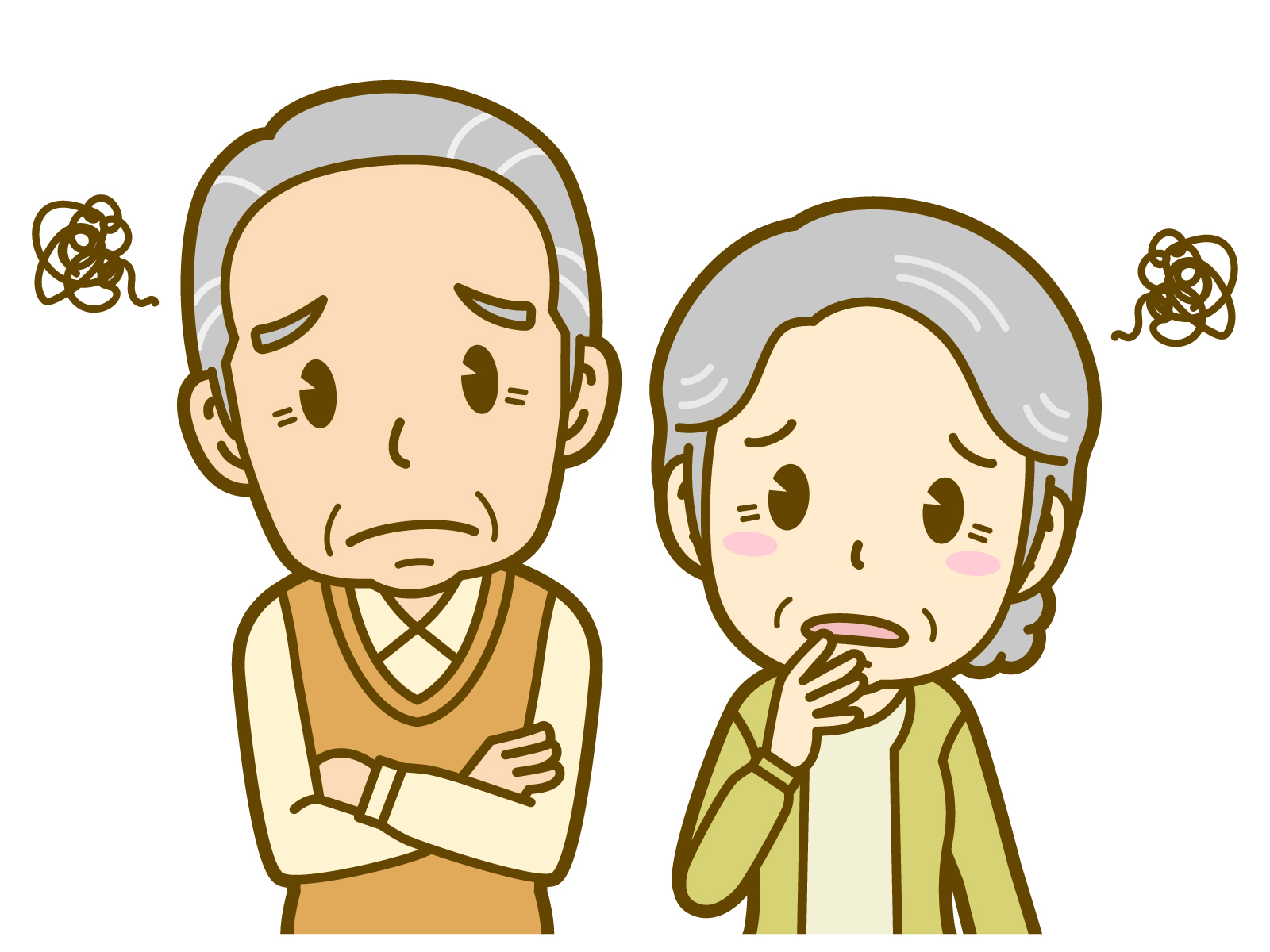
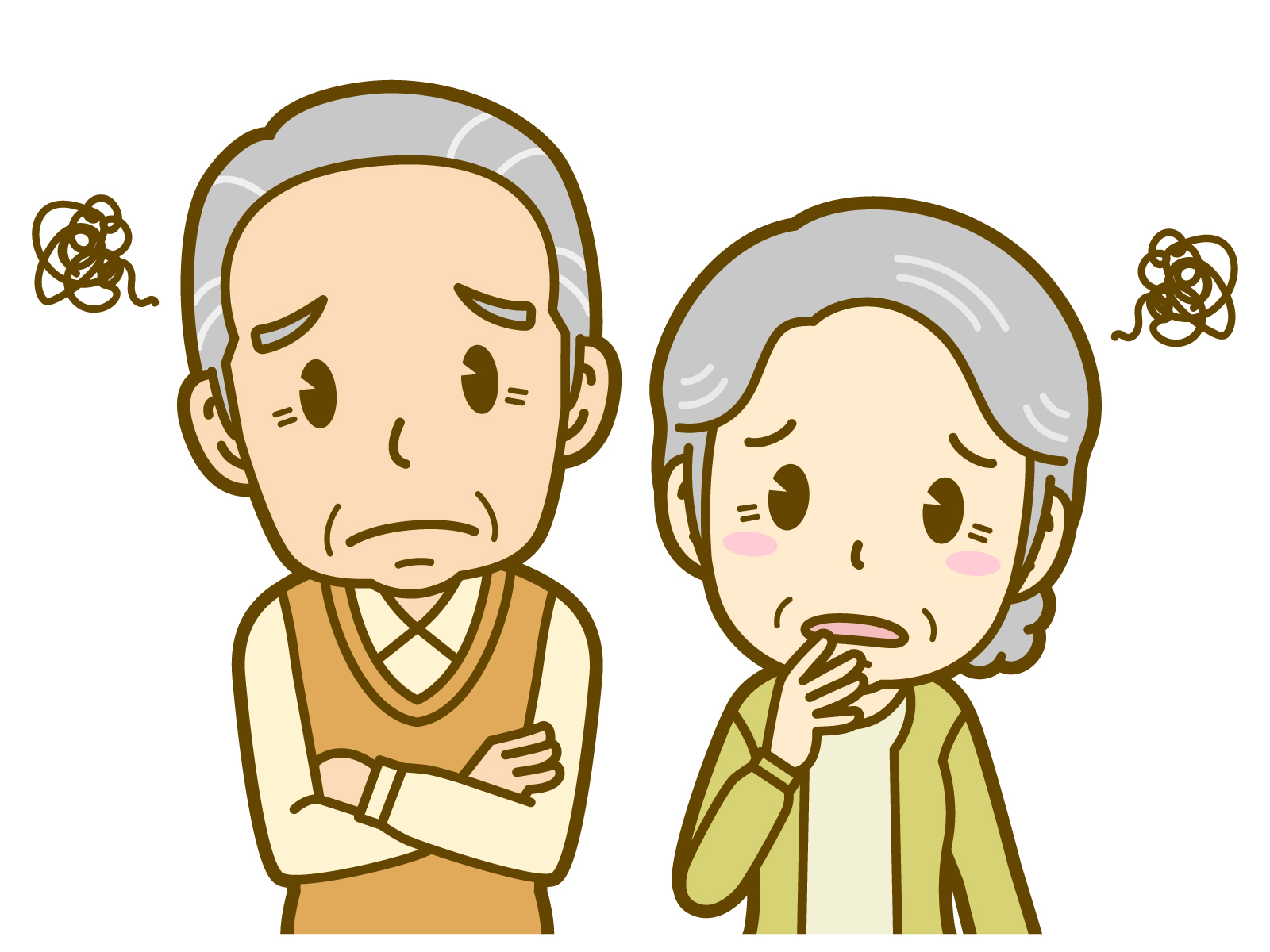
なぜ、成年後見が必要なの?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 成年後見制度とは?
- 法定後見と任意後見
- 成年後見人等が持つ権限
- 成年後見人等の業務範囲
- 成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度
もし、私が認知症になったら…。
誰もがこんな不安をどこかに抱えているものです。
高齢になれば、記憶力や判断能力なども衰えますから、悪質商法などの被害に遭う確率も高くなります。
また、事務手続きなども十分に行えなくなり、福祉サービスの申し込みや施設への入退所などが困難になることも考えられます。
財産管理などの法律的な手続きが、難しくなるのは言うまでもありません。
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下すると、自分の人生に必要な様々な選択をすることができなくなってしまいます。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えた人を保護・支援する制度です。
家庭裁判所の監督の下、支援者(成年後見人等)が、本人(成年被後見人等)に代わって財産を管理したり、契約を結んだりします。
成年後見制度は、裁判所の手続きにより後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ「任意後見制度」に分かれます。
法定後見制度は、判断能力が既に失われたか、又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。
これに対して、任意後見制度は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。



判断能力の衰えとは、自分が置かれた状況を正しく認識し、適切な判断を下すことが難しい状態のことを言います。判断能力の程度によって、後見制度による保護・支援の度合いが変わってきます。
- 法定後見 … 既に判断能力が衰えた人のための制度
- 任意後見 … 将来、判断能力が衰えた時に備えるための制度
財産管理・身上監護(身上の保護)
成年後見制度は、認知症などで判断能力が下がり、日常生活や財産管理に支障が出た人を手助けするための制度です。



成年後見制度で選任された成年後見人等には法的権限が与えられますが、これは「財産管理」と「身上監護(身上の保護)」に大別されます。
財産管理
財産管理とは、文字通り、本人の財産を管理することです。
具体的には、預貯金・保険・有価証券の管理、不動産などの重要な財産の管理や処分、相続における手続き、その他の収入・支出の管理などです。



後見人は、不動産の権利証や契約書、証書類、通帳など、貴重品や重要な書類を預かり保管します。本人の財産を全て把握した上で、日々の収入や支出を管理し、事情に応じて適切な管理・処分などを行います。
具体的には次のようなことが挙げられます。
- 不動産などの財産の管理、保存、処分など
- 銀行など金融機関との取引
- 年金や土地・貸家の賃料など定期的な収入の管理
- ローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金など定期的な支出の管理
- 日常的な生活費の送金や日用品などの購入
- 遺産相続などの協議や手続き
- 生命保険などの加入や保険料の支払い、保険金の受け取り
- これら財産に関する権利証や通帳など証書類の保管や各種行政上の手続き
身上監護(身上の保護)
身上監護とは、本人の意思を尊重し、且つ、本人の心身の状態や生活の状況などにも配慮しながら、本人の生活や健康・療養等に関する支援をすることです。
具体的には、本人の住居の確保、生活環境の整備、介護契約、施設等の入退所契約、病院での治療及び入院手続きなどの支援です。



本人が適切な環境で適切な医療や介護を受けることができるように配慮し、またそのための手配をすることを総称して「身上監護(身上の保護)」と言います。
- 医療に関する契約の締結
- 介護に関する契約の締結
- 要介護・要支援認定の要請
- 住居の確保に関する契約の締結
- 施設への入退所に関する契約の締結
- リハビリに関する契約の締結
- 見守り行為
権限の範囲外
後見人は本人の代わりに様々なことを行う権利を持っていますが、下記の事項については、後見人の権限の範囲外とされています。
①事実行為の代理
本人の身の回りのお世話や介護、看護などの「事実行為」は、後見人の権限とはされていません。
しかし、そのような介護、看護が必要である場合には、後見人として本人がそれらの支援を受けられるような契約を締結すべき義務があります。
つまり、成年後見人等は毎日の買い物や食事の支度、身体介護などを支援してくれるホームヘルパーを依頼するための相談や契約は行いますが、あくまでも本人が最適な治療や介護を受けるためのサポート体制を整えるだけで、実際に食事や排泄の介助をするのは契約を結んだヘルパーなどの第三者になります。



また、成年後見人等は、本人の病気の治療について、一般的な投薬・検査などの医療行為に対しては本人に代わって同意できますが、重大な手術を行うかどうかに対する同意権はないとされています。
②身分行為の代理
結婚、離婚、認知、養子縁組、遺言などの行為については、後見人が本人のために代理することが馴染まない行為として、後見人の権限の範囲外とされています。
本人が、本人の意思を持って結婚・離婚をしたい、養子縁組をしたいと意思表示している場合、これらの行為については「本人が単独」で法律行為を行うことができ、後見人の代理や同意は求められません。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下している場合で、自分で後見人を選び、契約することができない場合に家庭裁判所が申し立てに基づいて後見人を選定するものです。



それに対して任意後見制度は、本人が正常な判断能力を持っているうちに、自分で後見人を選んで契約します。
3つの類型
法定後見制度は、後見・保佐・補助の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
この制度においては、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)」が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
①後見
常時、判断能力を欠いている人を対象としたのが「後見」の制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人又は成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。



但し、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象になりません。
②保佐
判断能力がかなり不十分になってきた人を対象にしたのが「保佐」の制度です。
日常的な買い物はできても、不動産の売買や自動車の購入、お金の貸し借りなどといった、重要なことが自分一人でできない場合には、保佐が該当します。
保佐人は遺産分割や財産処分など民法で定められている「重要な行為」について、「同意権」を持ちます。
また、「取消権」により、本人が保佐人の同意を得ずに行なった法律行為を取り消すことができます。
さらに補助同様、申し立てのあった特定の法律行為について「代理権」も付与されます。



但し、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。
③補助
判断能力が不十分な人を対象としたのが「補助」の制度です。
一人暮らしで「預貯金など日常的な金銭管理が心許ない」「介護サービスなどの契約内容がよく理解できず、一人で手続きができない」という高齢者は少なくありません。
こういった「ちょっと不安」という人たちのために設けられたのが補助の制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権、取消権や代理権を与えることができます。
家庭裁判所が補助人に、申し立てのあった特定の法律行為について代理権を付与すれば、補助人が代わって預貯金の出し入れや、介護契約などを行うことができます。
また、悪質商法の被害に遭うことを考慮して、不動産など一定の重要な財産の処分について、補助人に同意権を付与することもできます。



補助人の場合は、前以てどのような行為について同意権・取消権、又は代理権が必要か、申し立てをしなければなりません。
例えば、「不動産の処分についての同意」と「建物の新築・改築・増築の同意」の申し立てをしておくと、万一、本人が補助人の同意なしで、不動産売却の契約をしてしまったとしても、取消権により契約を取り消すことができます。



但し、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取り消しの対象にもなりません。
後見人等に与えられる法的権限
成年後見制度では、成年後見人等は本人の意思を代弁し、本人が行うべき法律行為を本人に代わって行なったり、本人の行為を同意したりすることができます。
これらは家庭裁判所の審判により付与された「代理権」と「同意権・取消権」という二つの権限に基づいて実施されます。



それらがどんな権限なのか、簡単に説明しましょう。
①代理権
本人に代わって、他人が取引や契約などの法律行為を行うことができる権限を「代理権」と言います。
本人に判断能力があっても、第三者に代理権を付与して駐車場やマンションなどの賃貸管理を依頼することもありますが、成年後見制度で代理権という場合は、判断能力がない人の代わりに、家庭裁判所が選任した成年後見人等の代理人が、法律行為を行うことを指します。



例えば、成年後見人は本人所有の不動産を売却して、本人の生活費に充てたりすることができます。
②同意権・取消権
本人が売買契約など法律行為を行う時に、その法律行為を承諾する権限を「同意権」と言います。
成年後見制度では、本人が補助人や保佐人の同意を必要とする、不動産売買などの法律行為を行おうとしても、補助人や保佐人の同意なしでは契約は完全に有効にはなりません。
また、本人がたとえ不動産売買の契約書に署名・押印してしまっても、補助人や保佐人の同意のない法律行為は、取り消すことができます。
通常、契約を取り消す場合は、詐欺や脅迫など特別な理由が必要になりますが、判断能力が不十分な人を保護する成年後見制度では、同意のない契約(日用品の購入など日常生活に関する行為は除く)は取り消すことができます。
このように契約後にその効力を失わせる権利を「取消権」と言います。
任意後見契約
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は「本人の現在の判断能力」などを考慮したものですが、任意後見制度は「利用者の将来を見据えたもの」と言えます。
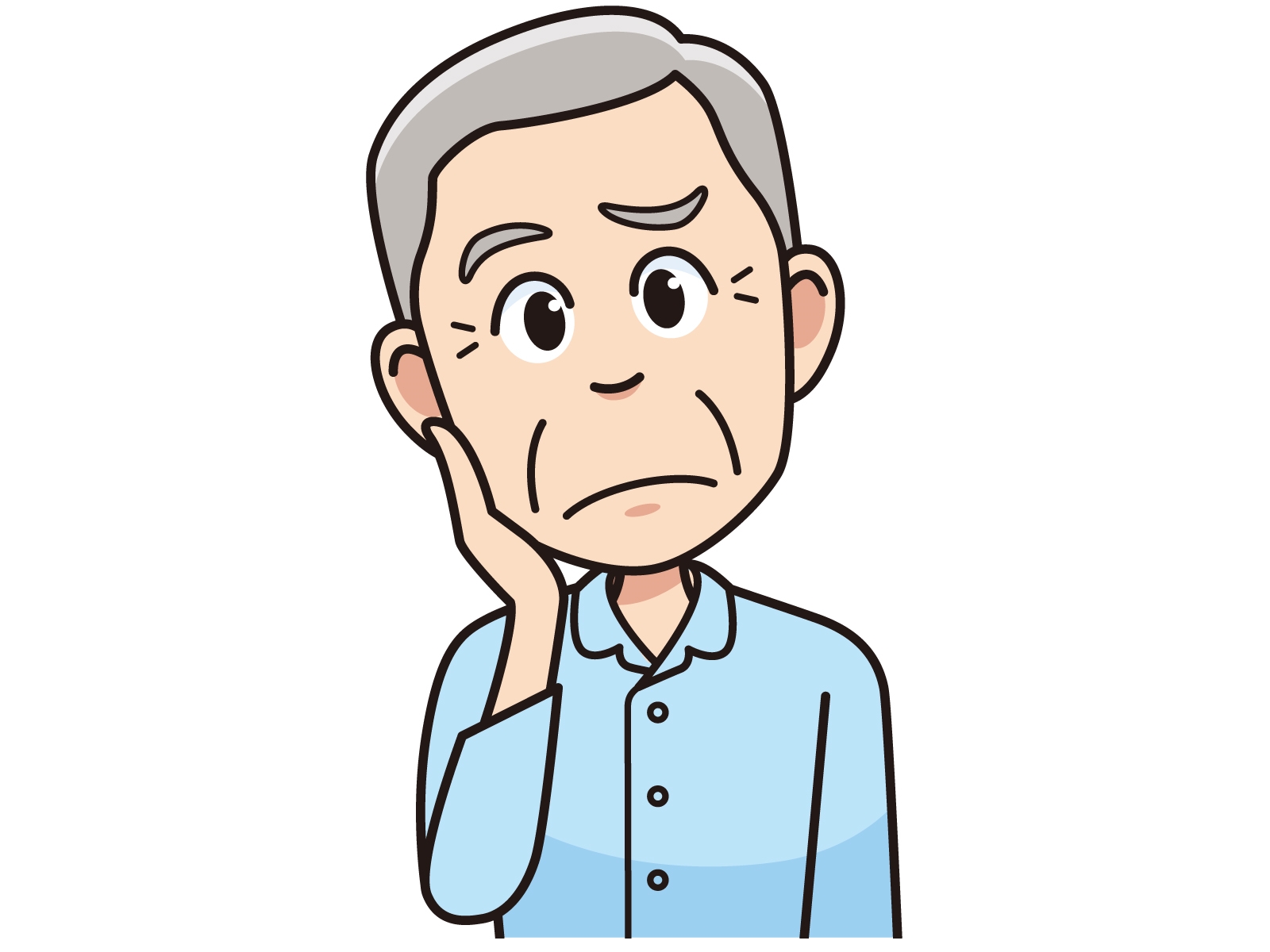
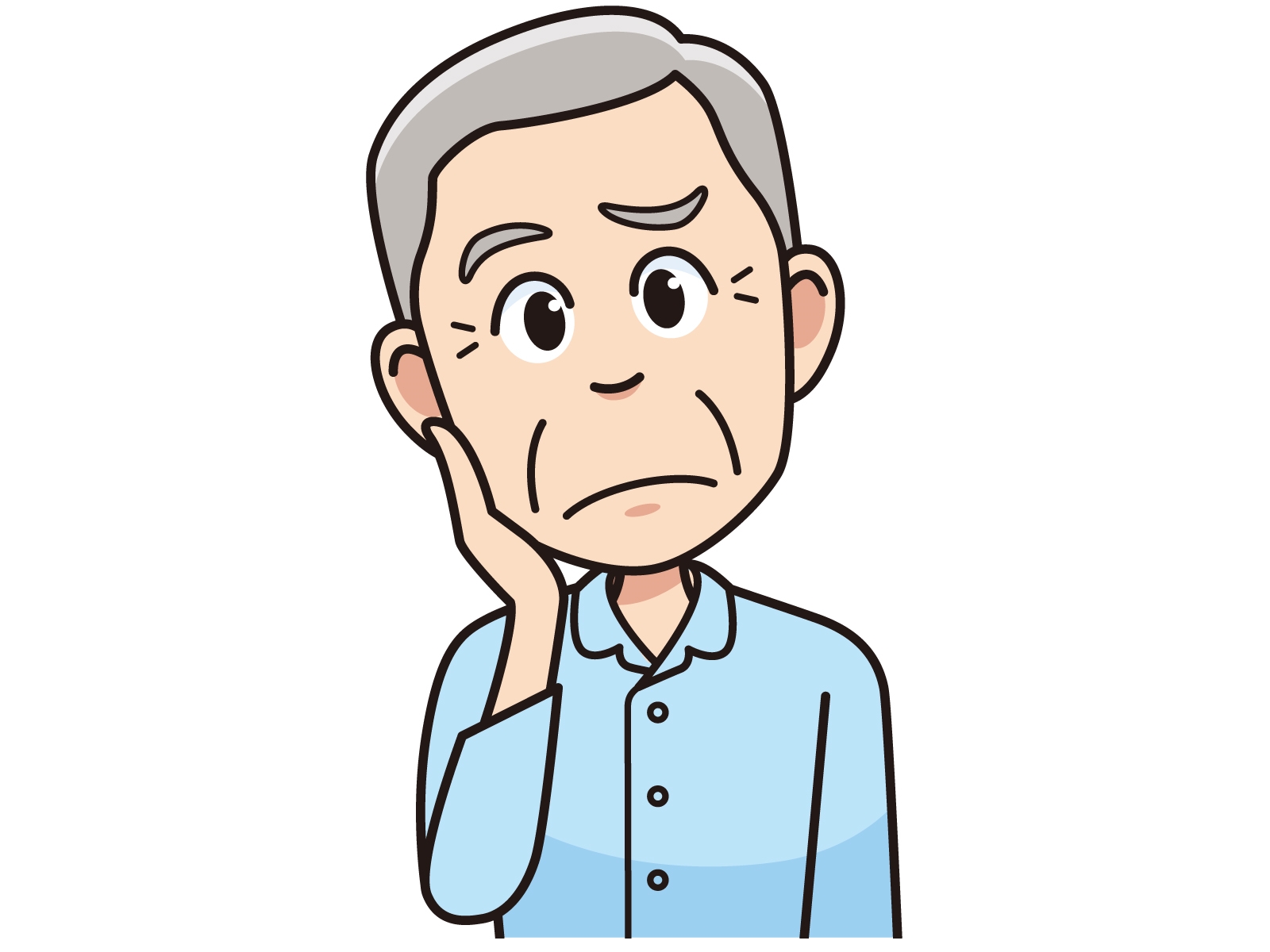
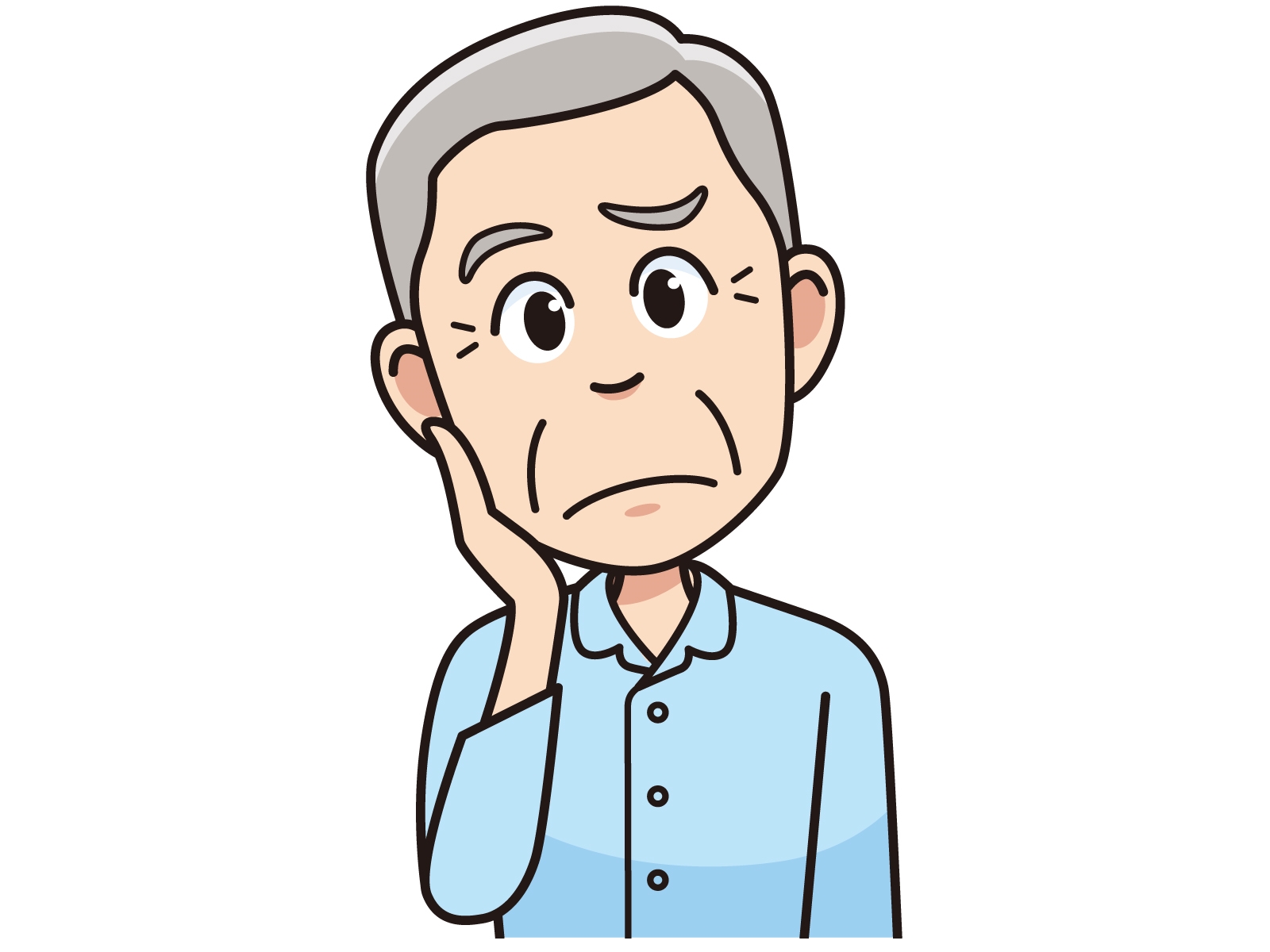
今はまだ元気。だけど、急な入院など、自分に万が一のことがあった時に頼れる親族が近くにいない…。
こうした漠然とした不安を取り除く方法はあるのでしょうか。



そのような人のために「任意後見」という制度があります。自らが、元気なうちに、契約で、将来自分の後見人になってくれる人と、予め(その人に)お願いする内容を決めておく、という点が任意後見制度の特徴であり、法定後見制度との大きな違いです。
財産管理はどうするか、どういう施設に入所するか、介護や看護はどうしたいかなど、具体的な事柄を自分の希望で決めることができます。
利用者は認知症や知的・精神障害などで判断能力が衰えた万一の場合に備え、判断能力があるうちに予め信頼できる人と「任意後見契約」を結びます。
この契約は任意後見人に代理権を与える委任契約の一つで、本人の判断能力が低下した時に、任意後見人による財産管理や身上監護などの後見事務が開始されます。
判断能力が低下しなければ、一生任意後見が開始されないこともあります。



現在、既に軽度の障害があり、判断能力が少し衰えてきた人が使うこともできます。例えば、法定後見制度の補助くらいの人でも、任意後見契約を結ぶ判断能力があれば、この制度は利用できます。
任意後見制度を利用するには、公証役場で公正証書による任意後見契約を結ぶことが必要です。
契約が公正証書によるのは、自由に決められる契約内容に不合理がないかどうかチェックするためです。



但し、法定後見制度と違って任意後見人に「同意権」・「取消権」はありません。
任意後見制度では必ず「任意後見監督人」が必要になります。
本人の判断能力が不十分になって、任意後見監督人の選任の申し立てを受けた時に、家庭裁判所が選任しますが、この選任によって任意後見契約は初めて効力が発生します。
監督人は任意後見人が契約通りに委任された後見事務を遂行しているかどうかチェックします。
言わば任意後見は、自分の将来を見通し、自分らしく老いていくことをサポートするための制度と言えるでしょう。
但し、任意後見人は事務手続きの代行であって、法律上サポートできない部分もあります。
例えば、重大な手術への同意や延命治療の有無を判断することはできません。
また、実際に介護などを行うのは、依頼したサービス施設や医療機関です。
成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度と家族信託は、どちらも財産管理手法の1つです。
しかし、この2つは様々な点で異なります。
家族信託というのは、自分の財産を、特定の目的を叶えるために信頼できる家族に託し、管理や運用・処分などをしてもらうものです。
例えば、次のような形です。
- 賃貸アパートを経営する人が、自分が管理できなくなっても家賃収入を得られて、良い物件があれば買い増すこともできるように、息子に不動産と預金の管理・処分を託す
- 預金に余裕のある人が、自分が認知症になった後も資産運用を続けられるように、娘に証券や預金の一部の管理・運用を託す
信託の契約をすると、管理の便宜上、財産の名義は信託を引き受けた家族に変わります。



だから、自分が認知症になっても、身体が不自由になっても、便宜上の名義人である家族が管理できるのです。
もちろん引き受けた家族は、自分自身の財産とは区別し、名義も信託専用のものになります。
そして、その財産は信託の目的にしか使えません。
信託の目的は、自分のためでなくても構いません。
例えば、次男に銀行口座の管理を託して、その口座から障害を持つ長男のために生活費を定期的に渡すといったこともできます。
これは、一度契約してしまえば、自分が亡くなった後も続きます。



成年後見制度は、本人の判断能力が低下してから、本人が亡くなるまで、つまり「一代限りの期間」に限定されるのです。それに対して家族信託は、信託契約を交わした時からスタートし、場合によっては、本人の亡くなった後も数世代にまたがって長期にわたり、財産管理をしていくことが可能になります。
また、財産は管理する次男の信託専用の名義になっているので、相続の対象にもなりません。
信託の目的を組み合わせることもできます。
初めは自分のために財産を管理してもらい、自分の死後は、障害を持つ子の生活費のために管理してもらうなどということも可能なのです。



但し、この信託で託せるのはあくまでも「自分の財産」のことのみ。成年後見のように、身上監護(身上の保護)に関する権限は託せません。
また、信頼できる家族がいることも条件となります。
信託の契約ができるだけの判断能力も必要なので、本人がしっかりしているうちに行います。
成年後見制度では、専門職後見人が財産の管理を行う時、報酬というランニングコストが月々発生します。
一方、家族信託は、受託者の報酬を無報酬とすることもでき、その場合はランニングコストが掛かりません。
まとめ
認知症や知的障害、精神障害など、判断能力が衰えた人を支援するために定められた国の制度を、「成年後見制度」と言います。
成年後見制度は、既に判断能力が衰えた人を支援する「法定後見制度」と、まだ元気なうちに将来の支援者と支援の内容を予め定めて契約をしておく「任意後見制度」の2つに分かれています。



認知症、知的障害、精神障害などで、既に判断能力が衰えた人を支援するための制度が、「法定後見制度」です。
法定後見制度は、支援が必要な人の判断能力の度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
支援が必要な人を「本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)」、支援する人を「成年後見人・保佐人・補助人」と言います。
法定後見制度を利用したい場合は、管轄の家庭裁判所に「成年後見人等選任申立て」を行う必要があります。
申し立てをする家庭裁判所、申し立てができる人は法律で定められていて、申し立ての際には様々な書類を用意する必要があります。



まだ元気で判断能力も十分にある人が、将来判断能力が衰えた時に備えて、今のうちに将来の支援者や支援内容を決め、支援者と契約をしておくという制度が、「任意後見制度」です。
支援が必要な人を「本人」、支援する人を「任意後見人」と言います。
任意後見制度を利用するには、支援者との間で公正証書によって「任意後見契約」を締結します。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所への申し立てによって「任意後見監督人」が選任されます。
これによって、任意後見が開始します。



しかし、任意後見契約は名前の通り「契約」なので、将来後見人を引き受ける人の「同意」がなければ、そもそも任意後見契約を締結することができない点に注意が必要です。
- 成年後見制度 … 判断能力が衰えてから選任する
- 任意後見契約 … 判断能力が衰える前に選任する
後見人が行う仕事には、大きく分けて「財産管理」と「身上監護(身上の保護)」があります。
財産管理の方法としては、「家族信託」の活用も考えられます。
家族信託とは、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託して管理や処分を任せる方法です。
例えば、家族信託で父を委託者と受益者に、息子を受託者にしておけば、父が認知症になり自分で金融機関に行くことが難しくなった場合でも、息子が父の預金を引き出して父の生活費を準備するということもできます。



複雑な制度のため、家族信託に詳しい専門家への相談をお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。