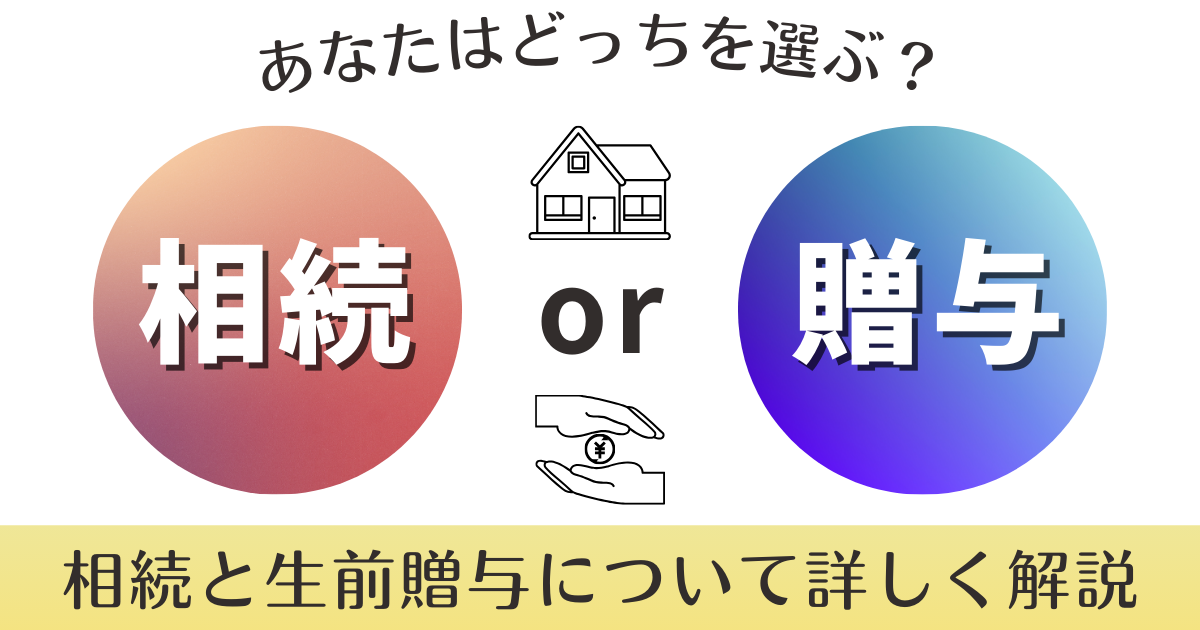悩める人
悩める人贈与と相続の違いを知りたい…



どういう場合に贈与税は掛かるのか?



こんな疑問・悩みを解決します!
- 贈与とは
- 贈与になる場合とならない場合
- 贈与と相続の違い
- 様々な贈与の手法
- 贈与税が掛かるものと掛からないもの
- 贈与税が掛かる時の計算方法
- 相続税の課税対象になる場合
- 贈与税の申告と納付について
贈与とは
双方の意思の合致
そもそも「贈与」とは何でしょうか。
よく理解していないのに「相続税が節税できるから」と、妻や子供に現金を譲り、それで贈与をしたと思っている人が結構います。
しかし、贈与した筈の財産が相続税の課税対象になってしまい、税金を追加で納めることになるケースが多発しています。



贈与をしっかり理解することが、相続税対策の基本中の基本となります。
贈与とは、財産を渡す人(贈与をする人)が「これこれをあげますよ」と意思表示をし、財産をもらう人(贈与される人)が「ではいただきます」とお互いに理解して初めて成り立つ行為です。
この財産を渡す人を「贈与者」、財産をもらう人を「受贈者」と言います。
契約書や遺言書などでしっかり取り決められた贈与もあれば、口頭で約束する贈与もあり、形態はいろいろ。



贈与と言えるためには、「あげます」「もらいます」という、「双方の意思の合致」が必要です。反対に、双方の意思の合致さえあれば、契約書などがなくても贈与は成立します。口約束だけでも贈与となります。
例えば、父親が長男に現金を贈与するつもりで、長男の預金通帳に振り込んだとしましょう。
この場合、長男がもらう意思を表明し、更に長男が自分で通帳を管理していれば「贈与は成立」します。
では、相続発生前に、長男がもらったお金を無駄使いしないように、親が預金通帳や印鑑を預かっていて、長男の知らないところで贈与しておくとどうなるでしょう。
このような場合には、贈与と認められません。
贈与と聞くと、多くの人は「贈与税」のことが気に掛かるようです。
贈与で注意しなければならないのは、贈与税だけではありません。
例えば、車を贈与する場合、名義変更の手続きも必要で、受贈者が保険に入り駐車場を用意するなど、準備が必要です。
贈与する側は「タダであげるのだから」と贈与した後の費用や手間を軽く考えがちですが、相手に思わぬ負担を強いることになるかもしれません。



だからこそ、お互いの意思の合致を大切にしましょう。
客観的な証拠が必要
口約束でも贈与は成立すると書きましたが、一般的に贈与する際は「契約書を残しましょう」「振り込みで履歴を残しましょう」と勧められます。
何故でしょうか。
贈与の当事者であれば、お互いに相手の意思の確認ができます。
しかし、客観的に見た時には、何か記録がなければ、他の人(税務署など)には確認することができません。



つまり、「これは贈与です」と第三者に主張するために、何か証拠が必要になるのです。そこで、契約書や振込履歴が重要になります。
生前に贈与をして相続財産を減らしておけば、相続税を安くすることができます。
しかし、贈与と認められなければ「相続税の節税効果」はないので、税務署に対して贈与の事実を証明するために、客観的な証拠を残しておく必要があります。
そこで、贈与の度に贈与の意思を確認して贈与契約書を交わし、契約書通りに財産を移転(預金の場合は銀行振込)させます。
さらに、贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行います。



これで、贈与の事実を税務署に対して証明することができます。
もしも贈与と認められなかった場合、贈与者の財産が移動していないと見なされることになります。
そうなると、贈与者が亡くなったとき、その財産は相続税の課税対象になることもあるのです。
さらに、行うべきだった「申告納税」がないということで、追徴課税の対象になることもあります。



相続税対策に贈与の活用を考えている人は、この点に注意しましょう。
贈与と相続の違い
そもそも「贈与」と「相続」の違いは何でしょうか。
贈与が「贈与者と受贈者双方の意思」で行われるのに対して、相続は「死亡によって強制的」に始まる点が最大の違いです。
また、相続は「法律で決められた相続人のみ」にしか行えません。
一方、贈与はその殆どが「贈与者の生きている段階」で行われ、「贈与の相手や時期も選べる」という特徴があります。



ですが、死亡時に行う「遺贈」と「死因贈与」というものがあります。
その共通点は、遺言や贈与契約によって、法定相続人以外の人への財産の贈与が可能なこと、財産の贈与の効力が贈与者の死亡時に発生すること、です。
相違点は、遺贈は遺贈者(遺言で財産を贈与する人)が一方的に行う意思表示であるため、受贈者(遺言で財産をもらう人)が財産の受け取りを放棄することができるということです。
これに対し、死因贈与の場合には、贈与者と受贈者の合意で贈与契約が成立しているので当然、受贈者の意思のみで財産の受け取りを拒否することはできません。
このように、死亡時に財産を渡したい時は「遺贈」や「死因贈与」も活用できます。
遺贈
遺贈とは、遺言書によって行う贈与のこと。
遺贈により、相続人以外の人に財産を残すことができます。
遺贈のメリットは、
- 遺贈者が死ぬまで遺言の内容を秘密にすることが可能
- 受贈者は遺贈を放棄することが可能
という点です。
一方、デメリットとしては、
- 遺言は厳格な法律様式が定められているため、些細なミスで遺言自体が無効となることもある
- 遺贈する財産が時間の経過と共に変化するため、定期的な見直しが必要
などが挙げられます。
死因贈与
死因贈与とは、「死んだら財産をあげる」というように、死亡を切っ掛けに贈与するというやり方です。
遺贈は必ず遺言書で行うという条件があります。
しかし、死因贈与にはそのような制限はありません。



但し、死因贈与は死亡する前に贈与者と受贈者との意思が合致し、契約が成立していなければならないという違いがあります。
書面で死因贈与契約を結んでおけば、しっかりした証拠が残り、相続が発生した時に無用なトラブルを避けることにも役立ちます。
また、死因贈与契約は被相続人にとって「負債」の一種なので、財産を相続する人は、この契約も相続し、履行する義務があります。
そして、死因贈与分は相続財産の分配以前に差し引かねばなりません。
法定相続人以外の第三者に財産を譲らなければならない場合には、この契約が大変効果的です。



但し、死因贈与は「契約」なので、一度結んでしまうと、気が変わったからと言って、遺言のように一方的に破棄したり内容を変更することは原則としてはできません。
今後の成り行きによって財産の分け方が変わるかもしれない場合には、遺言書を利用した「遺贈」という形を取った方が無難でしょう。
死因贈与のメリットは、遺言と違って、
- 特に形式は定められていないこと
- 贈与を放棄できないため、確実に財産を移転できる
という点です。
デメリットは、
- 負担付きの贈与契約(下記参照)で受贈者が贈与者の生前に義務・負担を履行している場合、贈与者が亡くなる前でも死因贈与契約を解消できないこと
- 死因贈与は遺贈よりも不動産の移転コストが高くなること
です。
様々な贈与の手法
贈与は相続とは異なり、死亡で強制的に発生するものではないため、色々な贈与手法があります。
遺贈に対し、生前に贈与することを「生前贈与」と言います。
教育資金の一括贈与、暦年贈与、配偶者への住宅贈与などはここに含まれます。
贈与に何らかの負担が付いてくるものは「負担付き贈与」と言います。
例えば、「家を贈与する代わりに、自分の老後の面倒を見てほしい」といったものなどです。
住宅ローン付きの家を贈与することも、負担付き贈与の一つです。
贈与に時期を指定する「条件付き贈与」というものもあります。
例えば、「大学に合格したら、車を買ってあげる」という条件(停止条件付き贈与)や、「大学を卒業するまで、毎月3万円のお小遣いをあげる」のような条件(解除条件付き贈与)があります。
- 停止条件付き贈与 … 何かをしたら効力発生 / ~したら
- 解除条件付き贈与 … 何かをしたら効力解除 / ~まで
このような「贈与」は、口約束(口頭)でも成立します。



しかし、遺贈は必ず遺言書で行わなければなりません。また、口頭の贈与はいつでも解消できるのに対し、書面による贈与は解消できないと定められています。
贈与税が掛かるものと掛からないもの
贈与には「贈与税」が掛かります。
贈与税が掛かるのは、個人から個人へ贈与が行われた場合です。
会社などから個人に贈与が行われた場合は「所得税」が掛かり、逆に個人から会社などに贈与を行なった場合は「法人税」の対象になります。
いずれの場合も、税金を払わなければならないのは「受贈者側」、つまり財産を受け取った側です。
個人的なやり取りに対して税金が掛かるのも変な話ですが、これは贈与税が元々「相続税を補完」する意味を持っているからです。



つまり贈与税には、「高額な相続税を逃れるために、生前に全財産を贈与してしまうことを防ぐ」役割があるのです。
では、どのような贈与が課税されるのでしょうか。
課税対象
贈与税の対象となる贈与は、金銭のやり取りだけではありません。
土地や家、株式、現金などの現物を贈与した場合はもちろん、借金の肩代わりをした額も贈与税の対象となります。
さらに、市価よりも安い値段で売った時なども、市価との差額分が贈与されたと見なされ、その金額に対して税金が課されます。



そして、贈与には全て課税されるのではなく、贈与の金額や条件によっては「非課税」にもなるのです。
課税対象外
例えば、贈与には受贈者1人につき年間110万円までの基礎控除がある他、教育資金の一括贈与など、様々な非課税制度が存在します。
また、扶養義務者からもらった生活費や教育費、支給型の奨学金なども金額に関係なく課税対象外です。
さらに、家族旅行などに対してお金を出しても、原則として贈与税は発生しません。
その他、香典や花輪代、年末年始の贈答品、お祝い物又はお見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは非課税となります。
- 冠婚葬祭
- お中元・お歳暮
- 教育費・奨学金
- お見舞い品
- 被扶養者に掛かるお金
- 仕送りなど生活費に付随するもの など



但し、いずれも「通常考えにくいほどの高額」になると、課税対象になることがあります。
尚、財産の受け渡しがある時に注意しなければならないのは「みなし贈与」です。
これは「贈与したつもりがなくても贈与と見なされるやり取り」のことで、例えば「お金の貸し借り」があり、「返済の事実がない」ものなどは「お金を贈与したのと同じ」と見なされ、金額によっては贈与税の支払いが必要になるのです。



節税を考える前に「そもそも課税か非課税か」の判断が必要です。
贈与税額の計算方法
贈与を受けることになったら、気になるのが支払う税金(贈与税)ではないでしょうか。



贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が支払います。そして原則、現金一括納付です。なので、多額の贈与を行う際には相手に納税する資金があるかどうかも気にしなければなりません。
贈与は1人につき年間110万円まで非課税です。
年間というのは毎年1月1日から12月31までです。
例えば、6月、9月、12月、翌年の2月にそれぞれ30万円の贈与が同じ人にあったとします。
この場合は6~12月の合計90万円が1年間の贈与金額となり、年をまたいでいる2月の分は含まれません。
尚、この場合は110万円以内(基礎控除内)なので非課税となります。
贈与する側は複数人に年間110万円を渡しても非課税ですが、受贈者は複数人から贈与を受けた場合、それら全てを合計した金額で計算します。
合計金が110万円以内なら非課税ですが、それを超えれば課税対象になります。
贈与税は、下記のような速算表を使って計算します。
速算表には18歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合と、そうでない場合との2種類があります。
基本的に、直系尊属からの贈与は税率が低く、それ以外の贈与は税率が高くなるようになっています。
参考のために、贈与税がどれぐらい課せられるかというと、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された合計額から基礎控除額である110万円を差し引き、その金額に税率を掛けて、更に控除額を差し引くことで算出されます。
- (1年間の贈与財産の合計-基礎控除額110万円)×速算表の税率-速算表の控除額=贈与税
- 贈与税の速算表 -
- 一般的な贈与(一般税率)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
- 直系尊属からの贈与(特例税率)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |



それぞれの場合で、税率が異なってきます。両方の速算表を使うような贈与を受けている場合には、計算の間違いに気を付けましょう。
贈与税は超過累進税率となっているため、一度に多額の贈与をすると納税額が高額となります。
例えば、父から子供に1,000万円を贈与するとします。
一度に贈与した場合は「(1,000万円-110万円)×30%-90万円(速算表の控除額)=177万円」となります。
これに対し、10年間に亘って毎年100万円ずつ贈与(暦年贈与)した場合は、全て基礎控除以下の贈与となり、贈与税は掛かりません。
贈与税は、
- 超過累進税率を採用しているため、贈与額が高額になるほど適用税率が高くなる
- 基礎控除額が110万円しかない
- 贈与が一定の条件を満たすと、住宅取得資金贈与を始めとした様々な特例が適用できる
などの特徴があります。



相続税対策として有効に贈与するのなら、「早いうちから長時間かけて少しずつ贈与を行う」のが鉄則です。
相続税の課税対象になる場合
贈与したつもり
相続対策として生前贈与を行なっていたにも関わらず、相続税の申告をする時になって、贈与が成立していないことがあります。
例えば、専業主婦の妻が多額の預貯金を持っていたり、子や孫の名義の預金(名義預金)があったことを本人たちが相続の開始まで知らなかったりする場合などです。
贈与は、財産を贈与する人と財産をもらう人の合意があって、初めて契約が成立するものです。
そして、財産の所有権の移転がなければ、贈与の事実を証明することができません。
不動産であれば、不動産登記により財産の所有権の移転は容易に判断できます。
しかし、預貯金などの場合は贈与の事実があったことを証明することが困難です。
贈与が行われたことを証明できなければ、相続税の課税対象になってしまうため、贈与をする時には贈与契約をきちんと締結することが重要になります。



生前に贈与したつもりでも、そう見なされないことがあります。その結果、贈与者が死亡した際には、贈与したと思っていた財産も含めて相続税を計算しなければならなくなることもあるのです。
このような事態に陥らないために「贈与契約書を作る」、「もらった財産を使う」などして対応しましょう。
生前贈与加算
生前贈与加算とは、相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、取得した財産の相続税の課税価格に、贈与された財産の贈与時の課税価格を加算する制度です。
つまり、相続などで財産をもらった人が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けていた場合には、その贈与財産も相続税の課税対象になるということです。



これには「相続税逃れのための贈与」は認めないという意味合いがあります。また、相続人以外への贈与ならば、相続開始前3年以内でも相続税に影響がありません。
生前贈与加算が適用されると、贈与は認められるものの、相続税の計算上は贈与がなかったものとして課税価格が計算されます。
従って、贈与税を納めている場合は二重課税にならないように、既に支払った贈与税分が相続税から控除されます(贈与税額控除)。
相続時精算課税による贈与
贈与をする時には、相続時精算課税を使うことができます。
これは、贈与時に贈与者一人につき2,500万円まで贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分について一律20%の税率で税金を納めるという制度です。
相続時精算課税では、贈与時には無税又は20%の贈与税を支払っておき、相続の時に精算します。
税金を払い過ぎていたらその分は返金され、不足分があれば納付します。
2024年以降は相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までなら贈与税も相続税も掛からず、贈与税と相続税の申告も不要に。



相続時精算課税制度は元々一度に多額の贈与をしたい時によく使われる制度ですが、今後は暦年贈与と同じような使い方も可能になります。
因みに、生前贈与の持ち戻しが適応されるのは相続人のみです。
また、相続時精算課税による財産を持ち戻しても、相続財産が基礎控除額以下でしたら、相続税は掛かりません。



相続時精算課税は、60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫への贈与の場合に認められています。しかし、これは節税には役立たず、単に課税の先送り制度と言えるでしょう。
死因贈与・遺贈
贈与には、相続発生によって生じる「死因贈与」があります。
これは、生前に「私が死んだら財産をあげるよ」と約束し、贈与者が死亡することで効力を発揮する贈与契約のことです。
財産をもらう受贈者は「死んだ時には財産をもらいます」と、契約に対して承諾する必要があります。



承諾しなければ、死因贈与契約は成立しません。
このように贈与者が死亡することで財産が贈与される場合は、贈与税の対象ではなく、相続税の対象となります。
また、遺贈された財産は全て相続財産として扱われます。
受遺者が相続人でなくても、贈与税ではなく相続税が課されるのです。
財産評価や計算方法も相続税の基準です。



受遺者が被相続人の配偶者、父母、子以外であった場合、税額が2割加算されるので注意が必要です。
贈与税の申告と納税
個人から財産をもらった時は、贈与税の課税対象になります。
贈与税は贈与した側ではなく、もらった側である受贈者が自分で納税額を調べて納税します。
納税は、納付書と共に受贈者の住所地を管轄する税務署、又は金融機関などで行います。
現金での納税の他に、e-Tax(電子納税)も利用が可能です。



納付書は税務署に備え付けられています。しかし、税務署から納付書が送られてくるわけではないので、申告・納税を忘れないように注意しましょう。
贈与税は金銭一括納付が原則なので、納税期限にも注意が必要です。
贈与税はもらった翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税しなければなりません。
所得税や消費税の確定申告のような振替納税の制度はありません。
例えば、2023年1月に贈与を受けた財産に対する贈与税の申告・納税は、2024年の2月1日から3月15日の間に行うことになります。
万が一、期限を過ぎても必要な申告・納税を怠っていると、無申告加算税や延滞税の対象になることも。
期限内に申告・納税をしなければ、更に負担が大きくなるのです。



しかし、多額の税を一度に納付することが困難な場合は「延納」という方法を使うこともできます。延納とは、5年以内の年賦(分割)で納付するという制度です。
延納が認められるためには、次の3つの要件全てに該当する必要があります。
- 納税額が10万円を超えていること
- 一括納付が困難な理由があること
- 担保を提供すること
延納申請書は申告期限までに申告書と一緒に提出する必要があり、その際に担保を提供することも義務付けられています。
担保となるのは、国債、地方債、社債、不動産、船舶などです。
但し、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合には、担保は必要ありません。
尚、延納すると数パーセントの利子が掛かります。
まとめ
- 贈与と贈与税の基礎知識 -
- 贈与とは「自分の財産を無償で誰かにあげる」ことです
- どんな財産でも贈与できます
- 贈与はお互いの「意思表示」が大事です
- 贈与はあげる側、もらう側の「同意」が必要です
- 口約束だけでも贈与となります
- お互いの「合意」がなければ贈与は成立しません
- あげた「つもり」は贈与になりません
- 贈与と認められるには「客観的な証拠」が必要です
- 税金面で贈与と認められるには、あげた財産をもらった人が「管理」していることが重要です
- 財産をあげる人を「贈与者」、もらう人を「受贈者」と言います
- 贈与と相続の違いは「受け取る人」と「時期」にあります
- 贈与はいつでも、誰に対しても行うことができます
- 贈与する時期は自由に選ぶことができます
- 相続は、相続人のみしか行えず、必ず死亡により開始します
- 贈与には様々な手法があります (生前贈与・負担付き贈与・条件付き贈与)
- 贈与者の死亡を切っ掛けに贈与することも可能です (死因贈与・遺贈)
- 贈与には「贈与税」が掛かります
- 贈与税は相続税を補完する意味を持ちます
- 贈与税は個人から受け取る財産が対象で、法人からの贈与は「一時所得」になります
- ケースバイケースで課税にも非課税にもなります
- 生活費、養育費、教育費は課税の対象外です
- お祝い金や香典なども、一般的には非課税です
- 常識の範囲を超える高額な場合は課税対象になります
- そのつもりがなくても、贈与になることもあります (みなし贈与)
- 生前に贈与したつもりでも、そう見なされないことがあります
- 贈与のつもりだった財産に相続税が掛かることもあります
- 相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加え、相続税の対象になります
- 相続時精算課税で受け取った財産は贈与時期に関係なく、全て相続税の対象になります
- 贈与税を計算し、納税するのはもらった側の「受贈者」です
- 1月1日から12月31日までの合計金額が課税対象です
- 年間の贈与額が110万円未満なら非課税です
- 暦年課税の税額は、年間の贈与額から基礎控除を引いて計算します
- 贈与税は贈与した人が誰かで税額が変わります
- 贈与税は「もらった翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税」しなければなりません
- 贈与税は現金による一括納付が原則です
- 贈与税の申告を忘れると無申告加算税・延滞税が課せられます
- 一括納付できない場合は「延納」という方法もあります
最後までお読みいただき、ありがとうございました。